Blog お役立ちブログ
数値で見る問い合わせ率向上の小さな改善10選
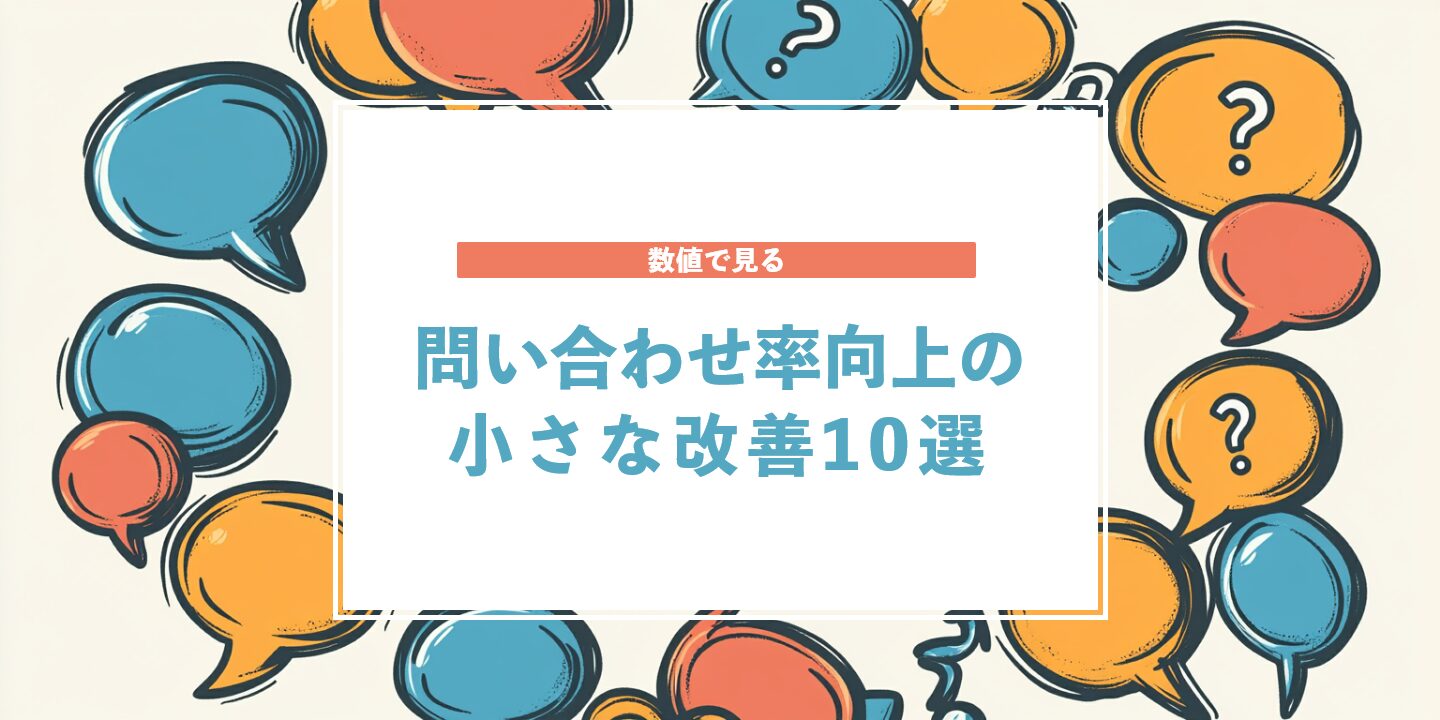
はじめに
中小企業において、問い合わせ率の向上は売上や顧客獲得に直結する重要な課題です。しかし、大規模なサイトリニューアルや大掛かりな広告投下だけが手立てではありません。小さな改善を積み重ねていくことで、実際の数値を少しずつ底上げし、最終的に着実な成果を得ることが可能です。
たとえば、お問い合わせフォームの入力項目数を一つ削減するだけでも、フォーム離脱率が下がるケースは珍しくありません。ボタンの文言を少し変えるだけで、クリック率が向上するケースも多く存在します。本記事では、こうしたちょっとした着眼点を10項目にわたって整理し、さらに成果を見える化するための数値測定やPDCAの回し方を解説します。
問い合わせ率向上における「小さな改善」とは
ここで言う「小さな改善」とは、大きなコストやリソースを投入することなく、既存のWebページやフォーム、ボタン配置などを微調整しながら問い合わせ率アップを目指す取り組みです。具体的には、以下のような点が含まれます。
- フォーム項目の見直し
- ボタンの配置・文言・色の変更
- ファーストビューやキャッチコピーの改善
- 一目でわかるアイコンやビジュアルの設置
- レイアウトやデザインのわずかな調整
こうした点を改善する際には必ず数値測定を行い、「何がどのくらい効果を出しているのか」を把握するのが重要です。裏付けのあるデータこそが、今後の施策の方向性を示してくれるからです。
数値に基づく10の具体的改善策
ここからは、小規模サイトでも取り入れやすい具体的な10の改善策を順番に解説します。いずれも、大きな出費を伴わずに実行できる工夫を中心に取り上げています。
改善策1:問い合わせフォームの入力項目を最適化する
フォーム改善は、問い合わせ率向上の基本とも言えます。入力項目が多すぎるとユーザーの負担が増え、途中離脱が起こりやすくなります。
- 要点
- 「必須」項目と「任意」項目を明確に分ける
- フォームデザインはシンプルにして入力しやすさを重視
- 一度に入力すべき項目数が多い場合はステップ形式も検討
下記の表は、問い合わせフォームでよく使われる項目と、その必要性を考える目安です。
| 項目名 | 必要性の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 氏名 | 高 | 個人とやり取りする上で必須 |
| 会社名 | 中~高 | BtoB業種なら高。個人向けなら任意可 |
| メールアドレス | 高 | 返信時に必須 |
| 電話番号 | 中 | 電話での即時フォローが必要なら高 |
| お問い合わせ内容 | 高 | 相談内容を把握するために必須 |
項目数を削りすぎると「信頼性が下がる」という懸念を持つ企業もあります。実際には、必要最低限の情報さえあれば後日のやり取りで詳細を詰められるケースが多いです。何よりもまず、入力項目を厳選し、ユーザーがストレスなく送信できるフォームを心がけましょう。
改善策2:ボタンの色・形・文言をテストする
ボタン一つを改善するだけでも、クリック率や最終的な問い合わせ率が変わる場合があります。色の心理効果やボタンの形状、文言は意外に見落とされがちです。
- 要点
- ボタンの背景色と文字色のコントラストを強める
- シンプルなラウンドシェイプを採用(角が丸い形状)
- アクションを分かりやすくする文言を使う(例:「無料で相談する」「今すぐ問い合わせる」など)
サイト全体の配色に合わせつつも、目立つ配色を意識しましょう。もし既存デザインと大きく乖離してしまうのが不安な場合は、サイト全体のテーマカラーのうち、一番鮮やかな差し色を使うのがおすすめです。
改善策3:ファーストビューのキャッチコピーを見直す
ページを開いた瞬間にユーザーの目に飛び込むファーストビューは、問い合わせまで誘導する最初の関門です。この部分のキャッチコピーが抽象的すぎると、ユーザーがメリットを瞬時に理解できず離脱してしまうリスクがあります。
- 要点
- 利益や解決策を端的に示す
- 具体的な数字や効果を示唆する表現
- 視覚的要素(アイキャッチ画像など)を活用
以下の例のように、キャッチコピーは短く簡潔にまとめるのがポイントです。
| 悪い例 | 良い例 |
|---|---|
| 「お問い合わせはこちら。お待ちしています。」 | 「短期で集客課題を解決。まずはお問い合わせください。」 |
| 「あなたのビジネスを応援します。」 | 「具体的な施策提案で売上アップを目指します。」 |
キャッチコピーがユーザーにとっての魅力や解決策を分かりやすく示しているか、定期的に確認してみましょう。
改善策4:問い合わせボタンを複数設置する
ユーザーが問い合わせに至るタイミングは一律ではありません。ページ上部で興味を持つケースもあれば、サービス内容を一通り読んで納得してから問い合わせるケースもあります。
- 要点
- ページの冒頭、途中、末尾など複数箇所に問い合わせリンクやボタンを設置
- スマートフォン画面でもわかりやすい配置にする
- 各ボタンが同じフォームにリンクしていても可
ただし、ボタンを乱立させすぎると逆に押し付けがましい印象を与えかねません。ページの流れに合わせて、自然に導入できる位置を検討しましょう。
改善策5:問い合わせ周辺の証拠・実績を提示する
ユーザーは「本当にこの企業に任せて大丈夫か」という不安を抱えがちです。その不安を払拭するために、実績や利用者の声を問い合わせフォーム周辺に配置すると効果的です。
- 要点
- 具体的な成果事例や導入事例を挙げる
- 実際の利用者の声(感想や評価)を引用
- 社会的信用を示す要素(受賞歴やメディア掲載実績など)があれば一緒に掲載
そうした情報が充実していると、ユーザーが安心して問い合わせへ踏み切りやすくなります。
改善策6:ページの読み込み速度を改善する
フォームやボタンの配置が良くても、ページの表示速度が遅ければ、ユーザーがページを離脱してしまう可能性が高まります。
- 要点
- 画像や動画などのファイルサイズを最適化する
- 不要なプラグイン・スクリプトを削減する
- レンタルサーバーの性能を定期的に見直す
「もう少し表示速度が速ければ問い合わせに進んでいたかもしれない」というケースは決して少なくありません。表示速度はユーザー体験の重要な部分です。
改善策7:フォーム入力エラー表示をわかりやすくする
ユーザーがフォームを送信しようとしてエラーが出るとき、その原因がどこにあるのか瞬時に分からないと、フォーム送信をあきらめることがあります。
- 要点
- 入力エラーが起きた項目を明確にハイライト
- 「どのように修正すればよいか」具体的なメッセージを表示
- 入力内容をクリアしないまま残す
エラーが出たときにフォーム全体が初期化されてしまう仕様だと、ユーザーの手間を増やす結果となり離脱を招きやすくなります。こうした小さな配慮が問い合わせ率を大きく左右します。
改善策8:ボタン文言と周囲の文脈を一致させる
サイト内の文脈とボタン文言をずらさないことで、ユーザーが直感的に行動を起こしやすくなります。
- 例
- サービス紹介ページの最後に「サービスの詳細を聞きたい方はこちら」ボタンを置く
- 事例紹介ページの途中に「同じように解決策を探している方はこちら」ボタンを置く
文脈と行動が一致しているとき、ユーザーの心理的ハードルは下がります。逆に文脈に合わないボタン文言があると、「いきなり売り込みをされている」と感じて離脱する人もいるので注意が必要です。
改善策9:問い合わせフォームをステップ形式に分割する
入力項目が多い場合、一度にすべてを入力させるとユーザーの負担が増えるだけでなく、ページが長くなりすぎて途中で離脱を誘発します。
- ステップ形式のメリット
- 一度に表示される項目が少ないため、ユーザーの心理的負担が軽い
- 「ここまで入力したから最後までやろう」という心理(コンコルド効果)が働きやすい
- 入力エラーや不備があっても、段階的に修正しやすい
ステップ形式にすることでユーザーが楽に進められ、最終的な送信率が上がることが多々あります。
改善策10:チャットサポートやFAQを併設する
問い合わせフォームから離脱してしまう理由として、「そもそも何を問い合わせればいいか分からなかった」「ちょっと確認したいだけなのに、入力するのが面倒だった」などの声が挙げられます。そこで、簡易的なチャットサポートやFAQを設置しておくと、ユーザーの疑問解決と問い合わせへの誘導がスムーズになります。
- 要点
- チャットウィンドウで担当者に直接質問できる環境を整える
- FAQでよくある質問を一覧化し、すぐ回答を得られるようにする
- 問い合わせフォームとFAQ・チャットの導線を合わせて設置
こうしたサポート手段があると、ユーザーが気軽に連絡しやすくなり、結果的に問い合わせ率アップにつながります。
改善策を定着させるための測定とPDCA
小さな改善を実施した後は、しっかりと数値を測定しながらPDCAを回すことが大切です。ここでは、測定すべき主な指標やPDCAの進め方を整理します。
測定すべき主な指標
- フォーム送信完了率: フォームを開いたユーザーのうち、何%が送信を完了したか
- クリック率(CTR): ボタンが設置されているページで、ボタンがどれくらいクリックされたか
- ページ滞在時間: ページを閲覧する時間が短すぎる場合、内容の理解が追いついていない可能性がある
- 直帰率: ランディングページにアクセスしてすぐに離脱するユーザーの割合
たとえばフォーム送信完了率が著しく低い場合は、入力項目の多さやフォームデザインの複雑さが原因かもしれません。データを見ながら原因を推察し、優先順位を決めて施策を打っていきます。
PDCAサイクルの進め方
- Plan(計画): 改善策を具体化し、期待する数値目標を設定する
- Do(実行): 実際にフォームやボタンを変更し、一定期間運用
- Check(評価): 変更前後で問い合わせ率がどう変化したかを測定
- Act(改善): 評価結果を踏まえて施策を継続・拡大するか、修正するかを判断
以下はPDCAの流れとチェック項目を対比させた簡易表です。
| フェーズ | 内容 | チェック項目 |
|---|---|---|
| Plan | 改善策を計画し、KPIを設定 | 目標値の設定は適切か、実現性はあるか |
| Do | 改善策を実施 | 実施期間の設定は十分か、原因要素を潰せているか |
| Check | 数値を評価 | 変更前後でフォーム送信率やクリック率がどう変化したか |
| Act | 改善策を継続・修正・廃止 | 次のサイクルに向けた課題は何か |
一度に多くの施策を試すより、1つか2つの変更点に絞って数値変化をトラッキングするほうが原因と結果を把握しやすくなります。
まとめ
問い合わせ率を上げるには、細かなポイントに着目しながら改善策を積み重ねることが効果的です。大がかりな投資をする前に、まずはフォームの入力項目を削減したり、ボタンの文言を変えてみたり、表示速度を見直したりといった小さなアクションを起こしてみましょう。そのうえで、実際の数値を計測し、PDCAを回していくことで、着実に問い合わせ率を底上げできます。
特に中小企業の場合、限られたリソースをどう効率よく活用するかが成功のカギです。大きな予算を投下しなくても、ちょっとした変更で成果につながるケースは少なくありません。小さな改善を繰り返しながら、自社に最適な方法を探っていきましょう。






