Blog お役立ちブログ
アクセス解析レポート外注したいけど何を提示してもらう?
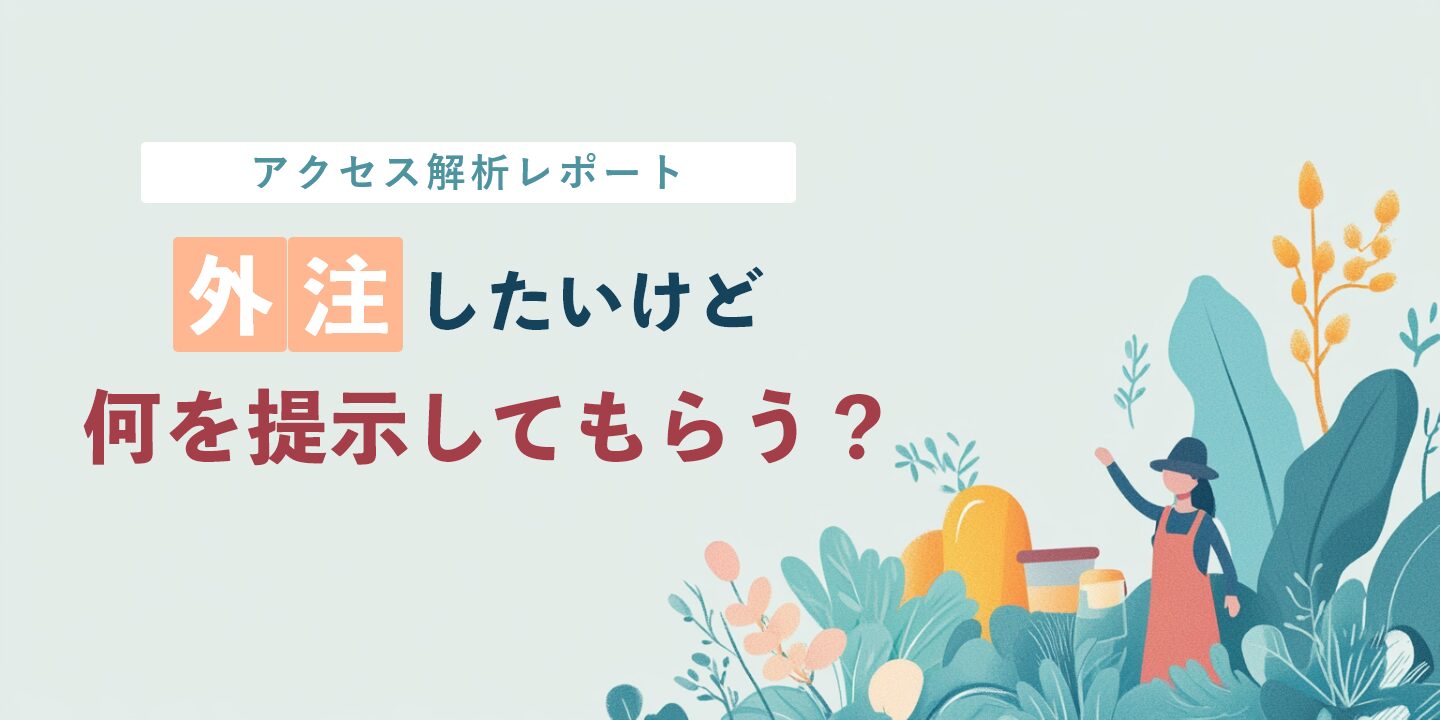
アクセス解析レポートを外注するメリットと必要性
中小企業がWebサイトを運用していると、アクセス解析のデータをどのように読み解き、経営判断やサイト改善に活かせばよいか分からず悩む場面は多いです。アクセス解析のツールには多種多様な指標やグラフが用意されていますが、それを実際の施策やビジネス成果に直結させるには、ある程度の専門知識が必要になります。
アクセス解析を外注することで、次のようなメリットが期待できます。
- プロ目線の分析・提案
専門家ならではの視点で、データから得られる示唆を抽出し、改善策や施策につなげることが可能。 - 時間と労力の削減
社内担当者が手作業でレポートを作成する手間を省き、コア業務に集中できる。 - 継続的なフォローアップ
定期レポートの納品だけでなく、改善状況を追跡しながらPDCAを回す仕組みを構築しやすい。
ただし、外注で成功するためには期待するレポート内容や指標、納品方法をしっかりとすり合わせることが重要です。次章では、具体的にどのような情報を提示してもらうと効果的かを解説します。
外注で期待できるレポート内容と注意点
アクセス解析を外注する際には、レポートが「どんな指標」や「どのような形式」を含むのかを確認しておく必要があります。曖昧なまま依頼すると、納品されたレポートが自社のビジネスにマッチしなかったり、せっかくのデータをうまく活用できなかったりするリスクがあります。
レポート内容の一例
以下のようなポイントを盛り込んでもらうと、施策の効果測定や次のアクションに結びつけやすくなります。
- PV数・セッション数・ユニークユーザー数
サイト全体の訪問ボリュームを把握し、トレンドを掴む。 - 直帰率・離脱率
コンテンツ内容やサイト導線の品質を確認する目安。 - 滞在時間・ページビュー(訪問あたり)
ユーザーがどの程度サイトに興味を持って滞在しているか。 - コンバージョン数・コンバージョン率
資料請求や商品購入など、サイトが最終的に目指すゴールの達成度を測定。 - デバイス別アクセス・ブラウザ別アクセス
モバイル対策や対応ブラウザを最適化するためのデータ。 - 流入経路(オーガニック検索、広告、SNSなど)
どこからユーザーが流入しているかを把握し、効果的なチャネルを強化する材料に。 - 重要ページのアクセス推移
新商品ページやサービス概要ページなど、特に力を入れているページの成果を追う。
また、外注で注意すべきこととしては、単に数値を羅列するだけでなく、解釈や改善施策の提案まで含まれているかを確認する点が挙げられます。専門的な分析をしてもらっても、結果をどう活かすかが明確でないと、レポートを見ても次のアクションが分からず、結局活用できないという事態に陥りがちです。
レポートの代表的な指標・KPIの例
レポートにはさまざまな指標を盛り込めますが、すべてを追いかけると分析が散漫になりがちです。自社サイトの目的やビジネスモデルを踏まえて、重要指標(KPI)を定め、そこを重点的にモニタリングすることをおすすめします。以下の表は、代表的な指標とその特徴・活用例の一部をまとめたものです。
| 指標 | 目的・特徴 | 活用例 |
|---|---|---|
| セッション数 | サイト全体の訪問回数を測る | プロモーション実施後のアクセス増加をチェック |
| 直帰率 | 最初のページだけ見て離脱した割合 | コンテンツの質や導線改善の優先度を判断 |
| コンバージョン率 | 目標達成(購入、問い合わせなど)数の割合 | 広告キャンペーンやページ改修の効果を比較 |
| 流入チャネル別PV | チャネルごとのアクセス数 | SNSや検索エンジンなど、注力チャネルを把握 |
| モバイル比率 | 携帯端末からのアクセス割合 | モバイル対応・スマホUI改善の優先度を検討 |
| 平均滞在時間 | サイト内でどれだけ時間をかけてコンテンツを見ているか | 興味度合いや読みやすさ、ユーザビリティ向上の指標に |
このような指標は多岐にわたりますが、あれこれと欲張るよりも、まずは売上や問い合わせ増加につながりやすいKPIを中心に据えると、レポートの内容がシンプルになり、意思決定に活かしやすくなります。
レポート作成のプロセスと発注時のポイント
アクセス解析レポートを外注する際は、ただ分析ツールからデータを引っ張り出して集計してもらうだけでは十分とは言えません。自社の課題に合わせて必要なデータを選び、明確な目的を共有することが重要です。
一般的なレポート作成の流れ
| 作業工程 | 内容 | 自社での対応 or 外注先への要望 |
|---|---|---|
| 目的・KPIの設定 | サイトの目指すゴールや注力ページを明確化 | 事前に自社の経営目標・施策目標を共有 |
| データ取得・集計 | 指定ツールからのデータ抽出、ExcelやBIツールでの集計 | 外注先にツール連携方法を伝え、アクセス権限を設定 |
| 分析と考察 | 数値の増減理由や改善余地を検討 | 自社の顧客層やビジネス背景を伝え、分析精度を高めてもらう |
| レポート作成 | グラフ化や指標ごとの見やすい形式への落とし込み | レポートのテンプレートや期待形式を事前にすり合わせる |
| 改善施策の提案 | レポート結果をもとに施策や次のアクションを提示 | 具体的な手法だけでなく、費用感や工数も簡単に示してもらう |
| フィードバック・修正 | レポートの内容を確認し、追加情報や指摘を反映 | 定期的なミーティングやチャットで、疑問点をすぐに解消 |
上記の流れを踏まえ、あらかじめ「どの段階まで外注先がサポートしてくれるか」を確認することで、納品後に「ここまでは対応してもらえないと思わなかった」といったミスマッチを防げます。また、最終的に自社の意思決定にスピーディーに活かすためにも、レポートの納期やフィードバックのタイミングを明確に決めておくとスムーズです。
外注先の選び方や費用相場の考え方
アクセス解析レポートを外注するにあたって、どこに頼めばよいか迷うことも多いです。費用を抑えたい一方で、専門性やサポート品質にもこだわりたいと考える中小企業は多いでしょう。そこで、外注先の比較ポイントを押さえておくと、選定がスムーズになります。
外注先の比較ポイント
- 専門性・実績
解析ツールの使い方だけでなく、Webマーケティング全般の知見を持つか。類似の業種やビジネス規模での実績があるか。 - コミュニケーション体制
レポート納品だけではなく、定期的な打ち合わせやチャット対応のスピード感。 - 契約形式・費用形態
月額定額制か、スポットでの依頼か、成果報酬的な部分が含まれるか。 - レポートの分かりやすさ
サンプルレポートを見せてもらい、グラフの多さ・注釈の丁寧さなどをチェック。
費用相場の目安と選び方
次の表は、アクセス解析レポートを外注する際の費用形態や特徴を簡単にまとめた一例です。(金額の具体的な数値は示さず、相対的な比較で紹介します。)
| 依頼形態 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 月額定額プラン | 月次レポートと簡単な改善提案がセットになっている | 継続的にデータを追いかけ、常に最新のサイト状況を把握したい場合 |
| スポット単発依頼 | 必要なタイミングだけレポート分析を依頼 | 新商品のローンチ時や短期キャンペーンなど、ピンポイントで使いたい場合 |
| コンサルティング契約 | レポート作成に加えて継続的な施策提案・運用サポートが含まれる | 社内リソースが少なく、施策実行も含めてトータル支援を受けたい場合 |
どの形態が自社に合うかは、サイトの運用体制や予算、目的によって異なります。レポートのクオリティだけでなく、施策実行まで視野に入れるのであれば、コンサルティング契約を検討するのもひとつの選択肢です。
レポートの活用事例・具体的な使い方
「レポートがあれば何か変わるだろう」と思っていても、実際にどのように使えばよいのか分からず、放置してしまうケースは少なくありません。ここでは、レポートをどのように活用して成果に結びつけるか、その例を挙げてみます。
- 経営会議での報告資料として
数値の変化に一喜一憂するだけでなく、「前期比でリード獲得数が伸びた理由」「問い合わせ率が下がった要因」などを客観的なデータで示し、意思決定の根拠とする。 - サイトのコンテンツ企画に活かす
ページ別の閲覧数や滞在時間を見て、人気コンテンツの特徴を分析し、新たなコンテンツの企画へ繋げる。 - 広告やSNSマーケティングの評価
アクセス経路別のPVやコンバージョン率を見て、広告キャンペーンの費用対効果を把握し、SNS運用の強化ポイントを見極める。 - ターゲットセグメントの見直し
地域別アクセスやユーザー層のデータを確認し、想定ターゲットと実際のユーザー層とのズレを修正する。 - UX改善の優先度決定
離脱率が高いページや導線が悪い箇所を洗い出し、改修の優先度を決める。
このように、レポートを「データ確認」だけで終わらせず、次の施策にどうつなげるかが重要です。外注先に報告してもらった情報を、経営や集客戦略の具体的な検討材料として落とし込みましょう。
まとめ
アクセス解析のレポートを外注する際は、単純に数値を示してもらうだけでなく、自社に本当に必要な指標や分析が含まれているかどうかをしっかり確認することが大切です。レポートの形式や納品頻度を事前に取り決めることで、納品後の運用や改善提案がスムーズになります。また、外注先の専門性やサポート体制を見極め、必要に応じて継続的なコンサルティングを依頼することで、より効果的にサイト改善を進められるでしょう。
レポートはあくまでも現状を示す「データのまとめ」であり、最終的なアクションを起こすのは社内の担当者や意思決定者です。データを有効に活かすために、外注先とうまく連携しながら、自社の状況や事業方針に合ったアクセス解析の仕組みを構築してください。






