Blog お役立ちブログ
制作費削減のための小規模企業LP対策
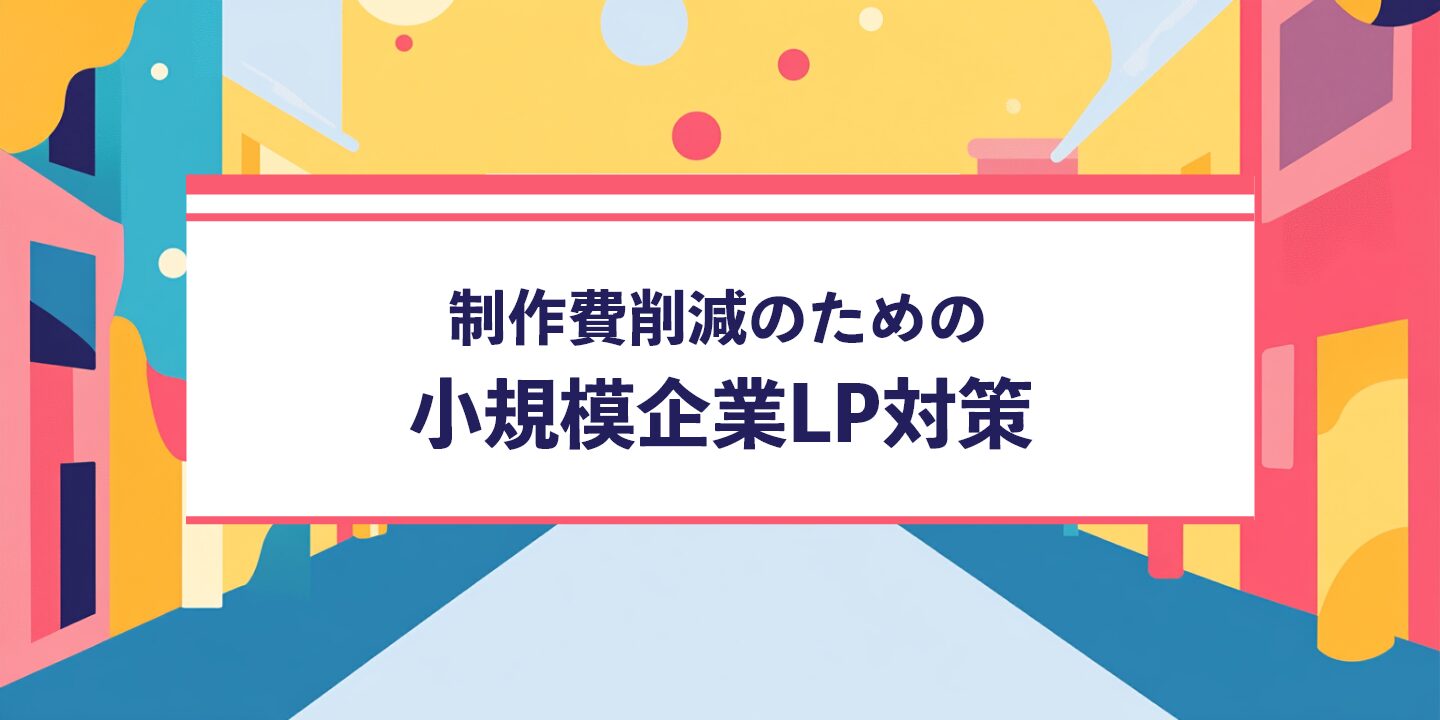
はじめに:1ページ構成(LP)の基本理解
中小企業がWebサイトを立ち上げる際、制作費の負担はできるだけ抑えたいというのが正直なところでしょう。その中で「1ページ構成のランディングページ(以下、LP)」を利用する方法が注目されています。1ページに情報を集約し、長いスクロールで完結させるスタイルを採用すれば、余計なページ数を増やさずに制作コストを圧縮しやすいと考えられます。
とはいえ、「LP」という言葉を聞いたことがあっても、具体的にどんな効果があるのか、どう作るのが正解なのか、よくわからないケースも多いのではないでしょうか。また、1ページに情報を詰め込むと読みにくさや離脱率の上昇が心配になるかもしれません。そこで本記事では、1ページ構成を検討している小規模企業の視点から、LPの基本やメリット・注意点、制作費や運用コストに関する考え方まで、幅広く解説していきます。
1ページ構成を選ぶメリットと注意点
まずは1ページ構成(いわゆるLP形式)を選ぶ際のメリットと注意点をまとめておきましょう。ここでは以下の表に整理してみます。
| 項目 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| デザイン面 | ・余分なページを作らないためデザイン制作の範囲が限定されコスト削減につながりやすい ・視覚的に一貫した世界観をつくりやすい | ・ページが長くなるため全体のバランスを考えたデザインが必要 ・1ページに大量の情報をまとめると見づらさが出る可能性 |
| コンテンツ構成面 | ・訪問者を1ページで完結する導線に誘導できる ・伝えたい情報をストーリー仕立てに組み込みやすい | ・情報量が増えすぎるとスクロールが長くなりすぎる ・途中離脱を防ぐために見出しや区切りの工夫が必須 |
| 制作・運用コスト面 | ・ページ数が少ないほど一般的には制作費を抑えやすい ・管理画面が複雑にならず運用がシンプル | ・1ページに集約した結果、後から情報を追加・更新するときにレイアウトを大きく変更する必要がある場合がある ・ページ速度に注意が必要 |
| 集客・マーケティング | ・特定の商品・サービスに集中して訴求できる ・LPへの流入を計測・改善しやすい | ・複数の商品や複雑なサービスを扱う場合は情報不足になる可能性 ・SEO対策としてはコンテンツ量やサイト構造の最適化が必要 |
1ページ構成を選ぶ最大のメリットは、特定のテーマに絞って内容を深堀りしやすい点と制作・運用コストの削減が期待できる点です。しかし、注意点としては「情報を詰め込みすぎると離脱が増える」「後から修正やコンテンツ追加をする際に手間がかかる」などが挙げられます。この両面を理解し、あらかじめ慎重に設計しておくことが重要です。
LP(ランディングページ)の目的と効果
LP(ランディングページ)とは、特定のサービスや商品の購入、問い合わせ、資料請求など、訪問者のアクションを高めることを目的としたページです。1ページ構成であっても、複数ページ構成であっても「訪問者が最終的に行動を起こしたくなるように情報を整理・演出しているか」が鍵になります。
多くの中小企業がLPを活用する理由は、次のように整理できます。
- 訪問者の集中力を途切れさせない
ページを分割せずに1つの流れで読んでもらうことで、複雑な移動が不要になり、訪問者をスムーズにコンバージョン(問い合わせや申込みなどの行動)へ導きやすくなる。 - 特定の商品・サービスに注力できる
コーポレートサイトなどでは企業全体の情報を分かりやすく載せる必要があるが、LPは1つのターゲットや訴求点にフォーカスできる。 - 効果測定と改善がしやすい
流入経路や離脱ポイントが比較的明確になるため、どの部分を変更すれば成果が上がるのか検証しやすい。
とはいえ、「LPを作るだけで成果が出る」というわけではありません。実際にはページのデザイン、コンテンツの見せ方、CTA(行動喚起)ボタンの配置など、細かい要素を適切に組み合わせることが必要です。特に1ページ構成の場合は、長いスクロールで読み進められるように全体の流れを工夫することが求められます。
下記の表で、LPが一般的なWebサイト(複数ページのコーポレートサイトなど)と比べてどのような特徴を持つかを簡単にまとめます。
| 比較項目 | LP(ランディングページ) | 一般的なWebサイト |
|---|---|---|
| 目的 | 特定のアクション(購入、問い合わせ、資料請求など)を獲得することに特化 | 企業情報や商品・サービス情報など多岐にわたる情報発信 |
| ページ構造 | 1ページまたは少数ページに情報を集約し、ストーリー性を意識 | 複数ページを階層的に分けて多数の情報を包括 |
| コンテンツの方向性 | 訪問者の悩みと提供価値を直接結び付け、強く訴求する | 企業理念、採用情報、製品一覧など幅広い情報を網羅 |
| デザイン・レイアウト | 集中力を維持するための視覚効果(画像、アイコン、CTAボタンなど)を駆使 | デザイン性よりも全体の情報量をわかりやすく整理する必要がある |
| 効果測定・改善 | ユーザーの流入~離脱までを一つのページ内でトラッキングしやすく、改善方針が立てやすい | 全体のアクセス分析は可能だが、ページが多いためどこを優先的に改善するかが把握しにくい場合がある |
1ページ構成でLPを作る意義は、「訪問者を迷わせない導線」「メリハリのある訴求」を実現することにあります。そのためには、企業が伝えたい情報の取捨選択が重要であり、ときにはサービスや商品の良さを端的にまとめるためのライティング技術も求められるでしょう。
長いスクロールページで意識すべき構成要素
1ページ構成のLPは、必然的に縦に長いスクロールページになることが多いです。長いページだと途中で飽きられて離脱されるリスクがあるため、構成をしっかり考える必要があります。訪問者が「先を読みたい」「最後までスクロールしたい」と思うように、以下のポイントに注意するとよいでしょう。
- 冒頭のキャッチコピー
最初に目に入る部分で「このページは何を扱っているのか」「どんなメリットがあるのか」を明確に打ち出す。ここが弱いとすぐ離脱される可能性大。 - セクションごとの見出しやビジュアル
ページが縦に長いほど、見出しや画像、アイコンなどでリズムを作り、読者の興味を引き続ける工夫が必要。文章が長く続くと退屈しがちなので、コンテンツを区切る見出しデザインが大切。 - 具体的な事例や数字を示す
長い文章よりも具体的な利用シーンや成果例があるとイメージしやすい。また、過度に数字を多用しなくても、イメージ図や簡単なチャートなどで要点を示すと効果的。 - ストーリー性とメリハリ
問題提起(悩み)→解決策(自社の提案)→効果や事例→問い合わせ・購入といった流れを意識する。1ページでも物語を読むように自然と読み進められることが理想。 - 呼びかけやボタン配置のタイミング
ページが長い場合、行動を起こしてもらうためのボタンやフォームは1ヶ所だけでなく複数用意することが多い。けれども、押し付けがましくならないようにテキストや配置に工夫を凝らす必要がある。
これらの要素をバランスよく盛り込みながら、あくまで「訪問者の目線」を忘れずにページを構成することが鍵です。
具体的なデザイン・コンテンツの作り方
具体的なLPのセクション構成は、商品やサービスの性質によって異なりますが、一般的な流れの例を示してみます。
- ファーストビュー(最初に見える部分)
- キャッチコピー、主要イメージ、簡単なCTAなどを配置
- サービスの特徴や魅力を端的に伝える
- 課題提起と共感
- 「こんな悩みはありませんか?」と問いかけ、読者に共感してもらう
- その悩みを放置すると何が問題かを示す
- 解決策の提示・特徴説明
- 自社(または自社サービス)の強み、他社との違いなど
- 具体的にどのように悩みを解決してくれるのか
- 事例・実績紹介
- 実際にサービスを利用した顧客の声や成果(可能な範囲で)
- 数字や簡単なグラフ、写真などのビジュアル要素を使うと説得力アップ
- 料金プランまたは導入ステップ
- 料金体系や申し込みの流れなど、読者が「自分にもできそう」「費用対効果が良さそう」と思える説明
- 問い合わせ・申し込みフォーム
- ページの最後だけでなく途中にもCTAを設置する場合がある
このようなセクションを組み合わせて長いスクロールページを形成します。あとはデザイン面で、視線誘導を考慮した色使い・レイアウトを工夫し、読み手がストレスなく内容を理解できるよう配慮することが重要です。
次の表で、セクションごとのポイントをシンプルにまとめてみました。
| セクション | 目的・内容 | デザイン/コンテンツのポイント |
|---|---|---|
| ファーストビュー | 最初に注目を集め、興味を惹く | 大きな文字のキャッチコピー、目を引くイメージ、ボタンの配置 |
| 課題提起と共感 | 読者が抱える悩みを代弁し、「自分のことだ」と感じさせる | 箇条書きやシンプルな言い回しで、読みやすさを重視 |
| 解決策の提示・特徴説明 | 製品・サービスの強み、メリットを分かりやすく示す | 図解やアイコンを活用してビジュアル化 |
| 事例・実績紹介 | 信頼感の醸成、具体的なイメージを提供 | 写真や実際の成果イメージがあれば効果的 |
| 料金プラン・導入ステップ | 具体的な費用対効果や導入プロセスを示し、行動へのハードルを下げる | 価格の見せ方を工夫(例:月額○円〜、プラン比較など) |
| 問い合わせ・申し込み | 最終的なアクションに誘導する | ページ最後とページ中ほど、2か所以上にフォームやボタンを設けると機会損失を防ぎやすい |
上記はあくまで一例ですが、これを参考に「訪問者の読み進める順序」と「掲載情報の優先順位」を意識しておくと、1ページ構成のLPでもスムーズに訴求を行いやすくなります。
制作費削減と運用コストの考え方
「1ページ構成なら制作費が安くなる」というイメージは確かにありますが、実際には以下のような点に気をつける必要があります。
- デザインやコンテンツの質が重要
短い開発期間や安い費用で作ろうとすると、どうしてもデザインやコンテンツのクオリティが落ちてしまうことがある。最終的に「成果が出ないページ」になっては意味がない。 - 後からの修正・改修に備える
1ページにすべてを詰め込むと、後日新たな情報を追加するときにページ全体を組み直す必要が生じる場合がある。制作時点で修正に強いデザインやCMS構成を考慮しておくと、結果的に長期的なコストを削減できる。 - 適度なコンテンツ量と読みやすさのバランス
文字数を減らしすぎると魅力が伝わりにくくなるが、増やしすぎると読みにくい。制作コストを下げつつ効果を狙うには、必要十分な情報量を厳選するスキルが必要になる。 - 運用担当者の知識と時間
外注するか、社内で担当者を置くかによって費用の発生箇所が変わる。簡単な更新は内製化し、大幅なデザイン変更は外注するといったハイブリッド方式も選択肢になる。
1ページ構成のLPだからといって、必ずしも制作費が「激安」で済むわけではありませんが、複数ページ構成のサイトに比べると管理範囲が少なくなるため、総合的には削減しやすいメリットがあります。とはいえ、肝心なのは「費用対効果」。どれだけ安く作っても、集客や問い合わせがゼロでは意味がありませんから、適度に予算を投下して納得いく品質を目指すのが理想です。
表を用いた比較・まとめ
ここまで述べた内容を再確認するために、以下にポイントをまとめた比較表を示します。1ページ構成のLPと複数ページ構成の一般的なWebサイトを比べる際、制作・運用・効果などの観点でざっくり把握しておくと良いでしょう。
| 観点 | 1ページ構成のLP | 複数ページ構成のWebサイト |
|---|---|---|
| 制作費用の目安 | ページ数が少ないため基本的には安価になりやすい ただし、デザイン・コピーに工夫が必要 | ページ数や機能が多いほど費用がかさむ 内容が整理されていれば外注管理もしやすい |
| デザインの自由度 | ページ全体を一貫したデザインで魅せやすい 長いスクロールに向いた視線誘導設計が必要 | ページごとにデザインを変える余地はあるが、全体としての統一感を保つ工夫が必要 |
| コンテンツの訴求範囲 | 1つのサービス・商品に特化した深掘りに向く 複数の訴求点がある場合は情報量とのバランスが課題 | 企業全体、複数サービス、採用情報など多岐にわたる情報を整理しやすい ただしLPほど一点集中は難しい |
| 運用・更新のしやすさ | 1ページゆえ更新箇所が分かりやすい ただし大幅改修時は全体レイアウトを見直す必要あり | ページごとに分かれているため、部分的な更新がしやすい 更新担当が複数いる場合は管理ルールが必要 |
| 集客効果・改善の方向性 | 訪問者の行動導線を測定しやすく、改善ポイントが明確になりやすい | いろいろな情報を提供できるが、アクセス解析やページ間の導線設計が複雑になりがち |
中小企業の場合、訴求すべき商品やサービスがそれほど多くないケースも多いでしょう。その場合は、1ページ構成のLPを活用することで、制作費を抑えつつも集客効果を得やすくなる可能性があります。ただし、将来的に事業領域や商品ラインナップが増えたときにどう運用していくかも想定しておくと、後々の負担を減らせるでしょう。
更新・改善の進め方とポイント
LPを一度作ったら終わり、ではなく、アクセス状況や問い合わせ数を見ながら定期的に改善していくことが大切です。ここでは更新・改善の進め方のポイントをいくつか挙げます。
- ページ分析ツールで離脱ポイントを把握
ページのどこで閲覧をやめる人が多いかを把握すると、改善すべきセクションが見えてきます。例えば、課題提起の段階で離脱が多ければ、「表現が大げさすぎないか」「読者の悩みに合っているか」を見直す必要があります。 - フォームやボタンのクリック数を確認
CTAボタンのクリックや問い合わせフォームへの遷移など、具体的な行動データを追いかけることで、配置や文言の調整をする際の根拠が得られます。 - 必要に応じて複数パターンをテスト
見出し文言、ボタンの色や位置などを変えてテストしてみると、どちらがより成果につながりやすいかを検証できます。大きな改修をする前に、こうした小規模なテストを繰り返すのが賢明です。 - 訪問者の声を活かす
問い合わせ時の質問内容やアンケートなどに目を通し、どんな点がわかりにくかったか、何を求めているかを聞き取ると、ページコンテンツの改善につながります。 - 技術的なメンテナンスも定期的に
画像の最適化や、ページ速度を遅くする要因の除去などはLPの離脱率を下げるうえで重要。1ページ構成の場合、ページ速度が遅いと途中で離脱されやすいので注意しましょう。
こうした改善を繰り返すことで、制作費を抑えながらも「効果的にアピールできるLP」に近づけることができます。最初に完璧を目指しすぎてコストが膨らむよりも、最低限の品質でリリースしてから段階的にブラッシュアップする方法を検討するのも一つの手です。
まとめ
1ページ構成のランディングページ(LP)は、中小企業が制作費を削減しつつ集客や問い合わせ増加を狙ううえで有力な選択肢となります。長いスクロールページは、訪問者に対してストーリー性を持って情報を伝えやすい反面、情報過多になりやすい点には注意が必要です。デザインやコンテンツ構成、ボタン配置などをしっかり設計し、更新時のメンテナンス性も見越して準備することで、費用対効果の高いLPを実現できます。
また、1ページ構成という特性上、離脱率やページ速度の影響を受けやすいため、改善サイクルを回し続けることが大切です。自社の目標(問い合わせ、購入などのコンバージョン)を明確にしながら、アクセス状況やユーザーの反応を踏まえて柔軟にコンテンツを変更していきましょう。最初に大きく費用をかけすぎず、テストや修正を通じて少しずつ成果を高める運用が、長い目で見ると効果的な手法となります。






