Blog お役立ちブログ
ネットショップの商品説明文はどう書けばいい?魅力を伝える具体手法
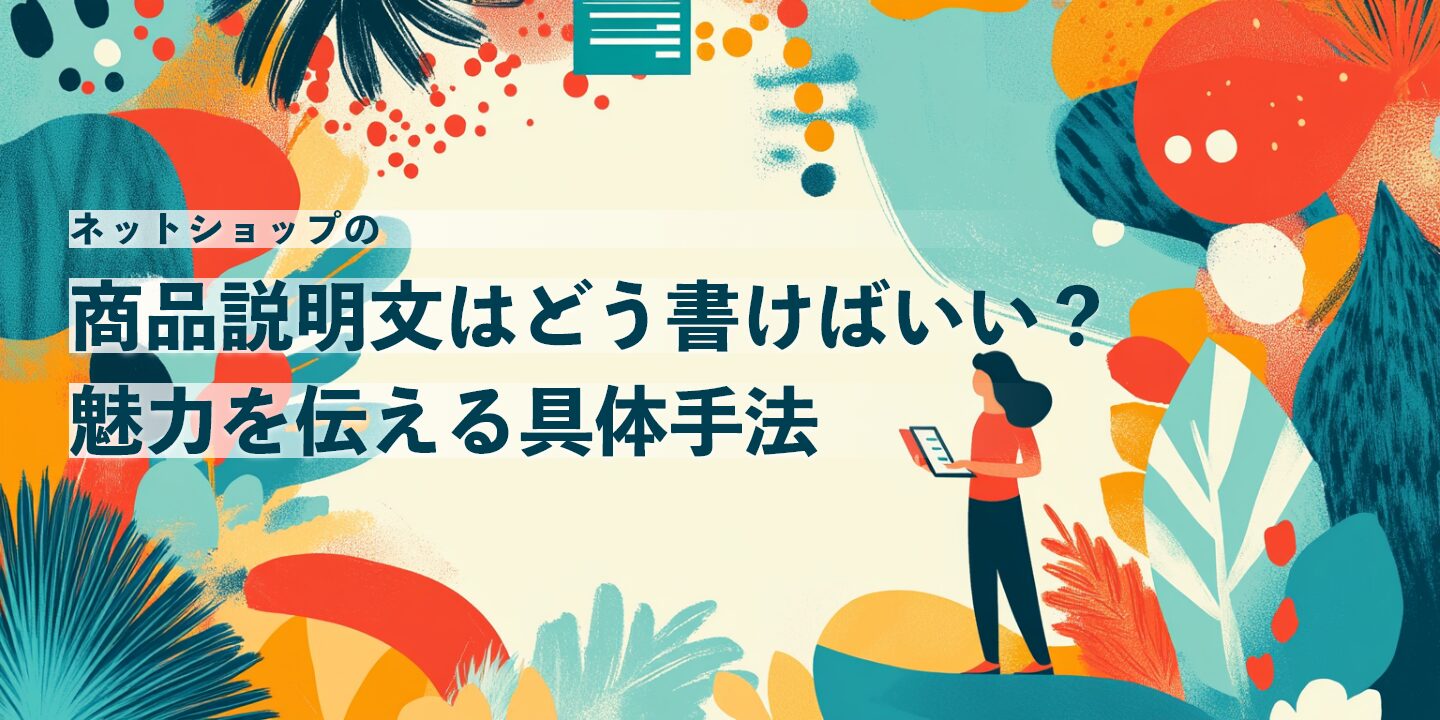
ネットショップの商品説明文が重要な理由
ネットショップを運営するうえで写真やスペック情報は欠かせません。しかし、それらを羅列するだけでは肝心の商品価値が十分に伝わらないことが多々あります。特に中小企業のネットショップでは、大手と比べて知名度や広告予算が限られ、文字情報でいかに魅力を伝えられるかが重要な勝負どころです。
なぜ商品説明文が重要なのかというと、実店舗と異なりオンラインでは実物に触れることができないからです。ユーザーは購入前にできる限り多くの情報を収集し、想像しながら購買を検討します。このとき「使っているイメージ」が浮かべられるような説明や、信頼感を得られるような言葉があると、購入へのハードルが下がります。逆に、情報が少ない・曖昧・魅力が伝わりづらい説明だと、ほかのショップや商品に流れてしまうケースも出てくるでしょう。
特に初心者や零細企業の皆さまからは、以下のような声がよく挙がります。
- 「写真と簡単な説明だけでは、本当に買ってもらえるか不安」
- 「文章を書くのが苦手で、一行だけの説明文になってしまう」
- 「サイトを見直しても、どこが良いのかわからないという声を受ける」
こうした悩みは決して特別なものではありません。多くのショップが同じように悩んでいるからこそ、しっかりと商品の魅力を伝える技術を身につけると差別化につながります。
では、どうすれば「読んで買いたくなる商品説明文」を書けるのか。これから詳しく解説していきます。
商品説明文でよくある失敗例
1. スペックや機能のみを羅列して終わり
通販サイトでありがちなのが、カタログのように数値だけを並べているパターンです。たとえば洋服なら「素材:コットン100%、カラー:赤、青、黒」だけで終わってしまい、そのアイテムの強みや着用イメージが伝わりません。結果として、ユーザーは興味を持てずに離脱してしまいます。
2. キャッチコピーだけで実態がわからない
もう一つの失敗例は、流行り言葉を使って商品の“雰囲気”だけを強調し、具体的なメリットが書かれていないケースです。キャッチーなフレーズだけでは興味を引くだけにとどまり、その後ユーザーが得られる価値を説明しなければ説得力を失ってしまいます。
3. 長文だが要点が不明瞭
一生懸命にたくさん文章を書いたとしても、読み手が欲しい情報がうまく整理されていないと意味がありません。たとえば長文なのに段落わけがなく、要点が埋もれて読みにくい文章だと逆効果です。結果として最後まで読んでもらえず、購買意欲を喚起しにくくなってしまいます。
読者の購買意欲を高めるライティングの基本要素
- ターゲットを想定する
ネットショップを訪れるユーザーは、商品によってニーズが異なります。たとえばギフト目的で買う人と自分用に買う人とでは、求める情報が違うはずです。事前に「誰に向けて書いているのか」を想定しておくことが大切です。 - 読みやすいレイアウト・構成
視線が流れやすいように、適切に段落を分け、見出しを挿入しておくと読者の理解度が高まります。また箇条書きを活用してメリットや特徴をまとめると、要点を素早く把握してもらえます。 - 具体例・使用シーン
ただ「便利です」と言うだけでなく、「たとえば外出先で、サッと取り出して使えます」といった使い方を示すと、ユーザーが購入後のイメージをしやすくなります。想像力を働かせる手助けをするのが文章の役割です。 - 商品のメリットと購入後の未来を描写
「この商品を買うと、どのような問題が解決され、どんなメリットが得られるのか?」を言語化します。たとえばダイエット器具なら、「日々の運動習慣が続けやすくなり、より健康的な生活に近づけます」というように、購入後のプラスの変化を想起させることがポイントです。
商品説明文の構成・レイアウトのポイント
構成やレイアウトをしっかり整えれば、ただ文章を増やすより効果的に読者に情報を伝えられます。たとえば下記の順序で書くと、情報をスムーズに理解してもらいやすくなります。
- キャッチコピーまたは商品名
- 短いフレーズで興味を引く
- 商品の特徴・スペック
- サイズ・素材・機能などの必須情報
- 使用シーンや具体的なメリット
- イメージしやすい具体例
- 詳細な説明やブランドストーリー
- 信頼感を持たせる企業・製品の背景
- アフターケアや注意点
- 安心感やリスク回避につながる情報
これをきちんと区分するだけでも、読み手にわかりやすい文章になります。
よくあるミスと解決策の比較表
| ミス | 具体例 | 解決策 |
|---|---|---|
| 機能のみ列挙 | 「サイズ:縦30cm 横20cm 重量500g」だけで終わり | ・使用シーンを交えて紹介 ・ユーザー目線でのメリットを追加 |
| キャッチコピーだけで終了 | 「驚きの体験!新感覚を味わえます」 | ・メリット・価値を数値や具体例で裏付け ・購入後の変化を描写 |
| 説明文が長いが要点不明 | だらだらと特徴を並べて結論が曖昧 | ・構成を見直す ・見出し・段落を入れて要点を整理 |
| 同じ表現を繰り返しマンネリ化 | 毎回「弊社独自のこだわり…」だけで終わる | ・文章テンプレートを複数用意 ・実際の活用例や利用シーンを入れ替えながら表現を刷新 |
上記のように、単に情報を並べるだけではなく、ユーザーにとってどんな価値があるのかを明確にすることが鍵です。さらに、購入後のイメージを持ってもらえるような使い方やエピソードを交えると良いでしょう。
訴求力を高める具体的テクニック
- 数字や実績をうまく使う
説得力を高めたいなら、抽象的な言葉より具体的な数字を入れるとイメージしやすくなります。ただし、無理に数字を入れるのではなく、商品の特徴を示すうえで役立つ指標があれば有効に活用するとよいでしょう。 - 専門用語をかみ砕く
商品に専門的な機能や技術がある場合、そのままの用語だけだと理解が難しい場合があります。たとえば「遠赤外線効果」と書くだけではなく、「身体を芯から温めるので寒い冬でも快適に過ごせる」といった解釈を添えると伝わりやすくなります。 - ユーザーの課題を先回りして答える
「洗濯しても色落ちしませんか?」といった疑問に先手を打って回答を載せておくことで、安心感が高まります。FAQ形式でまとめるのもわかりやすい方法です。 - ブランドの世界観を伝える
もし商品の背景にストーリーやブランドの理念がある場合、それを知ることでユーザーは親近感や共感を覚えるかもしれません。商品自体の品質だけでなく、「作り手の想い」や「どんな人に使ってほしいか」といったメッセージを伝えると差別化につながります。
ライティングのステップ表
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. ターゲット設定 | 誰向けにどんなニーズを満たすかを明確にする | ・年齢層や使用シーンを考慮 ・初心者向けか上級者向けか |
| 2. 要素出し | 商品の特徴やスペック、強みをリストアップ | ・スペックとメリットを整理 ・使用シーンや魅力を考慮 |
| 3. 構成づくり | 見出しや段落構成を決め、どの順番で書くか設計 | ・読者が知りたい情報を最優先 ・メリットと具体例を柱に |
| 4. 下書き | 実際に文章を書いていく | ・長くてもOKだが、後で削る ・まずは伝えたいことを全部盛り込む |
| 5. 推敲 | 冗長表現のカット、言い回しの修正、読みやすいレイアウトに調整 | ・段落分けや表・箇条書き活用 ・誤字脱字と重複表現をチェック |
| 6. 最終チェック | 読者目線で「わかりやすいか」「魅力的に見えるか」を再確認 | ・社内メンバーや第三者に読んでもらう ・ブランドイメージと整合性があるか |
このようにライティングを段階的に行えば、漠然と悩む時間を減らせるだけでなく、伝えたい情報の漏れも防げます。下書き時点で文章が長くても問題ありません。その後の推敲でキーワードを最適化し、不要な重複表現などを取り除けば、最終的に洗練された商品説明文が完成するでしょう。
魅力的な説明文を書くための実例・エピソード
ここでは、実際にありがちな商品カテゴリを例にとり、どのように説明文に工夫を加えると読者に刺さるかを考えてみます。
例:ハンドメイドのアクセサリーを扱うネットショップ
- 悪い例
「手作りのブレスレットです。素材は天然石とビーズ。色は3種類あります。」 これだけでは素材が何なのか、どんな雰囲気なのか、どんな想いが込められているのかが不明確です。 - 良い例(改善案)
「天然石を一粒ずつ厳選し、熟練の職人が丁寧に組み上げたハンドメイドブレスレットです。落ち着いた色味の石を使うことで、普段使いからフォーマルまで幅広いスタイルに調和します。たとえばオフィスではシンプルな装いの差し色に、自宅でくつろぐときは心を和ませるお守りとして手元に添えてみてください。石それぞれの持つ個性を生かすため、あえてビーズ同士のスペースにもこだわりを持たせています。」
このように、どのように制作しているのか、どんなシーンで活用できるのかといった具体的な情報を入れると、ユーザーは自分の生活に取り入れた時のイメージを沸かせやすくなります。
SEOとユーザビリティの両立
ネットショップの商品説明文を作るときには、検索エンジンでの評価(SEO対策)も意識したいところです。ただし、SEOだけを意識してキーワードを詰め込み過ぎると、読みにくくなってユーザーの離脱を招く可能性があります。大切なのは「検索エンジンにも伝わりやすい文章」を書きながら、同時に「ユーザーが読みやすい構成」にすることです。
- 適切なキーワード配置
タイトルや見出し、冒頭部分に狙いたいキーワードを自然に取り入れると、検索エンジンにとっても重要な文脈だと判断されやすくなります。ただし無理やりキーワードを詰め込むと不自然な文章になりがちなので、あくまで自然な流れを心がけましょう。 - 重複コンテンツを避ける
同じ商品でも色やサイズ違いがある場合、一言一句同じ説明を使い回すと、検索エンジンから重複コンテンツとみなされるリスクがあります。商品ごとの微妙な違いや特徴を強調するなど、説明文を少しずつ変えてみる工夫が必要です。 - 内部リンクや関連商品リンク
商品説明から関連商品の紹介や、カテゴリー案内へのリンクを適切に貼ることは、サイト内回遊率の向上につながります。ユーザーは興味をもった商品から次の候補を見ることができるので、結果的に滞在時間も増え、SEO評価にもプラスに働く可能性が高まります。
SEO視点とユーザー視点のポイント比較表
| 視点 | ポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| SEO視点 | – タイトルや見出しにキーワードを配置 – 重複コンテンツを避ける – 内部リンク最適化 | – キーワードの過剰詰め込みは逆効果 – 検索エンジンへの最適化だけを考えると離脱率が上がる |
| ユーザー視点 | – 読みやすい文章構成 – 具体例・使用シーンで購入イメージを高める – Q&Aで不安を解消 | – 情報量が多すぎると読むのが大変 – 要点をまとめつつ興味を引くバランスが必要 |
SEOとユーザー体験は対立するものではなく、どちらも大切にしてこそ効果を発揮します。検索エンジンが求めているものは「ユーザーにとって有益な情報が載っているページ」です。つまり読者を第一に考えてわかりやすい文章を書きつつ、検索ロジックにも配慮することが大切だといえるでしょう。
まとめ
ネットショップの商品説明文は、ただ「スペックを並べるだけ」「キャッチコピーだけで終わる」では不十分です。読み手であるユーザーは、商品の魅力や使い方、購入後の生活を具体的に想像したいのです。そのためには、ターゲットを意識し、商品の強みや使用シーンを丁寧に言葉にしていくライティングが求められます。適切に見出しや段落を使い、比較表や画像の配置などで視覚的にもわかりやすく提示すると、離脱を防ぎ、購買意欲を高める効果が期待できます。
またSEOを考慮するなら、自然な形でキーワードを配置し、重複コンテンツを避ける、内部リンクを活用するなど、基本的な対策を押さえておくとよいでしょう。ただし最終的にはユーザーが読みやすく、魅力を感じる内容であることがもっとも大事なポイントです。ライティングの基本ステップを踏みながら、商品説明文をブラッシュアップしていけば、中小企業でも大手と十分に戦える強いネットショップを育てられます。






