Blog お役立ちブログ
ホームページの色合いはどれにしたらいい?迷った時の配色ガイド
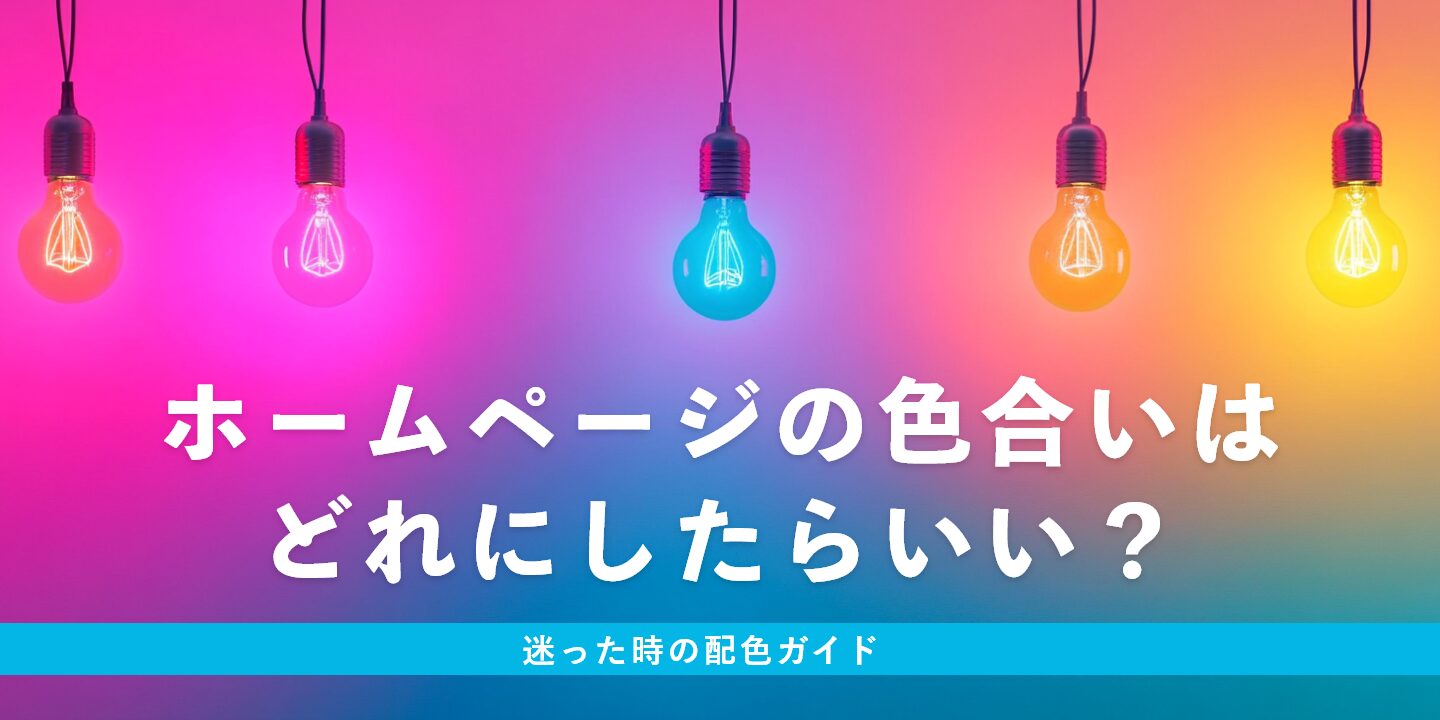
はじめに
ホームページの制作を考えている中小企業の経営者や担当者の中には、「色合いをどう決めたらいいのか」という悩みを抱えている方が少なくありません。特に、ブランドカラーが定まっておらず、どのような基準で選べばいいのか悩んでいる場合は、情報を集めてもかえって混乱しがちです。
予算の問題からデザイナーに丸ごと依頼するのが難しかったり、社内の複数人で検討するうちに意見が錯綜してなかなか決まらなかったり。結局、明確な判断基準がないままに配色を決めてしまい、後々「やっぱり別の色にすればよかった…」と後悔する例も珍しくありません。
本記事では、ホームページの色合いを選ぶ際に押さえておきたいポイントや基本的な配色ルールを整理し、具体的な手順や事例を交えて解説します。専門的な内容もできるだけ分かりやすく噛み砕き、実務に直結する形でお伝えしますので、初めて色選びをする方や、社内でなかなか意見がまとまらない方はぜひ参考にしてみてください。
ホームページの色合いが重要な理由
ホームページの色合いは、訪問者の印象や行動に大きく影響を与えます。視覚情報は人の脳で処理される情報の中でも優先度が高いため、色やデザインの印象がそのまま会社や商品・サービスへのイメージにつながりやすいのです。ここでは、色合いがもたらす重要性を大きく3つの観点から見ていきましょう。
1. 第一印象を左右する
訪問者がホームページにアクセスして、最初に目に飛び込んでくるのは色やレイアウトです。文字を読む前に「なんとなくの雰囲気」で好き嫌い、信頼できるかどうかを判断するケースも珍しくありません。そのため、配色によって「堅実な会社」「クリエイティブでカジュアルな会社」などの第一印象が形成されるのです。
2. 読みやすさと導線設計
色合いによっては文字が読みにくくなったり、ボタンなどの行動喚起要素が目立たなくなったりすることがあります。どんなに良質なコンテンツを掲載していても、色の組み合わせが悪いと訪問者が早々に離脱してしまうことも考えられます。ホームページのゴール(商品購入や問い合わせなど)に導くためにも、色合いによる視認性や可読性をしっかりと確保する必要があります。
3. ブランディングとの整合性
自社のブランドイメージや企業理念と合致した色を選ぶことで、名刺やパンフレット、店舗の看板などその他の販促物との統一感を生み出せます。これにより、訪れた人に「この会社は一貫性がある」という安心感を与えやすくなります。仮に方向性の異なる色をホームページだけで使ってしまうと、せっかくのブランドイメージを損なってしまう可能性があるのです。
色の心理的効果と基本的な配色ルール
色は人の感情や行動に多かれ少なかれ影響を及ぼすとされます。例えば赤は「情熱」や「危険」と結び付きやすく、青は「冷静」「信頼」といった印象を与えやすいともいわれます。こうした色彩心理をホームページの配色に活かすことで、より狙い通りの印象を与えることが可能です。しかし、あまりに理論にこだわりすぎると実用的でなくなってしまいますので、ポイントを押さえる程度で構いません。
色が与える主な印象(例)
以下の表は、代表的な色が与える印象を簡単にまとめたものです。実際には企業や文化、文脈によって異なる場合もありますが、参考程度にご覧ください。
| 色 | 一般的な印象 | 使われやすい業界・場面 |
|---|---|---|
| 赤 | 情熱、エネルギー、危険 | 飲食業、セール広告の強調 |
| 青 | 信頼、冷静、知的 | 金融、コーポレートサイト |
| 緑 | 安心、自然、調和 | 環境関連、健康・医療関連 |
| 黄 | 明るさ、注意、楽しさ | 子ども向けサービス、POP広告 |
| オレンジ | 活発、親近感、暖かさ | キャンペーン、イベント |
| 紫 | 高貴、神秘、独創性 | 化粧品、高級感を演出したい場面 |
| 黒 | 高級感、重厚感、威厳 | 高級ブランド、モダンなデザイン |
| 白 | 清潔感、純粋、余白 | 医療系サイト、ミニマルデザイン |
基本的な配色ルール
続いて、どのような組み合わせで色を選ぶかに関わる「配色ルール」について簡単に整理しましょう。色相環(いわゆる色の円環)をベースに、主に以下のようなパターンがあります。
| 配色パターン | 特徴 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| モノトーン配色 | 同系色や白黒のみを使用し、色数を絞る | 落ち着いた印象、統一感◎。単調になりがち |
| 類似色配色 | 色相環で近い位置にある色を組み合わせる | 優しい雰囲気、調和◎。コントラストが弱く存在感が薄れやすい |
| 補色配色 | 色相環で真逆に位置する色(例:赤と緑)を組み合わせる | インパクト大。目立つが、合わないと刺激が強すぎる場合も |
| トライアド配色 | 色相環を三等分した3色を組み合わせる | バランスのよい配色になりやすい。色が多くなる分、扱い難度UP |
| アクセントカラー | 基本はモノトーンや類似色でまとめ、1色だけ強調 | メインカラーを引き立てつつメリハリを演出。使いすぎ注意 |
こうした配色ルールを把握したうえで、自社サイトに最も合った組み合わせを選ぶのが理想です。ただし、必ずしも理論通りにしなければならないわけではなく、最終的にはターゲット層やサイトの目的を考慮したバランス調整が重要になります。
具体的な色選びの手順
それでは、「実際に色をどうやって選んでいけばいいのか」という具体的な手順を示します。以下の表にまとめてみました。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 目的とターゲットの確認 | サイトの目的(商品販売、問い合わせ獲得、情報提供など)とメインターゲットを再確認 | 売りたい商品やサービス、アプローチしたい層に合ったイメージを頭に描く |
| 競合や業界イメージのリサーチ | 同業他社や業界全体のサイトを調べ、どんな色が多いかチェック | 差別化したいのか、あえて似せたいのかをはっきりさせる |
| キーカラーの決定 | ブランドイメージに合う色をまず1色選ぶ | 心理的効果や業界の常識と照らし合わせながら決定 |
| サブカラーやアクセントカラーの検討 | キーカラーに合わせて2~3色程度を追加し、全体の配色パターンを作る | 配色理論をヒントにしつつ、視認性や読みやすさを考慮 |
| テスト運用 | 試しにデザイン案を作成し、社内外で簡単な意見収集を行う | スマホやタブレットでの見え方もチェックし、違和感がないか確認する |
| 最終調整と実装 | 必要に応じて微調整し、本番サイトへ反映する | 一度配色を決定したら、コロコロ変えすぎないよう注意 |
1. 目的とターゲットの確認
ホームページで「何を実現したいのか」を再度はっきりさせましょう。例えば、ネットショップであれば購買意欲を高める色合いが好ましいですし、コーポレートサイトであれば信頼感や清潔感を重視した色合いにするなど、目的によって必要な印象が異なります。また、ターゲットとなる客層(若い世代なのか、ビジネスパーソンなのか)によっても、好まれる色の傾向は変わります。
2. 競合や業界イメージのリサーチ
自社の業界でどのような配色が主流なのかを大まかにつかむことで、差別化のヒントが得られます。あえて業界の定番色を外して目立つ戦略もあれば、安心感を与えるためにあえて業界標準に寄せる場合もあるでしょう。
3. キーカラーの決定
まずは1色、メインとなるキーカラーを決めます。既に企業のロゴや店舗看板で使われている色があれば、それを基準にするとブランディング面での統一感が得やすいです。特に決まった色がない場合は、心理効果や業界の慣習も参照しつつ、自社の強みや理念を訴求できる色を検討してみてください。
4. サブカラーやアクセントカラーの検討
キーカラーが決まったら、それに合わせてサブカラーやアクセントカラーを追加していきます。色数は多くなりすぎないように注意が必要です。一般的には3色程度(メインカラー、サブカラー、アクセントカラー)が扱いやすいと言われています。
5. テスト運用
いきなり本番サイトに反映する前に、デザイン案をモックアップやテストページで試してみましょう。色彩はデバイスによって見え方が若干異なるため、PCだけでなくスマホやタブレットでも確認します。また、社内メンバーだけでなく、外部の知人やパートナー企業などから客観的な意見をもらうのも効果的です。
6. 最終調整と実装
テスト結果を踏まえて修正が必要であれば、細かい色味の変更など最終調整を行います。ホームページ公開後は、基本的には大きな色の変更は避けた方が無難です。ユーザーは意識せずともサイトの配色から印象を得ているため、コロコロと色を変えてしまうとブランドイメージが固定しにくくなってしまいます。
デザインの事例と配色パターン
ここでは、よくあるホームページの配色パターンの例を挙げてみます。自社の目的やイメージに近いものを探し、参考にしてみてください。
1. モノトーン+アクセントカラー
白と黒、あるいはグレーなどを基調として、アクセントとして1色(例えば赤や青など)を加えるスタイルです。洗練された印象を与えつつ、アクセントカラーを施した部分が強調されるため、ボタンや重要なメッセージを目立たせやすいのが特徴です。コーポレートサイトや士業サイトなど、信頼性を重視するケースでも使いやすい配色といえます。
2. 類似色配色で統一感を出す
例えば青系の色(紺色~水色)だけでまとめたり、緑系の色(深緑~黄緑)でまとめたりして、全体に落ち着いた雰囲気を持たせる手法です。やさしく調和のとれた印象になる半面、コントラストが弱くなるので、アクセントカラーや文字色の選び方に工夫が必要となります。
3. 補色を使って大胆に
緑と赤、青とオレンジといった、色相環上で反対に位置する色を組み合わせると、かなりのインパクトを与えられます。ただし、補色をそのまま同じ割合で使うと、目がチカチカしてしまったり、落ち着かない印象になることがあります。使う場合はメインカラーとアクセントカラーを明確に区別し、片方の面積を大きく、もう片方を小さめに配置するとバランスが取りやすいです。
よくある失敗例と対策
色選びの際に陥りやすい失敗例と、その対策をいくつか紹介します。事前に理解しておくことで、回避しやすくなります。
- コントラスト不足
背景色と文字色の明度差が足りず、文字が読みにくくなるケースです。特に淡い色同士を組み合わせる場合は注意しましょう。対策として、白背景に濃い文字色を使うなど、明度のメリハリを意識します。 - 色数の使いすぎ
せっかくキーカラーを決めても、あれもこれも使いたくなって色だらけになってしまうパターンです。見た目が散らかった印象を与え、どこを注目すればいいのか分からなくなります。対策は、メイン+サブ+アクセントの3色程度に絞ることです。 - 業界イメージと乖離しすぎ
例えば、金融系のサイトなのに派手な原色を多用すると、かえって不安感を煽ってしまう可能性があります。差別化を図るにしても、どこまで冒険していいのかのラインを見極めることが大切です。対策として、ユーザーが求める安心感と、会社の独自性の両立を目指すバランス感覚が必要です。 - スマホやタブレットでの配色を考慮しない
パソコンの大きなモニターでは問題なく見えていても、小さなスマホ画面では彩度が落ちて見づらい…といった事態が起こり得ます。対策として、必ず複数デバイスでテストし、背景画像や文字との組み合わせを確認しましょう。
まとめ
ホームページの色合いをどうするかは、デザイン面だけでなく、事業の方向性やブランドイメージにも大きく関わる重要な問題です。限られた予算の中小企業にとっては、専門家を雇わずに自力で決めることも多いでしょう。しかし、いくつかの基本的な知識と手順を把握しておけば、迷いを最小限にしながら効果的な色選びが可能です。
自社の目的とターゲットをはっきりさせ、競合や業界イメージを調査したうえで、キーカラーを軸にサブカラーやアクセントカラーを選び、複数デバイスでテストする。このプロセスを踏むだけでも、配色の失敗リスクは大きく減らせます。色はサイト全体の第一印象を左右する大事な要素ですから、時間をかけてでも丁寧に検討してみてください。






