Blog お役立ちブログ
ホームページのアクセス数の見方が分からない方へ
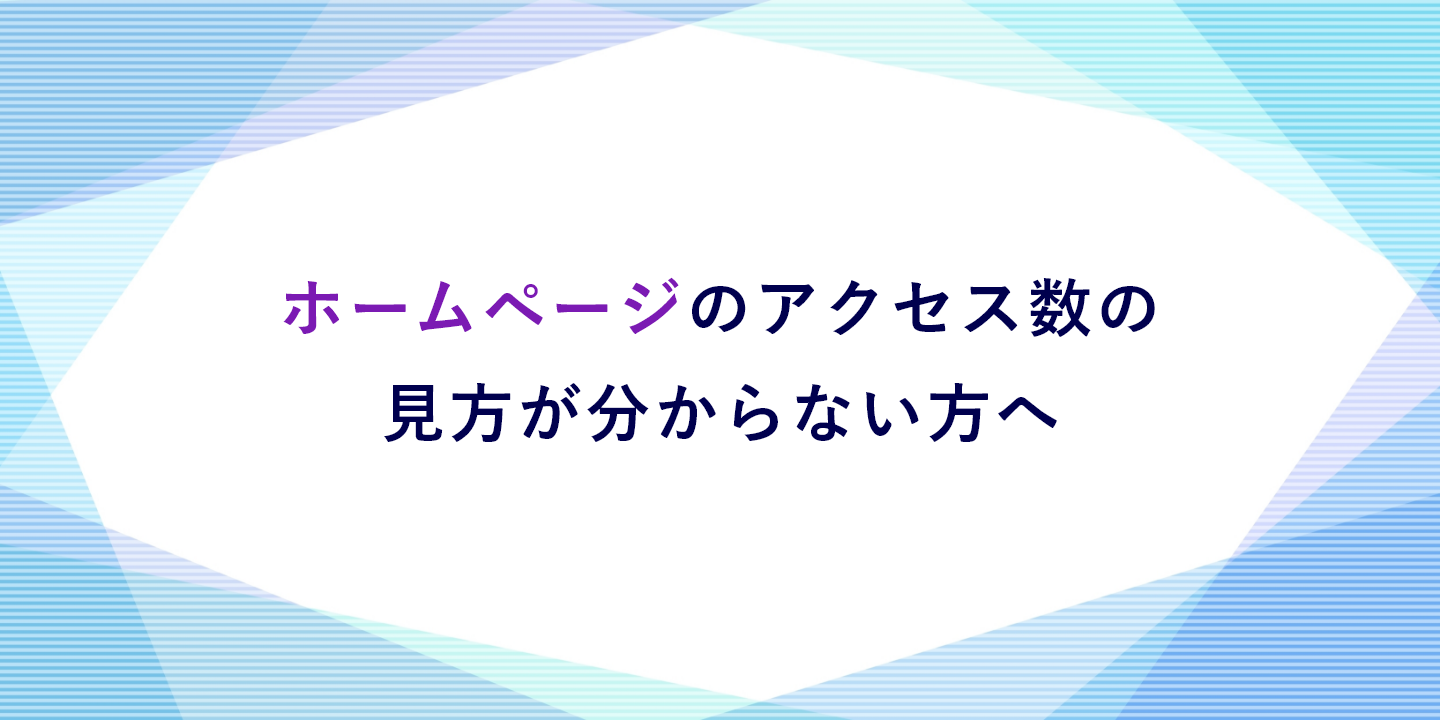
ホームページのアクセス数で迷わないためのやさしい読み解きガイド
はじめに
「アクセス数が増えたのか減ったのか、結局どう判断したらいいの?」──そんな声をよく耳にします。数字は正直ですが、見方を誤ると間違った改善策につながりかねません。今回は専門用語をできるだけかみ砕き、初心者の方でも“今日から”活用できるアクセス解析の考え方をまとめました。この記事を読み終えるころには、自社サイトの数字を「ただのグラフ」から「伸びしろのヒント」へ変換できるようになります。
アクセス解析の前に決めておきたい“たった一つ”のこと
アクセスデータを見始める前に、まず「サイトで実現したいゴール」を一文で言えるようにしましょう。
- お問い合わせを増やしたい
- 資料ダウンロードを増やしたい
- ブランドの認知度を上げたい
目的がはっきりすると、注目すべき数字が自動的に絞られます。たとえば資料DLがゴールなら「ダウンロード完了数」とその前後の動線が最重要です。反対に、ページビュー(PV)がどれだけ伸びてもDL数が変わらなければ施策を見直す必要があります。
まず用意したい3つの無料ツール
| ツール | できること | ポイント |
|---|---|---|
| Google アナリティクス 4(GA4) | 訪問者の行動を記録 | 新規とリピーター、流入経路を丸ごと把握 |
| Google サーチコンソール | 検索キーワードと検索順位 | どの語句でクリックされたかを確認 |
| ヒートマップ(例:Microsoft Clarity など) | ページ内のクリックやスクロール位置 | よく読まれている箇所・離脱箇所が一目瞭然 |
GA4は直帰率の扱いが変わり、「エンゲージメントのないセッションの割合」として再登場しています。加えて“エンゲージメント率”という前向きな指標も用意されているので、両方をセットで見るとユーザー行動がより立体的に理解できます。
覚えておきたい5つの基本指標
- セッション数
- のべ訪問回数。リピーターが多いかどうかは別途確認する。
- ユーザー数
- 「人」の目安。端末が変わると別人扱いになる点に注意。
- ページビュー数(PV)
- 1訪問あたりのPVが増えれば、サイト内を回ってくれている証拠。
- エンゲージメント率/直帰率
- GA4では“10秒以上の滞在”などを満たせばエンゲージメント扱い。直帰はその逆。
- 平均エンゲージメント時間(旧 平均セッション時間)
- 長ければ良いとは限らず、ページの目的に照らして判断。
「指標が多くて混乱する」という場合は、まず目的に直結する1~2項目に集中してください。そのほうが改善も早く、効果を実感しやすくなります。
アクセス数が増減する5つの代表的要因
| 要因 | 具体例 | 主な対策 |
|---|---|---|
| 検索アルゴリズムの更新 | コアアップデートで順位が変動 | コンテンツ品質を見直し、E‑E‑A‑Tを強化 |
| 季節・イベント | 決算期やセール時期 | イベントに合わせた特集や広告 |
| 広告出稿 | 広告停止でアクセス急減 | オーガニック流入の比率を高める |
| SNS・外部メディア | バズで短期的に急増 | SNS導線を整備し再訪を促す |
| サイト速度・UI | 速度低下で離脱増 | 画像圧縮とモバイル最適化 |
要因を特定できれば、打つべき改善策も自ずと決まります。
初心者でもできる7ステップ改善フロー
- 目的とKPI(指標)を確認
- 直近1〜3か月の数字を取得
- 昨年同月や前月と比較し“差”を把握
- 差が大きい箇所を仮説化(例:記事公開日とPV増が一致)
- 施策案を書き出し、工数と効果で優先順位付け
- 上位2〜3案から実行
- 1〜3か月後に再計測し、効果を検証
このサイクルを繰り返すだけで、“数字を見る→施策を打つ→結果で学ぶ”という好循環が生まれます。
SEOの最新視点:数字だけでなく「体験」を伸ばす
Googleは2022年以降、E‑E‑A‑T(経験・専門性・権威性・信頼性)の考え方を強調し続けています。単にアクセスを集めるだけでなく、
- 実際に体験した人の声や写真を載せる
- 著者プロフィールを明記する
- 第三者のレビューや統計データを引用する
といった工夫が評価されやすくなりました。合わせてCore Web Vitals(表示速度・インタラクティブ性・視覚的安定性)の改善も進めておくと、検索だけでなくユーザー満足度も底上げできます。
日常的にアクセスをチェックし続けるコツ
- 自動レポートを設定:GA4の「探索レポート」を週1でメール送信。
- 比較期間を固定:前週比・前年比など、ブレない軸を決める。
- 共有文化をつくる:数字をチームで見ることで次のアイデアが生まれる。
まとめ
アクセス数は「多い/少ない」を眺めるものではなく、サイトを育てる“健康診断書”です。
- ゴールを一文で言えるようにする
- GA4+サーチコンソールで数字の土台を整える
- 指標は目的に合うものから順に確認
- 要因→施策→検証のループを回す
- E‑E‑A‑TとCore Web Vitalsで“体験”を磨く
この5ステップを押さえれば、数字の波に振り回されることなく、ユーザーと検索エンジンの両方から選ばれるサイト運営が可能になります。ぜひ今日から実践してみてください。






