Blog お役立ちブログ
メディア掲載率を上げる!初めてのプレスリリース活用術
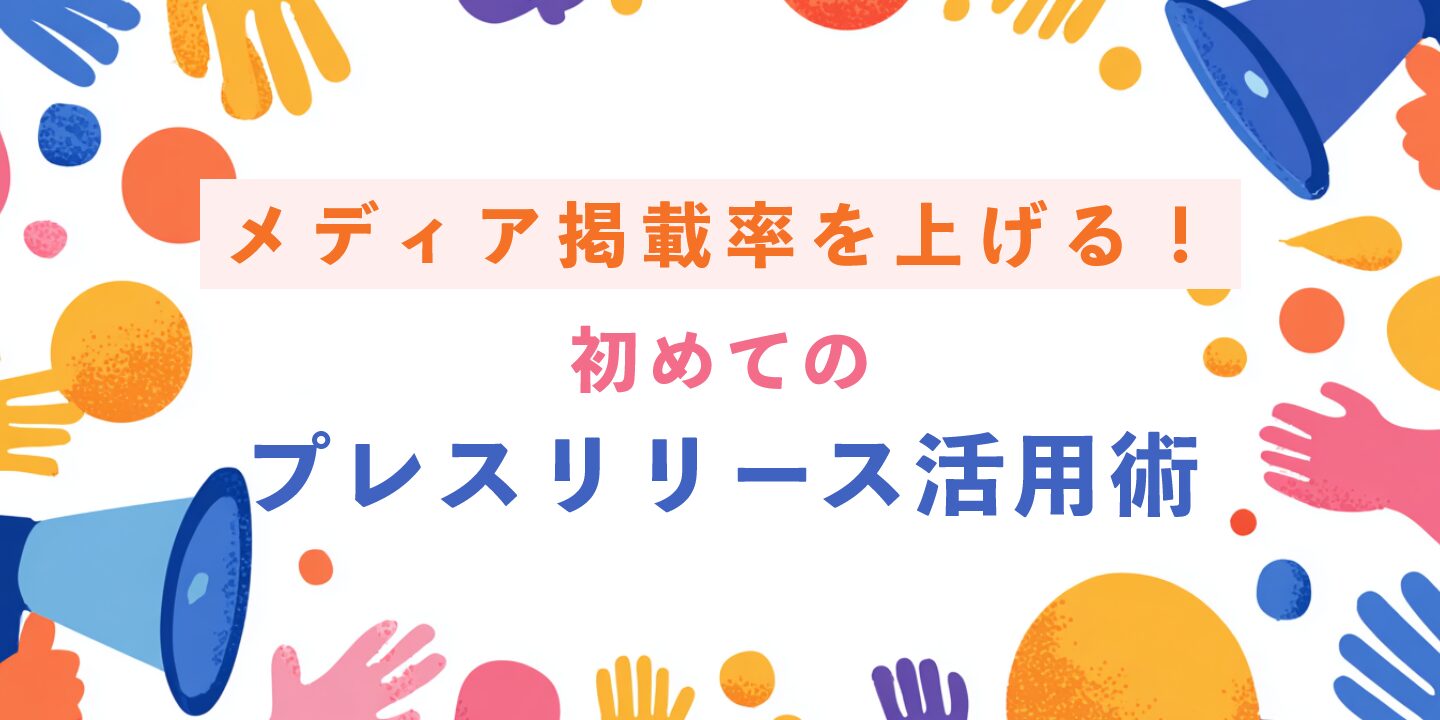
なぜ今プレスリリースなのか
新サービスを立ち上げた瞬間に「どう告知するか」は売上や認知度に直結します。検索広告やSNS広告は即効性がある反面、クリック課金がかさみやすく、しかも「広告」としての印象が強いため信頼形成に時間がかかります。その点、新聞や業界紙、ニュースサイトの記事として紹介されれば、いわば第三者のお墨付きが得られ、費用を掛けずに短期でブランド力を高められます。
プレスリリースはメディア側が記事を書くための“素材”です。記者の目に留まれば、自社の宣伝では届かなかった見込客や取引先、地域住民にまで情報が波及します。さらに検索エンジン上での指名検索や被リンク獲得にも寄与するため、長期的なSEO効果も見込めます。
とはいえ「書いたことがない」「どこへ送ればいいかわからない」という声は少なくありません。本記事では、外注費を抑えつつ掲載率を上げるための実践的な手順を解説します。
メディア掲載率を高める3つの視点
- ニュースバリュー – 読者が「知って得をするか」「社会的意義があるか」を軸にネタを磨く
- タイミング – 媒体ごとの締め切りと記者の行動パターンに合わせ、送付日と時間帯を最適化
- 記者フレンドリーさ – 連絡先、写真、参考データを揃え、即記事化できる状態で提供する
表:ニュースバリューを判定する5項目
| 判定軸 | 質問例 | 点数ガイド | 改善ヒント |
|---|---|---|---|
| 新規性 | 「地域初」「業界初」か | 0–3 | 競合比較データを用意 |
| 社会性 | 社会課題を解決するか | 0–3 | 関連法改正を引用 |
| 話題性 | トレンドに乗っているか | 0–2 | 季節イベントを紐付け |
| 公共性 | 地域住民にメリットがあるか | 0–2 | 住民アンケートを添付 |
| 人間性 | ストーリーがあるか | 0–2 | 創業者の想いを盛り込む |
判定合計が8点以上であれば、新聞やテレビなどマスメディアに取り上げられる可能性が高まります。点数が足りない場合は、「切り口の再構築」や「データの追加」でブラッシュアップしましょう。
プレスリリース作成7ステップ
1. ゴール設定
掲載媒体と反響指標(問い合わせ数、予約数など)を具体的に決めることで、メッセージの焦点が定まります。
2. ターゲット読者の明確化
士業であれば「地域の中小企業経営者」、宿泊施設なら「週末に家族旅行を検討する30〜50代」など、記者ではなく読者を起点に人物像を描きます。
3. ニュースバリューの設計
前章の表で採点し、弱い項目があれば事例データや顧客の声を追加して補強します。
4. 5W1H+Whyの骨子作成
What=サービス名と特徴、Why=社会的課題との関係性を盛り込み、「だからニュースになる」理由を明確化します。
5. 見出しとリード文の作成
30字以内の見出しに結論を入れ、リード文150字以内で読者の利点を端的に示します。
6. 本文+参考情報の整備
本文は400〜600字×3段落を目安に、図表や写真、FAQを付けて記者の手間を削減。会社概要は定型フォーマットで最後に置きます。
7. 校正と第三者チェック
誤字脱字だけでなく、読者目線で「具体性」「独自性」「エビデンス」の3観点を確認してもらいます。
ここまでで“素材”は完成です。次章では、実際に誰へ、どのように送るかを解説します。
よくある失敗例と回避策
- 製品カタログ化
自社の機能説明だけで終わり、「なぜ今これが必要か」が抜けていると記者の心は動きません。読者の課題を起点にストーリーを構築しましょう。 - 専門用語の多用
業界内では当たり前でも、一般紙の記者には伝わりません。例:『SOP』→『標準作業手順書』。一度すべての名詞を平易な言葉に置き換え、社外の人に読んでもらい確認します。 - 連絡先の欠落
取材依頼を送ろうとしても電話番号が見当たらず、機会損失になるケースが毎年報告されています。問い合わせ担当者の携帯番号まで必ず記載してください。
成功事例:地方製造業A社の場合
| 項目 | Before | After |
|---|---|---|
| 配信媒体数 | 5社(全国紙のみ) | 15社(地元紙+業界紙) |
| 記事掲載数 | 0本 | 4本 |
| 問い合わせ数 | 月3件 | 月28件 |
A社は「環境負荷を30%削減する新素材」を開発しましたが、当初は大手紙の経済面だけを狙って不採用に。配信リストを地域経済欄や専門紙まで拡大し、リリース冒頭に『二酸化炭素排出量削減の実証データ』を追記したところ、地元紙で見開き掲載を獲得。その記事がポータルサイトにも転載され、全国からOEM相談が舞い込みました。
記者の本音を知るチェックリスト
- 締め切り厳守 – 朝刊担当は夕方17時以降のメールは翌日扱い
- 添付ファイルは2MB以下 – 重い画像はDLリンクを別途用意
- 写真は横長1280px推奨 – 紙面レイアウトに合わせておくと即採用率アップ
- ファクトチェック済みか – 数値の出典を脚注に記載すると好印象
- 署名に携帯番号 – 取材は突然来る、出られなければ次のネタへ流れる
上記を押さえておくだけで、競合リリースより一歩リードできます。特に地方紙は人員が限られるため、“ほぼそのまま記事になる完成度”が編集デスクに歓迎されます。
プレスリリースがもたらす5つの副次効果
- 被リンク獲得 – オンライン記事にURLが掲載されれば、ドメイン評価が向上し検索順位の底上げに。
- 営業トークの強化 – 「○○新聞掲載実績あり」という権威付けで商談の信頼度が上がる。
- 採用ブランディング – 求職者は報道実績を企業研究に活用。イメージ向上で応募率アップ。
- 社内モチベーション – 社員が記事を家族や友人に共有し、誇りや帰属意識の向上に寄与。
- 行政連携の促進 – 地域振興施策の事例として自治体が注目、補助金や共同事業の声がかかりやすい。
これらは広告費を投入しても一朝一夕には得られない効果です。だからこそ、作り込みと配信戦略に時間を投資する価値があります。
次章の予告:配信先リストで成果を左右する
プレスリリースは「誰に読ませるか」で運命が決まります。掲載率を上げるには「記者名簿の鮮度」と「配信ルートの多層化」が鍵となります。
無料で使える公的データベースや、既存取引先を活かしたネットワーク構築法、Excelを使った管理テンプレートまで具体的に紹介します。自社のリリースを埋もれさせないための“攻めの名簿戦略”にご期待ください。
地元紙・業界紙に刺さるネタ選定法
同じ新サービスでも、地元紙と全国紙では“刺さる角度”が大きく異なります。地元紙は「地域貢献性」と「生活密着性」を重視し、業界紙は「技術革新性」と「市場インパクト」を評価軸にします。そこで重要になるのがネタの切り分けです。
- 地域性を盛り込む
例:宿泊施設なら「地域食材×サステナブルメニュー」を前面に出し、地元農家との協業背景を盛り込む。 - 具体的な数字を立てる
例:製造業の新装置なら「生産効率を25%改善」「消費電力量を15%削減」など読者がイメージしやすい指標を提示。 - 人のストーリーを添える
士業の新相談サービスであれば、実際に救われた中小企業経営者の声を引用し、「顔の見える物語」にする。
表:メディア別に好まれる切り口
| メディア種類 | 主な読者 | 好まれる切り口 | NG例 |
|---|---|---|---|
| 地元紙 | 地域住民・行政 | 地域経済活性化、雇用創出、観光振興 | 専門用語が多い技術説明 |
| 業界紙 | 同業者・取引先 | 技術革新、市場シェア拡大、法改正対応 | 地域限定の小規模トライアル |
| 経済紙 | 経営層・投資家 | 市場規模、投資額、将来性 | エピソード中心で数字がない |
| 専門誌 | 技術者・研究者 | 技術背景、具体的なプロセス、実証データ | ざっくりした概念のみ |
表をもとに、「どの媒体へ、どの角度で出すか」をマトリクスで整理すると、記者が記事を書きやすい情報設計になります。
配信先リストの作り方と管理術
配信リストの精度が掲載率を左右します。量より質を意識し、「記者と媒体の相性」を可視化しましょう。
- 情報源を洗い出す
- 地方自治体の記者クラブ名簿
- 商工会議所・業界団体のメディアリスト
- 既存記事の署名を検索し記者名を抽出
- 媒体・記者を属性で分類
「地域×テーマ」「業界×技術領域」などタグ付けし、Excelのフィルタ機能で即抽出できるようにします。 - 更新サイクルを決める
異動や編集方針の変更が頻繁なため、半年ごとにリンク切れとメール不達をチェック。
表:配信リスト管理テンプレート(例)
| 媒体名 | 記者名 | 専門分野 | 送信日 | 反応 | 次回アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| ○○新聞 経済面 | 山田太郎 | 地域産業 | 7/10 | 取材依頼あり | サンプル提供 |
| △△工業新聞 | 佐々木花子 | 新素材 | 7/10 | 既読のみ | 成果データ追送 |
| ××観光タイムズ | 田中健 | ホテル・観光 | 7/10 | 未開封 | 7/24追電予定 |
反応欄に「掲載」「未掲載」「既読のみ」などステータスを残せば、次回リリースの改善点が一目瞭然です。
送付タイミングとフォローアップのコツ
1. 送付タイミング
- 新聞(朝刊):締め切り前日の午前10時までがベスト。午後は翌日扱いになる。
- 業界紙・Webメディア:月曜午前はリリース集中日で埋もれやすい。火曜~木曜の9:00送付で開封率が向上。
- テレビ局:夕方ニュース枠の企画会議が午前11時前後。前日16時までに送ると翌日取り上げられやすい。
2. 件名と本文冒頭
- 件名は【数字+社会性+簡潔な概要】が鉄則。例:「CO₂排出30%削減の新塗料、堺市発製造業が提供開始」。
- 本文冒頭に「記事本文に即コピペ可」の100字要約を配置。記者が忙しい時でも重要情報を把握できる。
3. フォローアップ
- 電話は送信翌日の午後が基本。午前は編集会議で捕まりにくい。
- 質問には即返信:目安は30分以内。レスが早い企業は“書きやすい”という好印象を与えます。
- 感謝メールを忘れない:掲載後24時間以内にお礼+読者反響を共有すると、次回以降の関係が強化される。
成功率を高めるフォローアップシナリオ
- 送付後24時間:開封状況をメール追跡で確認
- 未開封・既読のみ:電話で「補足資料がございます」と切り口を提示
- 取材依頼後:即日Zoomまたは現場取材日を調整
- 掲載翌日:SNSや自社サイトで記事をシェアし、PVや問い合わせ数を記者にフィードバック
この“フィードバックループ”は、記者にとって自分の記事価値を測る貴重なデータとなり、次のネタ採用率を引き上げます。
取材を呼び込むメールテンプレート
件名:地域初のEV特化宿泊プラン、本日リリース — 環境省実証事業採択
〇〇新聞 経済部 山田様
いつもお世話になっております。株式会社〇〇 広報担当△△です。
今回、EV充電設備を備えた宿泊プランを地域で初めて開始いたしました。
● CO₂排出量を15%削減する試算データ
● 地元高校と連携した環境学習プログラム
など、地域活性と教育的視点を組み合わせた事例としてご検討いただければ幸いです。
本文下部に100字要約と高解像度写真へのリンクを添付しております。
ご多忙のところ恐縮ですが、ご査収のほどよろしくお願いいたします。
――――――――――
【100字要約】…
【連絡先】携帯:090-××××-××××
このテンプレートでは「地域性」「社会課題」「具体データ」の3要素を先に提示し、記者がニュース価値を瞬時に判断できる形にしています。
次章の予告:掲載後の効果測定と改善サイクル
メディア掲載はゴールではなくスタートです。次章では、アクセス解析と問い合わせデータを組み合わせた効果測定フロー、数値が振るわなかった場合の“次の一手”を解説します。測定と改善を繰り返すことで、リリース配信がマーケティング資産へ変わります。
掲載後の効果測定と改善サイクル
KPI 設定―“認知”と“行動”を分けて追う
メディア掲載の成果は、
- 認知指標:記事 PV、SNS シェア数、指名検索数
- 行動指標:問い合わせ件数、予約数、資料 DL 数
の二層で評価します。記事がバズっても商談が増えなければ施策は半成功に過ぎません。両方を同時に伸ばす設計こそ次回リリースの改善点を明確にします。
効果測定フロー
- UTM パラメータ付き URL を発行し、各媒体別に流入を識別
- アクセス解析ツールで「参照元/ランディングページ」レポートを日次で確認
- CRM 連携で問い合わせフォームや予約システムに「掲載媒体」項目を追加
- 週次レポート化し、営業・CS チームと共有して顧客の声を収集
表:効果測定ダッシュボード例
| 指標 | 目標値 | 実績 | ツール | 更新頻度 |
|---|---|---|---|---|
| 記事 PV | 5,000 | 4,200 | Google アナリティクス | 日次 |
| 指名検索数 | 1,500 | 1,800 | サーチコンソール | 週次 |
| 問い合わせ件数 | 30 | 28 | CRM | 日次 |
| 予約転換率 | 8% | 9.2% | 予約システム | 週次 |
| SNS シェア数 | 200 | 310 | 各 SNS | 日次 |
実績が目標に届かなかった指標は「原因→対策」の順にメモし、次回リリースの骨子に反映します。例えば PV は足りても問い合わせが伸びない場合、記事内にサービスページへの導線が弱いのが原因かもしれません。
改善サイクルの回し方
- データレビュー会議(月1)
マーケ、広報、営業の三部門で指標と顧客の生声を照合し課題を抽出。 - 次回リリース仮説立案
「タイトルに数値を入れる」「権威性の高い第三者コメントを追加」など改善案を複数立てる。 - ABテスト配信
無料配信ツールを使い、件名とリード文を変えて少数媒体へ試験的に送付。反応が良いパターンを本配信に採用。 - 知見のドキュメント化
フォーマットを固定しナレッジを蓄積。担当が変わっても再現できる体制にする。
失敗パターンと改善トリガー
| 兆候 | 典型的原因 | 改善トリガー |
|---|---|---|
| PV は高いが問い合わせゼロ | CTA 導線不足、読者が具体行動を取れない | 記事末尾に LP URL と特典を追加 |
| 掲載本数が減少 | 記者の担当替え、ネタマンネリ化 | 配信リストの更新、顧客事例の切り口変更 |
| 地元紙のみ掲載 | 社会性不足、全国的ニュース要素が弱い | 統計データや業界平均と比較し“全国初”の視点を強調 |
改善のたびに“どこを変えたか”“結果どうなったか”を表で残すことで、プレスリリースは社内資産として累積効果を生み出します。
まとめ:最小コストで最大リーチを実現するポイント
- ニュースバリュー×タイミングでメディア掲載率を底上げ
- 配信リストは半年更新、相性の良い記者との関係を深耕
- フォローアップはデータ提供で恩返しし次の採用率を高める
- 効果測定→改善サイクルを月次で回し、成功要因を“仕組み化”
- 表・テンプレートを活用し、誰でも再現可能なプロセスを構築
プレスリリースは広告費を掛けずブランドを伸ばす経営施策です。今回紹介した実践手順を自社に合わせてカスタマイズし、地域メディアと業界紙を味方に付けて継続的な認知拡大を狙いましょう。






