Blog お役立ちブログ
ホームページのお問い合わせが増えないのは何が問題?
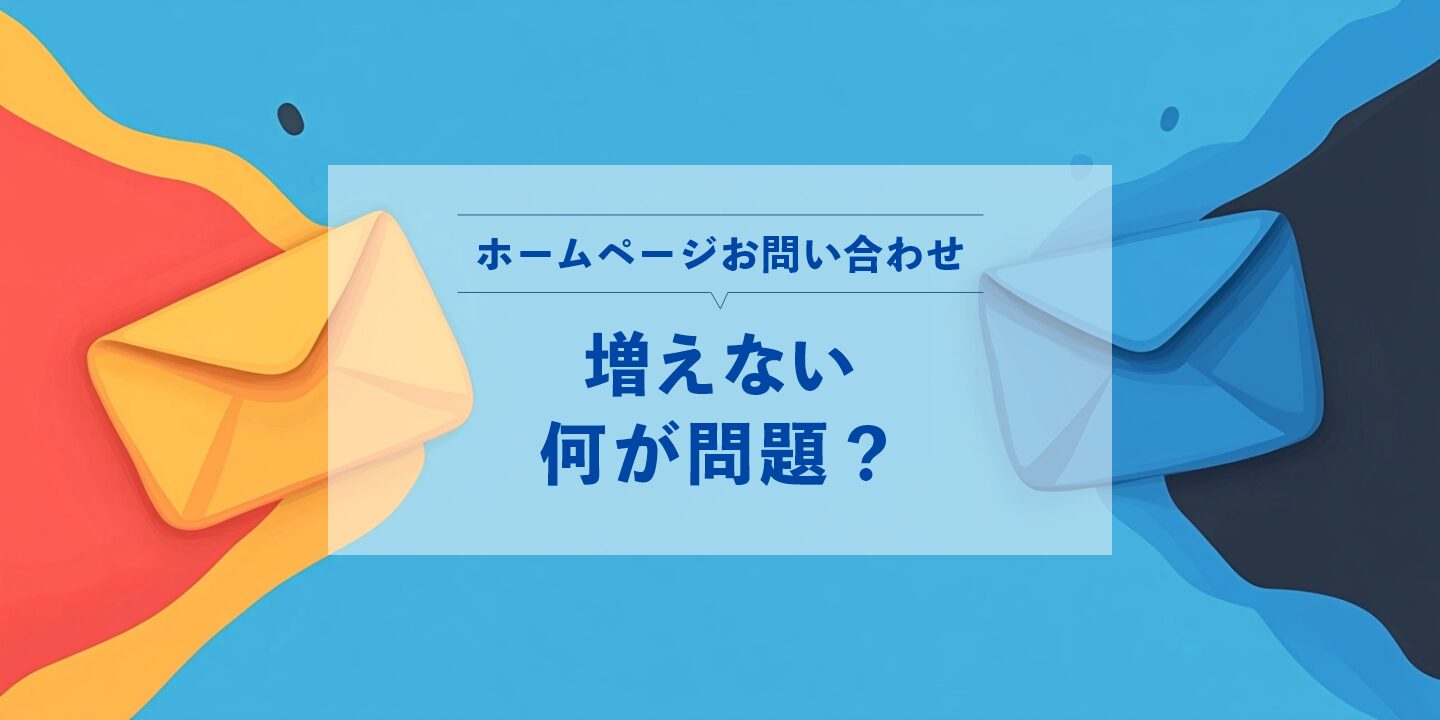
はじめに
中小企業の経営者や担当者の中には、「ホームページさえ作れば問い合わせや電話がどんどん増えるはず」と考えていたのに、思ったより反響が得られず困惑している方も多いのではないでしょうか。ホームページ開設当初は期待に胸を膨らませていたものの、実際には全くといっていいほど問い合わせが来ない…。そこで「ホームページ お問い合わせ 増えない 何が問題?」と検索して、このページにたどり着いた方もいるかもしれません。
実際、ホームページの問い合わせ数が少ない原因はさまざまです。デザインやサイト構成に問題がある場合、コンテンツが薄い場合、ターゲット設定があいまいな場合、SNSとの連携がうまくいっていない場合、そもそも集客できていない(アクセスが少ない)場合など、あらゆる要因が複合的に絡んでいます。
しかし一度しっかりと問題点を洗い出し、改善を続けていけば、問い合わせ数は着実に増やしていくことができます。本記事では、問い合わせが増えない原因とその具体的な解決策を、専門的な視点からわかりやすく解説します。
なぜホームページから問い合わせが増えないのか
まず、ホームページからの問い合わせが増えない主な原因を整理してみましょう。以下はよくある要因の一例です。
- サイトの目的・ターゲットが不明瞭
そもそも誰に向けて、どんなサービス・商品をアピールしたいのかがぼやけていると、訪問者は「自分に関係のないサイト」と感じてしまい、問い合わせにつながりません。 - サイトのデザイン・導線に課題がある
必要な情報が見つけにくい、問い合わせフォームへの導線がわかりづらい、フォームの項目が多すぎるなどの問題があると、途中で離脱されます。 - コンテンツ(情報)が不足している
問い合わせをしたいと思っても、具体的なサービス内容や料金、事例などが明確でなかったり、魅力を十分に伝えられていないと、問い合わせする前に離脱されてしまいます。 - アクセス自体が少ない
サイトの中身以前に、そもそも検索結果で上位に表示されず、ほとんどアクセスが集まらない状況ですと、お問い合わせどころではありません。 - 信頼感・安心感が不足
運営者情報や実績、お客様の声など、訪問者が「この会社なら安心」と思える根拠が不足している場合、問い合わせへのハードルが上がります。 - 更新や運用が滞っている
ホームページを一度作って放置していると、情報が古くなり、検索エンジンにも評価されにくくなります。結果として訪問者が少なくなるだけでなく、ユーザーの信頼も失いがちです。
問題点を洗い出すためのポイント
上記のような課題があるかどうかを調べるため、まずは自社ホームページを客観的にチェックする必要があります。具体的には以下のポイントを確認しましょう。
- アクセス解析ツールを導入し、どのページにどれだけ訪問があるか、どの程度の滞在時間があるかを把握する。
- 問い合わせフォームの離脱率を確認し、途中で入力をやめるユーザーが多いかどうかをチェックする。
- ページの構成がユーザーのニーズに合っているかを検証する。トップページからサービス内容までたどり着きやすいか、わかりやすいリンク配置になっているかを確かめる。
- 検索キーワードの意図に合ったコンテンツになっているか調査する。どのようなキーワードで訪問されているのか、そのキーワードに合致した情報提供ができているかを再確認する。
こうした実態把握を行わずにやみくもにデザインやレイアウトを変えても、的外れな施策になりがちです。自サイトが抱える問題点をしっかり把握したうえで、段階的な改善策を講じることが重要です。
問い合わせが増えるための改善策
実際に「問い合わせが増えない」状態を改善するには、複数の要素を組み合わせて対策を行う必要があります。ここからは具体的に取り組むべき施策を紹介します。
1. サイトの目的・ターゲット設定の見直し
・明確なペルソナ設定
ホームページは「誰に何を伝えたいのか」が明確でなければ、問い合わせにつながりません。たとえば「中小企業の新規顧客獲得を目指す経営者向け」「地方で店舗経営をしているオーナー向け」など、できるだけ具体的に想定読者を描きましょう。ターゲットが明確になることで、必要なコンテンツやデザインが自ずと定まります。
・サイトの役割とゴールの明確化
ホームページを利用して、最終的にどのような行動をユーザーに取ってもらいたいのかを再確認することも大切です。問い合わせフォームを利用してもらうことがゴールであれば、そのフォームへ誘導するための導線設計に重点を置く必要があります。
2. コンテンツの最適化
・訪問者の疑問や不安を解決する記事
商品・サービスの詳細や費用感、実際の導入・利用事例など、「問い合わせる前に知りたい情報」をきちんとコンテンツとして用意することで、訪問者が問い合わせしやすくなります。
・定期的な更新
新しい情報やトレンドに応じた記事をアップすることで、検索エンジンからの評価が高まりやすくなります。更新頻度が低いサイトは見込客の関心が薄れるだけでなく、検索順位にも悪影響を及ぼします。
3. デザインとユーザビリティの改善
・シンプルでわかりやすい導線設計
トップページから各サービスページ、問い合わせフォームまでの導線をできるだけシンプルにすることが重要です。ボタンやリンクが多すぎると混乱を招きます。
・フォームの入力負担を軽減
問い合わせフォームの入力項目が多すぎると、ユーザーにストレスを与えてしまいます。最低限の情報(名前、メールアドレス、問い合わせ内容など)に絞るなど、ハードルを下げる工夫をするのがおすすめです。
4. 信頼感を高める工夫
・会社情報や実績、レビューの公開
運営会社の情報(所在地や理念など)はもちろん、実際にサービスを利用したお客様の声、導入事例などがあると信頼度が高まります。顔写真やスタッフの雰囲気がわかる情報も効果的です。
・セキュリティ対策の周知
問い合わせフォームがSSLで保護されていることなど、ユーザーが安心して情報を送信できる環境が整っていることを明示するのも大切です。
5. アクセス解析と効果検証
・仮説を立てて検証・改善を繰り返す
アクセス解析ツールを使い、ページごとの訪問者数、離脱率、問い合わせフォームの完了率などをモニタリングします。仮説に基づいて改善策を実施したら、数字を比較して効果を検証し、次のアクションにつなげます。
問い合わせが増えない原因と対策の早見表
| 原因 | 主な症状 | 対策例 |
|---|---|---|
| 目的・ターゲット不明瞭 | 訪問者が自分向けの情報であるか分からない | ペルソナ設定、サイトのゴール設定を見直す |
| デザイン・導線の問題 | フォームへのボタンが見つけにくい、必要情報への導線が不明瞭 | シンプルなレイアウト、フォームへの遷移をわかりやすく設計 |
| コンテンツ不足 | 具体的なサービス紹介や料金の説明がない | 詳細情報や事例、Q&Aなどのコンテンツを充実させる |
| アクセスがそもそも少ない | 検索順位が低く、ほとんど流入がない | 記事更新、キーワード対策、SNS等を活用して流入増を図る |
| 信頼感・安心感の欠如 | 企業情報や実績が見当たらない、フォームが安全か不安 | 運営者情報やSSL化、実績公開、お客様の声を掲載 |
| 更新・運用が滞っている | 古い情報が残ったまま、サイトが放置状態で検索順位も下がる | 定期的な更新体制の構築、アクセス解析を継続的に確認 |
具体的なコンテンツ施策の比較表
どのようにコンテンツを強化していくかは、サイトの目的や業種によって多少異なりますが、以下のような方法があります。
コンテンツ施策の比較表
| 施策内容 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 専門性の高い記事投稿 | 検索エンジンからの評価を得やすい。 権威性・信頼性が上がる | 専門用語を使いすぎないようにする。 読者目線が大事 |
| 成功事例インタビュー | 実際の活用シーンが伝わりやすく、 見込み客の不安を解消できる | インタビュー対象者・企業の許可取得が必要。 時間と手間がかかる |
| スタッフ紹介ページ | 親近感や安心感を高められる | 個人情報の扱いに注意。 定期的なメンテナンスが必要 |
| よくある質問(FAQ)ページ | 問い合わせ前の疑問を解消でき、 問い合わせ数増加に直結しやすい | 質問・回答を定期的に更新する。 FAQだけで終わらない工夫 |
| 動画・写真を活用した紹介 | 視覚的に理解しやすく、 興味を引きつけやすい | 制作コストやデータ容量に注意。 スマホ対応必須 |
アクセス解析を活用する手順
アクセス解析ツールを導入してはみたものの、「どこを見てどう改善すればいいか分からない」という声もよく聞かれます。以下の手順を踏むことで、サイトの現状をより正確に把握し、適切な対策を検討しやすくなります。
アクセス解析を活用する手順表
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 設定確認 | トラッキングコードが全ページに正しく設置されているか確認 | 設置漏れや重複がないか要チェック |
| 2. 主要指標の把握 | ユーザー数、PV数、直帰率、滞在時間などを把握 | サイト全体と主要ページ単位で数値を比較し傾向を見る |
| 3. 流入経路の分析 | 検索、SNS、他サイトなど、どこから来ているかを分析 | 最も効果的な集客経路を特定し、強化すべき施策を検討する |
| 4. コンバージョン計測 | 問い合わせフォーム完了をコンバージョンとして設定 | 目標に達した数や率を追いかけ、改善効果を測定する |
| 5. 改善施策の実行 | 仮説に基づきサイト修正やコンテンツ追加などを実施 | 施策実施後の数字変化を追跡し、さらにPDCAを回す |
ここで大切なのは、数字の変化をきちんと検証しながら改善を繰り返すことです。一度の修正で完璧を目指すよりも、段階的に問題を発見・解決していくアプローチが効果的です。
具体的なエピソード・事例
実際に、問い合わせが増えなくて悩んでいた中小企業が、コンテンツやデザインを見直しただけで成果が変わったという事例は珍しくありません。たとえば、こんなエピソードがあります。
事例:サービス内容と導入事例を充実させた例
ある中小企業では、ホームページのトップページに会社概要と簡単なサービス紹介のみを掲載していました。訪問者はどのようなメリットがあるサービスなのか一目でわからず、問い合わせもほとんどありませんでした。そこで以下のように改善しました。
- ターゲットを「地域で事業を営むオーナー」に設定し、その方たちに向けたメリットや導入事例を詳しく掲載。
- 実際にサービスを導入した顧客の声やビフォーアフターの写真などを増やし、視覚的にもわかりやすく。
- フォームへの導線をはっきりと目立つボタンで設置し、「気軽に相談してみよう」と思える文言を配置。
結果として、サイトの滞在時間が伸び、1週間に1件程度しかなかった問い合わせが、1日1件以上のペースになるまで増加したそうです。重要なのは、ターゲット目線で情報を追加し、それらを適切に配置したことです。
まとめ
ホームページを通じて問い合わせを増やすには、まずは現在の課題を客観的に把握することが肝心です。デザインや導線、コンテンツの量と質、信頼性、そしてアクセス状況など、複数の要素が複合的に影響しているため、総合的な改善を意識しましょう。
- ターゲットや目的を明確にする
- 訪問者の疑問や不安を解消できるコンテンツを整備する
- わかりやすく、入力しやすい導線を設計する
- 運営者の実績や実例を掲載し、信頼感を高める
- アクセス解析を活用して、成果を計測しながら改善を重ねる
これらを地道に行うことで、問い合わせ数は少しずつでも確実に増やしていくことができます。一度で劇的に改善するケースもありますが、多くの場合は継続的な改善が必要です。長期的な視点を持ち、少しずつでも成果に結びつけていきましょう。






