Blog お役立ちブログ
創業融資を受ける時にホームページが有利って聞いたけど?
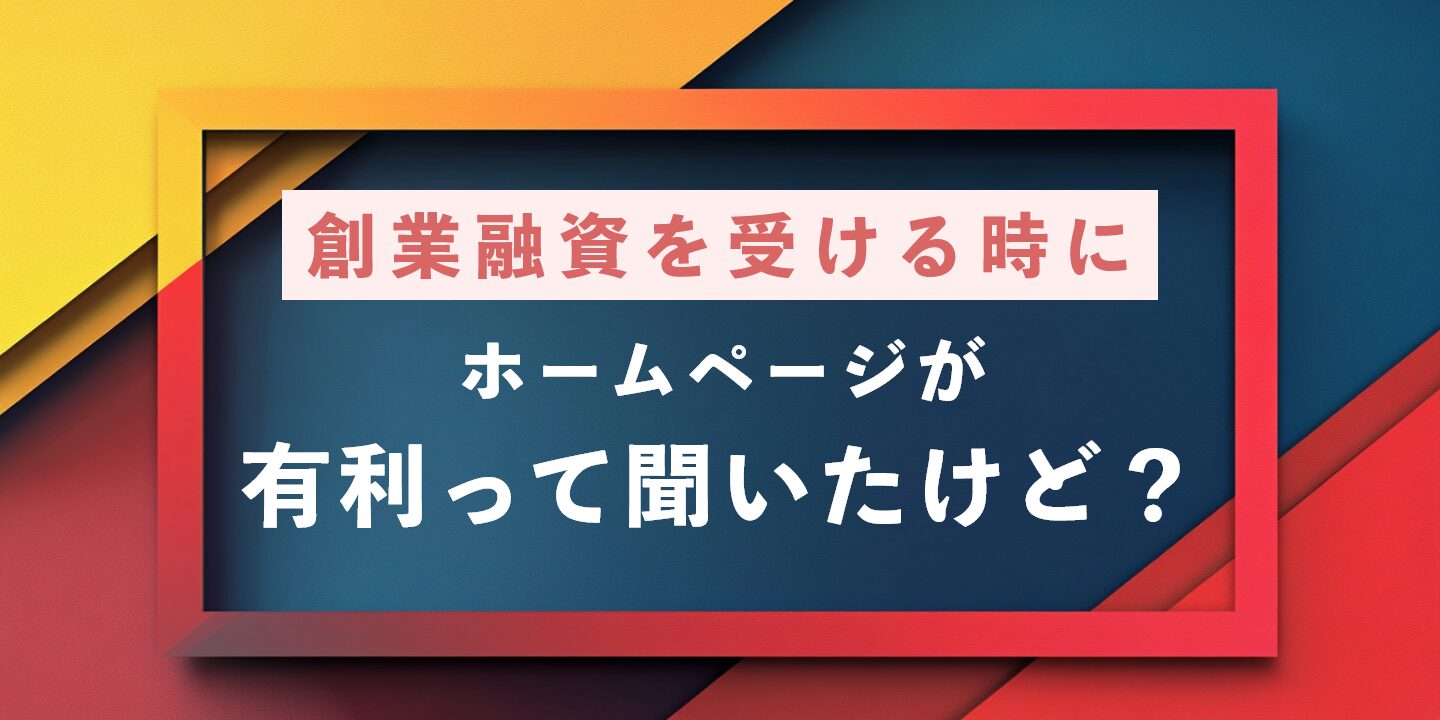
創業融資を検討している中小企業や起業家にとって、「ホームページは本当に必要なのか?」という疑問は少なくありません。書類審査やヒアリング面談と並行して、「事業内容をきちんと説明できるサイトがあると融資担当者からの印象が変わる」と聞くこともあるでしょう。とはいえ、どのようなホームページを用意すべきか分からなかったり、そもそも費用や手間がかかりそうで敬遠してしまったりといった悩みも出てくるかもしれません。
本記事では、創業融資を受ける時にホームページがどのように役立つのか、具体的なメリットや制作・運用上の注意点を詳しく解説していきます。金融機関が融資審査を行う際に重視するポイントと、ホームページを活用する際のヒントを整理し、自社の信頼性を高めるための基礎知識を得ることを目指します。
ホームページが審査に与える影響
まず、融資担当者や金融機関が企業のホームページをどの程度見ているかが気になるところでしょう。実際に書類審査や面談では事業計画書や収支予測などが重要視されます。しかし、インターネットが普及した今、企業の実態をざっくりと把握するためにホームページをチェックするケースは少なくありません。特に「どういう事業をやっているのか」「どのような商品・サービスを扱っているのか」「経営方針ははっきりしているのか」などを、第三者が手軽に確認できるツールとしてホームページは有効です。
下記は融資審査において、ホームページがどんな印象を与え得るのかをまとめた例です。
| 印象 | 補足説明 |
|---|---|
| 事業の実態が把握しやすい | 営業実績や取扱商品が分かりやすくまとめられていると、事業計画の具体性が増す。 |
| 信頼度が高いと感じられる | ホームページを持ち、更新が継続されていると「真面目に運営している印象」を与えやすい。 |
| 経営者の真剣度が伝わる | コストや手間をかけている点が、融資を受けた後の事業拡大意欲にもつながると見られる。 |
| 市場や顧客への対応力が伺える | スマートフォン対応や問い合わせフォームの整備があると、顧客対応意識が高いと思われやすい。 |
ホームページがあることで、金融機関が事業内容をイメージしやすくなり、さらに「この会社は将来性がありそうだ」「しっかり準備を進めている」と思ってもらいやすい可能性があります。もちろん、ホームページの有無だけですべてが決まるわけではありません。しかし、それでも審査の際にプラス要素となり得る要点があるのは事実です。
ホームページがもたらす主なメリット
次に、ホームページ自体が持つ役割やメリットを確認しましょう。「審査対策」だけを目的にホームページを準備するのは少しもったいないかもしれません。ホームページは、融資のためだけではなく、今後のマーケティングや顧客獲得の基盤にもなり得るからです。
- 事業内容の可視化
商品やサービスの情報をまとめることで、訪問者(金融機関や将来の顧客)にとって内容が理解しやすくなります。また、企業理念やメッセージを載せれば、経営者の思いや方針が明確に伝わります。 - 営業・集客の強化
ホームページがあると、オンライン上での問い合わせ窓口としても機能します。創業後の販路拡大に向けて、ネット検索での流入など新規顧客を獲得できるチャンネルが増える点は見逃せません。 - 信頼感の向上
実店舗やオフィスがなくても、Web上でしっかりと情報を発信している会社は「きちんと活動している」という印象を持たれやすいものです。逆に全く情報が見つからないと、金融機関に限らず消費者や取引先からも不安に思われる可能性があります。 - ブランド力の醸成
デザインや写真、文章、レイアウトなどを統一感のある形で提供すれば、企業イメージが確立されます。結果的に「この会社なら大丈夫そうだ」というプラスの印象をもたらすことにもつながります。 - 情報発信の柔軟性
印刷物のようにコストをかけずに随時更新が可能です。新しい商品リリースやサービス拡充、採用情報など、タイムリーに情報を発信できます。
ホームページを設ける大きなメリットとしては「Web上の名刺やパンフレット」のように機能しつつ、営業・マーケティング手段としても活躍する可能性があることです。創業融資の審査を意識しながら制作しても、その後の事業活動においても確実に資産として残ります。
金融機関に好印象を与えるサイト構成
では、具体的にどんなホームページなら融資担当者へ好印象を与えられるのでしょうか。以下は審査でも見られやすいポイントと、その対策例をまとめた表です。
| 審査で見られやすいポイント | ホームページでの対応例 |
|---|---|
| 事業内容の具体性 | トップページやサービス紹介ページで「何を、どう提供しているか」を一目で分かるように整理する |
| 経営方針・ビジョンの明確化 | 経営理念・代表挨拶ページなどで熱意や将来展望を示す |
| 信頼できる実績や取引先があるか | お客様の声、事例紹介ページなどで信憑性のある実績を分かりやすくまとめる |
| 問い合わせや契約・購入の動線がしっかりあるか | 電話番号や問い合わせフォームを分かりやすい場所(ヘッダー、フッター等)に設置する |
| 情報が最新の状態であるか | ニュースやお知らせの欄を定期更新し、活動が継続していることをアピール |
ホームページ全体としては、以下のような流れを意識すると分かりやすく伝えられます。
- トップページ: 事業の概要と会社の方向性をシンプルに提示
- サービス・製品ページ: 具体的な提供内容(料金形態がある場合はざっくりとした目安も)
- 事例・実績紹介ページ: 関連する受注実績やお客様の声(まだ実績が少ない場合は実際に作りたいサービスの詳細を記載)
- 会社概要ページ: 代表のプロフィールや企業理念、所在地などを明確に掲載
- 問い合わせページ: 問い合わせフォームや連絡先を明確に示す
事業のビジョンや活動内容をきちんと提示できるだけでなく、「この企業のウェブ戦略は今後も伸びそうだ」「説明力がある企業だ」といったプラス評価を得られる可能性も高まります。
制作・運用にかかる費用のイメージ
ホームページを作るとき、どうしても気になるのが費用です。融資申請の段階で制作費用をどの程度計上すべきか悩むケースもあるでしょう。制作会社に依頼する場合と自作(内製)する場合でコストや手間は変わります。以下は一般的な費用のイメージです。
| 項目 | 具体的な内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| ドメイン取得費 | 「.com」「.jp」などの独自ドメインを購入する費用。年額で支払うことが多い | 年額1,000~3,000円程度 |
| サーバー費 | ホームページを設置するためのレンタルサーバー代。安価な共有サーバーから高スペックまで様々 | 月額1,000~3,000円程度 |
| デザイン・コーディング費 | 外注する場合、デザインテンプレートかオリジナルかで大きく変動。ページ数や機能によっても変わる | 数万円~数十万円(規模による) |
| CMS導入・機能追加費用 | WordPress等のCMS導入、カスタマイズが必要な場合の作業料 | 数万円~数十万円 |
| 保守・更新サポート費 | 外部に更新作業を委託する場合や、セキュリティ対策などを含んだ保守料金 | 月額数千円~数万円 |
| 制作ツール・テンプレート代 | 自作(内製)する際に有料テーマやプラグインを購入する場合 | 数千円~数万円 |
もちろん上記はあくまで一般的な目安です。デザインをシンプルに押さえたり、ページ数を最小限にしたりすれば、コストを抑えることも可能です。逆にブランディングを重視したり、独自の機能を多数盛り込む場合は費用が膨らむ場合があります。
創業融資で借り入れをした資金の一部をホームページの制作やマーケティングに回すのも一つの戦略ですが、事業計画との整合性をしっかりと示す必要があります。たとえば、「ホームページを制作してオンラインで受注を増やす計画がある」など、具体的な売上見込みと投資理由をセットで説明できると納得感が高まるでしょう。
ホームページの作り方:外注と内製
続いて、「ホームページをどうやって作るか」という点について見てみましょう。大きく分けて、専門の制作会社に依頼する方法(外注)と、自社や個人で作る方法(内製)があります。それぞれのメリット・デメリットを把握した上で選択すると、効率的かつ納得感のある制作が可能です。
外注する場合のメリット・デメリット
- メリット
- プロが作るため、デザインや機能面でクオリティが高い
- 制作の進行管理やSEOなど、専門的なノウハウを持っている
- 短期間で完成しやすい
- デメリット
- コストが高くなりやすい
- 納品後の修正に追加費用が発生することがある
- 自社で更新するための知識が残りにくい
内製する場合のメリット・デメリット
- メリット
- 費用を抑えやすい
- 自社の意図を反映しやすく、細かい修正がすぐできる
- 仕組みを理解できるため、将来的な運用がしやすい
- デメリット
- Web制作の知識やスキルがないと時間がかかり、質も下がる恐れ
- デザイン面や機能面で完成度にムラが出やすい
- お客様目線の設計が難しい場合がある
このように、どちらの手段にも一長一短があります。融資担当者や金融機関は、企業のホームページが「どのような目的で」「どんな使われ方をし」「維持できるのか」に関心を持ちます。外注か内製かは、事業計画や予算、制作スキルなどを総合的に考えて決定すると良いでしょう。
サイト運用で信用度を維持する方法
ホームページは作って終わりではありません。定期的に情報を更新し続けることで、企業のアクティブさと信頼度を高める効果があります。「融資後もしっかり事業を継続していく姿勢」を見せるためにも、以下の点を意識しましょう。
- 最新情報の更新
商品追加やサービス拡充、活動報告などをホームページで随時発信する。数か月以上放置されると、「経営がうまくいっていないのか?」という疑念を持たれることもあります。 - デザインや構成の見直し
使い勝手が悪かったり、情報が増えすぎて整理されていない状態だと、訪問者が離脱しやすくなります。定期的にアクセス解析ツールなどを用いて改善点を洗い出すと良いでしょう。 - 商品・サービスの追加情報
実際の販売実績が出てきたら、事例紹介やお客様の声を逐次更新。これによりホームページの充実度が増し、信頼感がさらに高まります。 - SNSとの連動
ホームページにSNSリンクを設置し、SNS更新時に最新情報を共有するなど、多角的に情報を発信すると、さらに多くのユーザーにリーチできます。信用度にもプラスに働きやすいでしょう。 - セキュリティ対策
CMSやプラグインの定期的なアップデート、HTTPS化などは最低限実施しておきたいポイントです。セキュリティ面を疎かにすると、万が一のトラブルで企業イメージに悪影響が及びます。
運用がしっかり行われているホームページは、金融機関にとって「ビジネスを継続的に成長させようとする努力の証拠」にも映ります。逆に、制作しただけで全く更新されていないサイトは、不安要素になる可能性もあるため注意が必要です。
まとめ
創業融資を受けるにあたり、ホームページの有無が必須条件というわけではありません。しかし、事業内容や将来性をアピールする上で大きな助けとなるのも事実です。審査担当者は、多くの企業や事業プランを日々見ています。その中で、ホームページを通じて「自社の独自性をどれだけ具体的に伝えられるか」「経営者としてどのようなビジョンを描いているか」を明確に示せれば、それが審査のプラス材料になり得るでしょう。
ホームページ自体は融資後の事業成長にも役立つ資産です。制作や運用にかかるコスト、どのように更新・活用していくかを明確に考えておくと、金融機関への説明にも説得力が増します。最初の制作費を投資と考え、長期的な運用計画を立てることで、創業融資以外の目的でも多大なメリットを得る可能性があります。ぜひ、本記事で取り上げたポイントを踏まえながら、ホームページの活用を前向きに検討してみてください。






