Blog お役立ちブログ
会社設立前と後でサイトを作るタイミングはいつが正解?
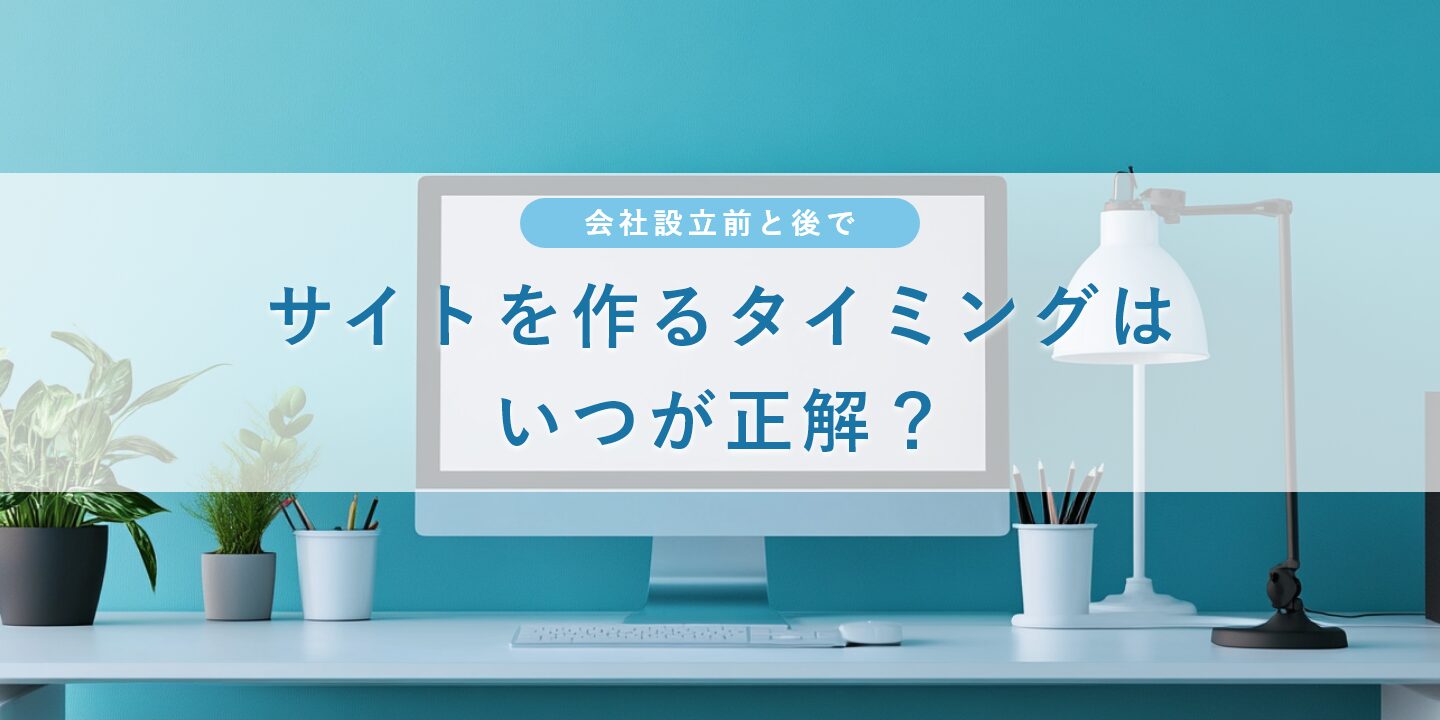
フリーランスや中小企業の経営者予備軍が、ホームページの制作時期を検討する際に大きな悩みとなるのは「事業内容や社名が固まる前に作ってしまっていいのか」という点です。設立後に社名変更や事業計画が変わる可能性があるなら、急いで作っても二度手間になるのではないかと心配になります。一方、設立後に着手すると、公開までに時間がかかり、その間にビジネスチャンスを逃してしまうリスクもあります。
また、サイトが本格的に稼働するのは検索エンジン上での評価が蓄積されてからになるため、なるべく早めに公開し、ドメインを育てることが有利といわれます。こうしたメリットの反面、「設立前にサイトを公開しても信頼度が低いのでは?」と不安を感じる方も少なくありません。
つまり、サイトを作る時期を会社設立前か後かにするかで、それぞれメリット・デメリットが存在します。これから詳しく解説していきます。
設立前にサイトを作るメリット・デメリット
まずは会社設立前の段階でサイトを作ることを検討した場合のメリットとデメリットをまとめます。
メリット
- 早めのブランディング・集客効果
まだ法人登記をしていない段階でも、サイトを公開しておくと検索エンジンからの評価が少しずつ蓄積されます。設立後に一気に露出を増やす準備として、あらかじめ始めておくのは大きなアドバンテージになります。 - 事業計画を具体化できる
実際にサイトを形にすることで、自分の事業内容や商品・サービスの説明を明確にするきっかけになります。文章化したり画像を整理したりする過程で、自分が想定しているターゲットやコンセプトのブラッシュアップが進むことがあります。 - ノウハウや運用スキルの習得
設立前にサイトを作ると、更新や運用に慣れる時間が生まれます。後から運用担当を雇う場合でも、自分でサイト運用の基礎を理解しておくと指示出しがしやすくなり、スムーズに社内フローを構築できます。
デメリット
- 社名やコンテンツの変更リスク
設立時に社名が確定する前だと、後から名称やブランドカラーを変更する必要が出てきます。ロゴやドメインも変更したくなるかもしれません。結果としてデザインやサイト構成を作り直す必要がある場合、余計なコストと時間がかかります。 - 信用力の不安
設立前のサイトは、見る人にとっては「本当にこの事業は大丈夫なのか」という印象を与えかねません。特にBtoB取引の場合は、法人格がない段階での信頼性は低めです。 - 余計なコスト発生
最初に安易に作ってしまうと、後で本格的に作り直す際に二重のコストが発生するリスクがあります。
ここではメリットとデメリットを簡単に示しますが、判断基準の一つとして整理した表を以下に示します。
| 項目 | 設立前に作るメリット | 設立前に作るデメリット |
|---|---|---|
| ブランディング・集客 | 事前にドメインの評価を蓄積できる | 事業内容の変更に伴い作り直しが必要 |
| 信用・信頼性 | 事業計画が明確ならば先行アピールが可能 | 法人格がない段階での信用力不足 |
| コスト・時間 | 運用方法を先に学べる | 二度手間になる場合は追加予算が必要 |
| 事業計画との整合性 | コンセプトを固める試金石になる | サービス内容や社名変更でサイト全体を修正する恐れ |
設立後にサイトを作るメリット・デメリット
次に、会社を正式に登記してからサイト制作を行う場合のメリット・デメリットを見てみます。
メリット
- 社名・事業内容が確定した状態で作れる
設立後であれば社名はもちろん、実際に行う事業内容がはっきりしているので、ブランディングをぶれなく進められます。後から大きく作り直すリスクが減り、最初から完成度の高いサイトを構築しやすくなります。 - 信頼性の向上
法人登記をすませた企業であると明確に示せるため、名刺や契約書などとも統一感を持たせた情報発信が可能です。BtoB取引や金融機関へのアピールなど、正式な対外的信用を得やすくなります。 - 法人としての資金計画に合わせた投資がしやすい
会社口座や設備投資の一環としてWeb制作費を計上できるため、資金計画とのバランスを取りやすいという利点があります。
デメリット
- ドメイン育成期間の遅れ
設立後に作り始める場合、サイト公開から検索エンジンの評価が上がるまでの期間が空いてしまいます。その間、Webからの集客やリード獲得に遅れが生じる可能性があります。 - 同業他社に先を越されるリスク
市場や競合の動きを考えると、早めにサイトを立ち上げて実績やコンテンツを蓄積しておいたほうが有利になるケースがあります。設立後の制作開始だと、急いでも公開まで時間がかかります。 - 初期段階の運用経験不足
実際に運用を始めるのが遅くなるため、設立直後にWeb集客を動かそうと思っても、慌ただしくなる可能性があります。先に学習しておく期間が取れません。
以下に設立後に作る場合を整理した表を示します。
| 項目 | 設立後に作るメリット | 設立後に作るデメリット |
|---|---|---|
| ブランディング・集客 | 法人格があるため信頼性を獲得しやすい | ドメイン評価の蓄積が遅れる |
| 信用・信頼性 | 事業内容が確定しており統一感を出しやすい | 公開が後ろ倒しになりビジネスチャンスを逃す恐れ |
| コスト・時間 | 資金計画を立てて制作費を確保しやすい | 法人設立後に制作に取りかかる分スケジュール逼迫 |
| 事業計画との整合性 | 実際の事業に即したサイト構築が可能 | 運用の経験値が不足しがち |
サイト制作の進め方と費用対策
サイト制作は大きく分けて、企画・デザイン・構築・運用のステップに分かれます。どの段階で着手するかによって、必要なコストや時間が変わります。サイト公開のタイミングを会社設立前にするのか後にするのか、いずれの場合でも下記の流れを意識して計画を立てると、二度手間を最小限に抑えられます。
- コンセプト・目的の整理
事業で何をどのように訴求するかを明確にする。 - サイトの構成・ページの洗い出し
トップページ、サービス紹介、会社概要、採用情報などの構成を整理。 - デザイン・ブランディング要素の検討
ロゴ、カラー、フォント、イメージ写真などブランディングに関わる要素を決める。 - 制作予算の策定
デザイン制作費や開発費だけでなく、運用費や更新費など継続コストも考慮する。 - 制作会社やフリーランスに依頼、もしくは内製化
どの範囲を外注し、どこを自社でまかなうかを決める。 - デザイン・コーディング作業
実際の制作工程。スケジュール管理が重要。 - テスト公開と修正
誤字脱字チェックや動作確認などを行い、修正対応を進める。 - 正式公開・運用開始
公開後の分析や改善、コンテンツ追加が長期的には重要。
サイト制作費用は、外注の場合は初期制作費に加えて更新・保守料金が月額・年額で発生するケースが多いです。設立前に作る場合は、後から修正コストがかさむリスクを意識し、なるべく修正しやすいプラットフォームを選ぶなど工夫が必要です。
会社設立時のブランド戦略とサイト運用のポイント
会社設立時期に合わせたブランド戦略では、ロゴや社名、スローガンが一体となっていることが理想です。サイトはそのブランド戦略を顧客や取引先に対して視覚的・情報的に伝える役割を担います。設立前に仮のロゴや社名で公開する場合は、余裕をもって変更できるデザインやコンテンツ管理体制にしておくと安心です。
ブランドとサイト運用の連動
- ロゴ・社名・ビジョンの統一
あとからロゴや社名を変更すると、サイトだけでなく名刺やパンフレット、SNSアカウントも修正が必要になります。 - コンテンツ更新の計画
サイト公開後は、商品・サービスの追加や最新情報の発信など、更新作業が日常的に発生します。運用担当や役割分担をあらかじめ決めておくことで、設立前後のバタバタにも対応しやすくなります。 - SNSや他メディアとの連携
設立前からSNSアカウントを運用する場合は、サイトとSNSが連動しているのが理想的です。設立後には名刺やチラシと併せた一貫性のあるブランディングが重要です。
具体的な準備ステップ(サイト構成・ドメイン・SNS連携)
ここでは、サイト公開に向けた具体的な準備ステップを紹介します。
- ドメイン取得とレンタルサーバー選定
- 設立前に社名が不確定なら、サービス名やブランド名をドメインに含める選択肢もあります。
- 後から変更しやすいよう、取得ドメインと運用中のメールアドレスの紐づけ管理を慎重に行うと良いでしょう。
- サイト構成案の作成
- 必要となるページ(事業紹介、会社概要、問い合わせなど)を洗い出し、サイトマップを作ります。
- 設立前と後で大きく変動するコンテンツは仮ページにして、後からの修正が容易な構造にしておくのも手です。
- デザイン方針の決定
- 仮のロゴや色使いをとりあえず設定し、後から置き換えられるようにレイヤー管理・テンプレート管理を徹底します。
- デザインテンプレートを使うか、オリジナルで制作するかによって予算も変わります。
- SNS連携の設計
- 事業内容に合わせて運用したいSNSを選び、アイコンやヘッダー画像の一貫性を持たせます。
- まだ法人アカウントの作成を急がないなら、個人アカウントと並行して運用し、設立後にスムーズに移行する方法もあります。
- コンテンツの制作・ライティング
- サービス詳細やブログ記事など、サイトに掲載する文章を準備します。
- 設立前に用意できる情報と、設立後に確定する情報を切り分けておくと効率的です。
設立前から始める場合の実践例
ここでは、設立前からサイトを用意した例を想定してみます。
- 事業内容がほぼ決まっているが、社名が流動的
→ ドメインにはサービス名やブランド名を利用。社名は暫定的な記載にとどめ、後で変更しやすいデザインとCMSを採用。 - 試作品やテスト販売を進めたい
→ サイト上で試験的に集客し、ユーザーからの反応を調査。SNSやお問い合わせフォームで市場ニーズを探り、正式リリース時に改善点を反映。 - すでにフリーランスとして活動し、顧客を持っている
→ フリーランスの実績を掲載する形で制作し、法人化した際に実績ページや会社概要だけを更新する。後からサイト全体のリニューアルをすることも想定して、汎用性あるレイアウトを使う。
こうした運用は設立後に大幅な変更が発生する可能性があります。しかし、リニューアルに備えて下記のようにしておけば被害は最小限で済みます。
| 設計段階 | 工夫した点 |
|---|---|
| ドメイン | サービス名を軸にしたドメインで、社名変更の影響を減らす |
| デザイン | ロゴや社名の配置を後から差し替えやすい位置・形式にする |
| コンテンツ | 法人名が大々的に必要なページ(会社概要など)は仮ページ |
| 運用体制 | サイト更新担当を決めておき、変更リクエストのフローを構築 |
設立後から始める場合の実践例
一方、設立後に本格的にサイトを立ち上げる場合の例です。
- 会社の登記が済み、社名・ブランドが確定
→ 公式ロゴを使った統一感あるデザインで一気に制作。対外的信用度が高く、取引先や金融機関にも安心して案内できる。 - 事業モデルがようやく明確になった
→ サービスや製品ラインアップを固めてから制作するため、無駄なページや情報が少ない洗練された構成に。 - 資金調達を行い、サイト制作に予算が割ける
→ 設立後の資金計画の中でプロの制作会社にまとめて依頼し、高品質なコーポレートサイトを構築。公開と同時に広報やPRも展開しやすい。
この場合の注意点としては、設立までWeb上での露出がほとんどなかったぶん、公開後しばらくは検索エンジンでの評価を上げるための対策に取り組む必要があることです。コンテンツの充実やSNSなどとの連携を強化し、短期間でサイトの存在感を高める計画を立てることが重要です。
タイミング別チェックリスト
最後に、会社設立前と後、それぞれのタイミングで確認しておきたいポイントをチェックリスト形式でまとめます。
| チェック項目 | 設立前 | 設立後 |
|---|---|---|
| 事業計画が固まっているか | 大枠はあるが詳細は未確定の場合が多い | 詳細が確定し、具体的なサービス内容が明確化 |
| 社名・ロゴが完成しているか | 暫定案を使用する可能性あり | 正式な社名・ロゴを確定 |
| ドメイン戦略 | 仮ドメインを使うなど柔軟性を重視 | 社名ドメインやブランド名ドメインを選定 |
| 予算・資金計画 | 個人資金で少額から始めるケースもある | 法人予算としてまとまった投資が可能 |
| 対外的信用力 | フリーランス・個人事業としての発信 | 法人としての信頼性を全面に打ち出せる |
| 運用リソース・チーム体制 | 小規模・個人が中心 | 社内で担当者を配置できる場合が多い |
| 公開後の修正コスト | 後から大きな変更が入るリスクが高い | 最初から完成度を高めたサイト構築が可能 |
| 集客開始までの期間 | 早めに公開するぶん検索エンジン評価が有利 | 公開が遅れるぶんスタートダッシュが遅れる |
まとめ
会社設立前にサイトを作るか、設立後に作るかは事業計画やブランド戦略、運用体制などさまざまな要素によって変わります。ポイントは、二度手間をどこまで許容できるか、あるいは公開の遅れによる機会損失をどう評価するかにあります。フリーランスとして既に実績があり、早期からドメインの評価を高めたいなら設立前の制作は大いに意味があるでしょう。一方で、社名やブランドイメージの確定を待ったほうが無駄が少ないケースもあります。
いずれにせよ、設立前から作るにせよ、設立後に作るにせよ、以下のポイントを押さえておくことでスムーズなサイト制作・運用が可能になります。
- 変更を前提とした柔軟な設計やCMSを活用する
- ブランド戦略とサイト制作を一貫性のある形で進める
- 公開後の運用と更新プランを明確にし、担当者や予算を確保する
- SNSや他の宣伝施策との連動を視野に入れる
- ドメイン取得やSEO対策を早めに検討し、公開時期に合わせた準備を怠らない
自社の状況に照らし合わせ、最適なタイミングを見極めながら、着実にWebの土台を築いていくことが大切です。






