Blog お役立ちブログ
小予算で実現するホームページリニューアルの進め方
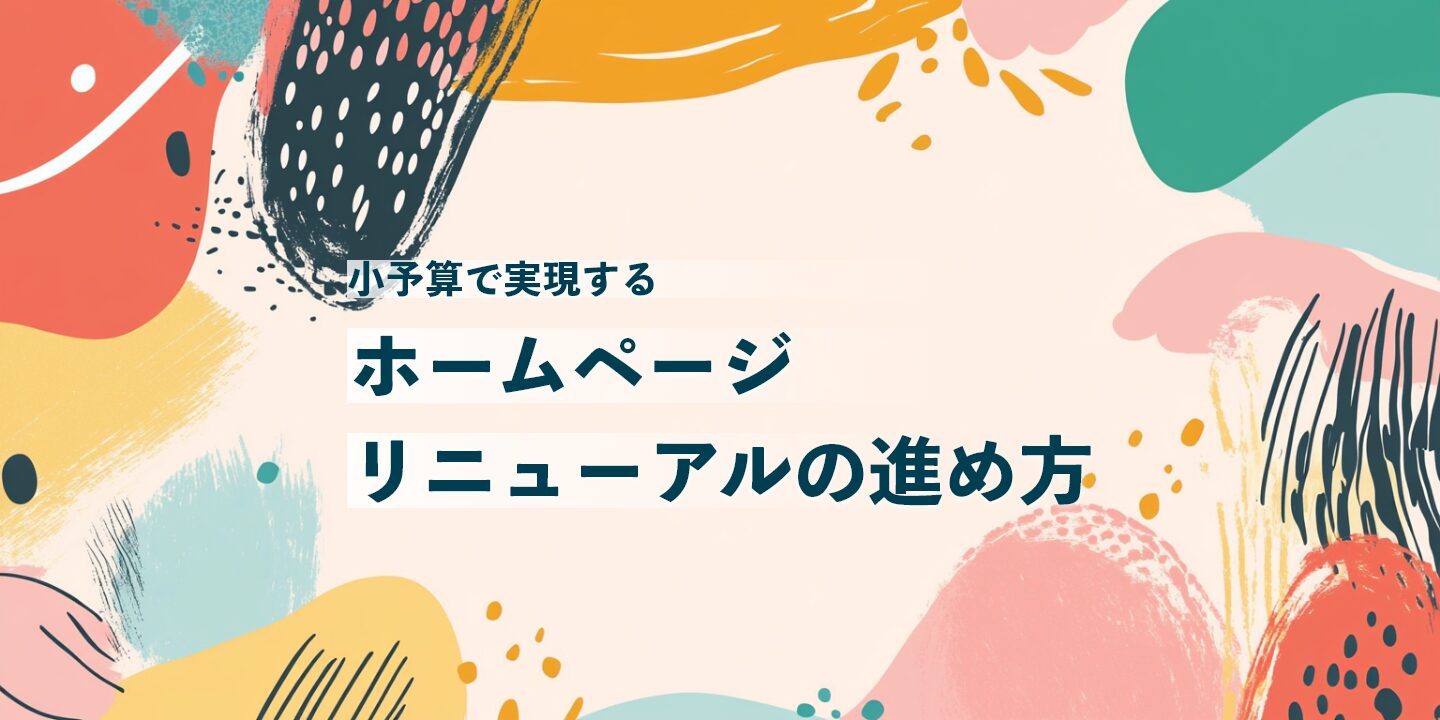
導入
現在、中小企業が運用しているホームページの中には、作成してから年数が経ち、デザインが古いままで放置されているケースが珍しくありません。しかし、初期費用や手間の問題から、なかなかリニューアルに踏み切れない状況もあるでしょう。そこで本記事では、小予算でホームページリニューアルを進めるための方法や注意点を詳しく解説していきます。
初めてホームページを作るとき以上に、リニューアルには既存サイトの構造を理解したり情報を再整理したりと手間がかかる場面が出てきます。また、限られた予算の中でどの部分を優先的に改修すべきかを決めるのも大切なポイントです。さらに、デザイン面の刷新だけに注力するのか、コンテンツや機能面まで見直すのかによってもやり方は変わってきます。
ここでは、最初に小予算でリニューアルを行う上での大まかな流れや準備すべきことを解説し、次にデザインやコンテンツ、外注・内製の進め方などを段階的に見ていきます。この記事を読めば、自社ホームページを大掛かりな投資をせずに刷新する際の具体的な手がかりを得られるでしょう。
小予算リニューアルの事前準備
はじめに、小予算でリニューアルを成功させるためには、事前の目的設定や現状分析が欠かせません。費用が限られているからこそ、的外れな改修をしてしまうと「せっかくデザインを変えたのに成果が出ない」という状況に陥りやすくなります。ここでは、事前準備で確認しておきたいポイントを整理します。
リニューアルの目的を明確にする
ホームページのリニューアルにはさまざまな目的があります。例えば「デザインが古く見えるので企業の信頼感を高めたい」「問い合わせ数が伸び悩んでいるので改善したい」「製品やサービス内容をもっとわかりやすく伝えたい」といった理由です。こうした目的を明確にしておくことで、リニューアル後のゴールを把握し、予算の配分を適切に行いやすくなります。
| 目的 | 主な効果 | 改善の優先度 |
|---|---|---|
| ビジュアル刷新 | 視覚的な印象アップ、ブランド強化 | 高 |
| 情報構造の再整理 | ユーザーの導線向上、理解度の向上 | 中 |
| 問い合わせ数の増加 | 売上や反響の増加につながる | 高 |
| 採用ページ強化 | 人材確保の機会拡大 | 中 |
| セキュリティ強化 | 信頼性向上、トラブル回避 | 低〜中 |
上の表は、リニューアルの目的例と、その効果・優先度を簡易的に示したものです。もちろん会社ごとに重点を置く部分は変わるため、まずは自社で「なぜ今ホームページをリニューアルする必要があるのか」を洗い出しましょう。
現在のサイトの問題点を洗い出す
予算をかけずにリニューアルをする場合、最も効果が期待できる箇所から改善するのがセオリーです。デザインそのものの古さも問題ですが、それ以外にも以下のような点を確認してみてください。
- スマートフォンやタブレットへの対応(レスポンシブ対応)が不十分
- メニューやリンク構造が複雑で、訪問者が目的の情報にたどり着きにくい
- 更新されていない情報が残っており、最新の社内情報やサービスが反映されていない
- カラーやフォントなどのデザイン要素が時代遅れの印象を与えていないか
- 表示速度が遅く、ユーザーにストレスを与えている可能性がある
これらの問題点をリストアップし、どれが優先して改善すべきポイントかを判断します。とりわけ、レスポンシブ対応と表示速度は、多くのユーザーがスマートフォン経由でアクセスする現代において軽視できません。
リニューアルに割ける予算とスケジュール
小予算で進める場合は、無理のない範囲でリニューアルを行うことが最も大切です。短期間で無理に全体を刷新すると、品質に影響が出たり、社内リソースが足りず中途半端に終わる可能性があります。以下のような計画表を作成しながら、予算とスケジュールを管理するとスムーズです。
| 項目 | 予定時期 | 担当者またはチーム | 必要予算 |
|---|---|---|---|
| 現状サイトの分析 | 〇月〇日〜 | 社内担当 | 0 |
| デザイン要件の策定 | 〇月〇日〜 | 社内担当・外注 | 見積もり次第 |
| 原稿・写真素材準備 | 〇月〇日〜 | 社内担当 | 0 |
| 実装・テスト | 〇月〇日〜 | 外注または社内 | 見積もり次第 |
| 公開・運用開始 | 〇月〇日 | 社内担当 | 0 |
簡易的なガントチャートやスケジュール表を作って、リニューアルの各工程にどれくらい時間とコストがかかりそうかを明示しておきましょう。予算が厳しい場合は、優先度の低い部分を後回しにするといった判断も必要になります。
デザイン刷新のコツ
小予算でのホームページリニューアルにおいて、デザイン面の刷新は重要なポイントです。第一印象が古いままだと、せっかくの訪問者が「この会社は時代に取り残されているのでは?」と感じてしまう可能性があります。ただし、デザインを一から作り直すには大きなコストがかかる場合もあるので、以下のようなコツを押さえて無駄なく進めることが肝心です。
テンプレートの活用
ワードプレスなどのCMSを利用している場合、あらかじめレイアウトが用意されているテンプレートを導入するのは有効な方法の一つです。テーマやテンプレートをカスタマイズすれば、プロに依頼するよりも費用を抑えつつ、それなりに洗練されたデザインを実現できます。ただし、テキスト量やコンテンツの構成がテンプレートと合わない場合は、不要な要素を削除したり調整する必要があります。
共通デザインルールの整理
小予算だからこそ、一度デザインを決めたら社内で統一したルールを作ると効率が上がります。具体的には以下のような項目を決めておくと良いでしょう。
- コーポレートカラーやアクセントカラー
- 見出しや本文で使用するフォントの種類・サイズ
- 写真やイラストなどのビジュアル素材の方向性(人物写真を多用するか、イラストベースにするか など)
- アイコンやバナーの形状・色合い
デザインルールがバラバラだと、部分的な差し替えや更新を行うたびにブレが生じます。早い段階でルールを固めておけば、社内担当者や外注先とのやりとりもスムーズになるでしょう。
レスポンシブデザインの優先
スマートフォンからのアクセスが大半を占める現状では、レスポンシブデザインは必須です。パソコン表示のみを綺麗に整えても、スマートフォンで見づらいと離脱率が高まり、成果につながりません。テンプレートやテーマを選ぶ際も、レスポンシブ対応を前提に検討しましょう。
コンテンツの見直しと更新方法
リニューアルは見た目を新しくするだけでなく、コンテンツの質を向上させる機会でもあります。コーポレートサイトやサービス紹介ページなど、現状の内容が時代に合っているか、最新情報を反映しているかを確認しましょう。限られた予算であっても、テキストと画像の入れ替えだけなら社内担当者が比較的容易に実施できる場合もあります。
コンテンツ整理の手順
- サイト内コンテンツのリストアップ: すべてのページについて、掲載している情報を洗い出す。
- 不要・重複コンテンツの整理: 似たような内容が重複していないか、古くなっている情報がないかをチェック。
- 優先度付け: すぐに手を入れるべき重要ページと、後回しにできるページを分ける。
- 内容の再執筆・更新: 情報が不足している場合は新たな文章を作成し、古い内容は最新情報に書き換える。
- デザインへの反映: 新しいコンテンツ構成に合わせてレイアウトを調整する。
こうした手順を踏むことで、サイト全体が整理され、ユーザーにとってわかりやすい構成になります。
更新作業を効率化するコツ
小予算でのリニューアルでは、外注に出せる範囲が限られるかもしれません。そこで社内でできる限り作業を進めるために、以下のような工夫が考えられます。
- CMSを導入する: 既存サイトがCMSを使っていない場合は、この機会に導入すると運用コストを下げられる可能性が高い。
- 原稿のテンプレート化: ページごとに「導入→要点→具体例→まとめ」などの流れを決めておく。
- 写真や画像素材の管理を一元化: 共通フォルダやクラウドストレージを使い、誰がどの素材を使用しても整合性が保たれるようにする。
- 権限管理の明確化: 最終的なチェック者や公開権限を誰が持つかを明確にしておく。
外注と内製の進め方
ホームページリニューアルは、外注するか内製(社内で作業を行う)するかで、かかる費用や時間、クオリティが大きく変わります。ここでは外注と内製それぞれのメリット・デメリットをまとめました。
| 項目 | 外注 | 内製 |
|---|---|---|
| コスト | 制作会社やフリーランスへの費用が発生 | 社員の人件費として算出(直接費としては見えにくい) |
| デザイン面 | プロの視点で洗練された仕上がりが期待できる | 社内リソースによるため、専門知識が足りない場合がある |
| スケジュール | まとまった内容で依頼すれば短期間で仕上げられる | 社内事情や他業務の兼ね合いで、作業が遅れがち |
| コミュニケーション | すり合わせが上手くいけば効率が良い | 社内メンバー同士で柔軟に情報共有できる |
| 更新後の運用 | 定期的に外注先に依頼するか、社内で更新するか選択可 | 内製の場合、運用フローが確立していれば柔軟に変更可能 |
小予算で進める場合、フル外注にするとコストが高くなる恐れがあります。一方、すべてを内製で行うと、スキル不足や人手不足で思うように進まないリスクもあります。中間案として、デザインやプログラミングなど専門性の高い部分のみを外注し、コンテンツや画像素材の用意などは社内で担当するという方法もあります。
外注先を選ぶ際のポイント
- 過去の制作実績: 似た業界や規模のサイトを手掛けたことがあるか
- 費用体系: 見積もりの内訳が明確か、追加費用が発生しやすい項目は何か
- やり取りのしやすさ: スタッフとのコミュニケーション体制やサポート体制
- 得意分野: デザインに強いのか、システム開発に強いのかなど、特徴を見極める
内製チームの編成と育成
社内リソースを活用する場合は、ウェブ制作の知識やスキルがある人材を中心に、小規模でも専用のプロジェクトチームを組むことがおすすめです。以下のような役割分担を明確にしておくと、スムーズな進行が期待できます。
- プロジェクトリーダー: 進行管理、外部とのやり取りの窓口
- デザイナー(またはデザイン担当): テンプレートの選定、レイアウト作成
- コーダー・実装担当: コード修正やCMS設定
- コンテンツ担当: 原稿作成、画像素材の選定、更新作業
- 品質チェック担当: 記事の校正、リンクやデザイン崩れの最終チェック
中小企業では、一人が複数の役割を兼任することも多いでしょう。兼任の場合でも、誰がどの業務を主として担当するのかを決めておくと、責任が曖昧にならず済みます。
段階的リニューアルのポイント
予算や人的リソースに限りがある場合、段階的にリニューアルを進める選択も有効です。たとえば、最初にトップページや主要サービスページだけを重点的にリニューアルし、次のフェーズでその他のページを順次更新していくやり方があります。
段階的に進めるメリット
- 一度に大きな予算を用意しなくて済む
- 社内の作業量を調整しやすい
- リニューアルした部分の効果を観察し、フィードバックを後続の改修に反映しやすい
優先度の付け方
段階的にリニューアルするためには、どのページを先に直すか優先順位を設定する必要があります。一般的には、アクセス数が多いページや直接問い合わせや購買につながるページを先に手を加えるのが望ましいでしょう。また、デザイン的に最も古い印象を与えている箇所や、機能面で不具合が生じている箇所も優先度が高いといえます。
運用の継続と改善サイクル
リニューアル後はそれで終わりではなく、定期的な更新と改善を続けることでサイトの鮮度や利便性が維持されます。段階的なリニューアルは、むしろ「長期的にサイトを育てていく」という考え方に近いともいえます。定期的にアクセス状況や問い合わせ数などの指標を観察し、必要に応じて微調整を行いましょう。
まとめ
小予算でホームページリニューアルを行う際は、まず目的や優先順位を明確にし、費用対効果の高い部分から段階的に手を加えていくことが重要です。デザイン刷新のコツやコンテンツ見直しの進め方を工夫し、社内リソースと外注先を上手に組み合わせれば、限られた予算や人手の中でも成果を得ることができます。また、一度リニューアルを実施して終わりにするのではなく、運用しながら継続的に改善を重ねる姿勢が、最終的にコーポレートサイトの価値を高める鍵となるでしょう。






