Blog お役立ちブログ
写真の統一感を出してブランドイメージを高める撮影ガイドライン
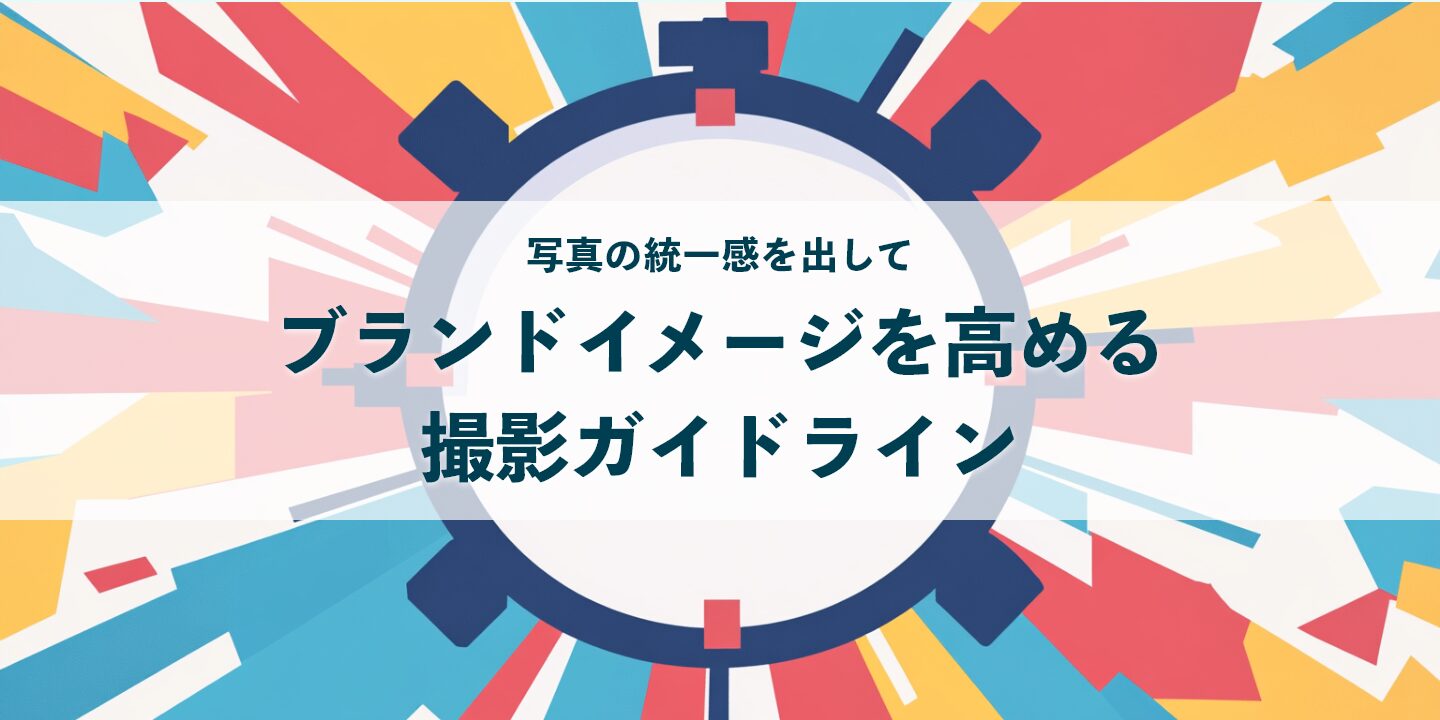
写真の統一感ガイドラインの重要性
写真は、企業やサービスが発信する情報のなかでも特に目に留まりやすい要素です。どれほど文字情報で丁寧に説明していても、写真に統一感がなくバラバラな印象を与えてしまうと、ブランドイメージの浸透を妨げる原因になりかねません。逆に、一貫性のある写真を戦略的に使えば、SNSやWebサイトを訪れたユーザーに「この企業はしっかりとした世界観を持っている」「ブランドとしての魅力が明確だ」と感じてもらうことができます。
特に中小企業では、専門のカメラマンを常駐させる余裕がなく、日常的な写真撮影をスタッフ自身が行うケースも多いでしょう。その結果、撮影スキルや機材の違いが写真のクオリティや雰囲気の差となって表れ、統一感を欠いてしまうことがあります。
しかし、撮影ガイドラインを作り、最低限のルールを社内全体で共有するだけでも、写真の質と統一感を大幅に向上させることが可能です。明るさや色味、構図など、基本的なポイントを合わせるだけで、「どの写真を見ても同じブランドらしさを感じる」という状態を作りやすくなります。
撮影前に押さえておきたい基本準備
誰が撮影を担当する場合でも、写真の品質と一貫性を確保するためには、撮影前の段階から目的やターゲットを明確にし、必要なものをきちんと用意することが大切です。以下のポイントを押さえておくだけでも、撮影後の写真を見比べたときに「軸」がぶれにくくなります。
- ブランドコンセプト・ターゲットの再確認
- 企業やサービスがどのようなイメージを打ち出したいのかを言語化し、関係者同士で共有する
- ターゲット層のニーズや好みに合った写真のテイストを話し合う
- 具体的な使用目的の明確化
- SNS投稿用、Webサイトのトップページ用、商品紹介用、採用情報用など、使用シーンを具体的にイメージする
- 使用場所やデザインレイアウトに合わせて必要なカットや枚数をリストアップしておく
- 担当者同士の情報共有
- 撮影担当者、デザイナー、サイト運用担当者が集まり、必要な写真や期待するイメージについて擦り合わせる
- 写真に文字を入れる場合や、加工前提で撮影する場合は余白の取り方を共有する
- 撮影候補リストの作成
- どんな被写体をどんな構図で撮りたいのか、撮影シーンをリスト化して優先順位をつける
- 商品やモデル、背景など、準備すべきアイテムを事前に確保しておく
以下のテーブルは、撮影前のチェック項目をまとめたものです。
| 撮影前チェック項目 | 内容の確認例 |
|---|---|
| 撮影目的 | SNS投稿用, Webサイトトップ用, 商品紹介用 など |
| 撮影イメージ | 明るい雰囲気, シックで落ち着いた雰囲気, カラフルな印象 など |
| ターゲット層 | 若年層, ビジネスパーソン, ファミリー層 など |
| 必要な道具・小物 | 商品サンプル, 小道具, 背景パネル, モデルの衣装 など |
| カメラ設定 | 画質, アスペクト比, RAW撮影の有無, ISO感度 など |
| 周囲の安全・準備 | 撮影スペースの確保, ケーブル類の整理, 周囲の照明機器の位置確認 など |
| 撮影後の編集前提 | 編集ソフト, 文字入れスペース, カラー補正の要否 など |
| 関係者への連絡・調整 | 希望イメージの共有, 撮影後のファイル名規則, 共有フォルダ など |
使用機材と環境の選び方
写真の仕上がりに大きく影響するのが使用する機材と撮影場所(環境)です。カメラの種類やレンズ、照明機材などがバラバラだと、同じ被写体を撮ってもまったく違う雰囲気になってしまう場合があります。できるだけ統一した機材・設定を使うか、そうでない場合は最低限揃えるべき基準を決めておくのがおすすめです。
カメラ・レンズの選定
- 一眼レフ・ミラーレスカメラ
一眼レフやミラーレスカメラは、レンズ交換や細かな設定が可能なため、高品質な写真を安定的に撮影できます。商品写真や人物写真で背景をぼかしたい場合、レンズ選びによって理想の雰囲気を作りやすいのが大きな利点です。 - スマートフォン
スマートフォンのカメラは近年、画質や機能が大きく向上しています。SNS投稿用の写真などであれば、しっかりとしたライティングや構図を意識するだけで十分なクオリティが得られます。ただし、暗所での撮影や細部の表現は一眼レフ・ミラーレスにはやや劣るため、使いどころを考えましょう。
照明・ライティング機材
- 定常光ライト
常に一定の明るさを保てる照明機材で、写真撮影に慣れていない方でも扱いやすいのが特徴です。影の出方をリアルタイムに把握できるため、ブランドイメージに合わせた雰囲気を作る際に重宝します。 - ストロボやLEDライト
瞬間的に強い光を当てられるストロボや、カラーフィルターを使いやすいLEDライトも便利です。商品の表面の光沢や質感を際立たせたり、ドラマチックな演出をしたい場合は積極的に活用しましょう。
撮影環境の統一
- 背景の色や質感
写真の統一感を出すうえで、背景の色と質感を統一するだけでも大きな効果があります。撮影ブースや背景紙を用意できれば理想的ですが、難しい場合でも撮影場所を固定することである程度の一貫性を保てます。 - 色温度・ホワイトバランスの調整
外光と室内照明が混ざると色がアンバランスになりやすいため、できるだけ光源を統一するか、カメラのホワイトバランス設定で整えておきましょう。
下のテーブルに、機材選定と環境整備のポイントをまとめています。
| 機材カテゴリ | ポイント | こんな場合におすすめ |
|---|---|---|
| カメラ | 一眼レフ・ミラーレスはレンズ交換や細かな設定が可能 | 高品質な商品撮影やモデル撮影、背景をぼかすなどこだわりたいとき |
| スマートフォン | 手軽さと機動力が魅力。SNS程度なら十分な画質を確保できる | 軽いイベント撮影や即時投稿が必要な場面 |
| 照明機材 | 定常光、ストロボ、LEDライトなど目的に合わせて選ぶ | 屋内撮影、商品のディテールを際立たせたい場合 |
| 背景・レフ板 | 背景紙や布で一貫した世界観に、レフ板で光の補正や影を除去 | 被写体をより引き立てたいとき、色味の統一感を出したいとき |
| 三脚 | 手ブレを防ぎ、構図を固定する | 商品撮影、同じアングルを繰り返し撮影したいとき |
構図・アングル・ライティングのポイント
写真の構図やアングル、そして照明の当て方は、見る人の印象を左右する重要なポイントです。同じ被写体でも撮り方が変われば、写真から受ける情報量やメッセージも大きく変わります。統一されたルールを設けることで、ブランドイメージをブレさせない撮影が可能になります。
- 構図の基本ルールを共有する
- メイン被写体の配置(中央寄せ、三分割法など)を決める
- バストアップ写真なのか全身を入れるのか、商品を大きく見せるか背景を活かすかなどを明文化しておく
- アングルをパターン化する
- 商品を斜め45度から撮る、モデルをやや上目線で撮る、などパターンを決める
- 違う撮り方をする場合でも、推奨のアングルをベースにアレンジすると仕上がりの統一感が保ちやすい
- ライティングでブランドの雰囲気を表現する
- 明るくポップなイメージなら、全体に光を回して影を作らない
- シックで洗練されたイメージなら、コントラストを強めて陰影を活かすライティングにする
- 複数の撮影パターンを試す際の注意点
- 撮影者や機材を変えて行う場合は、照明の位置や光量を記録して再現できるようにしておく
- すべてのパターンで共通する最低限のルール(背景色、被写体の大きさなど)を明示すると、撮影した写真同士のブレが少なくなる
撮影後の編集や補正によるブランドイメージ強化
撮影時点である程度品質や統一感を担保していても、仕上がった写真をさらに編集・補正することで、より鮮明にブランドイメージを打ち出すことができます。ただし、編集が行き過ぎると不自然になり、本来の商品の色や質感が損なわれてしまうこともあるため注意が必要です。
- カラー・トーンの調整
- ブランドカラーに合わせて全体の色味を微調整する
- ホワイトバランスがずれている場合は補正して、同じ撮影日の写真同士で色が揃うようにする
- 明るさ・コントラストの最適化
- 暗い写真は多少明るく、鮮やかさを足して見栄えをよくする
- コントラストを上げすぎるとディテールが飛んだり黒つぶれしたりするので、調整は控えめに
- トリミングと解像度
- SNSなどの投稿用に縦横比を整える
- Webサイトに掲載するときは、適度に解像度を落として表示速度を確保する
- フィルターの活用と注意点
- 統一感を出すために同じフィルターをかけるのは有効
- ただし、被写体によっては色味が変わりすぎて実物とのギャップが大きくなる場合がある
編集に使えるツールは多種多様ですが、以下のテーブルに代表的な例を挙げ、特徴と注意点をまとめました。
| 編集ツール | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| Photoshop | レイヤー機能が充実しており、細かい合成や加工が可能 | 多機能ゆえに習得コストが高く、操作に時間がかかる |
| Lightroom | 写真の一括管理と色補正が得意。露出や色調整を素早く行える | 大掛かりな合成や特殊効果の作成には不向き |
| スマホアプリ系 | フィルターや明るさ調整が簡単にできる | 過度なフィルターはブランドの世界観を損なう恐れがある |
| オンラインツール | ダウンロード不要でブラウザ上から利用できる場合が多い | 高度な編集には物足りない場合もある |
社内で共有すべき撮影マニュアルやルールづくり
ルールや基準が明確でないと、担当者や撮影時期、使用機材が変わるたびに写真のテイストがぶれてしまいます。最低限のマニュアルをまとめ、定期的に更新・周知することで統一感をキープしましょう。
- 撮影マニュアルの作成
- 使用機材(カメラ、レンズ、照明など)の基本スペックや推奨設定値
- 構図・アングル・ライティングの例、撮影時のチェックリスト
- ファイル形式や解像度、撮影後のリネーム規則・保管場所などの運用ルール
- 編集ガイドライン
- どのソフトを使うのか、どの程度の加工を施すのか、ブランドカラーはどれかなどを明示
- フォーマット(JPEGかPNGかなど)やサイズ最適化の基準を決める
- 社内研修・OJTの実施
- 撮影担当者が複数いる場合、実際に機材を使いながら確認・練習する
- スマートフォンで撮影する場合でも、カメラアプリの機能や簡単なライティングテクニックを共有すると効果的
- 定期的な見直しとアップデート
- ブランドイメージが変わったり、新しい撮影機材を導入したりした場合はガイドラインも更新
- サイトやSNSの写真を定期的に見直し、改善が必要なところを洗い出す
成功事例・失敗事例から学ぶポイント
具体的な成功事例や失敗事例を知ると、自社の改善点を見つけやすくなります。統一感のある写真を使い続けた結果、SNSのフォロワーから「どの投稿を見ても雰囲気がそろっていて、ブランドとして信頼できそう」と評価を得るケースもあれば、逆に写真のテイストがバラバラで「この企業は結局何を売りにしたいのか分からない」と思われてしまうケースもあります。
成功事例
- 背景や明るさが揃っている商品写真
商品同士を比較しやすく、カタログやネットショップでも見栄えが良い。顧客は迷わず商品を選べるため購買行動にも好影響をもたらす。 - SNS投稿がブランドカラーを踏襲
どの投稿を見ても同じカラーコードを基調とした色味調整が施されており、企業独自の世界観が築かれている。投稿を見たフォロワーが自然と企業を連想する仕掛けができている。
失敗事例
- 色味が違いすぎる写真を混在させている
同じ日のイベント写真でも、撮影担当者ごとにカメラ設定がまちまちで、全く別々の現場に見えてしまう。閲覧者が混乱し、統一感が失われる。 - 被写体の大きさやアングルが不統一
商品紹介ページに並ぶ画像が、あるものはドアップ、あるものは引きの絵で撮られているため、サイズ感や形状の比較が難しくなる。購買意欲をそぐ可能性がある。 - 背景に不要なものが映り込んでいる
賑やかな背景で撮ると、メイン被写体が埋もれて何の写真か分かりづらくなる。ブランドの魅力よりも周囲の雑多さが気になってしまう。
まとめ
写真の統一感を出してブランドイメージを高める撮影ガイドラインは、予算や人員に限りのある中小企業でも取り組みやすいブランディング施策のひとつです。
- 撮影前にブランドコンセプトや使用目的を再確認し、必要な機材や準備を整えることで、写真の軸をぶれさせない。
- 機材選定や撮影環境をある程度統一し、構図・アングル・ライティングの基本ルールを決めることで、誰が撮影しても近い雰囲気の写真が撮れる。
- 撮影後の編集では、色調補正や明るさ調整を行い、ブランドカラーを意識した写真に仕上げる。ただしやりすぎないことが大切。
- 社内マニュアルやルールづくりをして、撮影・編集の基準を明文化し、定期的にレビューや更新を実施する。
これらを実践することで、SNSやWebサイトを訪れたユーザーが「ここはしっかりとした世界観を持った企業だ」と感じられるようになり、商品やサービスへの信頼感も高まります。撮影ガイドラインは、一度作れば終わりではなく、運用を通じて随時ブラッシュアップし、より洗練されたブランドイメージを確立していくための礎となるでしょう。






