Blog お役立ちブログ
会社ホームページを作らないリスクと失う機会を徹底解説
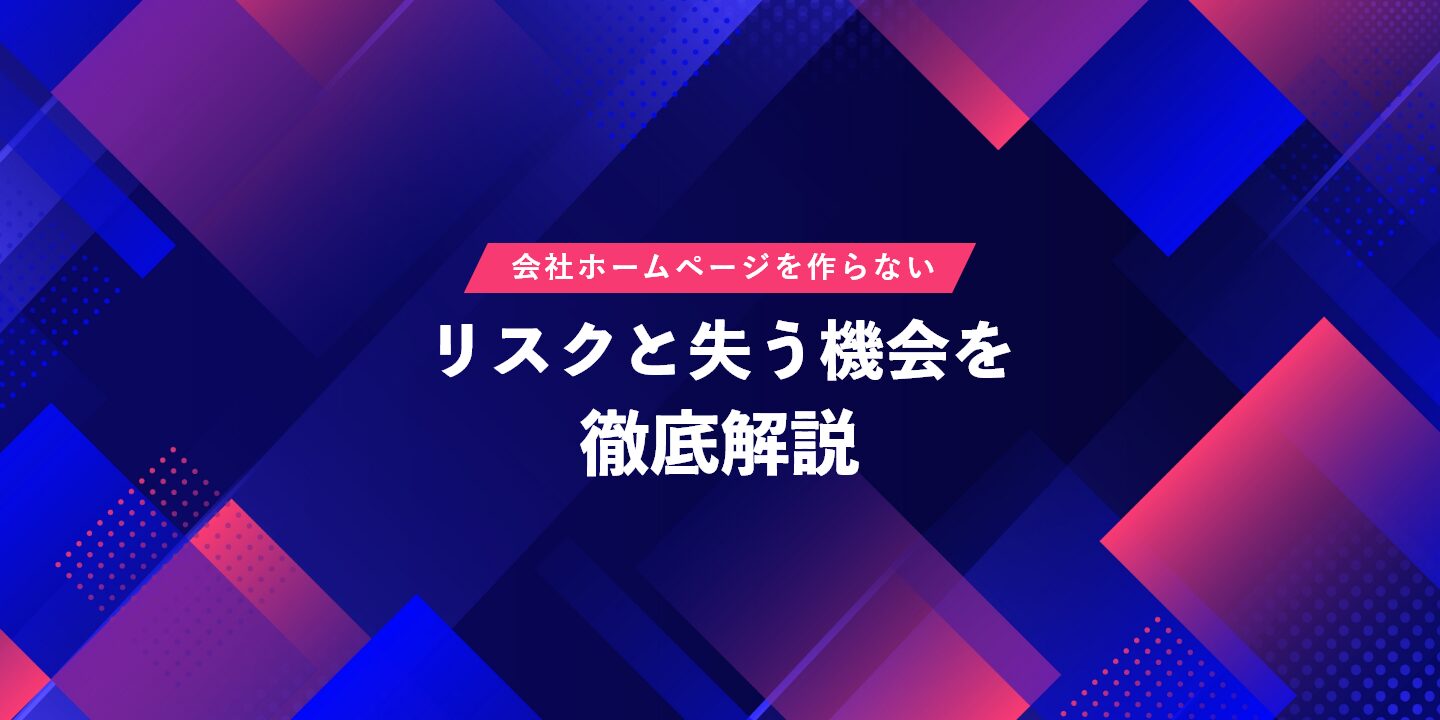
はじめに
中小企業の中には、「いつか作ろう」と思っているものの、なかなか会社ホームページの制作に踏み切れていないケースが少なくありません。身近な同業他社がホームページを立ち上げはじめると、「ちょっと焦る」「どこか置いていかれている気がする」と感じることもあるでしょう。また「ネットに情報がない会社は信用されにくい」という話を耳にしながらも、具体的に何から手をつければいいかわからず、結局先送りにしてしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし、会社ホームページを持たないことは想像以上に大きなリスクを伴います。信頼性の低下、問い合わせや取引のチャンス喪失、採用面での不利など、ビジネスのあらゆる面に影響を及ぼす可能性があるからです。本記事では、会社ホームページを作らないことによる主なリスクやその背景、さらにホームページを作成・運用するうえで押さえておきたいポイントを解説していきます。
会社ホームページを作らないリスクと背景
まずは、なぜ会社ホームページが必要とされているのか、その前提となる背景から押さえてみましょう。
インターネットで情報を得ることが当たり前の時代
現代では、商品やサービスを利用したいと考えたとき、まずインターネットで検索をして下調べをする人が圧倒的に多いといわれています。特にBtoBの取引でも、最初の情報収集をオンラインで進めるケースが増えました。もし企業の情報がネット上に全く存在しない、あるいは断片的すぎる場合、顧客や取引先は「この会社は本当に大丈夫なのか」と不安に思う可能性があります。
信頼獲得の場としてのホームページ
会社概要や実績、理念などがきちんと示されているコーポレートサイトは、対外的な「顔」として機能します。名刺やチラシだけでは伝えきれない要素をホームページでしっかり補完することで、企業の信頼度を高められます。ホームページを作らないことは、こうした「信頼獲得の場」を放棄しているとも言い換えられるのです。
作らない背景にある「コスト」「運用」「知識不足」
一方で、作りたくても作れない背景としてよく挙げられるのが「コスト面の不安」「運用にかかる手間」そして「制作知識やノウハウの不足」です。どこに外注していいのかわからない、制作後の更新を誰が担当すればいいのかが不透明、といった声は少なくありません。しかし、こうしたハードルを放置してしまうと、結果的にビジネスチャンスを逃す可能性が高まります。
よくある誤解と見落とし
企業のホームページに対して、以下のような誤解や思い込みを持っている経営者も多いです。
- 「SNSアカウントがあれば十分」
SNSアカウントは確かに手軽ですが、あくまでSNS企業のプラットフォーム上での存在です。SNSの仕様変更やアカウント凍結リスクもあるため、自社でコントロールできるホームページを持っておく意義は大きいです。 - 「取引先は昔からの顧客ばかりで、ネットからは来ない」
今は既存顧客がメインかもしれませんが、新規取引先が「会社の評判」を調べる際にホームページを確認する可能性は十分あります。また、既存顧客も追加発注や新製品の情報収集の際にホームページがないと不安を感じる場合があります。 - 「大手企業しか恩恵がない」
実は、中小企業の方がホームページを活用してターゲットを絞り込んだ展開を行いやすいといったメリットがあります。規模の大小にかかわらず、ネット上で情報を提供する意義は高いのです。
ホームページを持たないことで失う機会
ホームページを持たないままにしておくと、想像以上に多くの機会損失が発生する可能性があります。以下では、具体的にどんな機会を逃してしまうのか見ていきましょう。
- 潜在顧客へのアプローチ
新規に取引したい企業や顧客があなたの会社について検索したとき、情報が見つからないとそのまま他社に流れてしまうリスクがあります。 - 採用候補者との出会い
企業が自社の魅力を発信する場として、ホームページは重要です。求職者は会社名を検索してどんな事業をしているのか調べるのが一般的。ホームページがない、あるいは情報が不足していると、応募する前に離脱してしまうかもしれません。 - 社外パートナーや協力企業とのつながり
「実績のある企業と組みたい」「安心して任せられる会社を探したい」と考えた時、ホームページは一種の証明書になります。協業やパートナーシップの機会にも影響を与えます。 - ブランドイメージの醸成
企業理念や活動内容をオンラインで継続的に発信できるのはホームページならでは。SNSよりもオフィシャル感が強いため、ブランディングの観点からも欠かせません。
ホームページが与える信頼感とブランディング効果
ホームページは、企業の世界観や提供価値をわかりやすく伝えられる貴重なスペースです。デザインやコンテンツのトーンによって、ターゲットとする顧客層や企業姿勢を効果的にアピールできます。また、独自ドメインで発信する情報には公式感が伴うため、SNSや無料のブログサービスに比べて信頼度が高い傾向にあります。
さらに、ホームページ上で顧客の声や実績事例、導入事例などを紹介することで、事業の強みを具体的に伝えることができるため、他社と差別化しやすくなるのです。
ホームページを作らない場合のデメリット比較表
ここで、ホームページを作らないまま放置した場合の主なデメリットを整理した表を見てみましょう。
| デメリット | 内容 | 影響度 |
|---|---|---|
| 信頼性の低下 | 社名を検索しても情報が出てこない、もしくは断片的で公式ページがないため、信用面で損をする可能性が高い | 中〜大 |
| 検索流入の機会損失 | 商品名・サービス名・企業名などで検索したユーザーを逃してしまう | 大 |
| 説明コストの増加 | ホームページがないことで、商談・問い合わせ対応のたびに一から企業情報を説明しなければならず、リソースを浪費 | 中 |
| 新規顧客・パートナーの獲得機会損失 | 企業間取引や採用でホームページをチェックする慣習があるなか、情報不足により候補から外される | 大 |
| ブランドイメージ構築の制限 | SNSだけで企業イメージを伝えるには限界があり、オフィシャル情報を定期的・体系的に発信できない | 中 |
上記のように、ホームページがないというだけで、企業活動全般にわたる機会損失が広範囲に及ぶことがわかります。
ホームページを作るメリットと注意点
では逆に、ホームページを作ることで得られる主なメリットを整理してみましょう。
- 顧客との接点増加
24時間365日、企業情報やサービス内容を閲覧できる場所があることで、見込み客が問い合わせや購入に進む可能性が高まります。 - 信頼度・ブランド力の向上
オフィシャルな情報をまとめて発信できる場として、ホームページは大きな役割を担います。しっかりデザインされたホームページは、企業の信頼感を高める要因になります。 - 集客チャネルの拡大(SEO対策など)
検索エンジン経由で潜在顧客を取り込めるのは、ホームページならでは。SNSや紙媒体だけではアプローチできない層へのリーチが期待できます。 - 企業活動の効率化
お問い合わせフォームを設置する、FAQを作るなど、顧客対応の一部をオンラインに移行することで、営業やサポートの負担を軽減できます。
注意点
ただし、ホームページを作るだけでは不十分です。作成後の更新やセキュリティ対策、デザインやユーザビリティの改善を怠ると、むしろ企業イメージを損なう場合があります。特に長期間放置されているサイトは「この会社は大丈夫なのだろうか」というマイナスの印象を与えかねません。
ホームページ制作の基本手順表
ホームページ制作に踏み切る際、どのような手順で進めるべきかをまとめてみました。社内で検討する際の簡易的な指針として参考にしてください。
| 手順 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 目的・ゴールの設定 | 何を目標にホームページを作るのかを明確に。例:問い合わせ数増加、採用応募数増加など |
| 2 | サイト構成・必要ページの洗い出し | 会社概要、事業紹介、実績紹介、問い合わせフォームなど、必要なページをリストアップ |
| 3 | 制作パートナー選定 or 内製体制の構築 | 外部に任せる場合は相見積を取り、実績やサポート体制を確認。内製する場合は担当者のリソースを確保 |
| 4 | デザイン・コンテンツ制作 | ターゲット層に合わせたデザインや文章作成。写真や動画も適宜活用 |
| 5 | サイト公開・SEO基本設定 | 独自ドメイン、検索エンジンに登録、メタタグやセキュリティ対策など、初期設定をしっかり行う |
| 6 | 運用・定期的な更新 | ニュースやブログで最新情報を発信。アクセス解析をしながら継続的に改善 |
この表をベースに、必要に応じて項目をカスタマイズしながら進行するとスムーズに進めやすいでしょう。
ホームページ運用のポイントと改善策
ホームページは公開して終わりではありません。以下のような運用面でのポイントを押さえておくと、長期的な成果につながります。
- 定期的な情報更新
企業の動きや実績をタイムリーに発信することで、サイトの鮮度を保つことが重要です。新商品やサービスのリリース、イベント情報、受賞歴などを積極的に掲載しましょう。 - アクセス解析の活用
どのページがよく閲覧されているか、どういう経路でユーザーが来ているかを把握することで、改善のヒントを得られます。 - モバイル最適化
スマートフォンからのアクセス比率は高まる一方です。レスポンシブデザインや読み込み速度の最適化を行い、ストレスなく閲覧できるようにしておきましょう。 - セキュリティ対策
サイトが不正アクセスやウイルスに感染してしまうと、企業の信用問題に直結します。定期的なバックアップとセキュリティアップデートを怠らないようにしましょう。
事例・具体例の紹介
例えば、ある中小企業では長年にわたり地域のリピーターを中心にビジネスを展開していましたが、取引先が世代交代するにつれ「ホームページがないのは信用できない」と言われる機会が増加。そこでホームページを開設したところ、従来の取引先からの評価が上がっただけでなく、新規顧客層の問い合わせも増加したそうです。
また、別の企業では採用活動において「自社サイトがある」というだけで応募者が安心感を持ち、面接前の離脱率が下がったという報告もあります。やはり、オンライン上に公式情報があることが信頼性の向上に寄与していると考えられます。
リスクを回避するうえでのチェック項目表
最後に、会社ホームページの未開設・運用放置によるリスクを回避するために、最低限チェックしておきたい項目を表にまとめます。
| チェック項目 | 重要度 | 対応状況 |
|---|---|---|
| 会社ホームページ自体を保有しているか | ★★★ | 未対応 / 対応済 |
| 会社概要やサービス内容を整理したページがあるか | ★★★ | 未対応 / 対応済 |
| 問い合わせフォームや連絡手段がわかりやすく設置されているか | ★★ | 未対応 / 対応済 |
| 定期的に更新できる運用体制や担当者がいるか | ★★ | 未対応 / 対応済 |
| SNSや名刺など他の媒体との情報連携・誘導をしっかり行っているか | ★ | 未対応 / 対応済 |
| セキュリティやプライバシーポリシー、利用規約などは整備されているか | ★ | 未対応 / 対応済 |
この表を用いて自社の状況を点検し、対策が必要な部分を洗い出すことで、ホームページに対する不安やリスクを一つずつ減らしていくことができます。
まとめ
会社ホームページを作らないリスクは、中小企業にとって決して軽視できるものではありません。情報発信の場を失うだけでなく、信用力や将来のビジネス機会を大きく損なう可能性があります。逆に、しっかりと目的やターゲットを定めてホームページを構築・運用すれば、顧客との接点を増やし、信頼感を高める強力な武器となるでしょう。
コストや運用負担が不安で躊躇している場合は、まずは社内外のリソースや専門家の力を上手に借りながら、最低限必要な情報を整理するところから始めてみてください。今は高額な予算をかけなくても作りやすい選択肢は増えていますし、ターゲットに合った規模と内容でサイトを作ることも可能です。大切なのは、何よりも「ホームページがもたらすリスク回避と機会創出」のバランスを理解し、行動に移すこと。
自社の信頼度や将来の成長機会を逃さないためにも、会社ホームページの重要性を改めて考え、早めに対策を講じることをおすすめします。






