Blog お役立ちブログ
コーポレートサイトのトップページメニュー増やしすぎ対策
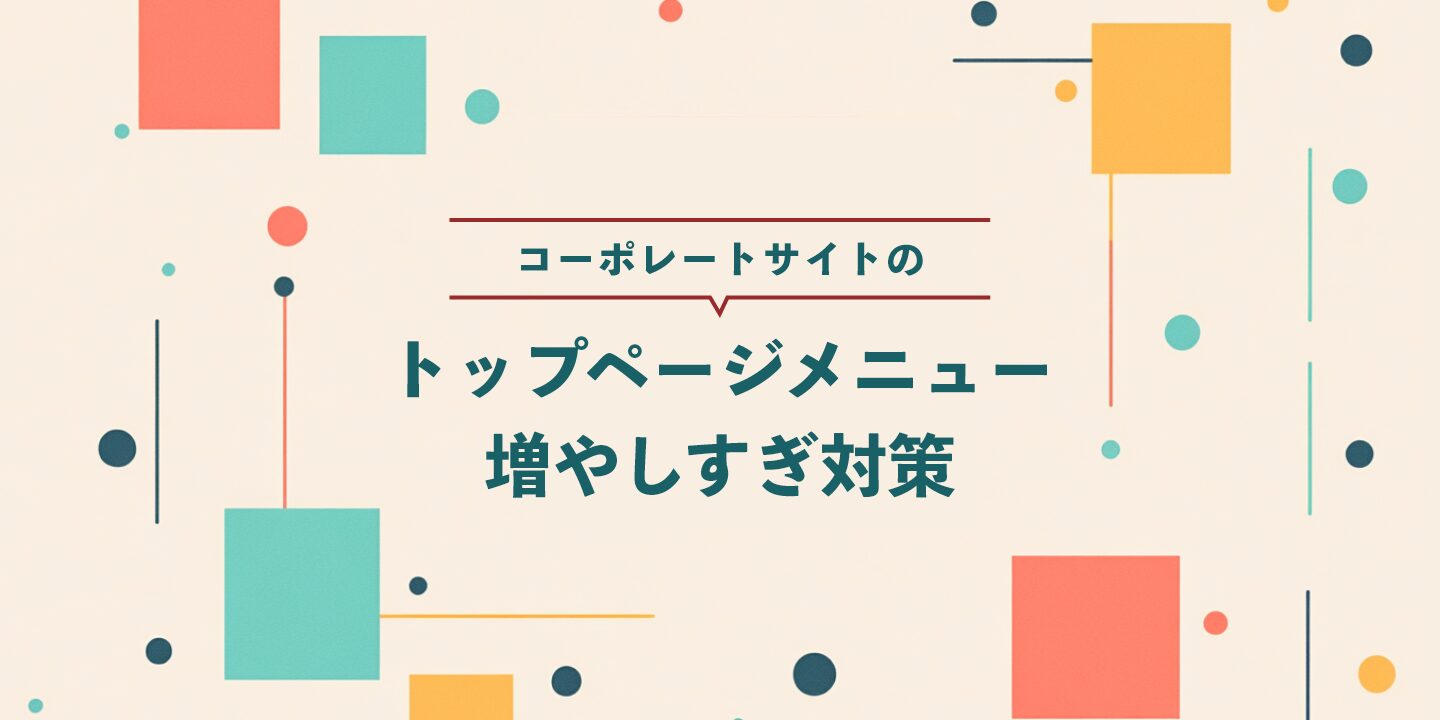
【はじめに】メニューを増やしすぎる背景と問題点
コーポレートサイトを運営する中小企業は、自社の情報をできるだけ多く掲載したいという思いから、トップページにメニュー(ナビゲーション)をどんどん追加してしまいがちです。新しいサービスや実績、採用情報など、扱いたい情報が次々に増えるにつれ、気がつくとメニューが10個以上に膨れ上がり、ユーザーにとってどこをクリックすれば目的の情報にたどり着けるのか分かりにくくなるケースは少なくありません。
トップページメニューが過剰になっている場合、以下のような問題が起こりやすくなります。
- ユーザーが迷う
メニューが多すぎると、どれをクリックすれば良いのか一目で分からず、ユーザーが探している情報にたどり着く前に離脱してしまう可能性があります。 - 重要な情報が埋もれる
せっかく用意した必須コンテンツや最新情報が、メニューの多さに紛れて利用者の目に留まりにくくなります。 - サイトの印象が散漫になる
トップページの外観に統一感がなくなり、ブランドイメージが確立しにくくなることがあります。 - 運用コストが上がる
更新やリニューアルを行う際に、どのページを残してどのページを再編すれば良いのか判断がつきにくくなり、運用にも手間がかかります。
本記事では、こうした「メニューを増やしすぎてしまう」状態を改善し、ユーザーが迷わず目的の情報へスムーズにアクセスできるようになるための考え方と具体的な手順を解説します。
【メニュー数を抑えるメリット】ユーザー目線・運用目線
ユーザー目線でのメリット
- 目的ページへのアクセスが容易になる
メニュー数が適切だと、ユーザーが必要な情報を探しやすくなります。トップページを訪れた瞬間に、欲しい情報がどのメニューに含まれているかをすぐに判断できるため、ストレスを感じにくくなります。 - コーポレートイメージが洗練される
情報が整理されていると、サイトを訪れた人に「この企業はきちんと情報を整理し、ユーザーを考えた設計をしている」という好印象を与えます。ブランディング面でもプラスに働きます。 - スマートフォンからの利用にも有利
スマートフォンなどの小さな画面で閲覧する際、メニューが多すぎるとスクロール量も増え、ユーザーが混乱してしまいます。メニューを絞ることでモバイル対応もしやすくなります。
運用目線でのメリット
- 管理がしやすい
ページ数が絞られていると、更新やリニューアル時に確認が必要なページを特定しやすいです。運用にかかる時間的コストと人手を削減できます。 - 情報戦略を立てやすい
無駄なページや重複するコンテンツが少なくなるため、コーポレートサイト全体として、どの情報を優先して配信していくかを考えやすくなります。 - ユーザーからの問い合わせ質向上
「どこを見ればいいのか分からない」「欲しい情報が見つからなかった」という理由での問い合わせが減り、より質の高い問い合わせや商談が増える可能性があります。
【情報整理とナビゲーション設計】カテゴリー分けと階層化
メニューを適正に保ち、かつユーザーに必要な情報を十分に提供するには、情報整理とナビゲーション設計が欠かせません。以下のプロセスを踏むことで、トップページに表示すべき内容を絞り込み、余計なメニューを排除しつつ重要な情報をまとめられます。
- 掲載情報をすべて洗い出す
まずは、現状サイトに掲載されているページや、将来的に追加したいと考えているページをリスト化します。メニューを整理するためには、現状をしっかり把握することが大切です。 - グルーピングと優先度の設定
洗い出したページを「サービス紹介」「会社情報」「ニュース」など大まかなグループに分けます。同時に、どの情報が最も重要で、ユーザーが頻繁にアクセスする可能性が高いのか優先度を付けましょう。 - トップページで表示する階層を決める
グルーピングしたカテゴリーの中でも、特にメインとなる数項目をトップページのメニューに表示し、必要に応じてドロップダウンメニューなどのサブメニューで階層を深めていくと分かりやすい設計になります。 - 階層化と命名のルール化
トップページに載せる大カテゴリーを決めたら、サブカテゴリーの命名や階層構造を統一感のある形で整理します。例えば「サービス紹介」の下に「サービスA」「サービスB」を置くなど、ユーザーが直感的に理解しやすい言葉を選ぶのが大切です。 - 最小限のメニュー項目数を意識
一般的に、メニューを一度に認識できる項目数は5〜7個程度が適切と言われることが多いです。メインメニューが10個を超える場合は、サブメニューやページ内リンク、バナーなどを活用して、トップページに並べる数を可能な限り減らす工夫をしましょう。
ここで、一度「メニュー数」をキーワードに考え方を整理するための表を紹介します。
| メニュー数 | ユーザーが感じる印象 | 適切な運用例 |
|---|---|---|
| 1~5個 | 分かりやすい, スッキリしている | メイン情報のみを厳選し、階層的に細分化 |
| 6~9個 | 少し多いが、うまく整理できていれば許容範囲 | グルーピングをしっかり行い、デザインを工夫する |
| 10個以上 | 分かりにくい, 情報過多 | サブメニューへの分割や不要項目の統合を検討する |
表をもとにサイトの現状をチェックし、必要に応じて情報を再編成するのがポイントです。
【具体例】メニュー再編の手順とポイント
以下に、メニュー数が10を超えてしまったサイトを例に、どのように再編すると良いかを示します。
- 現状把握
- トップページメニュー一覧
- ホーム
- 会社概要
- 代表メッセージ
- 事業内容
- サービスA
- サービスB
- サービスC
- ニュース・お知らせ
- 採用情報
- お問い合わせ
- トップページメニュー一覧
- 必要性の精査
- 「代表メッセージ」は「会社概要」に統合が可能か再検討
- 「ニュース・お知らせ」はトップページに最新情報を載せるウィジェットやバナーでカバーできないか検討
- カテゴリーの再編案
- 会社情報(会社概要, 代表メッセージ)
- サービス情報(サービスA, サービスB, サービスC)
- ニュース(お知らせ・更新情報など)
- 採用情報
- お問い合わせ
- 最小限のメニュー項目に絞る
- ホーム
- 会社情報
- サービス
- ニュース
- 採用情報
- お問い合わせ
- 階層化の活用
- 「会社情報」→ 「会社概要」「代表メッセージ」
- 「サービス」→ 「サービスA」「サービスB」「サービスC」
- 「ニュース」→ 「お知らせ」「イベント案内」「更新履歴」など
以上のように大カテゴリーを6項目程度に絞り、各カテゴリーの下位に詳しいページを配置することで、トップページがシンプルになります。重要情報がまとまっていて、かつ必要に応じて階層をたどって詳細情報を探せる仕組みです。
下記の表で、実際のトップページメニュー(大カテゴリー)とサブメニュー(小カテゴリー)の構成イメージを示します。
| 大カテゴリー | 小カテゴリー(サブメニュー例) |
|---|---|
| 会社情報 | 会社概要, 代表メッセージ, アクセスマップ |
| サービス | サービスA, サービスB, サービスC |
| ニュース | お知らせ, イベント案内, 更新履歴 |
| 採用情報 | 募集要項, 社員インタビュー, 福利厚生 |
| お問い合わせ | フォーム, 電話窓口 |
このように整理されたメニュー構成であれば、ユーザーが迷いにくく、運営側も新しいページの追加や更新がしやすくなります。
【表を用いた整理】わかりやすいメニュー構成の比較・事例
実際にメニュー構成を再設計する際、どのように比較検討すれば良いかが分かりにくい場合があります。下記の表を参考に、現状と理想を見比べる方法を示します。
| チェック項目 | 現状 | 理想 | 修正方針 |
|---|---|---|---|
| 大カテゴリー数 | 10 | 5~7 | 統合可能なページを整理 |
| 各カテゴリー内のページ数 | 1~2 | 2~4 | 必要に応じて新規作成・統合 |
| 階層深度 | 1階層目で10項目 | 1階層目5~7、2階層目も管理しやすく | サブメニューを活用し、深さを一定に |
| 用語の統一性 | バラバラ | 分かりやすい | 命名規則を決めて利用 |
このようにチェック項目を設定して比較することで、どこに問題があるのか明確になります。単純に「メニューが多い」と一括りにするのではなく、「どのカテゴリーを統合するか」「どの階層をどこまで深くするか」など、具体的に検討すべき点を洗い出すのが大切です。
【運用・改善の継続】定期的な見直しとリニューアル戦略
コーポレートサイトのトップページメニューを最適化しても、企業の事業内容や方針が変われば、再びメニューが増えていく可能性があります。よって、一度メニューを整理して終わりではなく、定期的な見直しを行う姿勢が求められます。具体的には下記の流れをおすすめします。
- 定期的にアクセス解析を確認する
どのメニューがよくクリックされているか、あるいはあまり利用されていないかを把握することで、メニュー構成の改善点が見えてきます。 - 社内での情報共有
新しいサービスや実績を追加する場合、既存メニューとの重複を避けられないか事前に検討しましょう。各部署や担当者との連携を取りながらサイト構成を考えることで、再びメニューが増えすぎるのを防ぎます。 - リニューアルのタイミングを決める
小さな改善は随時行いながら、2〜3年程度の周期で全体的なリニューアルを検討する企業もあります。リニューアル時には、メニュー構成の根本から見直し、新しい事業やサービスに合わせて再定義すると効果的です。 - メニューを追加するときのルール化
メニューを追加する際のチェックリストや社内ルールを作ると良いでしょう。例えば「既存カテゴリーでカバーできないか」「トップページに載せるよりもサブカテゴリとしての掲載で十分ではないか」といったフローを設けることで、安易にメニューを増やさない企業文化を築くことができます。
【まとめ】
コーポレートサイトのトップページメニューが増えすぎると、ユーザーの混乱を招き、企業の情報発信力が低下する恐れがあります。メニュー数を抑えて必要な情報を整理することで、
- ユーザーが目的の情報に素早くアクセスできる
- 企業のブランディングや信頼度が向上する
- 管理・運用コストが下がる
といったメリットを得られます。メニューを整理する際は、まずはサイトに掲載している情報をリストアップし、グルーピングや優先度の設定を行ったうえで、トップページに表示する大カテゴリーを絞り込んでみてください。さらに定期的に見直しを行いながら、企業の発展とともに最適なメニュー構成を維持していくことを目指しましょう。






