Blog お役立ちブログ
サービス名が先に取られてるドメイン、諦めるしかない?対応策を解説
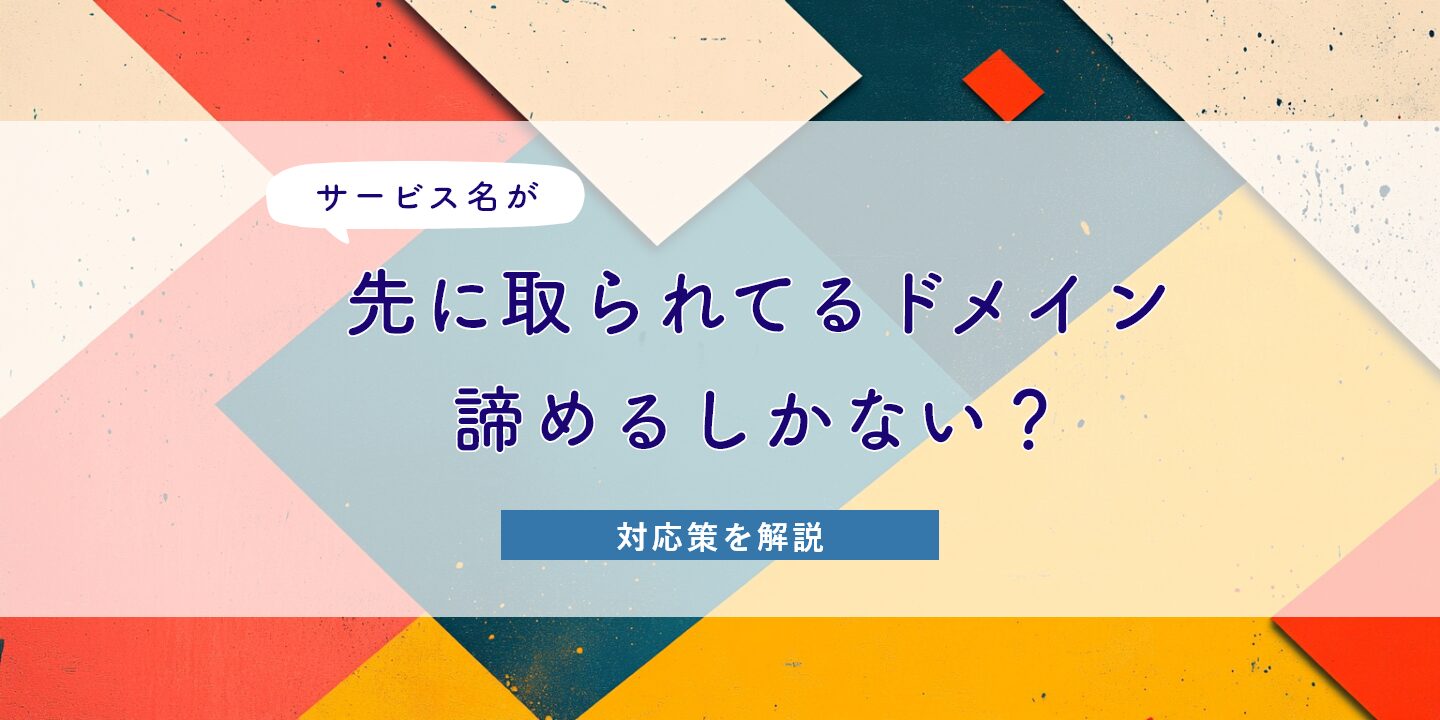
はじめに
新規に事業を始めるとき、あるいは既存の事業で新たにサービスを立ち上げるときに大切な要素の一つが「ドメイン」です。サービス名や企業名をそのままドメインとして使うことで、利用者に認知してもらいやすくなります。ところが、いざ調べてみたら希望していたドメインが先に使われていたということも珍しくありません。
この記事では、「サービス名 先に 取られてる ドメイン 諦めるしかない?」とお悩みの中小企業の経営者や担当者に向けて、
- すでに取得されているドメインに直面したときの課題
- 商標権との関係や交渉のポイント
- 代替ドメインやサブドメインの活用などの具体策
- ドメイン取得・管理の基礎知識
などを解説していきます。これを読めば、単純にあきらめるのではなく、リスクを整理しながら最適な落としどころを考えるきっかけになるでしょう。
ドメインが取られているときの代表的な課題
「サービス名のドメインが先に取られていた」という状況に遭遇すると、特に以下のような課題が浮上します。
- ブランド力やサービス認知への影響
自社サービスの名称でドメインを持ちたいのに、すでに同じ文字列のドメインが使われていると、ブランドメッセージの一貫性が損なわれる可能性があります。ユーザーが検索エンジンやアドレスバーに直接打ち込んだ際に、別のサイトへアクセスしてしまうと混乱が生じることもあるでしょう。 - 代替ドメインのネーミングが難しい
ハイフンや数字を入れる、文字列を少し変形するなどで新たにドメインを探す場合、覚えにくくなったり、見た目が長くなったりします。結果的にブランドイメージが弱くなる懸念があるため、なかなか踏み切れないという悩みがあります。 - 法的リスクや商標との衝突
自社のサービス名が実は他社によって商標登録されており、それを意図せず使用してしまうケースがありえます。この場合、ドメインを先に取られただけでなく、商標権侵害のリスクまで背負う可能性があります。
また、自分の企業が先に商標を持っていても、ドメインを他社が持っていることによって混乱を招く場合があります。 - 交渉・買収コストの負担
もしも現在使われているドメインを所有者から買い取る場合、予想以上に高額な交渉金額が提示されることがあります。新規起業の場合にはとくに予算を抑えたい事情があるため、この点で悩む中小企業は少なくありません。 - 時間と手間のかかるリスクマネジメント
法務的な確認や交渉、代替ドメインの検討など、すべてを短期間で決着させるのは容易ではありません。時間をかけて対応するうちに、事業計画そのものが遅れるリスクも生じます。
こうした課題の存在を把握しておくことで、「とにかくドメインが欲しいから買う」「あきらめるしかない」といった短絡的な判断を避けられるでしょう。
商標権とドメインの関係
ドメインが先に取得されていて困ったとき、見落としがちなのが「商標権との関係」です。サービス名や企業名をドメインに用いる場合、同じ名称が商標登録されている可能性もあるため、取得済みドメインと商標の関係を確認することは非常に重要です。
商標権とドメインの違い
- 商標権
企業や個人が特定の名称やロゴマークを独占的に使う権利を指します。原則的に商標は業種や商品・サービス区分によって保護される範囲が異なります。 - ドメイン
インターネット上の住所にあたる文字列です。同じドメイン名は全世界で唯一となり、重複はできません。基本的に「先願主義」であるため、早い者勝ちの仕組みが多いです。
ドメインを先に取得している人が必ずしも該当名称の商標を持っているわけではありません。しかし、万一相手が商標権も保有していれば、ドメインの使用をめぐる紛争に発展する場合もあるでしょう。逆に自社がその名称の商標権を保有していても、相手が先にドメインを取得しているケースでは、簡単に取り戻せるとは限りません。最終的には法律や裁判の話になる可能性もあり、そのためのコストや時間を考えると安易にトラブルを起こすのは避けたいところです。
事前に確認したいポイント
- その名称(サービス名)について、自社は商標を持っているか
- すでに取得されているドメインの所有者が、同じ名称の商標を持っているか
- 自社と同一または類似する区分(業態)で商標が成立しているか
- 商標権を保有していない場合、出願の予定や必要性があるか
こうした点を整理すると、単純に「同じ名前だから交渉しよう」と動くより、最適な選択肢を検討しやすくなります。
代替ドメインの考え方
希望していたドメインが取られていたとき、まず検討したいのが「代替ドメイン」です。どうしても譲ってもらえない、あるいは予算的に買収が難しいという場合は、サービス名を少しアレンジしたり、別のTLD(トップレベルドメイン)を選んだりすることで解決を図ります。
代替案をリスト化して比較する
代替ドメインを考える際には、いくつかの候補を挙げて比較検討してみましょう。下記のような表で整理すると判断しやすくなります。
| 候補ドメイン | 名前の短さ | 覚えやすさ | イメージ | 取得コスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 例)サービス名-hp.com | 中 | 中 | 若干落ちる | 安い | ハイフンが気になる |
| 例)サービス名.jp | 短 | 高 | 企業感ある | やや高め | 国別ドメインで信頼感大 |
| 例)サービス名.biz | 短 | 中 | ビジネス感 | 安い | 日本国内では馴染み薄い |
| 例)サービス名.net | 短 | 高 | 汎用的 | 安い | 利用者も多い |
ポイントは、「いかにユーザーに覚えてもらいやすいか」 を優先しつつ、取得可能な文字列の長さやコストなどを総合的に見て決定することです。
ハイフンや数字の取り扱い
ハイフンや数字を使うと、どうしても覚えづらい印象が強くなる可能性があります。ただ、サービス名が長い場合やすでに他の候補がすべて使われている場合には、有力な回避策にもなりえます。
- ハイフンは、単語をつなげる形で使うとある程度視認性を保てます。
- 数字はサービス名の末尾などに加えることで、別の意味合いを出すことができます(例:サービス名2など)。
- 日本語ドメインを使うという手もありますが、ブラウザや環境によって文字化けやPunycode表示になる可能性があるため、十分にメリット・デメリットを検討しましょう。
サブドメインや別ブランドでの展開
どうしても希望の文字列が取得できない場合、サブドメインや別ブランド名で展開するのも一つの手段です。
- 企業のコーポレートサイトがすでに存在し、「サービス名.企業ドメイン」などのサブドメインで運用する
- サービス名を少し変化させ、これを新しいブランドとして位置づける
これらの方法なら、新たに凝ったドメインを獲得する苦労が少なくなるかもしれません。ただし、長期的に見ればサービス名とドメインが一致している方がブランディング上はわかりやすいので、あくまでも「応急処置」として考えるのか、それとも「これが最終形」なのかを明確にしておきましょう。
買収や交渉の手順と注意点
ドメインをどうしても譲ってもらいたい場合、交渉を行って買収するという選択肢があります。ただし、以下の点に留意しましょう。
交渉のステップ
- 所有者の特定
WHOIS情報やドメインの登録代理店を調べ、所有者あるいは代理人の連絡先を確認します。 - 所有者への連絡
どのような用途でそのドメインを使用しているかをヒアリングし、買い取りの意思をやんわりと伝えます。 - 価格提示・条件交渉
相手の提示額が高すぎる場合には、他の選択肢(代替ドメインの可能性など)も示唆すると、過度に吹っかけられるリスクを下げられるでしょう。 - 法務リスクの確認
商標権や不正競争防止法に抵触しないかどうか、必要に応じて専門家に相談することで、後々のトラブルを回避しやすくなります。 - 契約書の取り交わし
ドメイン移管や所有権譲渡に関する正式な手続きと支払い条件を文書化し、双方が納得してから取引を完了します。
交渉・買収におけるメリット・デメリット
買収交渉に入る前に、下記のような表を参考にメリットとデメリットを把握しておくことが大切です。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 所望のドメインを取得 | ブランドイメージを統一できる | 価格が高騰する可能性がある |
| 時間と手間の削減 | 新規にネーミングを考える必要がなく、サービスリリースを加速できる | 手続きや交渉に時間がかかる場合がある |
| 競合他社への流用阻止 | 自社名・サービス名を守れる | すでにドメインが検索エンジンで評価を得ている場合、自社サービスと無関係な評価が混在 |
| 商標権とのクリアな関係 | 自社の商標があれば優位に交渉しやすい | 相手も商標を持っている場合、交渉自体が困難になる |
メリットだけに目を向けず、予算やリスク、将来的な利用価値を総合的に判断することが大切です。
交渉が難航した場合
もし交渉がまとまらない場合は、やはり「代替ドメインを使う」という選択肢に戻るのがベターです。高額な買収が必要なほど自社のビジネス上必須なドメインかどうか、改めて考え直すきっかけにもなるでしょう。
ドメイン取得・管理の基本的な流れ
すでに使われているドメインに対して交渉や代替案を検討する前に、そもそも新規でドメインを取得するときの基本的なプロセスを押さえておくと理解が深まります。
- ドメイン検索
各種レジストラ(ドメイン登録サービス)で希望の文字列とTLDを入力し、空きがあるか確認します。 - 利用規約・料金の確認
ドメインの種類によって取得費用や更新費用が異なるため、あらかじめ複数社で比較検討すると良いでしょう。 - 取得手続き
必要事項を入力し、クレジットカードなどで支払いを完了すると、指定の期間(通常は1年~数年)利用権を確保できます。 - ネームサーバー設定
ドメインをウェブサイトやメールで使うためには、ホスティングサーバーの情報を設定する必要があります。 - 定期的な更新
ドメインは取得して終わりではなく、期限が切れたら更新する必要があります。期限切れになると他人に再取得される可能性があるので注意が必要です。
取得費用・更新費用の目安比較
ドメイン管理を行ううえで、TLDによって費用が変わります。以下のような形で比較しておくと、自社に合ったTLDを選びやすくなります。
| ドメイン種類 | 初期取得費用 | 年間更新費用 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| .com | 比較的安い | 比較的安い | 世界的に最もポピュラー |
| .net | 安い | 安い | 汎用性が高い |
| .jp | やや高め | やや高め | 日本国内向けで信頼感高い |
| .co.jp | 高め | 高め | 企業限定、信用度が高い |
| .biz | 安い | 安い | ビジネス用途に特化 |
取得費用が安くても更新費用が高い場合もありますし、同じTLDでもレジストラによって価格差があります。事業の規模感や更新のしやすさを考慮して選択することが重要です。
具体例:起業家がやりがちな失敗と対策
ここでは、新規に起業した方がよく直面する失敗例と、その対策を示します。
失敗例1:急いで妥協したドメインを取ってしまう
新しいビジネスを始める際、「とりあえず急いでサイトを立ち上げたい」という気持ちが先行し、希望に近いようで微妙に違う長いドメインを取得してしまうケースがあります。結果として
- 覚えにくい
- 検索やクチコミで伝わりにくい
- デザイン上もタイトルとURLが食い違う
などの問題が出てくることがあります。
対策
- 代替案を複数出して、冷静に比較検討する
- すでに取得されているドメインとの交渉も視野に入れる
- 短くて覚えやすいものを最優先に考える
失敗例2:先に商標を調べずにサービス名を公表してしまう
「これが自分のブランド名だ!」と宣言し、ウェブサイトやSNSを作り始めてから、後になって同じ名前の商標が存在することに気付くケースがあります。最悪の場合、使用停止や損害賠償を求められることもありえます。
対策
- 事前に商標データベースを調べる
- 法的リスクを回避するために専門家へ相談する
失敗例3:ドメイン管理の更新を失念して失効する
頑張って取得したドメインを、更新時期を過ぎて放置した結果、再取得されてしまったという残念なケースです。特に起業直後は他業務に追われがちで、ドメイン更新を忘れてしまうことが少なくありません。
対策
- 自動更新設定をする
- 更新日をカレンダーアプリなどでアラート管理する
- 管理者アカウントや連絡先情報を定期的に見直す
まとめ
希望するドメインがすでに誰かに取得されているとショックを受けがちですが、必ずしも諦めるしかないわけではありません。
- まずは事実確認として、本当にそのドメインがどのように使用されているのか、商標権の状況はどうなっているのかを調べましょう。
- 交渉や買収を検討する場合も、メリット・デメリットを慎重に比較し、予算とリスク管理を踏まえた判断が必要です。
- 代替ドメインの候補をいくつか用意し、短く覚えやすいものを最優先に検討することで、ブランディングを大きく損ねずに解決できる場合もあります。
- ドメインは取得・更新で完結せず、長期的に管理してこそ価値を発揮します。事業の方向性やサービスの広がりに応じて、適切に運用していきましょう。
サービス名とドメインが一致していると、ユーザーにわかりやすいだけでなく、長期的なブランドイメージの向上にも寄与します。一方、あまりこだわり過ぎると時間とコストがかかり過ぎる場合もあります。この記事を参考に、まずは冷静な情報収集と分析を行い、自社にとって最も適切な道を模索してみてください。






