Blog お役立ちブログ
デザインだけこだわって中身スカスカ?SEO的に見落とせないポイント
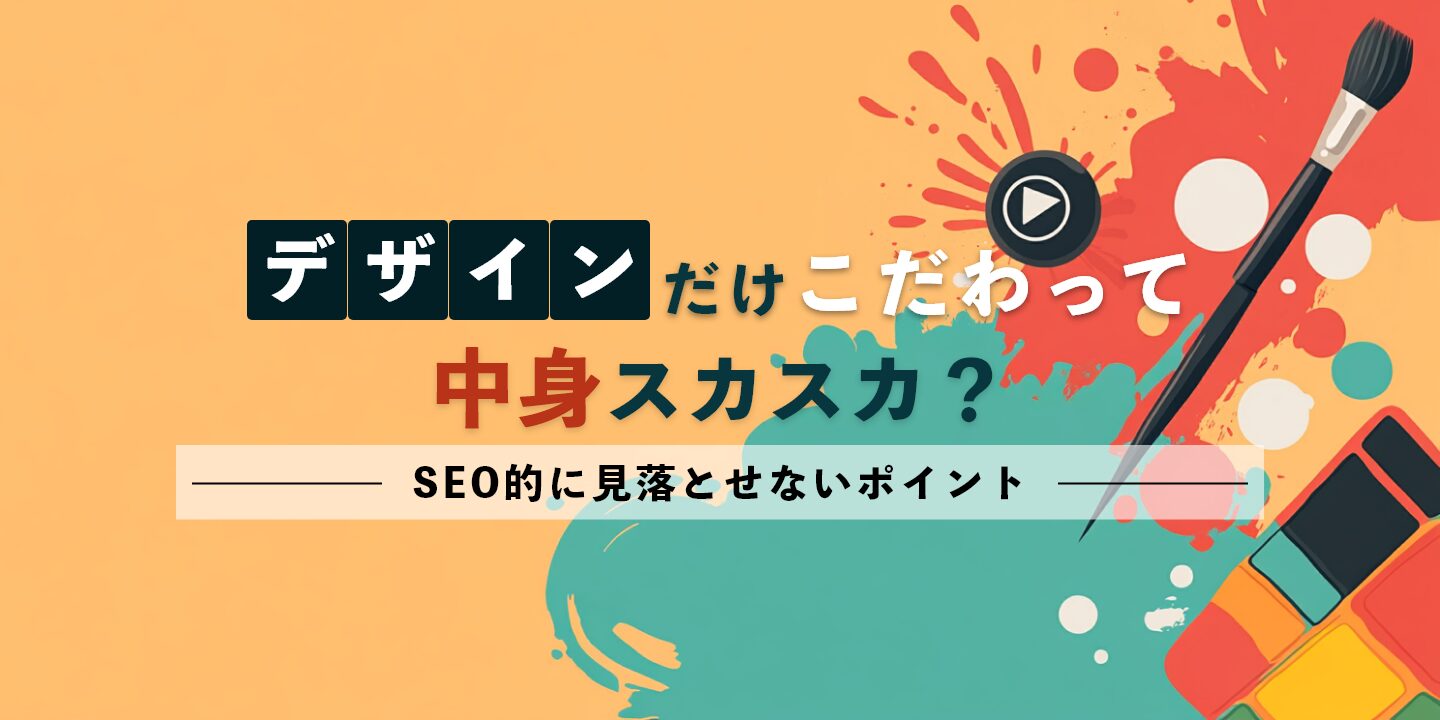
デザイン重視サイトが抱える問題点
「デザインだけこだわって中身スカスカ」という状況は、一見すると華やかなビジュアルでユーザーの目を引きつけることができるため、短期的には“きれいなサイト”というプラスの印象をもたらすかもしれません。しかしながら、サイトを運営していく上では検索エンジンからの評価や、実際にサイトを利用するユーザーの満足度も大きなポイントになります。ここでは、デザインにこだわりすぎた結果起こりがちな代表的な問題点を整理してみましょう。
- 検索エンジンの評価が低下する
デザイン重視で文章や説明が不足していると、検索エンジンのクローラーは有益な情報が少ないと判断します。結果として、検索結果での表示順位が下がり、サイトに訪れてもらえる機会自体が減ってしまいます。 - ユーザーが求める情報を得られない
視覚的には美しくても、具体的な商品やサービスの内容が不明瞭だったり、会社や運営者の理念や実績がまったく分からないと、ユーザーは「このサイトには自分の知りたいことがない」と判断し、離脱してしまいます。 - 問い合わせや売上につながりにくい
情報が不足していて信頼感が得られないサイトは、訪問者の次の行動(商品購入、問い合わせ、資料請求など)を促せません。デザイン面が優秀でも、最終的な成果(コンバージョン)に結びつかないというジレンマが発生します。 - サイト運用のモチベーションが下がる
更新しにくいレイアウトだったり、文章を追加するたびにデザインが崩れるリスクがあるような設計だと、コンテンツを増やそうという意欲も削がれてしまいます。結果的に放置され、アクセス数も減少してしまいます。
デザインとコンテンツのバランスが重要な理由
サイトを運営するうえで、デザインもコンテンツもどちらも欠かせません。デザインは第一印象を決める要素として非常に重要ですが、そこで得た好印象を確固たるものにするためには“中身”であるコンテンツが必要です。以下の表では、デザインに偏った場合とコンテンツに偏った場合、それぞれの長所・短所を簡単にまとめてみます。
| 偏り方 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| デザイン偏重 | ・第一印象が良い ・ブランドイメージを高めやすい | ・検索エンジンに情報が伝わらない ・訪問者が実際に得たい情報が不足する |
| コンテンツ偏重 | ・検索エンジンからの評価が高まりやすい ・信頼度向上につながる | ・文字ばかりで見づらい ・ユーザーに飽きられやすい |
このようにどちらか一方に偏ると、必ず何かしらのデメリットが生じます。大切なのは「ユーザーが求めている情報を、魅力的なデザインで分かりやすく届ける」というバランスです。検索エンジンの技術が進化している今、文字コンテンツだけを無理に増やせばいいというわけではありませんが、質の高い情報を確実に整理して盛り込むことが必要とされます。
コンテンツ不足のリスクとデメリット
中身の少ないサイトが抱えるリスクは大きく、意識していないと気づかないうちに検索順位の低下やユーザー離脱を招きます。ここでは、いくつかの具体的なデメリットを示しながら、なぜコンテンツの充実が不可欠なのかを掘り下げます。
1. 検索エンジンのクローリング効率が下がる
検索エンジンは多種多様な情報から“有益なサイト”を選び出し、ユーザーの検索結果に反映させています。コンテンツが少ないサイトは、クローラーが「このページにはあまり情報がない」と判断し、検索結果での評価も低くなりやすいのが現実です。
2. キーワード不足による順位低下
ユーザーが検索するであろうキーワードが十分に含まれていないと、そもそも検索画面に表示されません。また、主要なキーワードについて“充実したコンテンツ”を持つ競合サイトがあれば、当然そちらが優先して上位に表示されます。
3. 滞在時間が伸びず、信頼度も低い
情報量が少なく質も伴わないと、ユーザーはすぐにページを離れてしまいます。訪問者のサイト滞在時間や閲覧ページ数は信頼度を測る指標の一つであり、これが低いと「すぐに離れてしまうコンテンツ価値の低いサイト」という評価につながる可能性があります。
4. 更新・メンテナンスの機会を逃す
サイト運営をしていると、新しい商品・サービスの追加や実績の更新など、随時コンテンツを追記していく必要があります。もともとコンテンツを作りこむ土台がないと、新情報を掲載する枠組みすら整っておらず、結局更新できずに終わりがちです。
適切なコンテンツ戦略の考え方
「デザインだけこだわって中身スカスカ」という状態を脱却するには、継続的なコンテンツ制作がカギとなります。闇雲に文字数を増やせばいいというわけではなく、どのような情報を、どのように伝えるかを計画することが重要です。
- ターゲットの悩みやニーズを洗い出す
自社の商品やサービスを利用する人が、何を求めてサイトに訪れるのかを明確にする。そこから優先度の高いテーマを抽出し、それを軸にコンテンツを作成。 - 自社独自の強みやストーリーを組み込む
競合他社と比べて、自社がどのようなメリットを提供できるのか、どんな背景やこだわりを持っているのかを言語化する。オリジナリティの高い内容は検索エンジンにも高く評価されやすいです。 - 定期的に更新する体制を整える
最初だけ気合いを入れてコンテンツを作っても、その後放置してしまえば効果は半減します。運営に携わるメンバーで更新のスケジュールを共有し、負担が偏らない仕組みを用意しましょう。 - ビジュアルとの調和を考える
テキストだけでなく、図解や写真を交えた分かりやすいレイアウトを意識する。テキスト情報がしっかりあるうえで、デザインで補う形が理想です。
デザインとの調和を保つためのポイント
デザインが得意な方や、プロのデザイナーに依頼している場合でも、コンテンツ充実のための協議は欠かせません。デザインとコンテンツがうまく調和するポイントを以下の表で確認してみましょう。
| ポイント | 具体的な取り組み |
|---|---|
| レイアウト | ・見出しや段落を視覚的に区別しやすくする ・表やリストを活用して情報を整理しやすくする |
| フォントと文字サイズ | ・読みやすいフォントを選ぶ ・見出しや本文の文字サイズを変えてメリハリをつける |
| 画像・動画の活用 | ・テキストを補足するイラストや写真を追加 ・動画を使う場合は再生時間とデータ容量のバランスを考慮 |
| ホワイトスペース | ・余白を適度に取り、窮屈な印象を避ける ・要素間のスペースを意識して見やすさを向上 |
| メインカラーとアクセント | ・ブランディングを踏まえて統一感を保つ ・重要な部分にアクセントカラーを使い、視線を自然に誘導する |
このように、見やすさや導線を確保しながら、適切な情報量を盛り込むことが重要です。「ここにはどんな内容を置き、どうデザインするか?」という協議を社内外で綿密に行うことで、デザインを活かしつつ情報もしっかりと伝えることができます。
具体的な施策例・手順
中身のあるサイトにするためには、何をどの順番で行うとよいか迷う方も多いでしょう。以下では、大まかな施策例を示します。自社の事情に合わせてカスタマイズしてみてください。
- 現状分析
- 現在のサイトの目的は何か再確認する
- どのページがアクセス数を稼げているか分析する
- デザインとコンテンツの比率をチェックする
- ターゲット設定とテーマ選定
- 想定顧客の悩みや知りたい情報を洗い出す
- 重要度が高い順にテーマを決定し、ページや記事を設計する
- デザインとコンテンツ設計のすり合わせ
- デザイナーまたは担当者とレイアウトやビジュアル面を協議する
- 見た目を保ちつつ、情報量をどこまで増やせるか検討する
- コンテンツ制作・配置
- 執筆担当を決め、定期的に更新できる体制を確立する
- 画像や表、動画などを適切に配置して、文章だけで読ませない工夫をする
- 公開・検証・改善
- 公開後、アクセス解析で訪問者数や離脱率、滞在時間を計測する
- 改善点を洗い出し、定期的に更新または修正を行う
成果を上げるサイト運用の視点
中小企業が限られたリソースで成果を出すには、持続的なサイト運用が重要になります。単発でリニューアルして終わりではなく、コンテンツを少しずつ積み上げていく考え方が必要です。
- 定期的な分析
アクセス解析や問い合わせ数をチェックして、どのページが強みになるか、どのページを改善すべきかを把握します。場合によってはデザインの修正だけでなく、メニューやナビゲーションそのものを再構成する必要があるかもしれません。 - 社内の協力体制
営業部門、広報部門、技術部門など、それぞれの持つ専門知識を活かしながらコンテンツを作ると、より実態に即した情報を提供できます。担当者だけに任せず、全社的に情報発信に協力する文化を醸成することが望ましいです。 - 長期的な視野
SEOやブランディングは、一朝一夕で劇的に効果が出るものではありません。定期的な更新を続け、検索エンジンへの評価とユーザーの認知をゆっくり積み上げていく姿勢が大切です。
デザインとコンテンツを両立する実践的アプローチ
ここでは、より実務的な視点から「デザインも良く、内容も充実したサイト」を作るためのヒントをまとめます。
ユーザーの操作動線を可視化する
サイトマップやワイヤーフレームの段階で、ユーザーがどのページを経由してどの情報にたどり着くかを可視化する方法があります。これにより、情報が足りていない部分や導線が複雑すぎる部分が判明しやすくなります。紙に書き出してみたり、フローチャートを作成したりするだけでも、全体像が明確になります。
キャッチコピーと詳細情報のメリハリ
トップページや各セクションで、キャッチコピーで大きく印象づけ、その下に具体的な説明を用意するメリハリのある構成を考えましょう。過度に文字ばかりでも読みにくいですが、キャッチコピーだけでは情報不足になりがちです。バランスを保つことで、デザインの美しさと内容の濃さを両立できます。
コンテンツ制作のスケジュール管理
コンテンツを増やすには、人員と時間が必要です。無理なく作成を続けるためには、あらかじめ月ごとや四半期ごとの更新テーマを決めておき、スケジュールを共有することが大切です。次のような表にまとめておくと管理しやすくなります。
| 時期 | テーマ | 担当 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月~3月 | 新商品特集記事の作成 | マーケティング部 | バナーや写真の撮影も併行 |
| 4月~6月 | 導入事例・成功事例の紹介 | 営業部 | 顧客インタビュー実施 |
| 7月~9月 | サイトデザインの微調整 | デザイン担当 | レイアウトの見直し |
| 10月~12月 | 年末特需に向けた特集企画 | 全社協力 | コンテンツ数強化 |
こうした管理をすることで、思いつきだけで動かず、計画的にコンテンツを追加しながらデザインとの調和も検討できるようになります。
表を用いた比較・整理
最後に、実践の中で知っておくと便利な要素を、もうひとつ表で整理しておきます。以下のような指標を意識すると、デザインとコンテンツの両面から質を高めるのに役立ちます。
| 指標 | デザイン面のポイント | コンテンツ面のポイント |
|---|---|---|
| 見やすさ・読みやすさ | ・色使いを抑えつつメリハリを意識する ・行間や余白を効果的に使う | ・段落構成を意識し、重要度の高い情報を上部に配置 ・箇条書きや見出しを活用して情報を整理 |
| ユーザー導線 | ・ボタンやリンクは視認性の高いデザインを採用 | ・必要な情報まで最短でたどり着けるページ構成 ・関連ページへの内部リンクを適切に配置 |
| ブランディング | ・企業のロゴやテーマカラーを統一的に活かす ・写真やアイコンなどのイメージを一貫させる | ・企業理念や強みが伝わる内容を用意 ・実績や背景ストーリーをエピソードとして盛り込む |
| SEO評価 | ・読み込みスピードへの配慮(画像圧縮、コード最適化) | ・ターゲットの検索キーワードを意識した文章構成 ・重複コンテンツを避け、独自性のある情報を追加する |
| 更新性 | ・更新しやすい管理画面やテンプレートを使う | ・記事やコンテンツを定期的に投稿する ・時事ネタや最新情報を取り入れて常にサイトを新鮮に保つ |
デザインとコンテンツは対立する要素ではなく、むしろ相乗効果を生む関係にあります。美しいビジュアルがあればこそ、緻密に作り込んだコンテンツがユーザーの目に留まりやすくなるのです。逆に、役立つ情報がしっかり詰まっているからこそ、デザインのインパクトがより大きな意義を持ちます。
まとめ
「デザインだけこだわって中身スカスカ」という課題を解決するには、サイトの目的やターゲットを再確認し、適切なコンテンツを計画的に増やしていくことが不可欠です。デザイン重視とコンテンツ重視は相反するものではありません。むしろ、両者をうまく融合させてこそ、多くのユーザーや検索エンジンから「このサイトは見る価値がある」と判断されるようになります。
中小企業の場合、予算や人材の制約などでコンテンツに割けるリソースが限られることもあるでしょう。それでも、日々の情報を少しずつサイトに反映し、更新を続けることで、必ず成果は積み上がっていきます。最初は大変に感じられるかもしれませんが、ユーザーに対して有益であると同時に、自社のブランディングやSEO効果も高まる投資と考え、ぜひ地道に継続してみてください。






