Blog お役立ちブログ
スタッフブログを外注せず内製化するためのスケジュール管理
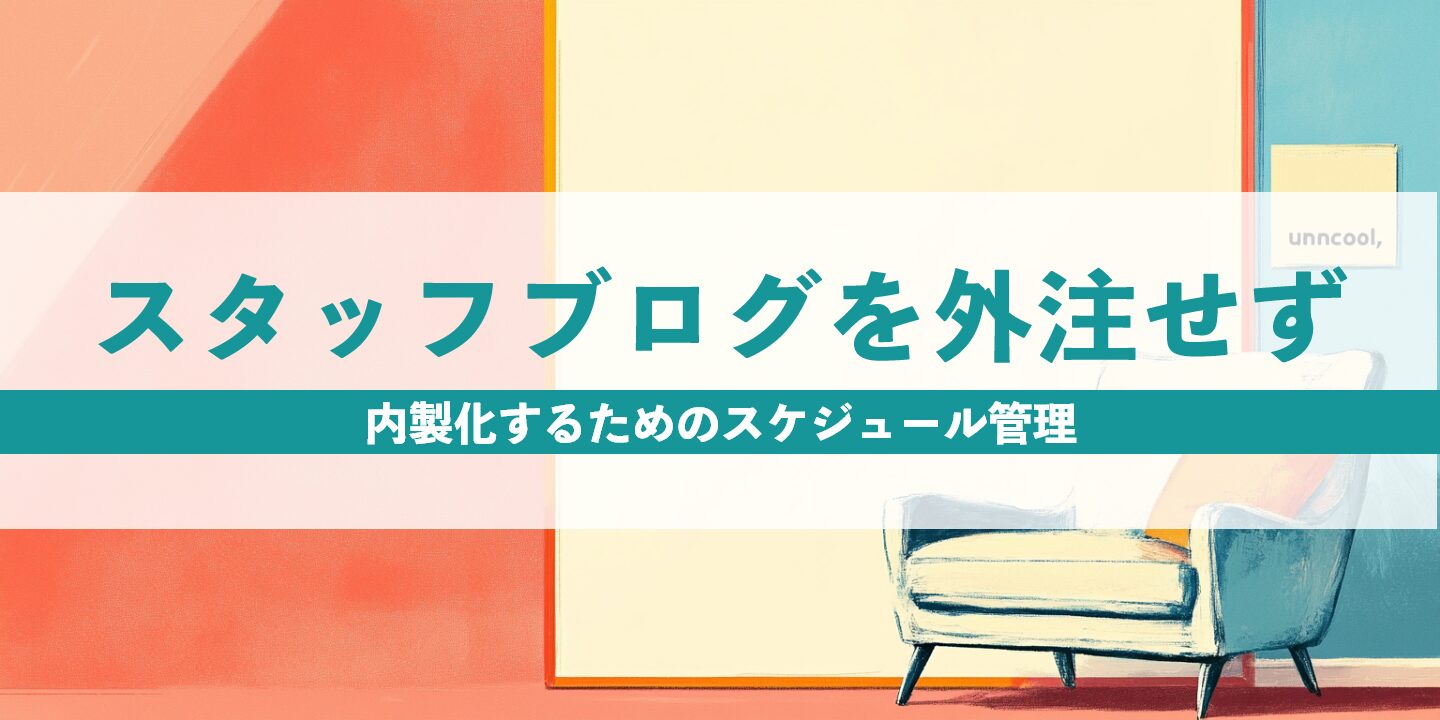
はじめに
中小企業が自社のスタッフブログを活用するケースは増えています。しかし、外注によるコスト負担を避けたい、あるいは社内の意見やノウハウを活かした記事を発信したいなどの理由から、内製化の道を選ぶ企業も少なくありません。ところが、いざ内製化に踏み切ったものの、スケジュール管理がうまくいかず更新が滞ってしまったり、通常業務に追われて中断してしまったりするケースが目立ちます。
このような問題を防ぐには、適切なスケジュール管理が不可欠です。本記事では、スタッフブログを内製化する際のスケジュール管理のポイントや、記事品質を落とさずに更新頻度を維持するためのノウハウを解説します。実際に社内で導入しやすい具体例や表を用いて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
スタッフブログ内製化のメリット・デメリット
まずは、スタッフブログを外注せずに内製化するメリットとデメリットを整理してみましょう。自社メンバーで記事を書く意味や、内製化の注意点を把握することで、スケジュール管理の大切さがより明確になります。
メリット
- コスト削減
外注する場合に比べて制作費用やライターへの支払いなどが抑えられます。 - 社内ノウハウの蓄積
業界特有の知識や社内の強みなどを直接反映でき、経験をメンバーに定着させやすいです。 - オリジナリティの確保
自社の文化や価値観を直接発信できるため、他社との差別化がしやすいです。 - コミュニケーション活性化
記事作成のために部署を越えたやり取りが増え、社内コミュニケーションが活発になることがあります。
デメリット
- 負担が大きい
通常業務に加えて記事作成のタスクが増えるため、メンバーに過剰な負荷がかかる可能性があります。 - 専門知識が必要
記事のテーマや読者目線に合わせたライティングスキルが必要になることがあり、学習コストがかかる場合もあります。 - スケジュール管理の難しさ
内製化によって担当者や工程が増え、管理が複雑化しがちです。 - モチベーション維持が難しい
長期的に継続するには、メンバーのやる気や協力体制が欠かせません。
こうしたメリットとデメリットを理解しておくだけでも、「なぜスケジュール管理が重要なのか」が見えてきます。次の章では、本格的にスケジュール管理を行う前の準備として、何を整えておくべきかを確認しましょう。
スケジュール管理を始める前の準備
スケジュール管理を行うには、先にいくつかの準備作業が必要です。以下では、成功確率を高めるための重要な準備事項を紹介します。
1. ブログの目的とターゲットを再確認する
スタッフブログを通じて、どのような目的を達成したいのかを明確にしましょう。
- 新規顧客の獲得
- 社内ブランディング向上
- 製品やサービスへの理解促進
これらの目的とターゲットが明確でないと、書くべき内容や更新頻度もあやふやになり、スケジュール管理もうまく機能しません。最初に目的・ターゲット像をメンバー全員で共有しておきましょう。
2. ブログテーマ・カテゴリーの選定
どのようなテーマの記事をいくつ書くのかを、あらかじめカテゴリごとに大まかに決めておくと、ネタ出しや担当割り振りがスムーズになります。具体的には下記のようにカテゴリを設定すると、全体像が見えやすくなります。
このようにあらかじめいくつかカテゴリーを設けることで、記事ネタの方向性をつかみやすくなり、スケジュール管理が組み立てやすくなります。
3. リソース(人員・時間・スキル)の把握
内製化を成功させるには、記事を書く人、画像を用意する人、校正・編集をする人など、必要な役割を明確にすることが大切です。そのためにも、まずは社内の誰がどの程度の時間を割けるのか、どのようなスキルを持っているのかを把握しておきましょう。
4. KPIや目標設定
更新頻度やアクセス数の目標などを設定しておくと、スケジュール管理に具体性が出てきます。「週に◯回必ず更新」「月間◯記事を目標」など、達成しやすい目標を設定しておくと、メンバーのモチベーション維持にも役立ちます。
効果的なスケジュール管理の実践ステップ
ここからは、具体的にどのようにスケジュール管理を行えばいいのか、そのステップを紹介します。
ステップ1:ネタ出し会議の実施と定例化
記事のネタがない状態ではスケジュールを立てようもありません。月に1度、あるいは隔週など、定期的にネタ出し会議を設定し、下記の流れで進めます。
- テーマのブレインストーミング
事前に各部署やメンバーからトピック案を収集しておき、会議中にブレストを実施。 - 優先度の振り分け
季節のトピックやキャンペーンなど、時期的に優先すべきものをまず確保。 - 担当者(仮)の割り振り
ある程度書けそうな人や興味を持っている人を仮担当とし、意欲を確認。
このネタ出し会議を定期的に行えば、記事ネタが枯渇しにくくなり、計画的に記事のストックを作ることができます。
ステップ2:編集スケジュール表(カレンダー)の作成
ネタ出し会議で出たテーマをもとに、下記のような編集スケジュール表を作成します。表計算ソフトを使ったり、専用ツールを導入したり、方法はさまざまですが、最低限以下の項目を含めましょう。
| 記事タイトル | 担当者 | 投稿予定日 | ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 〇〇の新製品紹介 | 山田 | 6/10 | 下書き中 | 画像素材要確認 |
| 社内イベントレポート | 佐藤 | 6/12 | 未着手 | イベント取材必須 |
| 業界最新動向まとめ | 鈴木 | 6/15 | 記事作成完了 | 校正依頼中 |
| 導入事例インタビュー | 中村 | 6/20 | 下書き中 | 担当部署への確認待ち |
このようにビジュアルで進行状況を把握できると、誰がいつまでに何をするのか明確になり、後になって「誰も書いていない」「締め切りを過ぎていた」というトラブルを防ぎやすくなります。
ステップ3:各工程のタスク管理
ブログ記事は「ネタ出し→下書き→校正→画像選定→公開」のように複数の工程があります。各工程の担当者や締め切りを明確にしておかないと、次の担当者に引き継ぐタイミングが遅れ、全体のスケジュールに影響が出ます。
たとえば以下のように工程ごとに担当者と期限を設定すると、管理がしやすくなります。
| 工程名 | 担当者 | 期限 | ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ネタ確定 | 山田 | 6/1 | 完了 | |
| 下書き(初稿) | 佐藤 | 6/5 | 下書き中 | 1,500文字程度を想定 |
| 校正(内容チェック) | 鈴木 | 6/7 | 未着手 | 意味重複や専門用語の校正 |
| 画像準備 | 山本 | 6/7 | 未着手 | 社内写真ライブラリ確認 |
| 校了(最終確認) | 中村 | 6/9 | 未着手 | 記事の体裁チェック含む |
| 公開 | 佐藤 | 6/10 | 未着手 | CMSへの入稿と最終プレビュー |
このように細かい工程を見える化しておくと、作業抜けやスケジュールの遅延にいち早く気づけるのが利点です。
ステップ4:定期レビューとフィードバック
スケジュール通りに記事を公開できたとしても、品質に問題があると継続は困難です。定期レビューを行い、記事の出来や公開後の反応などを評価しましょう。以下のような観点でフィードバックを共有すると、次の記事での改善につながります。
- 読者目線:専門用語が多すぎていないか、読みやすい構成か
- 長さ:冗長に感じる部分はないか、必要な情報が不足していないか
- 見出しや装飾:長文でも読みやすくする工夫がなされているか
- 画像や図表の活用:内容をわかりやすく補足するものがあるか
定期レビューを通じて蓄積されたノウハウは、次回のスケジュール管理に役立ち、全体のクオリティを底上げします。
ツール選定のポイント
スケジュール管理を円滑にするには、ツールの活用が欠かせません。表計算ソフトでも管理はできますが、規模が大きくなるにつれてタスクの重複や担当ミスが起こりがちです。そこで、以下のようなツールを使うことを検討すると良いでしょう。
| ツール名 | 特徴 | 適した規模・用途 |
|---|---|---|
| 表計算ソフト | シンプルで導入しやすい | 記事本数が少ない場合や試験導入段階に適切 |
| プロジェクト管理ツール | タスク管理・ガントチャートでの可視化が可能 | 複数メンバーが同時進行で多くの記事を書く場面に最適 |
| カレンダーアプリ | スマホとも連携でき、リマインダー機能が使いやすい | 忙しい中小企業の担当者が時間単位で予定を入れる時に便利 |
大切なのは、チームの規模や運用方針に合ったツールを使うことです。高機能なツールを導入しても、使いこなせなければ意味がありませんし、逆に表計算ソフトだけでは対応しきれない場合もあります。実際に数日~数週間単位のトライアルを行い、使いやすさを検証してから導入しましょう。
社内リソースの役割分担例
内製化を成功させるためには、単に「誰が記事を書くか」だけでなく、「校正」「画像選定」「スケジュール調整」などの役割を分散させることが重要です。一人にすべての作業が集中すると、負担過多でスケジュールに遅れが出たり、モチベーションが下がったりします。具体的な分担例を見てみましょう。
| 役割名 | 主な作業内容 | 適した人材の例 |
|---|---|---|
| メインライター | 記事の執筆(構成作成、文章作成) | 業務知識が豊富で文章を書くのが得意な人 |
| 校正担当 | 記事内容のチェック、誤字脱字の修正、読みやすさの向上 | 記事のクオリティを厳密にチェックできる人 |
| 画像・デザイン | 必要な画像素材の選定、記事内のレイアウトなど | クリエイティブ系の業務経験者 |
| スケジュール管理 | 記事の進捗確認、タスクの割り振り、公開スケジュールの調整 | プロジェクト管理経験のある人 |
| 全体監修 | 記事の方向性や最終的な品質確認、コメントフィードバック | 部署責任者やプロジェクトリーダーなど |
このように、各工程に適切な担当を配置すれば、全員が自分の責任範囲を明確に認識でき、タスクがスムーズに流れやすくなります。
トラブルシューティングと成功のコツ
トラブル1:担当者が多忙で記事執筆が進まない
忙しい中小企業では、担当者が他の業務に追われて記事執筆に割ける時間がないという事態がよく起こります。対策としては、以下の方法が考えられます。
- スケジュール設定の余裕を持たせる:あらかじめ締め切りにバッファを設ける
- タスクの一部切り分け:見出し構成だけ先に別の人が作成し、ライターの負担を軽減
- アーカイブの再編集:過去の記事の内容をアップデートすることで、新規執筆の手間を削減
トラブル2:ネタ切れで記事が書けない
定期的なネタ出し会議を実施していても、どうしてもアイデアが尽きることがあります。そんなときは、下記のような方法が役立ちます。
- 社内アンケートの活用:社員に「こんな情報を発信したい」「顧客からよくある質問」などを収集
- 読者コメントの活用:ブログへのコメントや問い合わせをもとに記事を作成
- 他社事例やトレンドの調査:競合他社のブログや業界ニュースをチェックし、自社の視点を加えて記事化
トラブル3:更新頻度は高いが品質が低下
更新を続けるあまり、記事の質が下がってしまうケースもあります。こうなると読者が離れてしまい、ブランドイメージの低下につながる危険も。以下の対策が有効です。
- 記事一本あたりの目標クオリティを設定する:最低限必要な情報量や記事構成の基準を設ける
- レビュー体制の強化:校正担当を増やす、公開前に必ず確認するプロセスを設ける
- 投稿ペースの見直し:更新頻度をやや落とし、その分クオリティに注力
成功のコツ
- 小さく始める
最初から完璧を目指そうとすると、スケジュール管理が煩雑になります。週1本の更新からスタートし、慣れに応じて本数を増やす方が定着しやすいです。 - 全員で運用意識を共有する
一部の担当者だけががんばると、その人のモチベーションが下がったときに更新が途絶えます。会社全体で「ブログ運用は自社の成長に直結する」という認識を持つことが大切です。 - 定期的に分析する
ページビューや問い合わせ件数など、記事公開の効果を定期的に振り返ることで、改善点や成功パターンが見えてきます。これを次のスケジュール管理に活かしましょう。
まとめ
スタッフブログを外注ではなく内製化で運用するためのポイントは、何よりも「無理のないスケジュール管理」と「適切な役割分担」にあります。担当者の負担を最適化しつつ、記事の質と更新頻度を両立するためには、社内コミュニケーションとツールの活用が大きなカギを握ります。
本記事で紹介した内容を参考に、ぜひ自社に合ったスケジュール管理の仕組みを整えて、ブログ内製化のメリットを最大限に活かしてみてください。継続的な運用の中で得られるノウハウや社内の連携強化は、長期的に見ても大きな財産になるはずです。






