Blog お役立ちブログ
ビジネスプランとホームページを“ズレなく”つなぐ完全ガイド
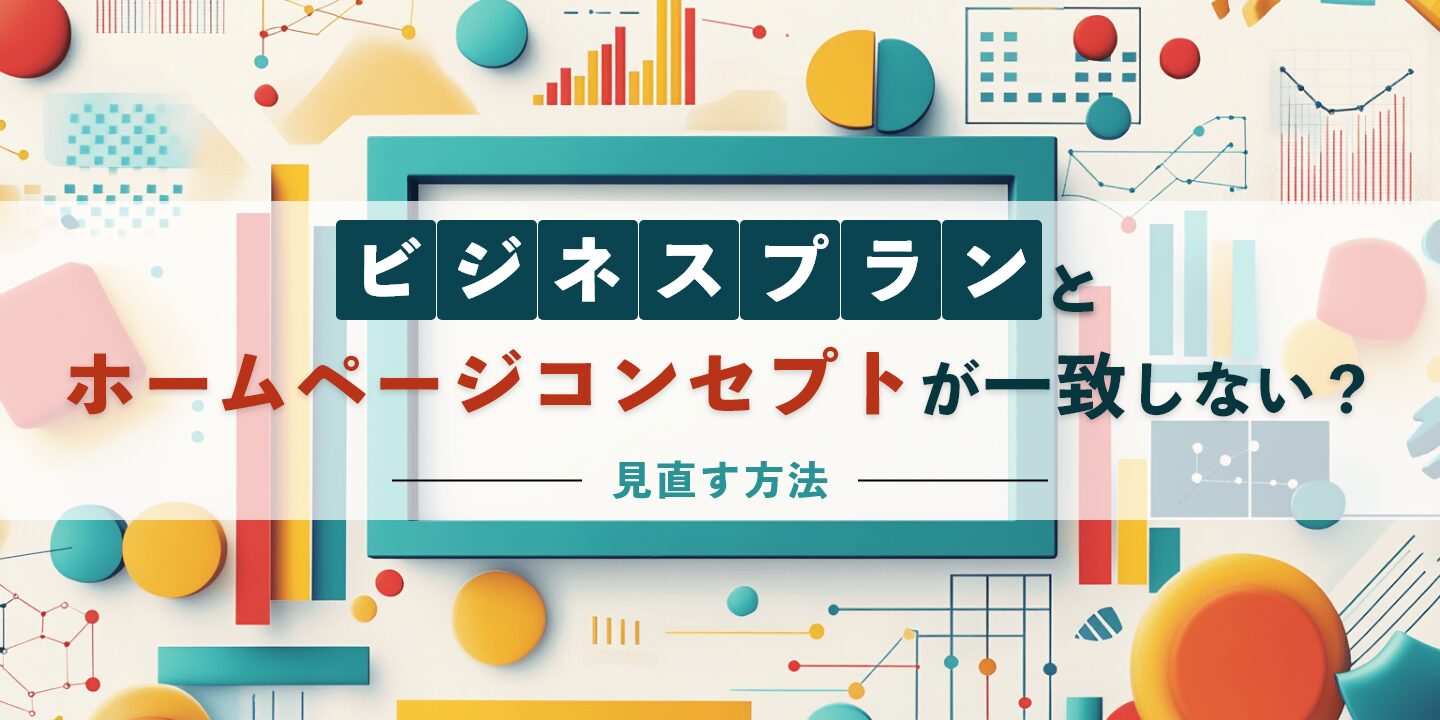
~2025年のSEOトレンドも踏まえた実践チェックリスト付き~
はじめに:サイトが“あなたの事業”を正しく語っていますか?
創業まもない頃、あるベーカリー経営者の方から 「売りは“毎朝店内で焼く無添加パン”なのに、ホームページを見た友人から“冷凍生地の量産店だと思った”と言われた」 という相談を受けました。
原因は簡単で、開業準備中にテンプレートで急いで作ったサイトをそのまま放置していたから。つまり ビジネスプランとサイトのコンセプトが噛み合っていなかった のです。これはパン屋に限らず、BtoB、士業、EC など規模・業種を問わず起こり得る問題です。
本記事では、そうした「ズレ」をなくし、事業とサイトを一本のストーリーで結ぶ方法を、
- 読み手に優しい言葉
- 2025年の最新SEO原則
- 今すぐ使えるチェックリスト・実例を交えて解説します。
ビジネスプランとサイトがズレると起こる4つの痛み
- 顧客の混乱と離脱
情報が散漫だと、検索で訪れたユーザーは「ここは自分向けの会社か?」と判断できず数秒で離脱します。 - 差別化ポイントの希薄化
本来の強みが伝わらず価格競争に巻き込まれやすくなります。 - 信頼の低下
高付加価値を謳うのに古いデザイン……それだけで「言っていることとやっていることが違う」と感じさせます。 - 社内認識のバラつき
ホームページは社外向け資料であると同時に、社員の共通言語でもあります。ズレたサイトは組織の方向性までブレさせます。
コンセプトを言語化するステップ
自社の強みを“短い言葉”で掘り当てる
- What(何を解決するか)
- How(どのように解決するか)
- Why(なぜ自社が最適か)
社内ワークとしてホワイトボードに付箋を貼り、「30分で無理やり3語に絞る」練習をすると、要点が浮き彫りになります。
ターゲット像を“困りごと”で描く
年齢や性別ではなく 「○○に困っている人」 と課題で区切ると、検索クエリ(例:業務効率 ERP 中小)と親和性が高まり、後述のSEO戦略とも噛み合います。
キーメッセージ(タグライン)を決める
10文字前後で価値を伝えるフレーズを作成。店頭や営業資料、SNSでも一貫して使うとブランド認知が加速します。
2025年版SEO視点:人を動かすサイト設計の要点
Googleは2024年3月のコアアップデートで Helpful Content System をアルゴリズム全体に組み込みました。要するに「人の役に立つ一次情報か」を徹底的に見る仕組みです。
さらに 2024 年 5 月以降、検索結果上部に AI 概要(AI Overviews)が表示され、クリックされない検索(Zero‑Click) が 69% まで増加したとのデータもあります。
これらを踏まえ、
- 一次情報を増やす:自社データ・事例・インタビューを積極公開
- 専門性と体験を示す:執筆者プロフィール、検証プロセスを明記(E‑E‑A‑T 強化)
- 検索意図を粒度で分ける:*比較*・*価格*・*口コミ* などクエリの段階ごとに専用ページを用意
- 構造化データで文脈を補足:FAQPage、Product、HowTo スキーマの実装
これにより AI 概要に引用されてもブランド露出を確保し、自然検索でも順位を落としにくくなります。
デザインとトーンを一本のストーリーに
視覚要素
- 色・フォント:ブランドパーソナリティに合わせ、最大 3 色に絞る
- 写真・イラスト:スマホファーストで視認性を確保し、alt テキストにキーメッセージを含める
コピーライティング
「誰に」「何を」「どう約束するか」を最初のスクロール以内に完結させます。ファーストビューの3秒ルールです。
情報設計(IA)
- 強み紹介
- 具体的事例
- CTA(お問い合わせ・見積もり)
の順に導線を敷き、各セクションを「1スクリーン=1メッセージ」で完結させると離脱率が下がります。
ページ別コンテンツとビジネスゴールのマッピング例
| ページ | ユーザーの疑問 | ビジネス側ゴール | 必須コンテンツ |
|---|---|---|---|
| トップ | ここは何の会社? | ブランド認知 | キーメッセージ、代表写真 |
| サービス | どう役立つ?費用は? | リード獲得 | 比較表、料金モデル |
| 事例 | 実績は? | 権威付け | ビフォーアフター、数値 |
| FAQ | 細かな不安は? | 問い合わせ効率化 | よくある質問+構造化データ |
| ブログ | 深掘り情報は? | SEO流入 | 専門コラム、一次調査 |
制作会社・社内メンバーと連携するコツ
- ビジネスプラン概要シートを共有
- 窓口を一本化(片手タッチポイントで情報ロス回避)
- 週次ミーティングでKPI確認:流入数だけでなく 「問い合わせ転換率」 も追う
- 校了前レビューは3回以内:フィードバック時期をあらかじめ決めておくと後戻りが減ります。
リニューアル or 部分改修?判断フローチャート
- デザインが5年以上前 → 全面リニューアル
- 強みが伝わっているか→No なら コアページ改修
- 更新が止まっているか→Yes なら 運用体制見直し
- 問い合わせが減少 → アナリティクスで離脱ページ特定 → 対象ページのみ改修
中小製造業A社の実例:問い合わせ3倍アップ
背景
- 高精度加工技術が強みだが、サイトに記載なし
施策 - トップに「±2μmの高精度加工を短納期で」のコピー
- 技術工程を写真で見せるHowTo記事を毎月更新
- FAQに「対応素材」「最小ロット数」を追加(構造化データ付き)
結果 - 3か月で検索流入 180%
- 月間問い合わせ件数 3倍
- 「精密加工 短納期」で1位獲得
2025年SEOトレンド対策 早見リスト
| トレンド | 意味 | 具体策 |
|---|---|---|
| Helpful Content System統合 | 人に役立つ一次情報が最優先 | 専門家インタビュー、事例数値公開 |
| AI Overviewsによるゼロクリック増 | SERP上で要約されクリック減 | 見出しにブランド名を含めAI引用を狙う |
| E‑E‑A‑T強化 | 体験と専門性の証明を評価 | 著者紹介、取得資格、実績年数を表示 |
| クローラビリティ最適化 | 不要リソース削減で予算節約 | robots.txtとX‑Robots‑Tagで重複排除 |
| マルチモーダル検索 | 画像+テキスト+音声が混在 | 画像のEXIF・alt、動画の字幕を整備 |
よくある質問(FAQ)
Q. そもそもビジネスプランを見直すタイミングは?
事業フェーズ転換(例:BtoC→BtoB参入)や顧客単価・商品構成が大きく変わった時が目安です。
Q. 社内に専任がいない場合の運用方法は?
月1回のブログ更新すら難しければ、実績紹介だけ更新するのも立派なコンテンツ運用です。
Q. AIが生成した原稿はSEO的に不利?
Googleは「AI生成=即ペナルティ」ではなく役立つかどうかを見ています。人の一次情報で肉付けすれば問題ありません。
まとめ:変化しても“芯”はぶらさない
ホームページは“完成”した瞬間から劣化が始まります。だからこそ
- ビジネスプランを定期的に言語化し直す
- ユーザー視点でサイトを点検し続ける
- Helpful Content の原則に沿って一次情報を更新する
このサイクルを回すことで、検索アルゴリズムや業界トレンドが変わっても「ブランドが伝わるサイト」を維持できます。まずは 今日、トップページのキャッチコピーが自社の強みを語れているか をチェックしてみてください。
あなたのビジネスが、ウェブ上でも“本来の価値”を正しく語り、次の顧客と出会えることを願っています。






