Blog お役立ちブログ
ホームページに動画を埋め込むと重くなる対策はある?
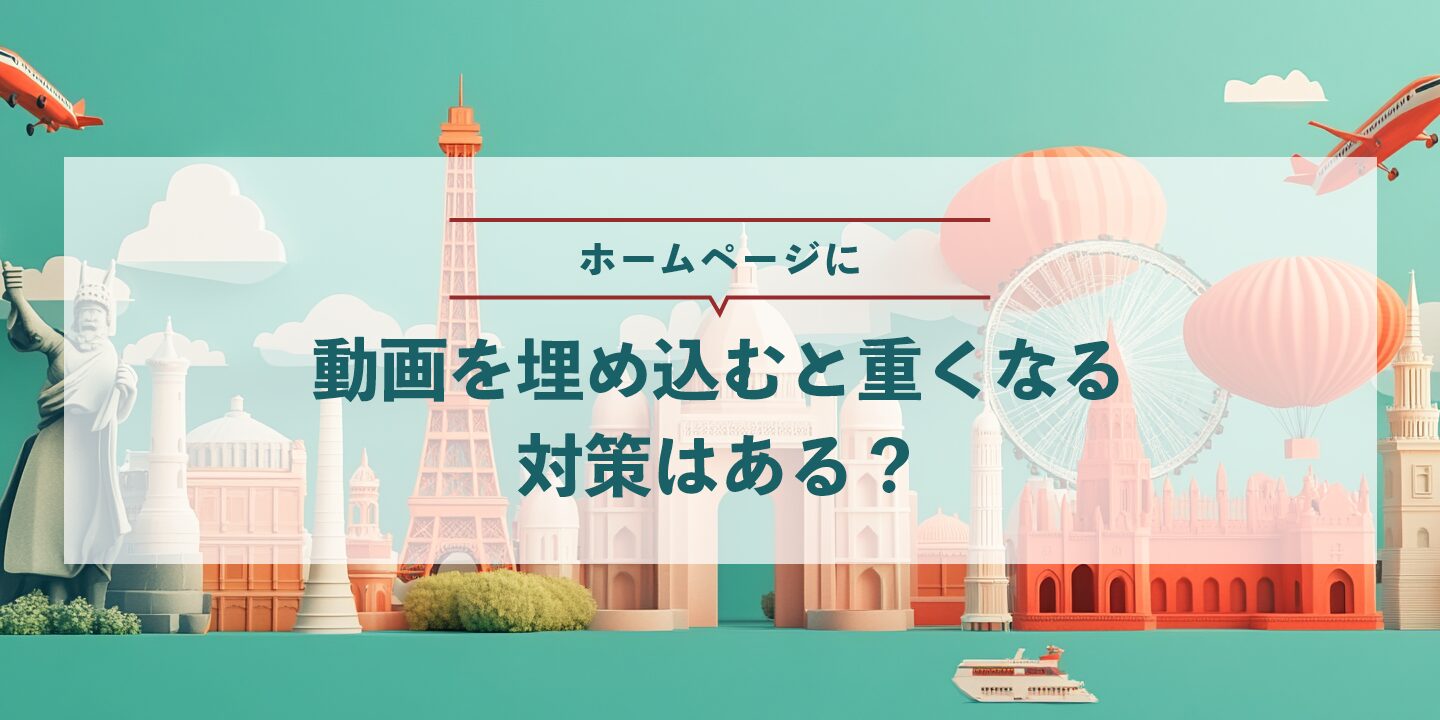
はじめに
ホームページに動画を埋め込むと、ページが魅力的になる一方で「重くなってしまうのではないか」「読み込み速度が遅くなり、訪問者が離脱してしまうのでは」という不安を抱く方は多いでしょう。特に地域密着型の中小企業にとっては、ローカルSEOやブランド力向上を狙って動画を使いたいものの、ページ速度への影響が気になるという声が少なくありません。本記事では、動画を上手に活用しながら、ホームページの表示速度を保つためのポイントを幅広く解説します。
動画を取り入れる目的は多岐にわたります。製品やサービスの使用シーンをリアルに伝えたり、会社の雰囲気をビジュアルで表現したり、顧客との信頼関係を深めたりなど、テキストや画像だけでは得られないインパクトを与えることができます。しかし、その反面、データ容量が大きくなり、ページ読み込みに時間がかかる懸念も出てきます。
ここでは「なぜ動画がページを重くするのか」「速度が遅いとどんなリスクがあるのか」をはじめ、具体的な改善施策や動画最適化の方法などを詳しく見ていきましょう。
なぜ動画を埋め込むとページが重くなるのか
大きなデータ容量
動画は画像やテキストに比べて容量が大きくなりがちです。一般的に高解像度で撮影された動画は数MB、長いものや高品質なフォーマットの場合は数百MBに及ぶこともあります。サーバーや回線の負荷が増大し、結果的にページ全体の読み込みが遅くなる原因となります。
自動再生・プレビューの影響
ページ読み込みと同時に動画が自動再生される設定にしている場合、訪問者のブラウザ側で大きなデータのやり取りが始まります。さらにサムネイルやプレビュー画像も大きなデータを使うことが多く、テキストメインのページに比べると読み込み開始までの時間が長引く傾向があります。
外部サービスの埋め込みコード
YouTubeやVimeoなど外部サービスを用いて動画を埋め込むと、外部のサーバーとの通信が発生します。外部サーバーの応答速度が遅かったり、呼び出しスクリプトが複数あったりすると、その分ページ全体の読み込み時間に影響を及ぼします。
複数動画の掲載
複数の動画を1ページ内に埋め込む場合、それぞれの動画に対してデータを読み込み、再生準備を行う必要があります。1本なら許容範囲でも、3本・4本と増えるごとに負荷が累積していき、訪問者が表示完了まで待てずに離脱してしまう可能性が高まります。
ページ速度が遅いと起こりうるリスク
ユーザー離脱
読み込みに数秒以上かかると、訪問者が待ちきれずにページを閉じてしまうことがあります。特にスマートフォン利用者は、モバイル回線の速度に依存しがちなため、表示速度の遅延に敏感です。
検索順位への影響
ページ速度は検索エンジンの評価要因のひとつとされています。表示速度が極端に遅いサイトは、検索結果での上位表示が難しくなり、結果的に新規のアクセス数が減る可能性があります。
信頼性の低下
ページ表示が遅いと、「この会社はサイト管理をきちんとしていないのでは?」「ユーザー体験を重視していないのでは?」というマイナスイメージを与えかねません。オンラインでの第一印象はサイトの見やすさや速度で決まる部分が大きいため、ビジネス上も影響が出るおそれがあります。
ホームページにおける動画埋め込みの代表的な方法
動画をホームページに埋め込む際には、主に以下のような方法が考えられます。どの方法を選ぶかでページ速度や運用面の負担が変わってきます。以下の表に代表的な埋め込み方法と特徴をまとめました。
| 埋め込み方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自社サーバーに直接アップロード | ホスティングサーバーに動画ファイルを置き、<video>タグなどで埋め込む形式 | ・外部サービスに依存しない ・ブランディングを統一しやすい | ・サーバー負荷が大きい ・大容量の場合コスト増 |
| YouTube埋め込み | YouTube上にアップロードした動画をiframeで埋め込む | ・無料で大容量を扱える ・誰でも再生しやすい | ・関連動画や広告が表示される場合がある ・外部サーバーの応答に依存 |
| Vimeo埋め込み | Vimeo上にアップロードした動画をiframeで埋め込む | ・デザインが洗練されておりブランド感を高めやすい ・広告が少ない傾向 | ・無料プランだと制限がある ・外部サーバーの応答に依存 |
| 動画プラットフォーム専用プレーヤー | カスタム動画プレーヤーを利用して配信プラットフォームからストリーミング | ・高品質の配信が可能 ・詳細な視聴解析などができる | ・サービス利用料が発生する場合が多い ・導入や設定が複雑 |
自社サーバーに直接アップロードする方法は、コントロールしやすい反面、大容量の動画を複数扱うとサーバーのパフォーマンスを圧迫するリスクがあります。YouTubeやVimeoなどの外部サービスを使うと、ホスティングコストを抑えられますが、外部への依存度が高まる点に注意が必要です。
表示速度改善のための具体的な施策
1. Lazy Loadingの導入
動画エリアが画面に表示される直前まで読み込みを遅らせる技術を「Lazy Loading」といいます。スクロールして実際に動画領域が見えるタイミングで初めて読み込みを行うため、ページの初期読み込み速度を改善できます。
2. サムネイルの軽量化
動画をサムネイル表示している場合、サムネイルの画像サイズを小さく抑えることが重要です。サムネイルだけで数百KBもあると、ページ全体が重くなる原因となります。ファイル形式や解像度を見直し、可能な限り軽量化を図りましょう。
3. CDN(コンテンツ配信ネットワーク)の活用
大容量の動画データやサムネイルをより高速に配信するために、CDNを利用する手があります。CDNは世界各地のサーバーにコンテンツをキャッシュし、ユーザーに最も近いサーバーから配信することで表示速度を向上させます。
4. 自動再生のオフ・再生ボタンの設置
動画を自動再生に設定していると、ページが表示されると同時に大きなデータを読み込み始めます。訪問者の意思で再生するように設定するだけでも、初期ロード時のデータ通信量を大幅に削減できます。
以下の表に、代表的な速度改善施策とそれぞれの主な特徴をまとめます。
| 施策名 | 方法 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Lazy Loading | プラグインやスクリプトで動画読み込みを遅延させる | 初期ロードを軽くする 多くの動画を掲載する場合に効果的 |
| サムネイルの軽量化 | 画像圧縮ツールで圧縮率を高めるなど | 視覚面のクオリティを保ちつつ容量削減 |
| CDNの活用 | 外部のCDNサービスと契約 | 地理的に近いサーバーから配信 海外ユーザーが多い場合にも有効 |
| 自動再生のオフ設定 | <video>タグやiframeの設定を変更 | 訪問者が再生するまで大容量読み込みを行わない 初期速度を高められる |
動画ファイルの最適化と形式選び
動画ファイル形式
動画形式には多くの種類がありますが、一般的によく使われるのはMP4(H.264 / H.265)、WebMなどです。MP4は幅広いブラウザやデバイスに対応しており、WebMは一部ブラウザで高い圧縮率と軽量な再生が可能です。中小企業のホームページで汎用性を重視するなら、MP4を基本としつつ、WebMを併用するケースも考慮するとよいでしょう。
解像度とビットレート
フルHD(1920×1080)や4Kなどの高解像度で撮影した動画は魅力的ですが、ホームページに埋め込む分にはオーバースペックとなる場合もあります。ビットレートが高い動画は画質が美麗な反面、ファイルサイズも大きくなり、表示に時間がかかります。
サイトの目的やターゲットユーザーの通信環境を踏まえ、フルHDより少し低めの解像度で十分なケースも多いです。またビットレートを適度に下げることで、ファイル容量を圧縮し読み込み速度の改善が期待できます。
エンコード設定
動画をエンコード(圧縮)する際の設定によって、最終的なファイルサイズと画質のバランスが変わります。ビットレートだけでなく、フレームレート(1秒間のコマ数)やエンコード方式(H.264、H.265など)を調整することで、容量を抑えつつ視聴に耐えうる画質を保つことが可能です。
次の表は、一般的に使用される動画ファイル形式と用途、メリット・デメリットをまとめたものです。
| 動画形式 | 用途 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| MP4 | 幅広いプラットフォームで再生可能 | ・高い互換性 ・画質と容量のバランスが良い | ・圧縮率はWebMにやや劣る場合もある |
| WebM | モダンブラウザ向け | ・高い圧縮率 ・軽量で再生負荷が少ない | ・対応ブラウザが限られる場合あり |
| Ogg | 一部ブラウザ・システム | ・フリーで利用可能 | ・対応環境が少なく推奨度が低い |
| MOV | Apple系環境 | ・高画質・編集用途に強い | ・容量が大きくなる場合が多い |
ローカルSEOと動画活用
ローカルSEOを強化したい中小企業にとって、動画は情報量や雰囲気を伝える上で非常に有効です。店舗の様子やサービスのデモ、顧客のインタビューなどを動画で紹介すれば、閲覧者の興味を引きやすくなるでしょう。ただし、動画を大量に掲載した結果、ページ速度が大幅に低下すると、かえってユーザーを取り逃す可能性があります。
表示速度と動画活用のバランスを取ることが重要です。たとえば、複数の動画を一斉にページ内に埋め込むのではなく、まずは1本を厳選して掲載し、残りはサムネイルやテキストリンクで別ページに誘導するなどの方法も検討できます。ローカルSEOで大事なのは、地域のユーザーが快適にページを閲覧できることです。動画を活用しながらも、表示速度が犠牲にならない工夫を忘れずに行いましょう。
中小企業が気を付けるべきポイントと成功例
運用体制のチェック
動画は撮影から編集、アップロード後のメンテナンスまで、ある程度の手間がかかります。人員や費用を考慮しながら無理のない範囲で取り入れることが大切です。定期的に更新できる動画コンテンツがあればSEO効果も期待できますが、放置してしまうと時代遅れの情報が残り、逆効果になることがあります。
外部サービスとの連携
動画埋め込みを外部サービスに任せる場合でも、自社サイト内でのデザイン面や読み込み速度などをしっかり確認しましょう。YouTubeであれば関連動画の表示を最小限にする、Vimeoであればプライバシー設定を適切に行うなど、細かなカスタマイズが可能です。外部サービスの使い勝手と自社サイトのブランディングを両立させる視点が必要になります。
成功例:店舗紹介動画で来店率UP
実例としては、飲食店や美容室などが店舗の雰囲気やスタッフの接客スタイルを動画で紹介して、予約や来店につなげるケースがあります。写真やテキストだけでは伝わりにくい空気感を動画で伝えることで、顧客が「行ってみたい」と思いやすくなるのが利点です。ただし高品質な動画を掲載する場合でも、実際に圧縮やLazy Loadingなどの対策を講じることで、ページ全体の読み込みを軽快に保っている点が成功の秘訣といえます。
まとめ
ホームページに動画を埋め込むことで、視覚的な訴求力が高まり、ユーザーの興味を引く強力な手段となります。一方で、動画ファイルは容量が大きくなりやすい点がデメリットです。そのため、Lazy Loadingをはじめとする読み込み速度の改善施策や、適切な形式・解像度の選択が必須となります。
また、動画の自動再生をオフにする、サムネイルを軽量化するなどの細やかな工夫によって、訪問者のストレスを軽減し、ページ全体の表示速度を保つことができます。ローカルSEOを狙う中小企業にとっては、地域のユーザーがサクサク閲覧できる環境づくりが何より重要です。動画の魅力を活かしつつ、快適なユーザー体験を提供するための対策をしっかり押さえておきましょう。






