Blog お役立ちブログ
制作依頼前に用意しておく素材や情報のまとめ方
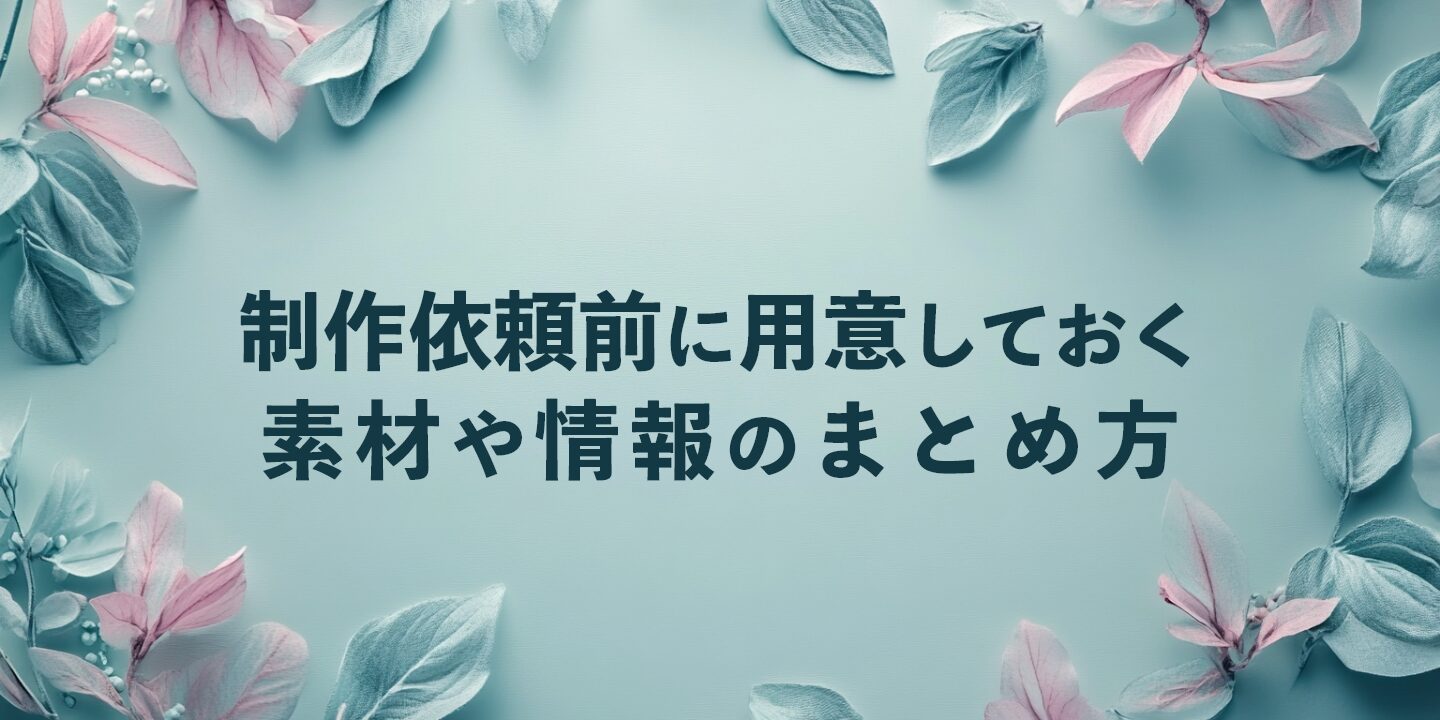
はじめに
制作を外部の専門会社へ依頼する前に、どのような素材や情報を用意し、どのようにまとめておくかは非常に重要です。事前準備が不十分だと、制作プロセスに入ってからあれこれ質問が飛び交い、やり直しやスケジュールの遅延につながりやすくなります。逆に、必要な素材と情報が整理されていれば、制作会社も方向性を明確に捉えやすく、スムーズにプロジェクトが進むでしょう。
本記事では、中小企業の経営者や決裁権をもつ方々が、制作会社から「最低限揃えてほしい」と言われる資料やデータをどのように管理し、提供すればいいのか、その具体的なポイントを分かりやすく解説します。特に、テキスト原稿や写真・画像素材の用意、ブランドイメージの共有方法、社内連携のコツなどを中心に、実践的な内容を盛り込みました。
制作前に準備すべき素材の整理
制作依頼を行う際は、最低限そろえておきたい素材と情報があります。それらをまとめると以下のようなカテゴリーに分けられます。
- テキスト情報:企業概要、サービスや商品の詳細、実績や導入事例など
- ビジュアル素材:ロゴデータ、写真、イラスト、アイコンなど
- ブランディング関連:コーポレートカラー、デザインガイドライン、参考サイト
- 社内で把握しておくべき情報:担当者や検討フロー、スケジュール、予算感、目指す方向性
これらを管理する際、別々のフォルダやファイルにバラバラに置いていては混乱のもとになりがちです。以下の表は、素材の管理方法を一例として示したものです。
| 管理項目 | 推奨するフォルダ構成例 | 備考 |
|---|---|---|
| 企業プロフィール | /情報整理/企業情報 | 会社概要や沿革、経営理念など |
| 商品・サービス詳細 | /情報整理/サービス | 各商品やサービスの特徴、料金プラン、導入メリットなど |
| 写真・ロゴ・画像 | /情報整理/ビジュアル | ロゴはできるだけ高解像度のデータで、拡張子も明記 |
| ブランドガイドライン | /情報整理/ブランド関連 | コーポレートカラーやフォント、使用許可範囲などの規定 |
| 制作進行管理 | /情報整理/スケジュールと担当 | 社内外の進行担当者や締め切りの管理に便利 |
このように大きなディレクトリ(フォルダ)構成を用意し、その中に関連するファイルを分類・保管することで、どこに何があるのか一目瞭然になります。特に、社内担当者が複数存在する場合は、誰でも同じ階層構成で探せるようにしておくと、情報の重複や紛失を防ぎやすいでしょう。
テキスト原稿の作り方
次に、テキスト原稿について考えてみましょう。テキスト原稿は制作物の骨格となる大切な要素です。口頭での説明だけに頼ってしまうと認識のズレが生じやすく、制作会社側で勝手に解釈してしまうリスクがあります。そこで、以下のようなステップを踏んでテキスト原稿を準備するのがおすすめです。
- 最終的な目的やゴールを再確認
- 新規顧客にサービスを分かりやすく伝えるのか
- 既存顧客との関係強化を図るのか
- 事業内容を包括的に紹介したいのか
- 情報を箇条書きに整理
- 企業概要、代表メッセージ、サービスの強みなどテーマごとに見出しを作る
- 余計な装飾は行わず、まずは情報をシンプルに羅列
- 簡潔に要約した文章を作成
- 箇条書きの内容を読みやすい文章にする
- 専門用語は最小限に抑え、一般的な言葉でまとめる
- 章立て(見出し)を明確にする
- H1、H2などの見出しを想定し、読み手が流れを追いやすい構成にする
- 1つの見出しに複数のトピックが混在しないように注意
- 最終チェックと修正
- 誤字脱字の確認
- 文章が重複していないか、また意図が曖昧になっていないかを精査
以下の表は、テキスト原稿を作成する際にチェックしておきたいポイントをまとめたものです。
| チェック項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 見出しの構成 | 見出し(H2、H3など)は論理的に一貫しているか |
| 文体 | ですます調など一定の文体で統一されているか |
| 専門用語の使い方 | 一般の人でも理解できる言葉を使っているか |
| 文字数・段落 | 長すぎる文章を区切って読みやすくしているか |
| 情報の重複 | 同じ内容を繰り返していないか、削除できる箇所はないか |
文章のクオリティは、読み手の理解度や興味の継続にも大きな影響を与えます。特に、自社のサービスの強みや他社と差別化を図るポイントなどは、どうしても冗長になりがちです。そこで、「最も伝えたい内容」を優先し、不必要に長い説明を省くよう心がけると、制作会社のデザイナーやライターにも意図が伝わりやすくなるでしょう。
写真・画像素材のポイント
テキスト原稿に加えて、写真や画像素材の準備も重要です。特に製品写真やサービスの利用シーンを伝えるビジュアルは、実際に閲覧するユーザーのイメージを大きく左右します。写真や画像素材を用意するときには、以下の点を押さえておくとスムーズです。
- 解像度とファイル形式
高解像度のJPEGやPNG、またはロゴなどに関してはAIファイルやEPSファイルなどベクター形式が好まれます。解像度が低いと画質が粗くなるため、最終的なサイトや印刷物のクオリティに影響が出る恐れがあります。 - 余白やトリミングの有無
写真の構図や被写体の位置を確認し、必要に応じてトリミングしておくと、使いやすい素材になります。ただし、過度にトリミングするとレイアウトの自由度が下がるので注意しましょう。 - 撮影時の注意点
社内で写真を撮影する場合は、十分な光量がある場所で撮る、背景をシンプルにするなど、基本的な撮影のコツを押さえておくと、後々の修正作業が軽減されます。
特に、企業のコーポレートサイトなどでは「製品写真」「サービス事例写真」「社内風景」「オフィス写真」など複数種類の画像が必要になるケースが多いでしょう。例えば以下のように、あらかじめカテゴリ別で整理すると混乱を防ぎやすくなります。
| カテゴリ | 内容例 | 保存先例 |
|---|---|---|
| 製品・サービス | 製品の正面・側面写真、操作画面キャプチャなど | /情報整理/ビジュアル/製品 |
| 事例・実績 | 導入事例の写真、お客様インタビュー風景など | /情報整理/ビジュアル/実績事例 |
| 社内・オフィス | 社内風景、社員集合写真、オフィス外観など | /情報整理/ビジュアル/社内オフィス |
| ブランド関連 | ロゴ(ベクター形式推奨)、アイコン、シンボル画像など | /情報整理/ビジュアル/ブランド |
また、画像を提供する際はファイル名やフォルダ名を分かりやすく付けておくと、制作会社も使いやすいでしょう。ファイル名だけで中身が想像できる状態が理想的です。
イメージ共有とブランドガイドライン
制作会社との認識合わせをスムーズに進めるには、ブランドの世界観やコンセプトを共有する資料が必要になります。たとえば、以下のような項目をまとめた「ブランドガイドライン」を用意している企業もあります。
- コーポレートカラー(色コードを含む)
- 推奨するフォントとその使用ルール
- ロゴマークの最小使用サイズや色指定
- デザイン上の禁止例(ロゴの変形、色変更など)
もしこうしたガイドラインが自社でまだ整備されていない場合、完成度の高いものを作り上げる必要はありませんが、少なくとも「好ましい色合いや雰囲気」「避けたいデザインの方向性」「競合企業の例」などはまとめておくと良いでしょう。
さらに、参考サイトやデザインの雰囲気を示すサンプルなどを提示することも効果的です。たとえば「シンプルで清潔感のあるイメージを理想としている」「動きのあるアニメーションを入れたい」「文字情報を主体とした落ち着いたデザインにしたい」など、抽象的な言葉に留まらず、具体例や画面キャプチャを添えると、制作会社の解釈とずれにくくなります。
社内情報共有の進め方
制作会社に素材や情報を渡す以前に、社内での情報共有体制を整えておくことも大切です。プロジェクトに関わるメンバーが複数いる場合、下記のような点を確認しておくと、混乱を防ぎスムーズに進行できます。
- 決裁ルートの明確化
誰が最終的な判断を下すのか、どのタイミングでレビューを行うのかを事前に決めておく。 - 担当範囲の割り振り
原稿を作る人、写真を撮る人、資料を取りまとめる人など、それぞれの担当を明確に。 - ファイル管理ルール
共同で使うオンラインストレージなどを用意し、アップロードのしかたやフォルダ名を統一。
特に、情報が更新されるたびに「どこにアップしてあるのか分からない」「どれが最新バージョンのファイルなのか不明」となると二度手間・三度手間が発生します。最新のファイルの管理方法や命名規則を一度決めておくと良いでしょう。
制作会社とスムーズにやり取りする工夫
制作会社とコミュニケーションを取るときは、お互いの時間と労力を節約するために、次のような工夫をすると良い結果が得られます。
- 要望や質問はまとめて送る
1つのメールやメッセージに、関連するトピックをできるだけ集約すると、やり取りが効率的です。複数の担当者がいる場合は、取りまとめ役を決めるのも手です。 - 優先順位を明確に伝える
要望すべてに同じ重みがあると、制作会社もどこから手をつければいいか迷います。実現したいポイントを優先度順にリスト化して伝えましょう。 - デザイン案や原稿へのコメント方法を統一する
PDFに注釈を入れる、チャット上でスクリーンショットを使うなど、フィードバックのやり方を決めておくと二重チェックが減ります。 - 定期ミーティングの設定
週1回、または隔週など、作業の進捗状況を共有する場を設けると、手戻りや情報不足に早期に気づけます。
以下は、制作会社との連携を円滑にするためのヒントをシチュエーション別にまとめた例です。
| シチュエーション | 工夫やヒント |
|---|---|
| 素材や原稿の受け渡しが頻繁 | オンラインストレージを活用し、ファイル名に日付とバージョンを付与する |
| デザイン案へのフィードバック | PDFの注釈機能や画面キャプチャを使い、具体的に修正点を示す |
| 社内レビューが多段階にわたる | 各段階での承認者を明確にし、メールやチャットで更新内容を記録する |
| スケジュール変更の可能性が高い | 余裕をもったスケジュールを提示し、変更が出そうな場合は早めに共有する |
上記のように事前の準備と連携手法を整備することで、お互いにスムーズにプロジェクトを進められます。
まとめ
制作依頼を成功させるためには、「必要な素材や情報をきちんと揃え、相手に伝わる形で整理すること」が欠かせません。テキスト原稿の作り方や写真・画像素材の選定・管理方法、ブランドガイドラインの準備など、どれも煩雑に見えるかもしれませんが、あらかじめ方針と手順を決めておけば確実に効率が上がります。社内体制の整備も大切で、スケジュールや担当者、決裁の流れを明確にしておくことで、制作会社とのやり取りが円滑になり、最終的に高いクオリティの成果物を得られる可能性が高まります。
自社の強みやブランドイメージを正しく伝えるためにも、事前の準備とコミュニケーション設計をしっかりと行い、制作会社との協力体制を築いてください。何をどのように用意するか迷っている方は、まずは本文で紹介した各ステップを参考に、自社の状況に合わせて一つずつ整備を進めていくとよいでしょう。






