Blog お役立ちブログ
仲間と共同創業する場合、サイトの名義はどうなる?
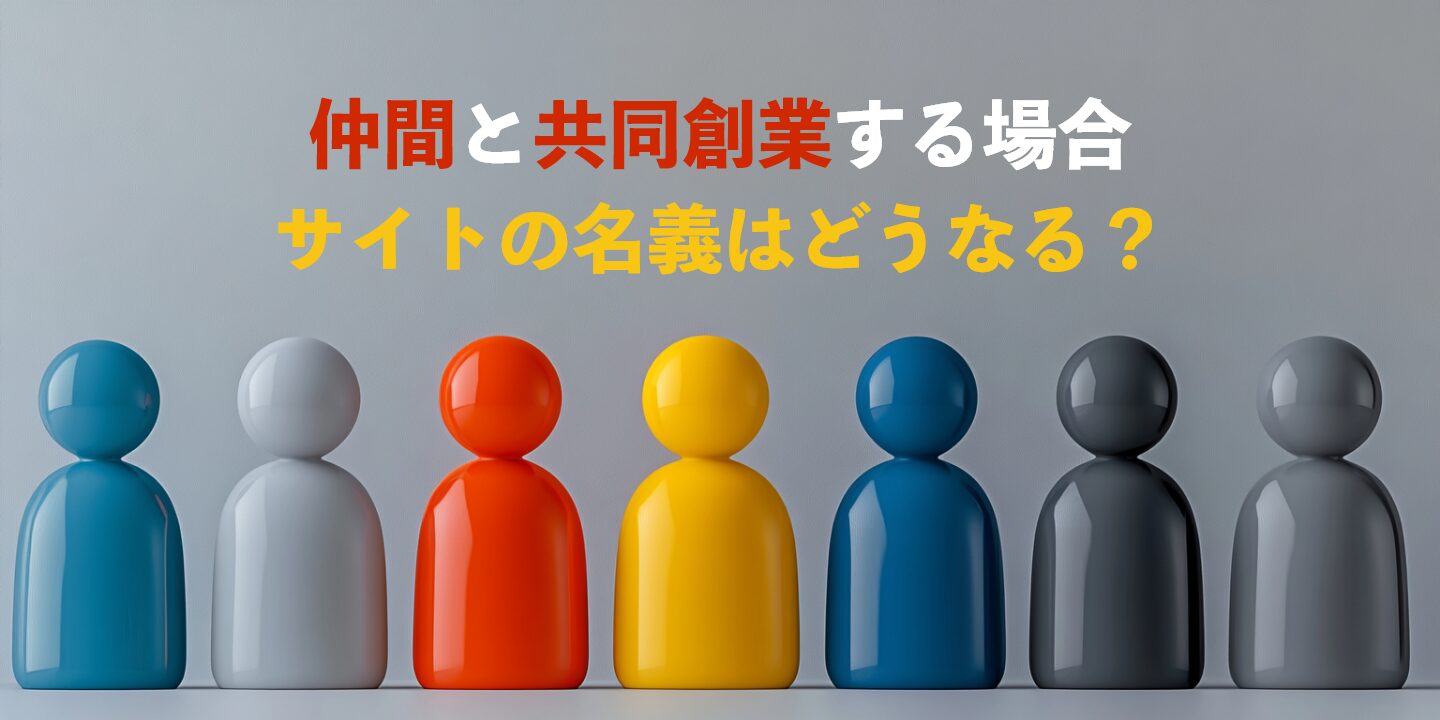
仲間や同業の友人など、複数人で共同創業するケースは珍しくありません。特に中小企業の場合はスモールスタートが多く、少人数で一斉に事業を始めることでリスクを分散させる意図もあるでしょう。しかし、事業運営の重要な基盤となるWebサイトやネットショップ、コーポレートサイトなどの「名義」をどのように設定するかは意外と見落とされがちです。
名義とは、ドメインやサーバーを誰の名前で契約するかといった権利上の問題に加え、「そのサイトが誰の所有物として扱われるのか」という法的・対外的な認識に直結する要素でもあります。単純に「ドメインは代表者Aさん」「サーバーは代表者Bさん」という形にしてしまうと、後から権利関係が複雑になるリスクがあるので注意が必要です。
ここでは、共同創業時にどのような名義体制を取ることが望ましいのか、大まかな考え方を説明します。
- 法人名義で一元管理する
- 法人格を取得したら、可能な限り会社名義で契約を行い、誰が退職・離脱しても影響を受けにくくする。
- 個人名義での分散管理はリスク大
- 個人単位で名義を分散すると、誰か一人が抜けたときに権利移譲の手続きが面倒になる。
- 将来の分社化・独立を見据えたルールづくり
- 事前に「名義の扱いはどうするか」「権利の移転時、費用負担はどうするか」などを定めておく。
上記のように、まずは「将来的に起こりうる変化」も見据えて、できる限り一本化あるいは契約・管理ルールを明確にしておくことが重要です。
共同運営時に起こりやすいトラブルと権利関係の整理
仲間同士のビジネスは信頼関係があるため、初期段階では「なんとなくの分担」で運営することも多いですが、後になって権利や契約の問題で意見が対立することがあります。たとえば、以下のようなトラブル例があります。
- サイトやドメインの所有権が不透明
- ドメインを誰が取得したか曖昧で、更新を忘れた結果、使えなくなってしまう。
- 名義人が契約解約を勝手に行う
- 対立が深まり、名義を持つ当人が一方的にサービスを止めてしまう恐れがある。
- 売上や運営費用の負担割合が不明確
- ドメインの更新費、サーバー費用などを誰がどれだけ出すのか曖昧で、経費計上が混乱する。
こうした混乱を防ぐためには、以下のようなポイントを押さえておく必要があります。
- 法人格の取得タイミング
- 事業規模が大きくなる可能性があるなら早めに法人化を検討し、会社名義で契約を一括管理する。
- 運用・管理責任の割り振り
- 「誰が更新を担当するのか」「決済や経費精算は誰が行うのか」を明確にしておく。
- 契約や権利移転のルール作り
- 独立や離脱が生じた際に、ドメインやサイトデータをどう扱うか、事前に決めておく。
以下の表は、名義に関する代表的なパターンと、それぞれのメリット・デメリットを比較したものです。
| 名義人パターン | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 個人名義(代表者) | – 手続きが早い – 初期費用を抑えられる | – 代表者が抜けると権利移転が煩雑 – 個人の信用に依存するためリスクが大きい |
| 個人名義(複数人分散) | – 負担を分散しやすい | – 全員の合意がなければ管理が難しい – 意見対立時にサービス停止リスクが高まる |
| 法人名義(会社で一括) | – 権利が法人に集約される – メンバー交替の影響を受けにくい | – 法人維持コストがかかる – 設立初期は負担が大きい場合がある |
共同で創業する際は、なるべく「法人名義(会社で一括)」にしておくほうが、将来的なトラブルを回避しやすいといえます。
サイト・ドメイン管理体制のつくり方
具体的に、サイトやドメインをどのように管理していけばよいのか、ポイントを押さえてみましょう。とくに複数メンバーで運営する場合は「担当業務の明確化」「管理ツールの共有」「更新作業の手順化」の3つが鍵になります。
担当業務の明確化
- 契約担当
- ドメイン取得やサーバー契約をどのタイミングで行うか、それらを誰が主導するか。
- 運用担当
- コンテンツの更新作業やサイトのデザイン調整など、日常的な運用業務を誰が担うか。
- 会計担当
- サーバー費用やドメイン更新費、各種ツールの利用料などの支払いと会計処理を一括管理するか分担するか。
これらをあいまいにしていると、作業を忘れる・経費がどこから出るか分からないといった混乱を招きがちです。
管理ツールの共有
共同運営では、メンバー間のコミュニケーションをスムーズにし、サイト管理に関する情報を共有する仕組みが必要です。
- クラウド上のプロジェクト管理ツール
- タスク一覧やスケジュール管理を全員が確認できるようにする。
- ドキュメント管理ツール
- サーバー情報やログインID・パスワードなど、セキュアな形でメンバー間で閲覧できるようにする。
- 連絡チャットツール
- 運用方針や緊急対応などを迅速に共有するためのコミュニケーション環境を整備。
更新作業の手順化
更新作業やシステムのメンテナンスが必要なとき、誰が何をすべきかを手順化しておくと、トラブルや作業漏れが起きにくくなります。たとえば「ドメインの更新通知メールが来たら会計担当に報告し、支払いを完了する」「CMSのバージョンアップ前に必ずバックアップを取る」などのフローを共有することが大切です。
以下の表は、共同運営における代表的なトラブルと、その原因・対処法をまとめたものです。
| トラブル例 | 原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| ドメイン更新漏れでサイト停止 | 担当者が不在、または誰も気づいていない | 自動更新設定を有効にし、管理ツールでリマインダーを設定する |
| サイト管理画面へのアクセス不可 | パスワードが共有されておらず、別メンバーだけが知っている | パスワード管理ツールを導入し、全員がアクセス情報を引き継げるようにする |
| 請求書の支払先が不明で経費混乱 | 会計担当が曖昧、複数人が別々に支払いを行っている | 会計担当を明確化し、一括で支払い管理を行う |
| 運営方針の対立でコンテンツ更新停止 | 経営方針や更新ルールが明確でなく、責任範囲が不透明 | 更新方針や運営ガイドラインを策定し、事前に合意を得ておく |
分社化・独立を見据えた名義と運用方法の工夫
共同創業時点では想定していなくても、事業が軌道に乗り、やがて分社化や経営者同士の独立が起こることは珍しくありません。その際に問題となるのが、「ウェブサイトをどう扱うか」です。たとえば、コーポレートサイトやブランドサイトなど、事業の顔として育ててきたサイトを安易に手放すと、集客力やブランド力を大きく損なう恐れがあります。
分社化・独立時に検討すべきポイント
- サイトをどちらが引き継ぐのか
- 新事業側が引き継ぐのか、元々の法人側が保持するのか。
- ドメインや商標に関する権利移転
- 分社先に移す場合はどのような契約形態で譲渡するか。
- サイト内コンテンツの著作権
- 執筆者や制作会社との契約内容によっては、コンテンツの利用範囲を再調整する必要がある。
- 引き継ぎ後のSEOやブランドイメージへの影響
- ドメインを変える場合、リダイレクトの設定やブランド名称をどう扱うかなどの注意が必要。
独立や分社化を円滑にするための準備
- 契約書や規約で取り決める
- 共同運営開始時点で、将来の独立・分社化シナリオを想定し、サイト・ドメイン移転に関する取り決めを書面化しておく。
- コンテンツの著作者を明確化する
- 文章や画像、動画などを誰が作成したものかを記録し、著作権の所在をハッキリさせる。
- ブランドや商標の登録状況を把握する
- サイト名を商標として登録する場合は、その名義をどちらにするか決めておく。
下記の表は、分社化・独立を想定したときに検討しておきたいサイト管理の選択肢をまとめたものです。
| 運用方式 | 特徴 |
|---|---|
| 法人名義で引き続き運用 | – 元の法人が継続してサイトを保持 – 新事業が別ドメイン・別サイトを立ち上げる場合に有効 |
| 分社先へ権利を全面的に譲渡 | – 新事業のコアとなる場合、サイトを譲渡してドメインも移転 – 旧法人には一定額の譲渡費用が入るケースも |
| 一部コンテンツを切り分ける | – メインのサイトは元法人が保有し、サブドメインや特定ディレクトリ部分を切り離す |
| 新規に独立用のサイトを構築 | – 既存サイトからリンクを張るなどしてSEO影響を最小限にする – ブランディング再構築時に有効 |
共同運営開始当初は大きな変化をイメージしづらいものですが、「長期的にどのようにサイトを運用していくか」「メンバーが抜けたときにどう対処するか」を見据えておくことで、後になって重大な衝突を避けられるでしょう。
軽いエピソード:共同運営サイトの名義でもめたケース
ある中小企業のA社は、共同創業メンバー3人で立ち上げたばかりの頃、代表者の個人名義でドメイン・サーバー契約をしていました。サイトの更新や支払いは何となく交代で行っていたのですが、1年後に1人が別事業に専念するため離脱。すると残った2人は「代表者の個人名義でサイトを持たれると、会社の資産としてカウントしづらい」「ドメインを譲渡してくれないか」という話になり、譲渡条件でもめ始めました。
最終的には「会社を正式に法人化して、サイト名義を法人に移す」「離脱したメンバーには譲渡費用として一定額を支払う」ことで決着がつきましたが、思わぬお金と手間がかかったそうです。最初から法人名義にしておけば、こうしたトラブルは最小限に抑えられたかもしれません。
まとめ
仲間や知人と共同で創業する際は、Webサイトやドメインの名義をどのようにすべきか、早い段階で合意形成を図ることが重要です。特に下記のポイントを押さえておきましょう。
- 法人名義での一元管理がベター
個人同士の名義分散よりも、後々の管理や権利移転が容易になります。 - 管理体制や契約ルールを明確化
誰が運営担当なのか、誰が会計担当なのかを決め、ツールを使って情報共有しましょう。 - 将来的な分社化や独立シナリオも想定
サイト・ドメインをどちらが引き継ぐのか、譲渡方法はどうするのかなどを想定しておくと安心です。
共同創業はメリットも大きい反面、権利や契約関係があいまいだとトラブルに発展しやすい側面があります。Webサイトの名義や運用方法は、ビジネスの顔や集客チャネルを守る上で非常に大切なポイントです。ぜひ参考にして、仲間との共同運営を円滑に進めてください。






