Blog お役立ちブログ
外注ライターを活用してブログ更新を継続する運営体制
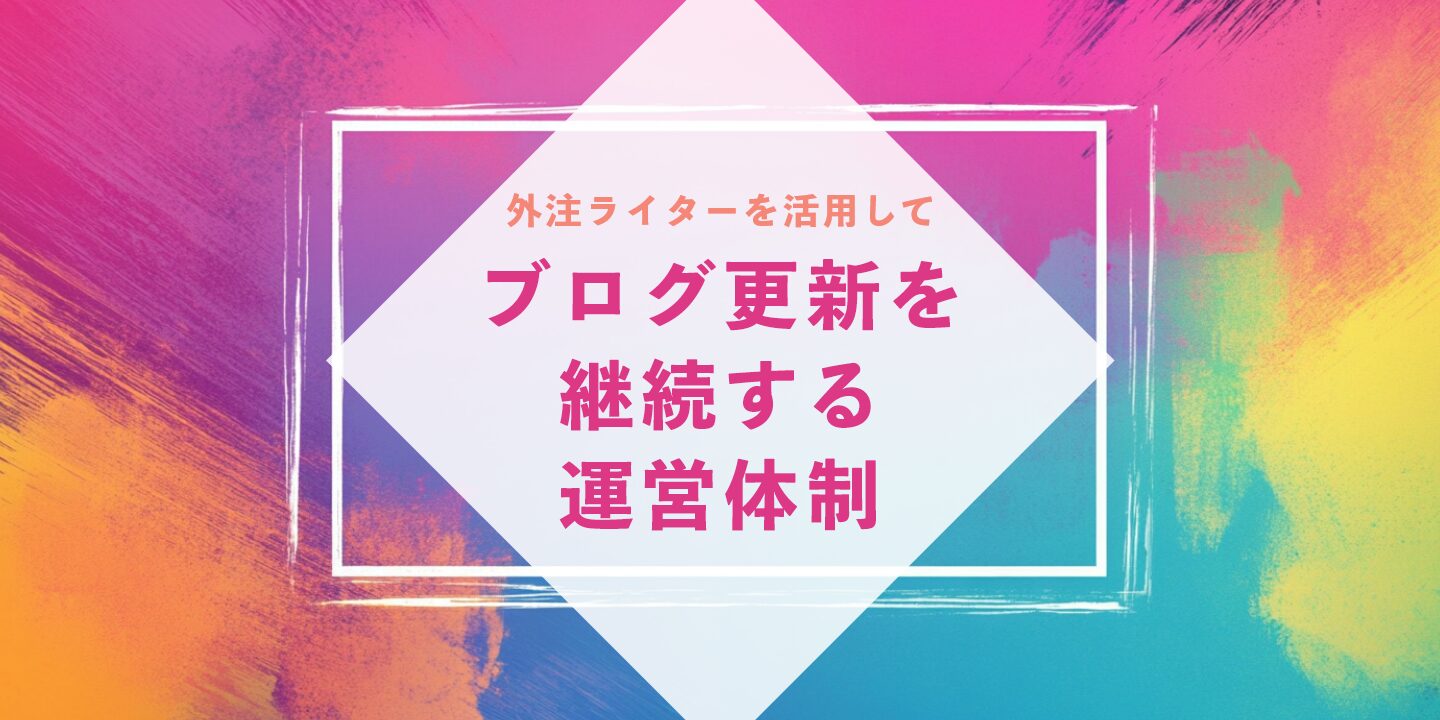
はじめに
中小企業が自社ブログを継続的に更新していくためには、専門的な文章を書くスキルや時間を確保する必要があります。しかし、実際には社内にライティング経験のある人材がいなかったり、日々の業務が忙しくてブログ執筆に時間を割けなかったりと、さまざまなハードルが存在します。そこで注目されるのが、外注ライターをうまく活用する方法です。
外注ライターに依頼すれば、専門的な領域の執筆や定期的な記事更新を実現できます。ただし、外注費と記事のクオリティをどう両立するのか、品質チェックはどう進めるのかなど、気になるポイントも多いでしょう。本記事では、外注ライターの探し方や依頼手順、費用対効果を高めるコツ、そして継続的に更新を行うための運営体制づくりについて詳しく解説していきます。
外注ライターを活用するメリット
まず、外注ライターを活用することで得られるメリットを整理してみましょう。以下の表では、主なメリットとデメリットを比較してあります。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 専門性 | 専門分野に強いライターに依頼できるため、高品質なコンテンツを提供できる | 特定分野に強いライターが少ない場合、見つけるのに時間がかかる |
| コスト | 社員を増やすよりも安定したコストで必要な分だけ依頼できる | 外注費が積み重なるとランニングコストが大きくなる恐れがある |
| 作業効率 | 社内リソースを他の業務に集中させやすくなる | 発注業務やコミュニケーションに一定の工数がかかる |
| 多様な視点 | 外部の視点を取り入れられるため、記事のバリエーションが広がりやすい | 自社の方針やブランドイメージを理解してもらうのに時間が必要 |
| ブログ更新の継続 | ライターを定期的に手配することで更新がストップしにくくなる | 契約トラブルやライター不足などで、突然更新が滞る可能性もある |
外注ライターを使う最大の利点は、専門家に任せることで記事クオリティを高められることと、社内人材をライティング以外のコア業務へ集中させられる点にあります。一方で、コミュニケーションや品質管理の仕組みを整えないと、思ったような成果につながりにくいため注意が必要です。
外注ライターの選び方
外注ライターを選ぶ際には、いくつかの観点を押さえておくと失敗しにくくなります。以下では、ライター選定時にチェックしたいポイントを紹介します。
1. 実績や得意分野
ライターにより、得意とする分野や文体、トーンは異なります。自社の商品やサービスに近い分野での執筆経験があるライターを選ぶことで、よりスムーズに記事の品質を上げられます。また、ポートフォリオやサンプル記事を確認することで、実際のクオリティを把握しやすくなります。
2. コミュニケーション能力
記事執筆は単に文章力だけでなく、クライアントの要望を正しく理解し、それを表現できる能力も欠かせません。メールやメッセージのやり取りがスムーズにできるかどうかも大きなポイントです。レスポンスが極端に遅かったり、問い合わせに対して内容が伝わりにくい場合は、長期的なコラボレーションに不安が残ります。
3. 料金形態
ライターへの発注料金は、文字単価や記事1本あたりの固定料金など、いくつかのパターンがあります。自社の予算や必要な記事量に応じて、無理のない料金プランを選択しましょう。文字単価が安すぎる場合はクオリティ面のリスクがありますし、高すぎる場合はブログ運用全体のコスト増につながるのでバランスが重要です。
4. 継続的な対応の可否
ブログを定期更新するためには、継続的に依頼できるライターが必要です。単発案件しか受けない、あるいは執筆スケジュールに余裕のないライターに依頼すると、更新ペースを維持できない場合があります。事前に相談し、毎月何本まで対応可能なのかを確認しておくと良いでしょう。
外注ライターへの依頼手順とポイント
ここでは、実際に外注ライターへ発注する際の大まかな流れを、表を使いながら整理します。依頼の手順を明確にしておくと、ミスコミュニケーションや納期遅延を防ぎやすくなります。
| 手順 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1.要件定義 | 記事の目的、ターゲット、文字数、キーワードなどの基本事項を決める | 自社ブログの狙いや読者層が明確になるほど、ライターに的確な指示がしやすい |
| 2.ライター選定 | 実績や得意分野、コミュニケーション頻度などを確認し、候補を絞り込む | 得意分野が自社テーマと合っているか、納期や予算の相性などを確認 |
| 3.発注仕様作成 | ライター向けに執筆ガイドライン(文体、構成、禁止事項など)を用意し、発注書をまとめる | 箇条書きなどで具体的に指示。加えて例文やトーン&マナーを提示すると品質が安定 |
| 4.やり取り | ライターと納期や記事構成のすり合わせを行い、必要に応じて初稿の方向性をチェック | 仮タイトルや見出し案をライターと相談し、方向性を先に揃えておくと大幅なリライトを回避 |
| 5.初稿確認 | 納品された初稿に対し、修正指示やフィードバックを行う | 大きな修正点は早めに共有し、なるべく都度小出しにしないよう注意 |
| 6.最終納品 | 修正後の記事を受け取り、公開用の状態に整える | 画像や内部リンクの設定など最終調整を行い、スケジュールに沿って公開 |
上記を踏まえて、外注ライターに依頼する際には以下のポイントを意識しましょう。
- 発注前のリサーチ
ライターの経歴や実績、得意ジャンルを確認。自社ブログとの相性を見極める。 - 具体的な指示書を用意
曖昧な要望だけでは、ライターも望む仕上がりをイメージしにくい。書いてほしい内容やトーン、ターゲットを具体的に伝える。 - コミュニケーションの頻度調整
進捗状況や初稿の方向性を早めに共有する。不要な修正を減らし、スムーズに納品まで進める。 - 修正対応のルールづくり
無制限に修正依頼できると、ライターのモチベーション低下や納期遅れのリスクが高まる。指示とフィードバックをまとめて行い、必要な回数を事前に決めると良い。
ブログ更新を定期的に継続させるための運営体制
外注ライターを活用してブログ更新を続けるためには、社内の運営体制も整えておく必要があります。具体的には、どのような流れで運営すればスムーズに継続できるのか、次の表にまとめました。
| 役割 | 主な担当 | メリット |
|---|---|---|
| 運営責任者 | 記事テーマの決定、最終的な方向性チェック、全体スケジュール管理 | 全体方針がぶれにくくなる。スケジュール管理も一本化できる |
| コンテンツディレクター | ライターへの発注仕様策定、執筆ガイドライン作成、初稿レビュー | ディレクション業務を一元化し、効率的にライターをコントロール |
| 校正・編集担当 | 校閲や表記揺れチェック、書き手の癖の修正、用語の統一 | 細かい品質面に気を配る役割がいることで、記事のクオリティを一定以上に保ちやすい |
| ライター管理担当 | 外注ライターへの連絡・窓口、スケジュール調整 | ライターとのやりとりが一本化されるため、混乱が少なくなる |
| 公開担当 | 記事をWeb上で公開し、必要に応じて画像選定・SEO設定などを反映 | 各工程を連携しながら最終的な公開手順をスムーズにできる |
運営体制のポイント
- 責任者の明確化
ブログ運営の最終判断を行う人をはっきりさせましょう。テーマ選定や方向性の確認、スケジュール管理など、一元的に決定できる体制が望ましいです。 - ディレクション能力の確保
外注ライターに依頼するとき、単に記事を書いてもらうだけでなく、全体の構成やキーワード選定などのディレクションが欠かせません。社内に専任担当を置くか、外部のディレクターを活用するなど、ディレクションの役割を誰が担うかをはっきりさせましょう。 - ライターのモチベーション管理
定期的にライターへフィードバックを行い、成果物がどのように活用されたかを共有すると、ライター自身のモチベーション向上につながります。モチベーションが高いほど記事クオリティも上がりやすいでしょう。 - 継続的な更新テーマのリスト化
ブログのネタ切れを防ぐためにも、あらかじめ「年間のテーマ」や「月ごとの特集内容」などをざっくり決めておくと、毎回の記事依頼をスムーズに進められます。定期的にアクセス解析を行い、人気コンテンツや読者の反応を踏まえてテーマを更新していくこともポイントです。
外注ライターとのコミュニケーションと品質管理
外注ライターをうまく活用するには、ライターとのコミュニケーション設計が重要です。コミュニケーション不足でイメージ違いが生じると、修正が増えてコストがかさむだけでなく、双方のストレスも高まります。次の表では、品質管理とコミュニケーションを円滑に進めるための具体的なアクションをまとめています。
| 方法 | 内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 初稿レビューのタイミングを事前設定 | 記事の構成案やリード文など、早い段階で方向性を確認し合う | 大幅なリライトを避け、納期遅延や追加コストを防ぐ |
| 執筆ガイドラインの細分化と更新 | 用語の表記統一、文体ルール、禁止表現などをリスト化して定期的に更新 | ライターが手戻りなく執筆でき、品質が安定する |
| 定例ミーティングまたはオンライン報告 | 進捗状況や次回記事のテーマを共有し、疑問点をその場で解消 | ライターとの信頼関係が深まり、継続的なコラボレーションがしやすくなる |
| 修正依頼のまとめ方 | バラバラに送るのではなく、ある程度まとめて依頼する。指摘箇所に根拠や意図を添える | 不必要なやりとりを減らし、ライターが納得感をもって修正できる |
| 定量評価とフィードバック | キーワード配置、読みやすさ、ターゲットとのマッチ度などを基準にして客観的に評価し、次回の改善点をフィードバック | ライターが自身のパフォーマンスを振り返り、次の記事の品質向上に活かせる |
品質管理のコツ
- チェックリストを活用する
見出しやリード文の長さ、重要キーワードの活用、誤字脱字などをチェックするためのシートを作成すると効率的です。誰でも同じ基準で記事を確認でき、担当者が変わってもクオリティに大きな差が生じにくくなります。 - 校正や編集の専門知識を取り入れる
タイポや文法ミスの修正だけでなく、読みやすさや論旨の整理などを行う編集力が加われば、全体として質の高い記事に仕上がります。外注先が対応してくれる場合もありますし、社内担当者を育成していくのもひとつの方法です。 - 継続的な評価制度
依頼本数が増えてきたら、ライターごとに定期的な評価を行い、追加で教育が必要な点や特に優れている点を共有していきます。成果に応じて報酬を見直すなどの仕組みを作ることで、ライターとの関係性を良好に保ちやすいでしょう。
具体例・エピソード
ここでは、実際に外注ライターを活用している中小企業の例を想定して、どんな流れで成果を出しているかを簡単に紹介します。
- 事例1:技術系のブログを運営する中小企業
専門用語が多いジャンルの記事を社内で書くのは時間と労力がかかるため、ライターを複数人外注して効率化を図ったケース。最初はライターが技術的な用語を誤用するなどのトラブルがあったが、専任の編集担当がガイドラインを整え、継続的にフィードバックする仕組みを作ったことで、最終的には安定した品質の記事を定期的に公開できるようになった。 - 事例2:新商品の紹介を月ごとに行う小売企業
自社で顧客対応や販売戦略を優先する一方、商品紹介記事は外注ライターに任せて毎月決まったタイミングで更新している。毎月の新商品リストをライターへ渡し、商品コンセプトやセールスポイントだけを伝えれば、後は各商品ごとに魅力を引き出す記事を書いてもらえる。結果として、担当者は在庫管理や仕入れ交渉に時間を割けるようになり、本業とブログ運営の両立が可能になった。 - 事例3:複数の外注ライターをマネジメントするチーム体制
月に数十本の記事を公開する企業の場合、1人のライターだけでは対応しきれないので複数ライターに同時発注している。コンテンツディレクターがそれぞれのライターの得意分野を把握し、記事のジャンルや難易度に応じて割り振ることで効率的に作業が進む。ライター間でのクオリティのばらつきは、最終的な編集担当が表記統一やトーンをそろえることで抑えている。
どの企業も、外注ライターを単に「記事を書いてもらう」だけではなく、運営体制として管理やコミュニケーションの仕組みを整えることで、定期的かつ高品質な更新を実現しています。
まとめ
外注ライターを活用してブログ更新を継続する運営体制を構築するには、まずライター選びと依頼手順の明確化が欠かせません。社内では記事執筆を担当できる人がいなくても、外注ライターに的確に指示し、品質管理とコミュニケーションを円滑に行えば、定期的な更新を続けることが可能になります。
大切なのは、単発の執筆依頼に終わらせず、長期的な体制づくりを視野に入れることです。目指すのは、ブログが企業の情報発信や集客のための重要な役割を果たすこと。運営責任者やディレクター、編集担当などの役割分担を明確にし、ライターと協力関係を築くことで、より安定した成果を得られます。
外注に任せるメリットとしては、専門家の知識やスキルを取り入れられることや、社内リソースをコア業務に集中できることが挙げられます。一方で、コミュニケーション不足や品質チェックの不備は、成果につながりにくい原因となりやすいため、あらかじめ運営体制を整え、ライターへの丁寧なディレクションと定期的なフィードバックを実施することを心がけてください。






