Blog お役立ちブログ
キーワード関係なくブログ書きすぎるとSEOに悪影響?
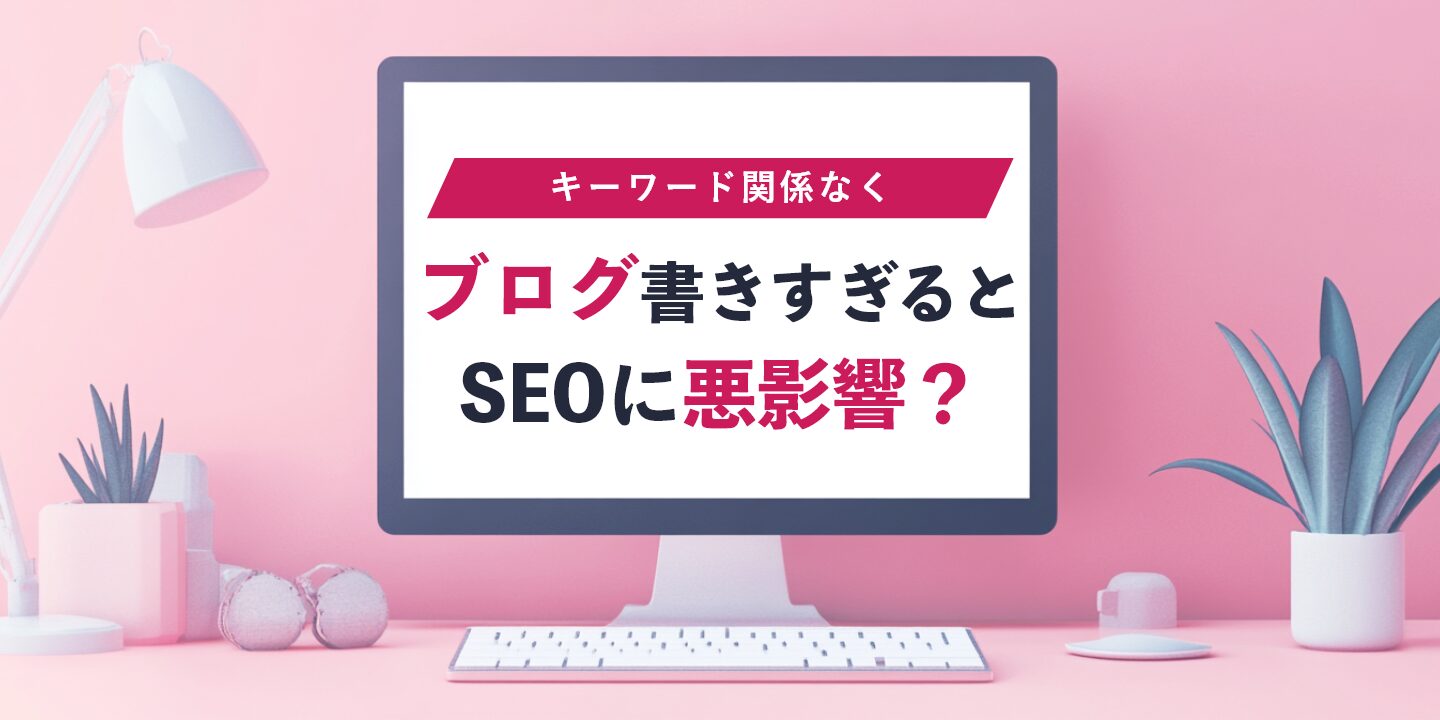
はじめに:雑多なブログ運営が抱える問題点
企業のウェブサイトやブログを運営する際、記事の本数を増やせばアクセスが増えると思い、手当たり次第に幅広いテーマで記事を投稿してしまうケースがあります。確かに記事数が増えると、サイトが充実しているように見えるかもしれません。しかし、キーワード選定をまったく意識せずに書きすぎると、「何の専門サイトなのか」が検索エンジンやユーザーに伝わりにくくなり、結果的にSEO面で不利になることがあります。
たとえば、飲食店を営む中小企業がブログを通じて自社の食材や調理法のノウハウを発信しているなら、読者は「ここでは食に関する専門的な情報が得られるはず」と期待するでしょう。ところが、突然テクノロジー関連の雑多な記事が増えたり、全く違う趣味の話題が中心となったりすれば、せっかく形成し始めた専門性のイメージが崩れやすくなります。検索エンジンは「サイト全体として何を提供したいのか」も判断材料にしており、テーマが散漫だと評価を落とす可能性があります。
本記事では、キーワードの専門性を維持しながら、なおかつ適度に幅をもたせて更新していくためのポイントや手順を解説します。何でも書けば良いというわけではない、バランスを保ったコンテンツ戦略を理解いただくきっかけになれば幸いです。
キーワードと専門性の重要性
検索エンジンはページ単位のみならず、サイト全体としての専門性や信頼性も評価します。特定の分野に対して、どれだけ深い知見や有用な情報を提供しているかは非常に重要です。たとえば「イタリアンレストランの特徴的なメニュー」に関する記事を複数書いているサイトは、イタリアンに関する専門的な情報源として評価を得やすくなります。
一方で、特に関連性がないジャンルの記事を大量に追加すると、サイトの専門性が薄まり、「結局何について知りたい人向けのサイトなのか」が不透明になります。その結果、検索エンジン側も評価を定めにくくなり、検索順位で苦戦するリスクが高まるのです。
たとえ複数の事業や多角的な情報を発信する必要がある場合でも、各ジャンルごとにきちんとカテゴリーやキーワードを設定して整理することが大切です。むしろ関連分野であれば、専門性を補完し合う形で相乗効果を生むことさえあります。
多岐にわたる記事を扱うメリットとデメリット
サイトテーマを限定せずに幅広い内容を扱う方法は、デメリットばかりではありません。中小企業が取り扱う商材やサービスの幅が広いケースも多く、複数のキーワードをカバーすることで多様な検索ニーズに応えられるのはメリットです。
しかし、行き過ぎると「何でも屋」になり、どれを強みとするのかが見えなくなってしまいます。企業がSEO対策としてブログを活用する場合は、基本となる事業領域を軸に据えて、関連キーワードを展開していく方が長期的には評価を得やすいのです。以下にメリットとデメリットをわかりやすくまとめた表を示します。
| 観点 | 幅広いジャンルを扱うメリット | 幅広いジャンルを扱うデメリット |
|---|---|---|
| ユーザ層の拡大 | 多方面からのアクセス流入が見込める | 興味が分散し、コアユーザーの定着が難しくなる |
| 専門性のアピール | 幅広い知識やサービスの豊富さをアピールできる | 専門性がブレて検索エンジン評価が下がる可能性 |
| 運営リソース | 多彩なネタで記事を書きやすい | 管理やカテゴリー分けが煩雑になり、運営負担が増す |
| ブランディング | 企業の柔軟性や多様性を印象づけやすい | ブランドイメージがぼやけ、方向性が定まらない危険性 |
デメリットを回避するためには、「幅広い内容を扱うにしても全体の方向性を揃える」「記事テーマを分類し、関連分野ごとに濃い情報を提供する」などの工夫が求められます。
ブログテーマの整理方法
ブログをただやみくもに書き続けるのではなく、一度運営方針を整理してみることが大切です。次のようなフローでテーマを洗い出し、絞り込みを行うとよいでしょう。
- ビジネスのコア領域を明確化
まずは自社の事業ドメインや強みを再確認し、どの領域について最も発信する価値があるかを決める。 - 関連する周辺キーワードの抽出
メインとなるビジネスと関連性の高いキーワードをリスト化する。ここでは市場のニーズや顧客が抱える疑問を想定しながら洗い出すと効果的。 - 記事の優先順位を設定
ビジネス貢献度が高い順、ユーザーのニーズが高い順などを考慮してテーマを並び替える。 - カテゴリーやタグを整理
メインテーマ・サブテーマを軸に、サイト上でのカテゴリー分けを検討する。タグは補足的な要素や横断的なキーワードに使う。
下のテーブルは、ブログのテーマ整理手順を例示したものです。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. コア領域定義 | 自社のメイン事業や強みを再確認する | 企業理念やサービス概要などの基本情報も振り返る |
| 2. 周辺キーワード | メイン事業と関連の深いキーワードを抽出 | 顧客が抱える悩みやよくある質問などをヒントにする |
| 3. 優先順位設定 | 洗い出したキーワードを重要度順に並べる | 何を最優先で発信すべきか、運営方針と照合する |
| 4. カテゴリー分割 | メイン、サブ、補足のように大枠を決める | 記事が増えても迷子にならない階層を意識する |
| 5. 記事化 | 一覧からテーマを取り出し、記事を作成する | キーワードの重複や内容の偏りに注意しつつ計画的に投稿する |
テーマが明確になると、単なる投稿数の増加だけでなく、読者や検索エンジン双方に「このサイトは○○分野の情報源」と認識してもらいやすくなります。
適切なキーワード設計と優先度の付け方
キーワードには大きく分けて「ビッグキーワード」「ミドルキーワード」「ロングテールキーワード」があります。ビッグキーワードは検索ボリュームが大きいぶん競合が多く、初心者がいきなり攻略するには難易度が高い場合があります。それに対してミドルやロングテールキーワードは、比較的競合が少なく、顧客の具体的なニーズに応えやすい特徴があります。
「キーワードを無視して書きすぎるとSEOに悪影響」というケースの背景には、ブログ運営者が自社に関連の薄いビッグキーワードを無闇に狙おうとしている事例や、そもそもどのキーワードで評価されたいのかを整理していない事例が含まれます。しっかり優先順位を付けて地道に実績を積み上げることが重要です。以下のテーブルでは、キーワードごとの特徴と向き合い方をまとめました。
| キーワード種別 | 特徴 | 運用ポイント |
|---|---|---|
| ビッグキーワード | 検索数が多いが競合サイトが非常に強い | いきなり狙うよりも中長期的に対策し、専門性を深める方が安全 |
| ミドルキーワード | 検索数はそこそこあるが競合がビッグより少ない | 少し工夫すれば上位表示のチャンスがあり、狙いやすい |
| ロングテールキーワード | 検索数は少ないが具体的で成約率が高い傾向 | 自社ならではの切り口で情報提供し、徐々に評価を高めていく |
このようにキーワードの設計と優先度を決めることで、単に記事数を増やすのではなく、検索エンジンとユーザーが求める内容に的確に応えることができます。
具体例:ブログ運営の失敗と成功のパターン
ここでは実際にありがちな例を挙げてみます。
失敗パターン
- テーマが日替わりでバラバラ
ある日はスポーツ、次の日はビジネスマナー、さらに次は旅行記など、統一性が全くない。投稿数はそこそこあっても、検索エンジンからは専門性がないと見なされる。 - キーワード設定が曖昧
キーワードをほとんど気にせず「日記のように書いている」だけ。検索需要のある用語を入れたり、カテゴリを適切に設定したりといったSEOの基本が抜けている。 - 内部リンクが機能していない
関連性のある記事同士を結ぶ導線がなく、サイト内を回遊しにくい。結果的に「このサイトは何が強みなのか」を読み手が理解しづらい。
成功パターン
- コアテーマを明確化し、周辺トピックも関連性を持たせる
たとえば「飲食店経営ノウハウ」というメインテーマの下に、「レシピ紹介」「キッチン設備」「衛生管理」「集客アイデア」など、互いに関連度の高い記事を展開する。 - 検索意図を想定したキーワード設計
「読者はこのキーワードで検索するとき、どんな答えを欲しているのか」をしっかりと考え、その欲しい情報にフォーカスした記事を作る。 - カテゴリーやタグを適切に使い、回遊性を高める
関連記事への内部リンクを整備し、読者が深堀りしやすい仕組みを用意する。
テーブルで見るテーマ選定の手順例
前述したフローをもう少し具体化し、テーマ選定の大まかなステップを下表に示します。すでにブログを運営している場合は、既存記事を整理・再分類する際のチェックリストとしても活用できます。
| 大項目 | 中項目 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 1. 現状分析 | 既存記事の洗い出し | 記事数、カテゴリー、タグ、重複テーマの有無などを把握する |
| アクセス解析の確認 | どの記事がどんなキーワードでアクセスされているか把握する | |
| 2. コアテーマ再定義 | ビジネス目標との連動 | 自社ビジネスの重点ポイントとブログの方向性が一致しているか |
| 主要ターゲットのニーズ把握 | ターゲット読者が本当に知りたい内容を洗い出しているか | |
| 3. 具体キーワード選定 | キーワード候補のリスト化 | ビッグ、ミドル、ロングテールに分けて抽出し、整理する |
| 優先度・競合分析 | 競合状況を踏まえ、どこから攻略すべきかを決定する | |
| 4. カテゴリー再構成 | 読者目線での使いやすさ | 同じカテゴリー内に関連性のある記事がまとまっているか |
| サイト内回遊の導線 | 関連記事にスムーズにアクセスできるリンク構造になっているか | |
| 5. 改善施策実行・検証 | 記事のブラッシュアップ | 古い情報の更新、見出しや本文のリライトで検索意図への最適化を行う |
| 定期的な分析と改善 | アクセス動向を定期的に追い、修正点を洗い出して改善を続ける |
テーブルで見るコンテンツの質を高めるコツ
テーマ選定だけでなく、「どう書くか」も重要です。以下のポイントを意識してコンテンツの質を向上させましょう。
- 適切な見出し構成:H2, H3などの見出しを設けて論点を明確にする
- 読みやすい文章:専門用語ばかりにならないよう平易な言葉を心がける
- 具体例やエピソードの活用:数字や実例でわかりやすく補足する
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 見出し構成 | 各セクションで何を伝えるかが明確になるように、H2やH3を設計する |
| 文量バランス | 長すぎる文章は分割、箇条書きでポイントをまとめて読みやすくする |
| 具体例やエピソード | 抽象的な概念のみでなく、実際のケーススタディや身近な例を交えて説明する |
| ユーザー視点での解説 | 自社目線だけでなく、「読者が知りたいこと」を優先して書く |
| タイトルやサマリーでの要約 | 最初に結論や要旨を伝え、深掘りを本文で行う |
テーブルで見るキーワードの優先度判断
書きたいキーワードと書くべきキーワードが一致しない場合もあります。以下の視点でキーワードを優先度付けしてみると、自然とブログのテーマ設計が整理しやすくなります。
| 優先度 | 判断基準 | 注目ポイント |
|---|---|---|
| 高 | 自社ビジネスに直結し、検索意図が明確なもの | すぐに読者の疑問や課題を解決できる具体的情報を提供できるか |
| 中 | 周辺トピックであり、関連度は高いが競合がそこそこ強いもの | 時間をかけて専門性を高めていくことで効果が期待できる |
| 低 | 関連は薄いがニッチな需要がある、または試験的に書いてみる余地がある | 大幅なサイトテーマとの乖離を招かない範囲で扱う |
まとめ
キーワードを全く気にせず雑多にブログを量産することは、たしかに短期的には記事数を増やせるかもしれません。しかし、サイト全体として検索エンジンの評価を獲得したり、ユーザーに専門的で信頼感のある印象を与えたりするためには、ある程度の統一感が必要です。ビジネスのコア領域を軸にして、関連キーワードをうまく整理し、それぞれに深い情報を提供することで、「このサイトならでは」の価値を出すことができます。
加えて、記事内の見出しや具体例の使い方、カテゴリー設定などの工夫で、読者が自分の知りたい情報に辿り着きやすい導線を作りましょう。不要にテーマを拡散させるよりも、軸をしっかり定めながら少しずつ広げる方が、最終的により多くのユーザーの期待に応えられるサイトへと成長するはずです。






