Blog お役立ちブログ
狙いすぎないSEOで顧客の本音に寄り添う記事を作るポイント
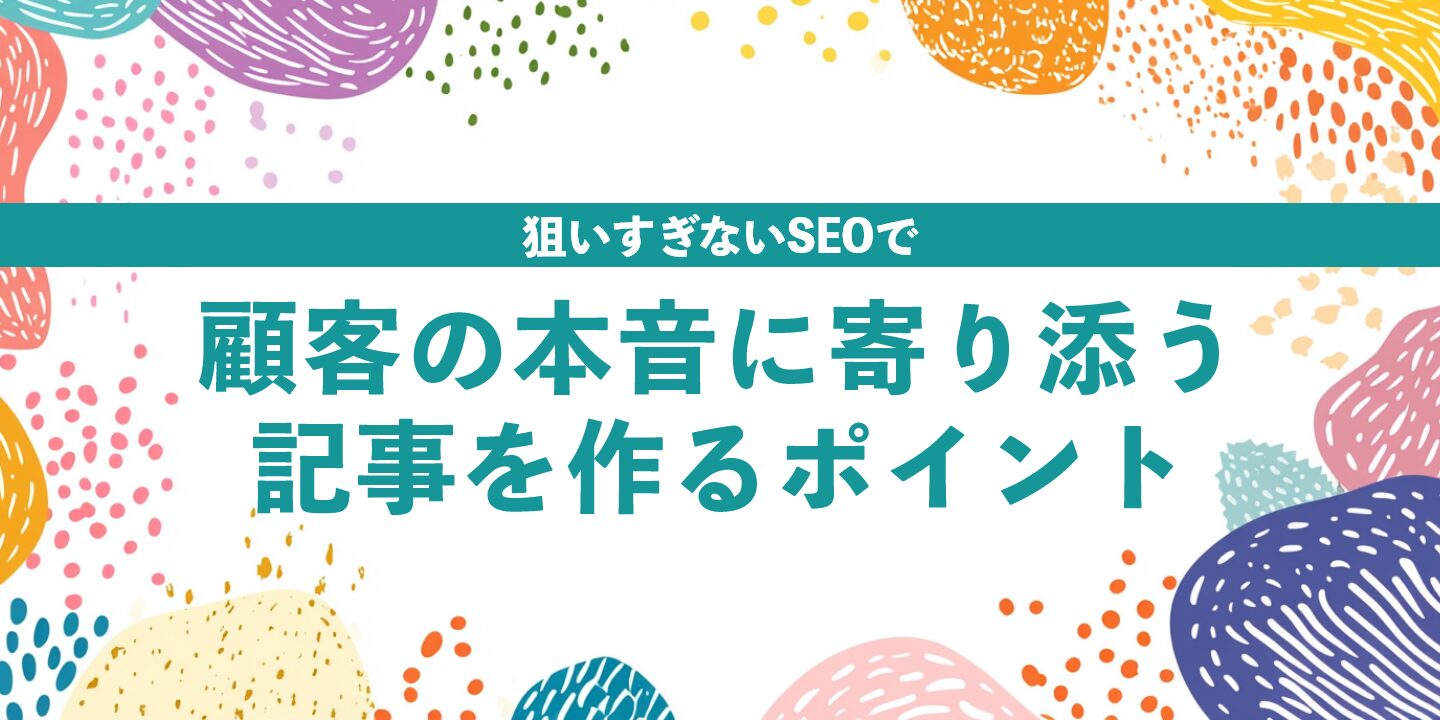
はじめに
多くの中小企業が検索エンジンでの上位表示を目指してさまざまな対策を行っています。しかし、過度にキーワードを詰め込んだり、不自然な文章になってしまうことで、読み手の満足度や信頼感を損なうリスクが高まります。検索エンジン対策をしながらも、記事を実際に読む顧客の本音に寄り添い、自然な流れで情報を提供していくことが、長期的なファンづくりには不可欠です。
本記事では、「狙いすぎないSEO」という考え方をベースに、読み手の悩み・疑問の解消を第一に考えつつ、最適な形で検索エンジンにアプローチするためのポイントを解説します。具体的な記事構成や、キーワードの選定・配置方法、ユーザー視点に立ったコンテンツづくりの実践策などを詳しく紹介します。最後まで読むことで、顧客の本音にしっかり寄り添った記事を作るためのヒントを得られるはずです。
狙いすぎないSEOとは何か
「狙いすぎないSEO」とは、あまりにも検索エンジンへの最適化に傾きすぎず、記事を読む人(顧客)の体験や納得感を重視した取り組みです。もちろん、検索エンジンでの露出を無視するわけではありませんが、いわゆる「キーワードの詰め込み」や過度なテクニック依存を避け、自然な文章や構成を整えていく手法を指します。結局のところ、検索エンジンが評価するのは「ユーザーが満足できるコンテンツ」であり、読む側にとって価値ある記事を提供することこそが本質といえます。
- キーワード過多による不自然さを避ける
読み手としては、知りたい情報が得られることが第一であり、「キーワードが多用されているか」は重視しません。むしろ、不自然な表現や文章が散見されると離脱率が高まってしまうため、最適なバランスを保つのが重要です。 - 長期的なファンづくり
その場限りで検索エンジンに上位表示されたとしても、中身が薄かったり読みにくかったりすれば、読者が継続的に記事を読むことはありません。顧客の本音に寄り添い、信頼を積み重ねるような記事を継続的に提供することが、結果的にSEOにも好影響を及ぼします。
顧客の本音に寄り添う記事を作るメリット
検索エンジン対策をしつつも、「顧客の本音」をしっかりくみ取る記事を書くことには、具体的にどんなメリットがあるのでしょうか。ここでは、いくつかの代表的な利点をご紹介します。
- ブランドイメージの向上
読み手の疑問や不安にストレートに応えることで、親近感や安心感が生まれやすくなります。いくら検索エンジン対策を万全にしても、読者に響かない内容では「この会社は自分たちのことを考えていない」と感じられてしまう可能性があります。顧客の目線を大事にする文章は、企業姿勢の好印象に直結します。 - 検索エンジンからの評価向上
検索エンジンは、読者がどの程度満足するかをアルゴリズムの軸に据えています。読者が記事の内容に満足すれば、滞在時間や回遊率などの指標も高まりやすく、それは検索結果の評価につながりやすいものです。 - リピート率や口コミが増えやすい
「悩みが解決した」「読みやすくて役立った」と感じた読者は、また同じサイトを訪れてくれたり、知人に紹介してくれたりします。結果的に長期的なアクセス増につながり、自社のファンを獲得する大きなきっかけにもなります。 - 過度な対策コストの削減
不自然なキーワードの詰め込みや、テクニックに走った対策には労力と時間がかかります。それらを削減し、本質的に読み手が求める情報提供に集中することで、結果的に運用もスムーズになる可能性が高まります。
キーワード選定の考え方と実践方法
ここからは、具体的にどのようにキーワードを選び、「狙いすぎないSEO」を実践するかを考えていきます。顧客の本音に寄り添うためには、まず「どんな言葉で情報を探しているのか」を把握する必要があります。
顧客目線のキーワード抽出
よくあるのは、専門的な用語ばかりで記事を固めてしまい、読者が実際に検索しない言葉を盛り込んでしまうケースです。自分たちが使う業界用語だけでなく、素人や初心者がどんな表現で悩みを検索するのかを意識してみましょう。
- FAQの活用
既存の顧客や問い合わせで多く寄せられる質問を洗い出し、それをキーワード候補としてピックアップする方法です。実際に使われている言葉であるため、読者にも響きやすいのが特徴です。 - 顧客の行動や心理を想像する
「何に困っていて、どんな具体的なワードで情報を探すか」を考えることで、より実情に即したキーワードを抽出できます。思いつかない場合は、身近な人や取引先などにヒアリングしてみるのも有効です。
キーワードの優先度付け
候補キーワードを得たら、次は優先度をつける作業に移ります。優先度とは、「自社がアピールしたい内容」と「顧客が求めている内容」が交わる部分を探し、その中で適度な検索ボリュームと競合状況を踏まえた上で決定します。
以下のような項目で比較・検討するとわかりやすいでしょう。
| キーワード候補 | 自社との関連度 | 想定顧客の検索意図 | 競合状況の目安 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| A | 高い / 中 / 低 | 詳しい情報を欲する / なんとなく知りたい など | 高 / 中 / 低 | 最優先 / 次点 / 保留 |
| B | 高い / 中 / 低 | 詳しい情報を欲する / なんとなく知りたい など | 高 / 中 / 低 | 最優先 / 次点 / 保留 |
| C | 高い / 中 / 低 | 詳しい情報を欲する / なんとなく知りたい など | 高 / 中 / 低 | 最優先 / 次点 / 保留 |
上記のように、複数候補を目視しながら検討することで、狙いすぎないSEOの観点でも無理なく収まるキーワードを抽出しやすくなります。たとえ検索ボリュームの大きいキーワードであっても、自社のコンテンツと全くかみ合わなければ読者の満足度は得られず、離脱を招きやすいので注意しましょう。
記事内でのキーワード配置と自然な文章づくり
キーワードを選定したら、それらをどのように記事に落とし込むかが次の課題です。ここでは、キーワード配置の基本ルールと、自然な文章づくりのポイントを見ていきましょう。
記事全体の流れとキーワード
狙いすぎないSEOでは、むやみにキーワードを並べるのではなく「読者が最も欲しがっている情報の流れ」に合わせて、適切な箇所にキーワードを盛り込むことが重要です。以下の例のように、「見出し」「冒頭」「本論部分の小見出し周辺」「まとめ」など、読者の視線が集まりやすい部分で自然に使っていきましょう。
| 配置箇所 | 具体的なポイント |
|---|---|
| タイトルやH1見出し | 最も重要視される場所。過度に詰め込まず、1~2つ程度で十分。 |
| H2・H3などの見出し | 見出し自体にキーワードを使うことで、読者が求める情報を素早く把握できる。 |
| 本文の冒頭部分 | 記事全体の概要や狙いを簡潔に示す。キーワードを自然に含めると内容が伝わりやすい。 |
| 本文中の小見出し周辺 | 説明したい内容に合わせて、キーワードを強調する。流れを壊さない範囲で取り入れる。 |
| まとめ部分 | 記事の締めくくりとして要点を再確認。再度キーワードを自然に入れると効果的。 |
もちろん、読者に分かりにくい量の繰り返しは逆効果になるため、あくまで自然に文章を組み立てることがポイントです。
自然な文章を書くための工夫
キーワードを活かしつつも、不自然さを回避するには以下のような工夫が考えられます。
- 言い換え表現を活用する
同じ意味の言葉を繰り返すよりも、関連する言い換えや類義語を使ったほうが読みやすくなります。読者に正確な情報を届けるためにも、使い分けを意識しましょう。 - 余計な装飾をしすぎない
太字やマーカーを使いすぎると、返って読み手の集中を削いでしまいます。必要な部分をさりげなく強調する程度にとどめるのがベターです。 - 文章の繋ぎを自然に
「キーワードを使いたいからといって、文章の途中で突然出す」のは避けます。説明の流れに沿った形で、読者が疑問に思うタイミングなどを狙って入れるとスムーズです。
具体的な記事構成や実例
次に、狙いすぎないSEOを意識した記事構成のイメージを示します。ここでは、仮に「ユーザーが抱える課題を解決する方法」をメインテーマとする記事を想定します。
記事構成の一例
- 導入(読者の悩みを明確化)
- どのような悩みを解決するのか
- 記事全体の大まかな流れ
- 問題点の深堀り
- 具体的にどんな困りごとが多いのか
- その原因は何か
- 解決策の提示
- ステップごとに解説
- メリット・デメリットを同時に示す
- まとめ・次のステップ
- 要点の振り返り
- 読者が明日から実践できる簡単な行動例
- 記事全体の締めくくり
これを踏まえた具体的な例を、次の表でまとめます。
| セクション | 目的 | キーワード活用例 | 文章のトーン |
|---|---|---|---|
| 導入 | 悩みの提示と記事内容の概要を示す | 「○○に困っている方へ」「解決策として○○を提案」など | 読者に呼びかけるようなフランクな調子 |
| 問題点の深堀り | 読者に「共感」「自分ごと化」させる | 「よくある問題」「本音として○○がわからない」など | 少し掘り下げながら、丁寧に説明 |
| 解決策の提示 | ステップ形式で解説し、取り組む意義を伝える | 「○○の手順」「実践すると○○を期待できる」など | ポジティブかつ分かりやすい言い回し |
| まとめ・次の行動 | 全体をまとめ、行動を具体化して終わる | 「要点は○○」「最終的には○○が重要」など | シンプルに結論を示し、読者を応援するような口調 |
ここで示した構成はあくまで一例ですが、特に「問題提起→解決策→まとめ」の流れを意識することで、読者が理解しやすい記事づくりが実現しやすくなります。
エピソードや具体例を挟む重要性
人は抽象的な説明だけでなく、現実味のある体験談やエピソードを好む傾向があります。例えば、「実際にこういうケースがあった」「こう取り組んだら効果が上がった」という話を入れることで、読者は自分の状況と照らし合わせて理解しやすくなります。とくに中小企業の場合、自社で経験したエピソードを記事に活かせば、より「本音」に寄り添う内容に仕上げやすいでしょう。
継続的な記事運用と改善ポイント
一度記事を書いて終わりではなく、読者や顧客の反応を踏まえながら、コンテンツを継続的に磨き上げていくことも重要です。
運用フローの例
| 運用ステップ | 具体的アクション | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 記事の初期公開 | 選定したキーワードと構成をもとに執筆し、公開 | 最低限の装飾と、分かりやすい文章を心がける |
| 2. 読者の反応確認 | アクセス解析ツールなどを使用し、滞在時間や離脱率を把握 | 反応が悪い箇所は、記事の流れや文言に問題がないかチェック |
| 3. 記事の加筆・修正 | コメントや問い合わせなどのフィードバックを反映し、内容を強化 | 読者の疑問が多かった部分をより詳しく書く |
| 4. 再度の公開・拡散 | 修正した記事を改めて公開し、他の関連ページなどから誘導 | 新たにキーワードを追加する場合は文章の自然さに注意 |
このように、記事公開後にも継続的に内容を見直すことで、読者のニーズに即した最新の情報を提供できます。特に季節や時期によって変化する需要があるテーマであれば、定期的にアップデートしておくと良いでしょう。
PDCAサイクルの活用
継続的に記事を改善していくには、いわゆるPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)が有効です。記事制作を「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)」の流れで回し、改善のたびにSEOの観点と顧客視点の両方から検証し続けることで、より質の高いコンテンツに仕上がっていきます。
- Plan(計画): テーマ設定、キーワード選定、記事構成の設計
- Do(実行): 実際に記事を書き、公開する
- Check(評価): アクセス解析やフィードバックを確認し、課題を把握する
- Action(改善): 修正ポイントを明確化し、内容をアップデートする
このプロセスを繰り返すことで、顧客の本音に寄り添いながらSEO効果も逃さない記事へと成長させることができます。
まとめ
「狙いすぎないSEO」とは、ただやみくもにキーワードを詰め込むのではなく、あくまで顧客の本音を第一に考えるアプローチです。読み手が本当に求めている情報を丁寧に提供し、それを検索エンジン側にも適切に伝わる形で整えていくことで、長期的にファンを増やしながら検索エンジンでの評価も高めることができます。
- キーワード選定は顧客目線で
専門用語だけでなく、実際に顧客が検索しそうな言葉を考える。 - 自然な配置と文章づくり
過度なキーワード使用は避け、読者が読みやすい流れを大事にする。 - 具体的な記事構成やエピソードでわかりやすく
抽象的な説明にとどまらず、実例やエピソードを挟むことで説得力を高める。 - 継続的な改善を忘れない
公開した記事を定期的に見直し、読者の反応を反映してブラッシュアップする。
このようなポイントを押さえながら記事を運用していけば、検索エンジンの評価だけに縛られず、読み手との信頼関係を構築しながら成果を上げることができるでしょう。企業が発信する情報の目的はあくまで「読者にとっての価値提供」です。それを忘れずに記事を育てていけば、自然と検索順位も後からついてくるはずです。






