Blog お役立ちブログ
検索順位が下がった理由は何が悪いの?原因と改善策
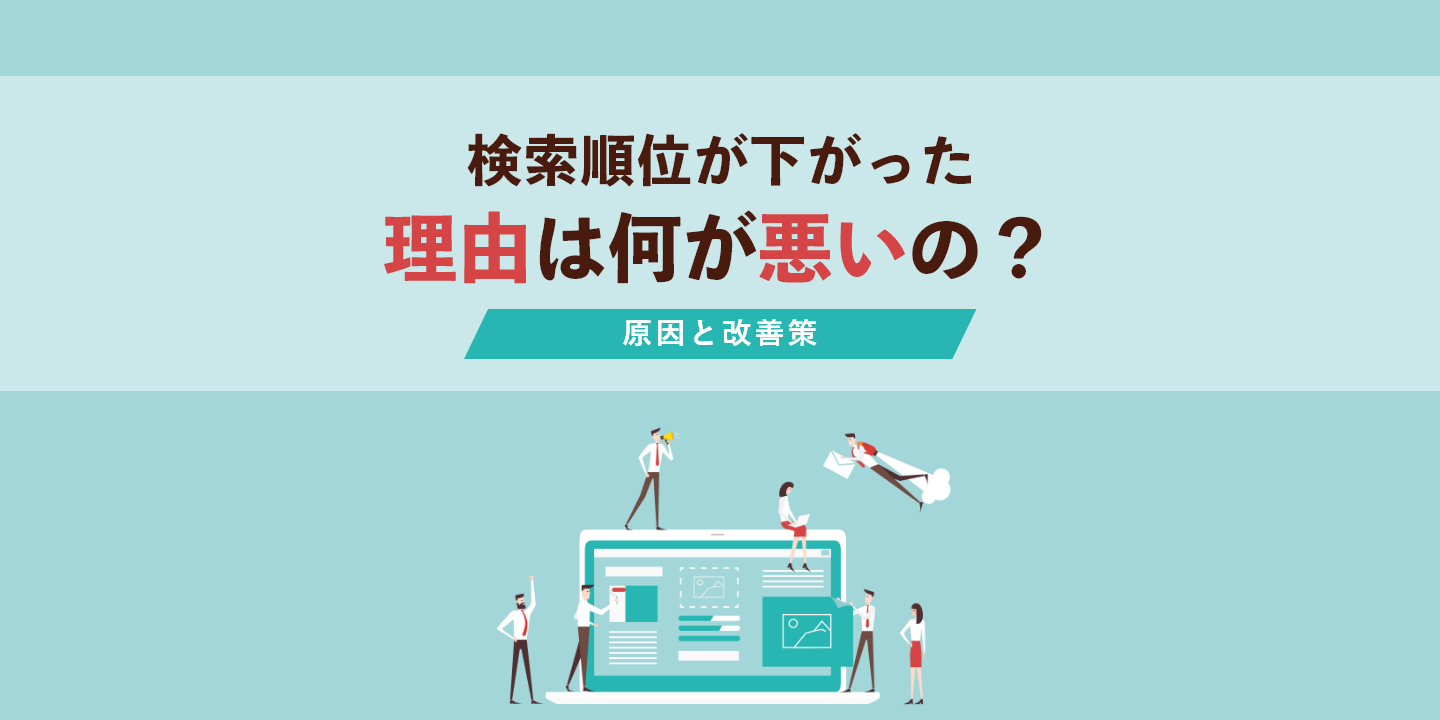
はじめに
中小企業が運営するWebサイトやネットショップにとって、検索エンジンからの集客は重要な売上源のひとつです。しかし、ある日突然「検索順位が下がった」という事態に直面すると、売上に影響が出始めるだけでなく、何が原因なのか不安になるものです。「検索順位 下がった 理由 何が悪いの」と疑問を抱えていても、具体的に何を改善すればよいのか判断できずに戸惑っている方も少なくありません。
本記事では、検索順位が下がる主な要因とその背景をわかりやすく解説し、さらに実践しやすい改善策や注意点をまとめてご紹介します。サイトを運営する店主やオーナー、自分たちでSEOを取り組む担当者など、誰もが理解しやすいよう専門知識をかみ砕きながら説明していきます。ぜひ最後までお読みいただき、今のサイト運営に役立ててください。
検索順位が下がる主な要因
まずは、検索順位が下がる原因として考えられる一般的な要因を概観してみましょう。大きく分けると、内部要因と外部要因に分類されます。
- コンテンツの質や量に問題がある(内部要因)
- 古い情報が放置されている
- 競合他社と比べて専門性や独自性が弱い
- 重複コンテンツが多い、または内容が薄い
- サイト構造や技術面での問題(内部要因)
- サイトの表示速度が遅い
- モバイル対応が不十分
- 内部リンクが整理されていない
- 被リンクや評判の低下(外部要因)
- 質の低いリンクが増えてしまった
- 以前はあった良質な被リンクが削除・改変されてしまった
- SNSなどでの評価や話題性が低下
- 検索エンジンのアルゴリズム更新(外部要因)
- アルゴリズムの変化で評価基準が変わった
- 適切だった対策が古くなったり、ペナルティ対象になる場合がある
- 競合サイトの強化(外部要因)
- 同じキーワード領域のサイトが急速にクオリティを上げてきた
- 新規参入者や大手サイトが強いコンテンツを投入してきた
これらの要因が複合的に絡み合って順位低下を招くケースが多々あります。どこか1つが悪いというより、「複数の小さな課題の積み重ね」によって検索順位が下がることも少なくありません。
内部要因と外部要因の具体例
順位低下の原因をより具体的に把握するために、内部要因と外部要因を整理した表を確認してみましょう。
| 分類 | 要因例 | 具体的な症状(例) |
|---|---|---|
| 内部要因 | – コンテンツの品質低下 – 重複コンテンツの増加 – サイト速度の低下 – モバイル対応不備 – 内部リンクの不整合 | – 古い情報で更新が滞り、検索者のニーズを満たせない – 似たような記事ばかりで目新しさがない – ページ表示に数秒以上かかり離脱率が上がる – スマホで見づらく離脱される – サイト内のリンク切れ多数 |
| 外部要因 | – 被リンクの質の変化 – 競合サイトの台頭 – アルゴリズムの更新 – SNS評価の低下 | – スパム的な被リンクが増えた or 良質リンクが失われた – 競合他社が専門性の高い記事を大量投入 – 新アルゴリズムでコンテンツ評価基準が変更 – SNSでのシェアや言及が減少 |
内部要因が大きいと判断される場合は、サイトの構造・コンテンツ品質を優先的に見直すことが重要です。一方で、外部要因の場合は、被リンクの質やSNS上の評価を正しく把握する、あるいは競合リサーチをしっかり行うなどのアプローチが必要になります。
検索エンジンの評価が下がる代表的なケース
検索エンジンの評価を下げてしまうケースとして、いくつか代表的な例を挙げます。
1. ユーザーのニーズに合わないコンテンツが多い
検索エンジンは「ユーザーの疑問や問題を解決するコンテンツ」を高く評価するといわれています。サイト運営者が一方的に発信したいことばかりを書き並べていても、実際にユーザーが求めている回答や専門性が欠けていれば順位は下がりやすくなります。
2. 更新頻度が極端に少ない、あるいは過度に多い
定期的な更新がないと「情報が古いサイト」とみなされる可能性があります。一方で、質を伴わない大量更新もスパム的と評価されかねません。読者が得られる価値を重視しながら適切なペースで更新を行うことが重要です。
3. 過剰なキーワード詰め込みや無意味なリンク
昔はキーワードを詰め込むことで検索エンジンが有利になった時代もありましたが、現在は不自然なキーワードの乱用はむしろペナルティ対象になる恐れがあります。さらに、無意味な内部リンクや不自然な外部リンクが多いと検索エンジンからの評価が落ちる要因になります。
4. モバイルフレンドリーでない
スマートフォンでの検索が主流となっている今、モバイルページの最適化は欠かせません。文字が小さすぎて読めない、ボタンが押しにくい、表示が遅いなどの問題はユーザーエクスペリエンスの観点で大きなマイナスになります。
5. ページ速度(表示速度)の問題
表示が遅いサイトはユーザーが離脱しやすく、結果的に検索エンジンに悪影響を与えます。特に競合他社が高速化を実施している状況で自社サイトだけが遅いと、順位が下がる要因のひとつになる可能性があります。
実践的な改善策・プロセス
では、具体的な改善策をどのように進めればいいのでしょうか。以下のようなプロセスを踏みながら、自社サイトの問題点を洗い出し、対策を講じるのが効果的です。
- サイト診断・アクセス解析の実施
まずは現状把握が必要です。どのページのアクセスが下がったのか、どのキーワードからの流入が減っているのか、サイト速度はどの程度なのか。アクセス解析ツールなどを活用して、客観的なデータを取得しましょう。 - 問題点の優先順位付け
問題点が複数見つかった場合、どれから手をつけるべきかを明確にします。たとえば、サイト速度が極端に遅いなら、それを最優先で改善する。モバイル対応が不十分なら、そこから取り掛かる、といった具合です。 - コンテンツリニューアルや追加
ユーザーにとって魅力的で価値の高いコンテンツを提供し続けることが重要です。必要に応じて古い記事をリライトしたり、新しい情報を追加したりして、常に最新状態を保ちましょう。 - 内部リンクやサイト構造の見直し
関連性のある記事やカテゴリ同士をわかりやすくリンクでつなぎ、検索エンジンとユーザー双方に有益な構造を整備します。また、トップページから重要なコンテンツへ適切に誘導できるかも確認しましょう。 - 被リンク・SNS評価の改善
良質な被リンクやSNSでのシェアは、コンテンツが支持されている指標として検索エンジンにアピールできます。コンテンツを整えたうえで、関連業界や知り合い、顧客などから自然な形でシェア・言及される仕組みを検討してみましょう。 - 継続的なモニタリング
一度対策を施しただけで安心せず、定期的なチェックを続けることが大切です。アルゴリズムの変動や競合状況の変化などに対応するためにも、継続的な改善サイクルをまわしていきましょう。
改善策比較表
下記の表では、代表的な改善策と「対応難易度」「効果が期待できるスピード」「主な対象領域」をまとめています。自社の状況にあわせて、着手しやすいものから優先的に取り組むと良いでしょう。
| 改善策 | 対応難易度(目安) | 効果のスピード | 主な対象領域 |
|---|---|---|---|
| サイト速度改善 | 中~高 | 中~やや速め | ホスティング環境、画像最適化など |
| モバイル対応強化 | 中 | 中 | レスポンシブデザイン |
| コンテンツのリライト・拡充 | 中 | 中~長期 | ブログ記事や商品紹介ページなど |
| 内部リンク構造最適化 | 低~中 | 中 | サイト全体の情報設計 |
| 被リンク強化(自然獲得) | 高 | 中~長期 | 他サイトやSNS上の露出 |
難易度が高いものは、専門家に外注する選択肢もありますが、予算やリソースに限りがある中小企業の場合、まずは自分たちで着手可能な部分から少しずつ改善を進めることが多いです。
具体的な注意点とポイント
検索順位の回復を目指す際、以下のポイントを押さえておくとスムーズに取り組めます。
1. 焦りすぎない
検索エンジンの評価回復には時間がかかる場合が多いです。特に大幅に順位が下がった場合、テコ入れをしてもすぐには成果が出にくい可能性があります。短期間ですべてを改善しようと無理をすると、かえって不自然な対策をしてしまい、さらに評価を落とすリスクもあるため注意が必要です。
2. ペナルティの有無を確認する
もし過去に過剰なキーワード詰め込みや質の低い被リンクを集める行為をしていた場合、検索エンジンからペナルティを受けている可能性があります。ペナルティの場合は通常より対応が難しく、長期戦になりやすいです。サーチコンソールなどのツールを活用して警告の有無をチェックしましょう。
3. 競合サイトの研究を行う
順位を奪われている原因が、競合サイトの質の向上にある場合は、まず競合を研究することが大切です。以下のような視点でチェックすると、自社サイトのどこを強化すべきか見えてきます。
- 競合サイトのコンテンツボリューム、切り口
- デザインやユーザビリティ
- SNSや外部サイトからの評価・リンク状況
また、競合がどんなキーワードで上位をとっているのかを確認することで、自分たちが攻めるキーワードを見直す材料にもなります。
4. 定期的なサイトメンテナンスを怠らない
コンテンツの見直しやリンク切れの修正、サイト速度の検証などのメンテナンス作業は、日々の運用のなかでつい後回しにされがちです。ですが、継続的にメンテナンスをしているサイトほど検索エンジンの評価も安定しやすくなります。大規模に修正する時間がない場合でも、小さな修正や更新を定期的に積み重ねていくことで、長期的な順位維持につながりやすくなります。
手順表:順位低下から回復までの流れ
下記に、検索順位が下がった際に取り組むべき手順の例をまとめました。自社の状況に合わせて必要なステップを柔軟に追加・省略してください。
| 手順 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 現状把握・アクセス解析 | どのキーワード・ページが下がったかを明確にする |
| 2 | 原因調査 | 内部要因・外部要因をリスト化 |
| 3 | 対策内容の優先順位決め | 早期改善が見込める部分から着手 |
| 4 | 改善策の実施 | サイト速度やモバイル対応などから取り組む |
| 5 | コンテンツリライト・追加 | キーワードを再確認し、ユーザー視点を重視 |
| 6 | 被リンク対策やSNS連動 | 自然なリンク獲得・SNSシェアを促す |
| 7 | 効果測定と次のサイクルへ | 改善結果を計測し、新たな課題を洗い出す |
上記の流れを何度も回しながら、問題点を少しずつ解決していくのが基本的なスタンスです。一度で全てを直しきることは難しいため、焦らず継続的にチェックし続けることが大切になります。
エピソード:実際の小さな成功体験
たとえば、ある中小企業が運営するサイトで長年手を入れていなかった商品紹介ページが検索順位を大きく落としていた事例があります。サイトの管理者は「以前は上位にいたし、商品情報はあまり変わっていないから大丈夫」と思い込み、更新や改善を怠っていました。
しかし、実際に検索エンジンのアルゴリズムが変わり、「より詳しい商品レビューや比較情報が掲載されているサイト」が上位表示されるようになり、競合他社に順位を奪われていたのです。そこで、以下のような対策を行った結果、数ヶ月後には順位とアクセスが回復傾向となりました。
- 商品の特徴や利用シーンをわかりやすくまとめたコンテンツ追加
- 過剰な装飾を抑え、モバイルでも見やすいデザインに変更
- 商品ごとにユーザーからのQ&Aを掲載して具体的なニーズに応える
- ページ速度を改善し、離脱率を低減
このように、昔はよかったものが時代の流れと共に評価を落としているケースは多々あります。「今の検索エンジンが求めている価値提供」を意識して内容を見直すことで、順位下降を食い止めたり、再度上位を狙う可能性を高められます。
まとめ
検索順位が下がった理由を「何が悪いのだろう?」と漠然と悩んでいても、実際には複数の要因が絡み合っていることがほとんどです。サイト内部の問題(コンテンツ品質やサイト速度など)から外部の要因(競合サイトの台頭や被リンクの質の変化、アルゴリズム更新など)まで、幅広い視点で調査し、優先順位をつけて改善を進めていくことが大切です。
特に中小企業の場合、リソースや予算が限られるケースも多いため、「まずは何からやるか」をはっきりさせることが成功への近道になります。アクセス解析や競合リサーチ、そして自社サイトのメンテナンスを継続的に行い、今の検索エンジンやユーザーにとって本当に価値のある情報を提供することで、順位の回復や安定を目指していきましょう。






