Blog お役立ちブログ
同時起業でいくつかのサイトを立ち上げるのは無謀?
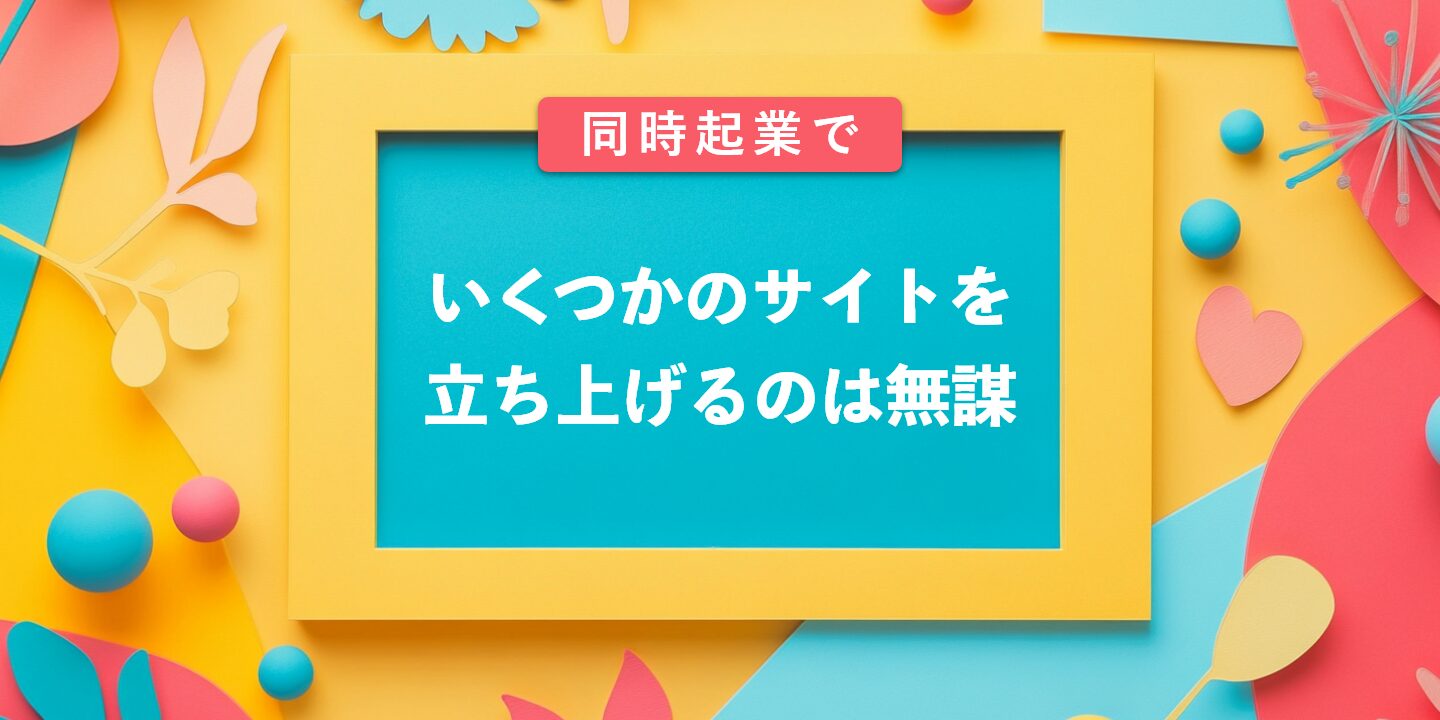
同時起業と複数サイト運営の背景
同時に複数の事業を始めるとき、それに伴って複数のサイトを一気に立ち上げようと考える経営者は少なくありません。新規ビジネスを複数展開し、さまざまなターゲットを狙いたい、あるいは業種・サービスごとに独立したブランディングを行いたいという意図があるでしょう。しかし「無謀」という言葉が出てくるほど、同時起業による複数サイトの運営はリスクや不安も大きいものです。
そもそも、中小企業にとって複数サイトを立ち上げるハードルは決して低くありません。制作コスト、運営工数、コンテンツ作成など、やるべきことが増えれば増えるほど、どこかで手が回らなくなる可能性が高くなります。とはいえ、正しい優先順位とリソース配分を行えば、複数のサイトを同時運営することで相乗効果を狙うことも可能です。本記事では、その具体的なポイントを分かりやすく解説します。
複数サイトを同時に立ち上げるメリットとデメリット
複数サイトを同時に立ち上げる行為には、当然メリットだけでなくデメリットも存在します。まずは両面を整理し、リスクとリターンを正しく理解しておきましょう。
メリット
- 異なるターゲット層へのアプローチ
- サービスや商品、ターゲットが異なる場合、サイトを分けることでコンテンツやデザイン、導線を最適化できる
- 各サイトで特化したテーマや特徴を打ち出しやすくなり、複数の顧客層を同時に獲得しやすい
- ブランド価値の明確化
- 事業ごとに別ブランドとして育てることで、認知度やイメージを確立しやすい
- 雑多な印象を避け、専門性や信頼感を高める
- リスク分散効果
- あるサイトが伸び悩んでも、別のサイトが成長軌道に乗る可能性がある
- サイトを運営していく中で得られるデータやノウハウを横展開しやすい
デメリット
- 運営コストの増大
- サイトを増やすほど、ドメイン管理費やデザイン費、サーバー費などもかさむ
- それぞれのサイト用に新たにコンテンツを用意する必要があり、制作・更新の手間が倍増する
- 運営リソースの分散
- 複数のサイトを同時に育てるとなると、人員や時間が分散し、どれも中途半端になるリスクがある
- コンテンツ品質が低下する可能性がある
- ブランディングの一貫性への懸念
- サイトごとにコンセプトを変えすぎると、企業全体としてのイメージ統一が難しくなる
- 顧客が混乱してしまうケースもある
下記の表は、複数のサイトを同時に運営する際に検討すべき主な要素をまとめたものです。事前にしっかり検討しておくことで、リスクを最小限に抑えることができます。
| 要素 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ターゲット | サイトごとに明確に異なるのか | 類似するターゲットなら統合した方が効率的な場合がある |
| ブランディング | 事業・サービスごとに差別化が必要か | 企業全体の一貫性を保ちつつサイト個別の個性を出すのは難易度が高い |
| 制作・更新コスト | デザイン、システム、コンテンツ制作などにかかる費用・時間 | 数が多いほど指数的にコスト増になるので事前に予算組みをする |
| 運営体制 | サイト別の担当者や運営ルールの設計、運用フロー | 運営者が混同しないような管理システムやフローづくりが重要 |
| スケジュール | 同時立ち上げ・運用スケジュールの策定 | リリース日や更新頻度など、重ならないように計画的に進める |
成功のカギ:リソース配分と運営体制
複数サイトを同時に立ち上げることは、言わば「リソースの綱引き」を常に意識する必要があります。限られた人員、時間、予算をどう配分するかが成功のカギです。ここではリソース配分と運営体制について考えてみましょう。
運営リソースの優先順位を決める
まず重要なのは、各サイトの事業価値や将来性を見極め、優先順位を設定することです。すべてを同時に最大化しようとすると、どれも中途半端に終わる可能性が高まります。以下のような運営リソース配分表を参考にして、サイトA・B・Cなどそれぞれへの人件費や時間をどう振り分けるのか検討しましょう。
| サイト | 目標(売上や認知度など) | 運営担当者 | 週あたり作業時間 | 予想コスト |
|---|---|---|---|---|
| Aサイト | 中核事業、売上の柱 | 1名(主担当) | 20時間 | 中 |
| Bサイト | 新規事業、将来性大 | 1名(副担当) | 10時間 | 大 |
| Cサイト | 補助的役割、情報発信向け | 兼任 | 5時間 | 小 |
こうした形で運営体制を可視化することで、「誰が、いつ、どこまで担当するのか」が分かりやすくなります。また、サイトごとに明確なKPI(例:問い合わせ件数、メルマガ登録数など)を設定し、進捗を管理することも大切です。
運営フローの標準化とツール活用
複数のサイトを同時に管理すると、更新作業や集客対策など多くのタスクが重複します。そこで可能な範囲で運営フローを標準化し、作業効率を高めることが必要です。
- 更新作業のルール化
例)各サイトは週に1回の定期的な更新日を設け、担当者が必ず最新情報をチェック・反映する - コンテンツ企画の共通テンプレート化
例)サイトごとに異なるジャンルでも、ライティングや構成の基本フォーマットを共通化しておけば作業時間を短縮できる - ツールの一元管理
例)複数のサイトを一つの管理ツール(CMS、アクセス解析ツールなど)で管理し、IDやパスワードの混乱を防ぐ
具体的な戦略立案のポイント
ここからは、実際に複数サイトを立ち上げる際の具体的な戦略立案について解説します。中小企業だからこそ、明確な戦略なしに複数のサイトを運営するのはリスクが大きいと言えます。
1. サイトごとの明確な目的設定
複数サイトを同時に運営する際、各サイトの目的があやふやだと方向性がぼやけます。「売上拡大」「ブランド認知」「新規顧客獲得」など、具体的かつ測定可能なゴールを設定することが大切です。たとえば、下記のようにサイトA・B・Cそれぞれ目的を明文化しておくと、運営時のぶれが減ります。
| サイト | 主な目的 | 評価指標 |
|---|---|---|
| Aサイト | 商品の販売 | 月間売上高、在庫回転率 |
| Bサイト | 新サービス告知 | 問い合わせ件数、契約数 |
| Cサイト | ブランド育成 | SNSシェア数、ファン数 |
2. コンテンツの作成計画
どんなにサイト数を増やしても、結局は「中身」が伴わなければ集客できません。コンテンツの品質を維持するためにも、下記のポイントを意識しましょう。
- ライターやデザイナーとの連携
内製化が難しい場合は、専門の人材を積極的に活用する。サイトによって得意なジャンルやトーンが違うライターをアサインしてもよい - 定期的なコンテンツ更新スケジュール
一度だけ大量にページを作って終わりではなく、継続的な更新によりユーザーや検索エンジンからの評価を高める - 検索エンジンの最適化(SEO対策)
基本的なキーワード設定やメタ情報の最適化、サイト速度の向上などはサイト数に関わらず必須
3. ブランドの一貫性と差別化
サイトを分ける理由の多くは「差別化」ですが、それぞれが別々の世界観を持ちすぎると、企業全体としての印象が希薄になります。以下の点に注意しながら差別化と一貫性を両立させましょう。
- ロゴやカラーリングの共通性
完全に同一にする必要はありませんが、「同じグループ」であると分かる程度の要素を取り入れる - コアメッセージの統一
企業が本質的に提供している価値や想いがぶれないように、どのサイトでも共通のコアメッセージを示す - デザインテンプレートの活用
大枠のレイアウトやフォントは似通ったものを用い、サイト間での移動がスムーズに感じられるよう工夫する
運営をスムーズにするための工夫と実例
同時に複数サイトを運営するには、実務面での工夫が欠かせません。実例として、ある企業が3サイト同時運営を行った際のポイントを紹介します。
- サイト別に役割を明確化
- コーポレートサイト(Aサイト):会社概要、採用情報、実績紹介など
- プロダクトサイト(Bサイト):製品やサービス詳細、資料請求フォームなど
- ブランドサイト(Cサイト):企業のストーリーや世界観を訴求するコンテンツ中心
- 運営担当を分割しつつも定例会議で共有
- 週1回程度、A・B・Cサイトの担当者で定例会議を行い、進捗や課題を共有
- 互いのノウハウや成功事例を吸収し合うことで、全体の品質を底上げする
- アクセス解析を活用して効果測定
- 各サイトのアクセス状況やコンバージョン数を可視化し、施策の有効性を比較
- 反応の鈍いサイトはその原因を分析し、改修プランを立てる
- コミュニケーションツールの一本化
- チャットツールやタスク管理システムを統一して、複数サイトの連絡を円滑にする
下記の表では、サイトA・B・Cそれぞれで行った主な施策と成果を簡潔にまとめています。
| サイト | 主な施策 | 成果(例) |
|---|---|---|
| A | コーポレートサイトのリニューアル(実績紹介) | 企業信頼度の向上、採用応募数が増加 |
| B | 製品サービス専用ランディングページの充実 | 資料請求が増加し、営業リード獲得数が拡大 |
| C | ブランドストーリー・ビジュアルの強化 | SNSでの拡散が増え、若年層への認知度が向上 |
表を使った比較・整理
前述のように、複数サイトを同時に展開するには、各サイトの目的や運用方針を可視化するのが不可欠です。以下の表は優先順位を見極める際の観点を整理したものです。どの観点をどれほど重視するかによって、どのサイトを最優先で育てるかが変わります。
| 観点 | 具体例 | 重視度 | コメント |
|---|---|---|---|
| 収益性 | 売上、利益貢献度など | 高・中・低 | 企業の短期的な収益源となるか、長期的に育てる必要があるかで判断 |
| ブランド価値 | 企業イメージや信頼度への影響 | 高・中・低 | 長い目で見て投資すべきかどうかを検討 |
| 市場規模 | ターゲット市場の大きさ | 高・中・低 | 市場規模が小さいと感じても、将来性があれば高評価を与える場合も |
| 運営負荷 | 更新頻度や人員投入コスト | 高・中・低 | 小規模なリソースで大きな成果が見込めるサイトを優先するのも一つの考え方 |
| 将来性 | 事業の拡張性や持続可能性 | 高・中・低 | 新たなサービスや製品ラインを展開できる見込みのサイトは投資する価値があるかもしれない |
このように総合的に各サイトを評価し、「今はサイトAに注力すべき」「将来的にはサイトBが成長見込み大」といった判断を明確にしておけば、リソースの分散を防ぎやすくなります。
まとめ
同時起業でいくつかのサイトを立ち上げるのは一見「無謀」に感じられるかもしれません。しかし、綿密な事業戦略とサイト運営の方針を確立し、適切なリソース配分を行うことでリスクを最小限に抑えながら、複数のサイトを同時に育てることは可能です。
ポイントは以下のとおりです。
- まずは各サイトの目的とターゲットを明確にし、優先順位をつける
- 制作コストや運営工数を正しく見積もり、無理のないスケジュールを組む
- ブランド全体の一貫性を保ちつつ、サイトごとの差別化をはかる
- 運営フローを標準化し、ツールや定例会議を活用して効率的に管理する
- 定量的な評価指標を導入し、PDCAサイクルを回して各サイトの成果を検証・改善し続ける
このようなアプローチを採用することで、「複数サイトの同時立ち上げ」は単なるリスクではなく、むしろ事業拡大に向けた有効な戦略になり得ます。むやみにサイトを増やすのではなく、戦略性を持って計画・実行すれば、中小企業でも十分に成功のチャンスを掴むことができるでしょう。






