Blog お役立ちブログ
複数決済手段を用意して購買ハードルを下げるEC運営術
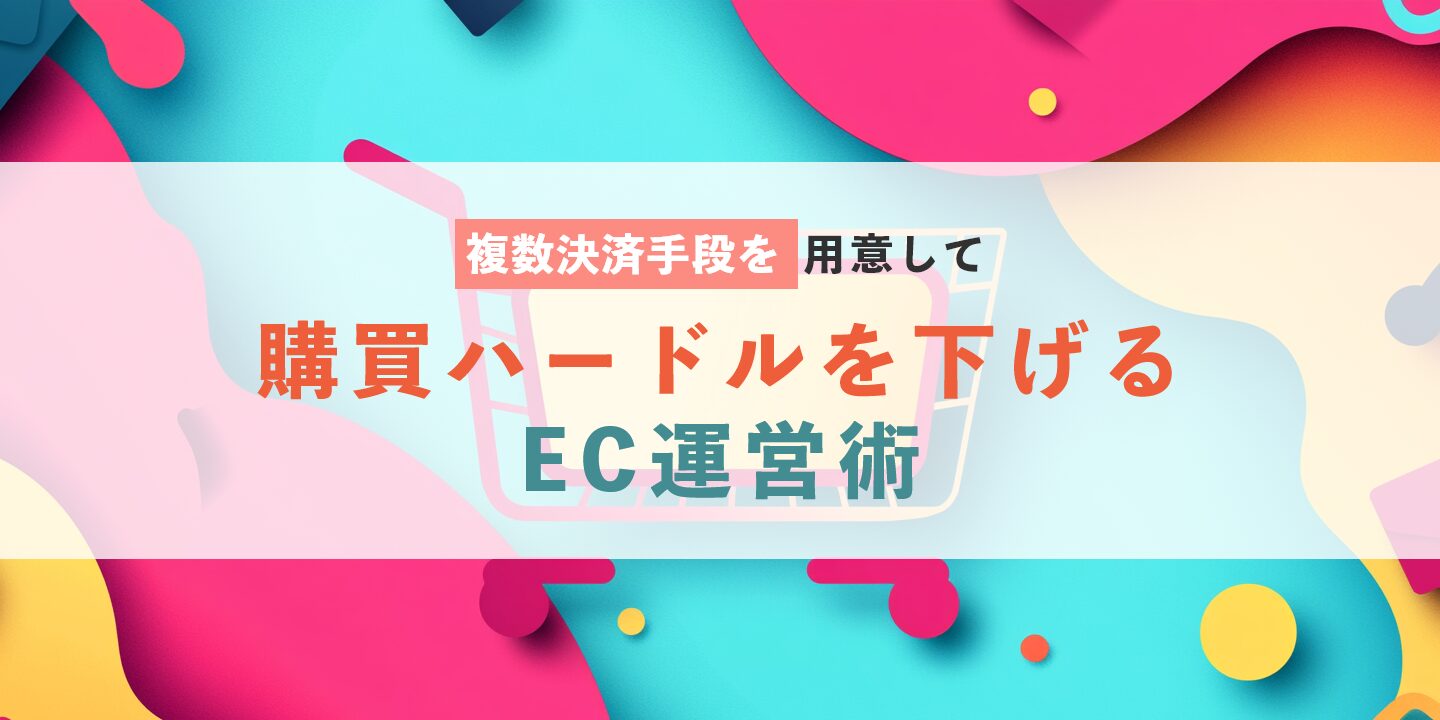
はじめに
ネットショップを運営するうえで、「商品の質」や「配送の速さ」などはもちろん大切ですが、「支払い方法の多様性」も売上向上において欠かせない要素の一つです。近年ではクレジットカードだけでなく、電子マネーや後払いといった多様な決済手段が普及し、消費者のニーズはますます多岐にわたっています。クレジットカードを持たない層や、現金主義のユーザー、あるいは支払いタイミングを後日にしたいユーザーなど、それぞれの事情に合わせて支払い手段を選べるようにしておくことで、購買意欲を高める可能性が広がります。
一方で、複数の決済手段を導入しようとすると、「契約の手順が複雑ではないか」「手数料が増えて経費がかさむのではないか」など、さまざまな疑問や不安が生じるかもしれません。そこで本記事では、中小企業がネットショップを運営する際に複数の支払い手段を導入するメリットや手順、注意点を総合的に解説します。購買ハードルを下げることで売上向上やリピーター増につながる可能性がありますので、ぜひ参考にしてみてください。
複数決済手段を導入するメリット
複数の決済手段に対応することは、運用コストが増えるかもしれないという不安をかきたてる反面、十分なメリットも期待できます。まずは、どのような利点があるのかを整理してみましょう。
多様な顧客ニーズへの対応
クレジットカード決済しか利用できないECサイトでは、クレジットカードを持っていなかったり、現金主義で後払い派のユーザーが離脱してしまうリスクがあります。代金引換や後払い決済、電子マネーなどに対応していれば、「ほしい」と思っているのに「支払方法が合わない」ためにあきらめていた顧客も取り込むことができます。
購買意欲の向上
ユーザーが「自分の好きな支払い方法で決済できる」という安心感を得られることで、購買意欲が増す傾向が見られます。クレジットカード決済のみに固執せず、幅広い選択肢を設けておくことで、注文を完了するまでの心理的障壁を低くする効果があります。
販促キャンペーンとの連動
複数決済手段を導入していると、特定の決済サービスが独自に行っているキャンペーン(ポイント還元、割引など)と連動できる場合があります。これによってユーザーが「今この決済手段を使うとお得だ」と感じ、購入を後押しする場面が増えます。
リピーター獲得
気に入った支払い手段でスムーズに購入できるショップは、リピート利用されやすい傾向にあります。ユーザーは慣れ親しんだ支払い方法を好むケースが多いため、自分の好みの支払い方法が選択できるECサイトであれば、今後も継続して利用してもらえる可能性が高まります。
こうしたメリットを踏まえると、「導入コストが少し増えても、長期的には売上とリピート率の向上が見込める」という観点から、複数の決済手段を導入する判断がなされることが多いのです。
主な決済手段と特徴
ネットショップにおける代表的な決済手段は以下のとおりです。ここでは、それぞれの特徴や利用シーンを簡潔にまとめた表を用意してみました。
| 決済方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| クレジットカード | 一般的かつ利用者が多い | 手軽で即時決済が可能 | カードを持たないユーザーは利用不可 |
| 後払い決済 | 請求書ベースで後日支払い | 商品到着後に支払う安心感がユーザーにとって大 | 手数料が高い傾向、未回収リスクが業者側にある |
| 代金引換 | 配送時に現金払い | クレジットカード不要で高齢層にもなじみ深い | 受取拒否などトラブル発生リスク |
| 電子マネー | プリペイド型やポストペイ型 | キャッシュレス志向の若年層に人気 | 電子マネーによっては限度額が低い場合あり |
| 銀行振込 | 事前に指定口座へ振込 | オンライン決済が苦手なユーザーに向いている | 入金確認に時間がかかり、手作業が増える |
実際に導入を検討する際には、以下のような視点で判断するとよいでしょう。
- 顧客層
- 若年層が多いのか、高齢者が多いのか
- 法人向けか個人向けか
- 売上単価が高めなのか低めなのか
- ショップ運営方針
- できるだけ自動化したいのか
- サポートにリソースをかけられるのか
- 回収リスクをどこまで許容できるか
- 手数料やシステム導入コスト
- 予算の範囲内か
- 売上増とのバランスはどうか
導入前に自社の顧客属性や運営体制を踏まえ、しっかり検討することが重要です。
複数決済の導入手順
ここからは、複数の決済手段を実際に導入する際の一般的な手順について解説します。各ステップでの注意点もあわせてご紹介します。
1. ショップの現状把握
まずは、自社のネットショップがどのような顧客層を対象にしているのか、現時点で何が強み・弱みになっているのかを整理しましょう。どのようなユーザーが多く、単価や購入頻度はどの程度か、といった情報を分析することで、導入すべき決済手段が見えてきます。
2. 導入する決済手段の候補を絞り込む
顧客層や商品特性、運用体制を考慮しながら、まずは導入したい決済手段を候補としてリストアップします。決済代行会社によっては複数の支払い方法をパッケージで提供している場合もありますので、個別に契約するよりコスト面・管理面でメリットが得られることもあります。
3. 各決済サービス事業者との契約・システム接続
候補が決まったら、各決済サービス事業者と契約を進めます。必要書類や審査の内容は事業者によって異なるため、事前にチェックリストを作成しておくとスムーズです。また、導入を決めた決済方法をネットショップのシステムと連動させる作業も発生します。プラグインやAPI連携など、どのような形で接続するかは事業者との打ち合わせが必要です。
4. テスト運用
導入が完了したら、実際にテストを行います。テスト用のカード番号や電子マネー決済で試行し、エラーが発生しないか、注文情報が正しく反映されるか、ユーザーがわかりやすい操作画面になっているかなどを確認しましょう。
5. 公開・運用開始
テストで問題がなければ実運用を開始します。ユーザーにとっては大きなメリットとなるため、サイト上での告知や説明を丁寧に行いましょう。決済方法が増えるほど、決済画面が複雑になりがちなので、「わかりやすい支払いフロー」を心がけることが大切です。
以下は、導入検討から運用開始までの流れを簡単にまとめた表です。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 現状把握 | 顧客属性・購入動向の分析 | 購入頻度や支払いトラブルの有無を確認 |
| 候補の選定 | 取り扱い決済サービスの情報収集・比較 | 導入コスト・対応範囲・手数料をチェック |
| 契約・システム接続 | 必要書類提出、API連携やプラグイン導入など | 審査に時間がかかる場合もある |
| テスト運用 | テスト環境での決済テスト | エラー対応・UI/UXチェック |
| 公開・運用開始 | サイト告知やユーザーへの説明 | 決済画面をわかりやすく整理 |
複数決済導入時の注意点とトラブル対策
複数の決済手段を導入するときには、以下のような点に注意する必要があります。特に運用開始後のトラブルは売上や顧客満足度に直結するため、事前に対策を講じておきましょう。
手数料負担と価格設定
複数決済手段を導入すれば、それぞれに応じた手数料が発生します。売上が増える分、手数料の総額も大きくなってしまう恐れがあるため、商品価格や送料などの調整が必要かもしれません。とくに後払い決済は手数料が高めなので、販売価格の設定に影響を及ぼす場合があります。
管理画面・入金確認の煩雑化
支払い方法が増えると、それぞれの決済サービスごとに管理画面や入金確認のフローが異なります。同じ決済代行会社であれば一元管理できることも多いですが、別々に契約している場合は確認作業が煩雑化しがちです。以下のように、管理画面や決済サービスごとの入金サイクルを一覧表にして把握するとよいでしょう。
| 決済サービス | 管理画面のURL(またはアクセス方法) | 入金サイクル例 | メモ |
|---|---|---|---|
| クレジットカード決済 | 〇〇ペイ管理画面URLなど | 月1回~月2回 | 締日・支払日を確認 |
| 後払い決済 | 〇〇アカウント管理ツールなど | 月1回 | 売掛金管理を要チェック |
| 電子マネー | 〇〇サイト管理画面など | 週1回 | 残高照会タイミングに注意 |
このような一覧を作ることで、どの時点で売上が確定し、いつ入金があるのかを一目で把握できます。スタッフが複数いる場合でも、誰が見てもわかるルールを決めておくと、情報共有がスムーズです。
セキュリティリスク
オンライン決済にはセキュリティリスクがつきものです。クレジットカードの不正利用や、後払い決済の未回収リスクなど、導入する決済手段によって異なるリスクが存在します。対策としては以下のようなものがあります。
- SSL/TLSなどのセキュリティプロトコルをしっかり導入する
- 不正注文を検知する機能のある決済代行会社を選ぶ
- 後払い決済では、与信審査が厳正なサービスを利用する
- システム上にクレジットカード情報を保存しない
- 問題発生時の問い合わせ窓口を明確にしておく
カスタマーサポートの整備
多様な決済方法を導入すると、ユーザーからの問い合わせ内容も多様化します。「後払い決済の支払い期限を過ぎたらどうなるのか」「電子マネーのチャージ方法がわからない」といった問い合わせが増えるかもしれません。これに対応できるサポート体制を整えておくことで、顧客満足度を損ねずに運営できます。
追加コストとROIのバランス
導入コスト・手数料と、それによって見込める売上増を比較検討し、ROI(費用対効果)を計算することは非常に重要です。「手数料が大きい割に利用される頻度が低い支払い方法」ばかりを導入してしまうと、経営に悪影響を及ぼす可能性があります。最初はメジャーな支払い方法を中心に導入し、アクセス解析や売上レポートを確認しながら少しずつ追加・削除を検討するのも一つの方法です。
まとめ
複数の決済手段を用意することは、ECサイトの購買ハードルを下げ、売上拡大に貢献する有効な施策です。クレジットカードのみの時代から、後払い決済や電子マネーなどの新たな選択肢が増えたことで、幅広いユーザーにアプローチできるようになりました。一方で、導入に伴うコストや手間、セキュリティリスクなどの課題もあるため、事前にしっかりと準備することが大切です。
まずは自社の顧客属性や商品特性を再確認し、最適な決済手段を選定しましょう。続いて、決済代行会社との契約やシステム連携を進め、テスト運用を実施します。運用開始後は、手数料や利用率を比較しながら適宜見直しを行うことで、より効率的かつ魅力的なEC運営が可能になります。上手に複数決済を取り入れて、ユーザーの満足度を高めながらショップ全体の成長を目指していきましょう。






