Blog お役立ちブログ
ネット販売と店舗販売を両立する要点
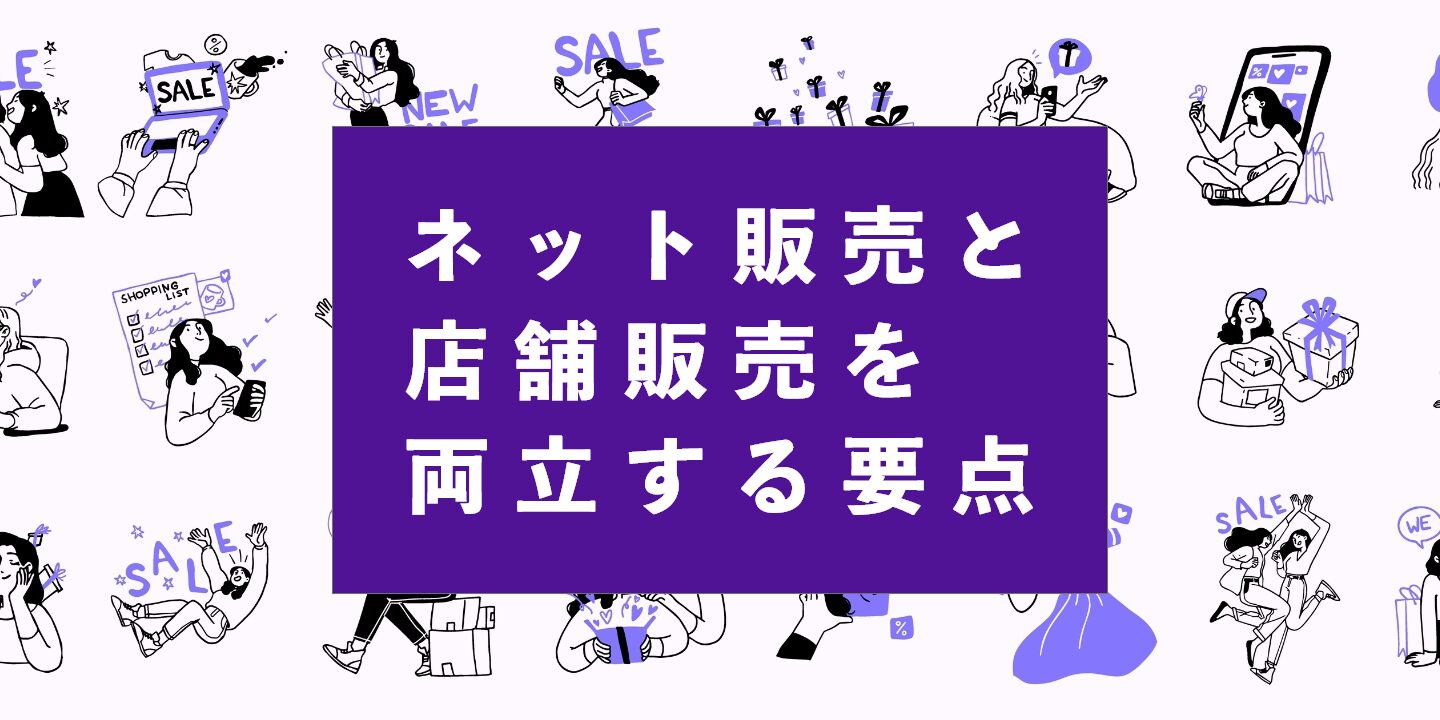
ネット販売と店舗販売を両立する意義
中小企業の店舗経営者がネット販売にも挑戦する意義は大きいです。実店舗のみの運営では、地域の来店客が収益の柱になります。しかし、近年の消費行動の多様化に伴い、オンライン上での購入を好む層が増加しているのも事実です。そこで、実店舗販売を続けながらネット販売を併用することで、新たな顧客層を開拓できるだけでなく、顧客の利便性や満足度を高めることが期待できます。
一方で、「在庫をどのように管理すれば良いか」「スタッフの負担が増えてしまわないか」などの不安がある経営者も多いでしょう。こうした懸念を整理しながら、自社に適した形でオンラインとオフラインの販売を両立させることが重要です。本記事では、運営体制やマーケティング、スタッフ育成などの観点から、具体的なヒントを紹介していきます。
ネット販売と店舗販売、それぞれの特徴と役割
ネットと店舗では、販売チャネルとしての特性が大きく異なります。まずはそれぞれの特長を把握し、「なぜ両立する価値があるのか」を整理してみましょう。
| 項目 | ネット販売 | 店舗販売 |
|---|---|---|
| 顧客との接点 | 全国・世界へ拡大しやすい | 地域密着でリピーターを生みやすい |
| 販売時間 | 24時間販売が可能 | 営業時間内のみ |
| 顧客体験 | 商品情報の比較・レビュー確認が容易 | 実際に商品を触れて試せる接客体験 |
| 運営コスト | サイト構築費やシステム利用料がかかる | 店舗家賃や光熱費、人件費がかかる |
| 在庫管理のしやすさ | システム連携でリアルタイムに把握しやすい | 直接棚卸を行いながらリアルに数を管理しやすい |
両者を並行して運営するには、それぞれの強みを活かし合うことがカギです。例えば、店舗での商品体験やスタッフの接客で顧客満足度を高めつつ、「在庫を切らしたくない」という顧客に対してオンライン在庫を提供するといった補完関係をつくれます。逆に、オンライン上で認知を広げ、興味を持った顧客に店舗へ来てもらうという流れも可能です。
在庫管理とスタッフワークのポイント
両立の際にネックになりがちなのが、「在庫の分け方」と「スタッフ不足」の問題です。限られた人員で実店舗とネットショップの双方を運用するためには、まずは在庫管理を整理しなければなりません。
在庫管理の方法
在庫管理を一元化するか、実店舗用とネット用で分けるかは、商品特性や販売規模によって異なります。おおまかに以下の3パターンが考えられます。
| 在庫管理パターン | 特徴 | 適したケース |
|---|---|---|
| 1. 完全一元管理 | すべての在庫を一本化して運用する。オンラインの在庫数が店舗在庫と連動するため、売切れ・在庫過多リスクを最適化しやすい。 | 在庫の回転が速く、リアルタイム連携の仕組みを整えられる中小企業に向いている。 |
| 2. オンライン用・店舗用で分割 | オンライン販売用と店舗販売用に在庫をある程度確保しておく。 | 商品の性質上、店舗での試着や体験を重視する一方、オンライン上でも一定数の顧客需要がある場合。 |
| 3. 部分的連携(限定商品を分割) | 限定商品や在庫数が少ない商品だけ店舗在庫と分割し、その他は共通在庫とする。 | 新商品や限定品を店舗で先行販売したい場合や、オンラインでしか買えないレア商品を設定したい場合などに適している。 |
多くの場合、「完全一元管理」もしくは「部分的連携」が、在庫コントロールをしやすいでしょう。特に、店舗で人気商品が急激に売れた場合や、イベント時に予想外の需要があった場合でも、オンラインの方で在庫を抑えておいたり、逆にオンラインが完売した分を店舗在庫から素早く補充したりできるメリットがあります。
スタッフワークと運営負荷の調整
ネットショップを運用するには、商品ページの作成や受注処理、問い合わせ対応、発送業務などのタスクが増えます。これらを店舗のスタッフだけで対応するのか、専用担当を置くのかで負荷が大きく変わってきます。
- 業務分担を明確にする
- 受注管理や顧客対応は誰が行うのか
- 商品撮影やページ更新などのクリエイティブ作業は誰が担当するのか
- 店舗スタッフとネットスタッフの垣根をどうするのか
- システム活用
- 受注、発送、在庫管理が連携できるシステムを導入する
- 作業の重複や入力ミスを減らし、スタッフの負担を軽減する
- 外部リソースの活用
- 撮影やデザインなど、特定の作業は外注する
- 繁忙期やキャンペーン時だけ臨時スタッフを追加する
少人数で運営している中小企業であれば、特にシステム導入や外部リソース活用は検討に値します。最初から全業務を内製化しようとすると、スタッフの負担が過剰に増えてしまい、結果として店舗運営にも悪影響が出てしまうからです。
販促・マーケティング手法の組み合わせ方
オンラインとオフライン、それぞれでの販促施策をうまく組み合わせることで、相乗効果を狙うことができます。単独のチャネルだけでは得られないメリットを生み出すために、基本的な考え方を整理しましょう。
店舗×ネットの主な販促アイデア
- 店舗来店特典 + オンラインクーポン
店舗で買い物をしてくれたお客様に、次回はオンラインショップで使えるクーポンを配布する。これにより、店舗のお客様をオンラインへ誘導しやすくなります。反対に、オンラインショップで購入したお客様に、実店舗の割引券やイベント招待券を同梱すれば、リアル店舗にも足を運んでもらえる可能性が高まります。 - SNSやメルマガで実店舗イベントを告知
ネットショップの顧客データやSNSフォロワーなどのオンライン顧客に対し、実店舗のセールやイベント情報を告知します。地方の中小企業でも、SNSを活用すれば遠方からの集客も期待できるでしょう。 - 商品レビューやSNS投稿を店舗にフィードバック
オンライン上で集まったレビューやコメントは、店舗スタッフの接客にも活かせます。「この商品はこういうポイントが評価されていますよ」といった形で、接客の質を高める材料にできます。
オンライン広告と地域密着販促の両立
オンラインで全国や地域外へ販路を広げる一方で、店舗が地域のお客様と直接繋がりやすいという強みも見逃せません。地域のイベントや商店街での共同セールに積極的に参加することで、ネットショップだけでは届かない層との接点を確保できます。
- 地域情報サイトとの連携: 地域のニュースサイトや情報ポータルに自店の情報を掲載してもらう
- POPやチラシ: オフライン販促もしっかり活用し、オンラインショップへの誘導を行う
- SNS広告ターゲティング: 店舗周辺エリアを指定して広告を配信し、興味を持ちそうな層を店舗へ誘導する
店舗ならではの「顔の見える安心感」を武器にしつつ、オンラインでは検索・比較しやすい利便性を提供し、幅広い層にリーチすることが望ましいです。
店舗とネットの運営体制づくり(スタッフ育成・業務分担)
店舗スタッフがネット販売にも関わる場合、事前に必要なスキルや知識を共有しておく必要があります。たとえば、以下のような項目を共有・研修するだけでも、ネット事業をスムーズにスタートしやすくなります。
| 項目 | 具体的内容 | 主な担当または研修対象 |
|---|---|---|
| 基本的なサイト操作方法 | 商品登録、価格変更、在庫数の更新など | 店舗スタッフ全員(最低限の知識を持つ) |
| 受注管理システムの使い方 | 注文データの確認、顧客情報の確認、発送処理 | 一部スタッフを中心に担当を決め、重複作業をなくす |
| 顧客対応・問い合わせ対応の基礎 | メール、チャットなどオンライン特有のコミュニケーション方法 | 接客経験が豊富なスタッフを中心に、言葉遣いやスピード感を含めて教育 |
| 発送・梱包方法の標準化 | 梱包資材の選び方、伝票の貼り方、破損や返品に関する対応方法 | 主に倉庫担当や発送担当が習得し、クレーム対応リスクを最低限に抑える |
| 簡単なマーケティング知識 | SNS運用、キャンペーン企画など | 店長やマーケティングに興味のあるスタッフが積極的に習得 |
特に大切なのは、運営の要となる受注管理や在庫管理、顧客対応のフローを整理し、誰がどのタイミングで作業をするかを明確化することです。たとえば、受注データの確認は毎日何時に誰が行い、発送作業は何時から誰が行うのか。そして、もし店舗が忙しい時間帯はどのようにネット側の作業をカバーするのか。こうした具体的なスケジュール設計が、円滑な両立に欠かせません。
成功事例・具体的な運用例
ここでは、一般的に言われる成功事例の一例を紹介します。実際に実店舗がありながらネット販売を展開し、相互補完に成功している企業のイメージです。
ケース1: 衣料品店の事例
- 店舗ではベテランスタッフが顧客の体型や好みに合わせたコーディネートを提案
- その接客力をオンライン上でも活かし、ネットショップに「スタッフおすすめコーデ」コンテンツを載せる
- 店舗で試着した商品を迷った末に購入しなかった顧客が、後日ネットショップで注文するケースが増えた
ケース2: 食品・地元特産品の事例
- 実店舗では試食イベントや地元イベントへの出店で知名度向上
- ネットショップを活用して遠方からのリピーターを獲得
- 地元イベントで配布したオンラインクーポンが引き金となり、地域外のリピート顧客を安定的に増やす
いずれの例も、「店舗での強みをネットに活かす」「ネットでの広がりを店舗に還元する」という循環をつくり上げています。この相乗効果を意識した運用設計こそが両立の肝と言えるでしょう。
よくある課題とその解決策
実際にネットと店舗の両立を始めると、以下のような課題に直面することがあります。それぞれ代表的な対処法をまとめてみます。
- 忙しくてネットの更新が滞る
- 定期的に更新作業を行う担当者を決める
- テンプレートや自動投稿ツールを活用して作業負荷を軽減する
- 商品撮影や商品説明の作成をまとめて行い、分割して公開する
- ネットと店舗の在庫にずれが出る
- 在庫管理システムを導入し、可能な限りリアルタイム連動させる
- 店舗で売れたら即座にシステムへ入力する運用ルールを明確にする
- 一部商品は安全在庫を持たせて急な需要にも対応できるようにする
- スタッフがネット担当に慣れない
- 研修やマニュアルを整備して、ネット運用の基本をしっかり学んでもらう
- 得意分野を活かせる形で業務をアサインする(撮影が得意なスタッフ、文章作成が得意なスタッフなど)
- 外部リソースも併用し、負担を分散させる
- ネット販売の集客が思うように伸びない
- SNSや広告、SEO対策など多角的な集客施策を検討する
- オフラインで来店した顧客にネットショップを案内する仕組みを強化する(チラシやQRコード設置など)
- 商品写真や説明文のクオリティを上げる、レビュー促進キャンペーンを実施する
- ネットでのトラブル対応に戸惑う
- 配送ミスや初期不良などが発生した場合の対処フローを事前にマニュアル化する
- 返品や返金に関する規定をわかりやすく提示しておき、スタッフ間でも共有する
- トラブルがあった場合の連絡先や責任者を明確にし、顧客対応のスピードを重視する
まとめ
オンライン販売とオフライン販売を両立するためには、両者の特長を理解したうえで、在庫管理やスタッフワーク、そしてマーケティング施策を一元的かつ柔軟に設計する必要があります。中小企業の場合、どうしても人手やリソースに限りがあるため、どこまで内製化するか、どの業務を外注やシステムに任せるかを適切に判断することが大切です。少しずつテストを重ねながら、自社にとって最適なバランスを見つけ、店舗の強みとネットの強みを組み合わせることで、より多くの顧客を満足させ、売上拡大につなげることができるでしょう。






