Blog お役立ちブログ
無料ツールで始める競合サイト分析のやり方──広告費ゼロで勝つ
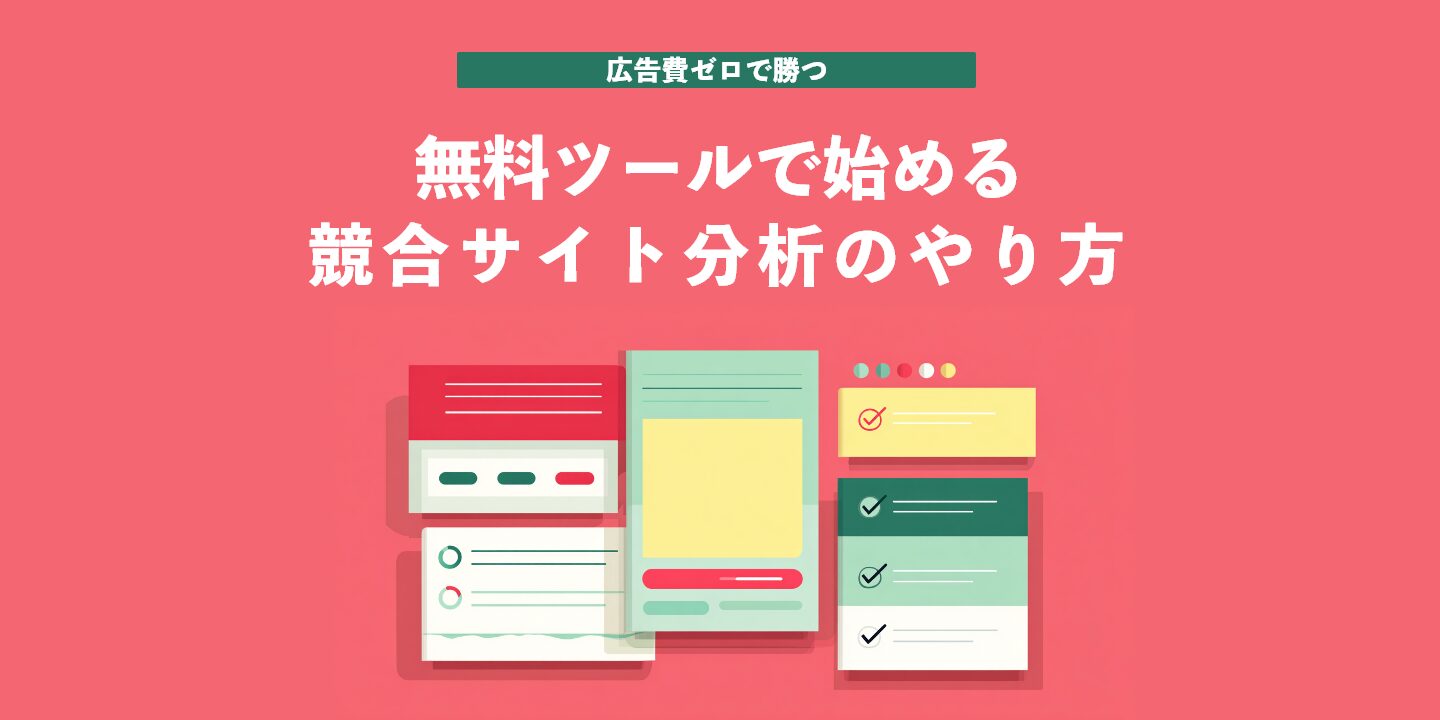
競合サイト分析とは何か
競合サイト分析とは、検索結果やサイト構造、被リンクなど外部から取得できるデータを用いて「ライバルがどのように集客しているか」を数値で可視化し、自社の改善方針を決める調査手法です。
大切なのは「勝ち筋を見極める」ことであり、膨大な情報を集めることではありません。無料ツールでも、指標を絞り込めば十分に実戦的な示唆を得られます。
なぜ今、無料ツールなのか
- 広告費の高騰で、クリック単価は年々上がっている
- 有料ツールは月額1万円を超えるものが多く、中小企業には負担が大きい
- 無料ツールは機能が限定される一方、基本指標の把握には十分
- 使い方を社内に共有しやすく、人材を固定化しなくても継続できる
分析前に整理すべき自社の目的と指標
調査を始める前に「何のために分析するのか」を明確にします。目的が曖昧なままでは、取得した数字をどう解釈するか迷い、行動に結びつきません。
| 目的 | 具体例 | 優先指標 |
|---|---|---|
| 新規リード増加 | 資料請求を月30件に | 検索順位・CVR |
| 広告費削減 | CPCを20%削減 | オーガニック流入数 |
| ブランド強化 | 指名検索を倍増 | ブランド名検索数 |
上表のように「KPI→指標」を1行にまとめると、ツールで追うべき項目が絞れ、関係者の認識がそろいます。
指標は“3つまで”に絞る
欲張って10項目を同時に追うと、かならず優先順位がブレます。まずは
- 流入量を示す指標
- コンバージョンを示す指標
- 競合比較を示す指標
—この3分類から代表指標を1つずつ選ぶと管理が楽になります。
無料ツール一覧と得意領域
無料ツールごとに得意な調査範囲が異なります。目的に合わせた“使い分け”が成果への近道です。
| ツール名 | 得意領域 | 取得できる主なデータ | 備考 |
|---|---|---|---|
| Google Search Console | 自社サイト | 検索クエリ、平均順位 | 必須。最新データは48時間遅れ |
| Googleキーワードプランナー | キーワード規模 | 月間検索回数、入札単価 | 要広告アカウント |
| Ubersuggest(無料枠) | 競合KW・被リンク | キーワード難易度、被リンク数 | 1日3回まで |
| OpenLinkProfiler | 被リンク | リンク元ドメイン | CSV出力可 |
| SimilarWeb(無料版) | トラフィック推定 | 流入元チャネル割合 | 大規模サイト向き |
得意領域マッピング
以下の図式で整理すると、ツールを横断する際の混乱を防げます。
arduinoコピーするキーワード調査:キーワードプランナー/Ubersuggest
被リンク調査:OpenLinkProfiler/Ubersuggest
トラフィック推定:SimilarWeb
自社データ連携:Search Console
キーワード調査の手順(無料版)
ここからは具体的な作業フローに入ります。まずは検索需要を把握するためのキーワード調査です。
手順1:主要競合サイトを3社選定
競合選定は「検索結果で上位」「サービス内容が近い」「規模が近い」の3条件で行います。
学習塾の例なら「エリア名+塾」で検索し、上位10件から対象を抜き出すイメージです。
手順2:キーワードプランナーで種キーワードを取得
自社と競合のURLをキーワードプランナーに入力し、関連キーワードを抽出します。
- 月間検索数が100以上
- 競合性が「低」または「中」
- 検索意図が自社サービスと一致
—これらの条件に絞り込むと、初期リストが100語程度にまとまります。
手順3:Ubersuggestで検索難易度を確認
抽出したキーワードをUbersuggestに貼り付け、SD(SEO Difficulty)が30未満の語句を優先します。
SDが高い語句は、被リンクやコンテンツボリュームが足りないと上位化が遅れるため、短期的な成果を狙う場合は避けるのが無難です。
手順後のリスト整理
最終的には
- 月間検索数
- SD値
- 検索意図(情報/比較/購入)
を並べたシートを作成し、戦う価値があるキーワードを「優先」「保留」「除外」に色分けすると、チーム内の共有と実行がスムーズになります。
手順4:競合とのギャップを見つける
エクセルやスプレッドシートで次の列を作成します。
- キーワード
- 競合順位(平均)
- 自社順位
- ギャップ(競合−自社)
このギャップ列がプラスなら「奪取対象」、マイナスなら「防衛対象」と分類できます。食品メーカーの場合、レシピ系キーワードは指名検索に直結しやすく、ギャップが小さくても早めに施策を打つ価値があります。
手順5:実装難度と効果を掛け合わせて優先度を付与
- 効果:検索ボリューム × クリック率推定 × コンバージョン率想定
- 難度:コンテンツ作成工数 + 技術的対応工数 + 被リンク必要量
2×2マトリクスで「High効果/Low難度」に落ちるキーワードから着手すると、小規模なチームでも初期成果を出しやすく、社内の理解を得る材料になります。
よくある質問:キーワードプランナーの数字は信用できる?
「推定値だから当てにならない」という声を聞きますが、重要なのは絶対値ではなく“相対比較”です。無料版でも同じ基準で比較すれば、競合より検索需要が大きい領域を選ぶ判断材料になります。どうしても精度を高めたい場合は、Search Consoleの実測値で3か月分の平均を取り、補正係数として掛け合わせる方法が現実的です。
ここまでのまとめ
- 分析の前提を固めないと、数字は宝の持ち腐れになる
- 無料ツールは得意領域を理解して使い分ける
- キーワード調査では「検索ボリューム×難易度×意図」で優先度を決める
ここまでで、競合との差を可視化するための“種キーワードリスト”が完成しました。次章では、このリストを使って被リンクとコンテンツ構造をどう読み解くかを解説します。
ケーススタディ:地域密着型学習塾
大阪市内で4校舎を展開する学習塾A社は、広告費を年間300万円まで削減するために無料ツール分析を導入しました。
- 「大阪市 塾 中学生」という主力KWでの自社順位は14位
- 競合B社は同KWで4位、被リンクは300本
- リスト整理の結果、B社が獲得していない「大阪市 定期テスト対策 塾」というミドルKWが月間1,300回の需要を持つと判明
A社はこのKWで対策記事を公開し、3か月で5位まで上昇。広告費を掛けずに問い合わせが月15件増加し、主力KWでも11位まで順位を押し上げる相乗効果が生まれました。
被リンク調査の手順(無料版)
被リンクは「他サイトからの紹介票」のようなもので、質と量の両方が検索順位に影響します。無料ツールでも、競合との差を見極める指標は十分取得できます。
手順1:競合リンク総量を把握する
OpenLinkProfilerに競合3サイトのURLを入力し、
- 総被リンク数
- リンク元ドメイン数
- 新規リンク獲得数(直近90日)
を記録します。数だけでなく“リンク元ドメイン数”を見ることで、同じドメインからの重複を除いた純粋な広がりを確認できます。
| サイト | 総被リンク数 | リンク元ドメイン数 | 新規リンク(90日) |
|---|---|---|---|
| 競合A | 4,820 | 310 | 55 |
| 競合B | 2,450 | 185 | 22 |
| 自社 | 1,200 | 92 | 7 |
上表のように数値を並べると、どこが“量の壁”になっているか一目で分かります。
手順2:リンクの質を判定する
質の高い被リンクは、以下の3条件を満たすものです。
- 業界やテーマが近いサイトからの紹介
- 有料広告や相互リンクでない自然獲得リンク
- ドメイン評価(DRなど)が一定以上
無料版Ubersuggestで「被リンク→参照ドメイン」タブを開き、DR40未満のリンクは参考値として扱い、DR40以上を重点的に抽出しましょう。OpenLinkProfilerでもドメイン評価スコア(0〜100)が併記されるので、重複計測で誤差を補正できます。
手順3:ギャップと優先度を付ける
- 競合Aとの差分:リンク元218ドメイン
- 競合Bとの差分:リンク元93ドメイン
すべて埋めるのは現実的ではないため、次のように“質”と“工数”でマトリクス化して優先度を決めます。
質×工数マトリクスの例
コピーする高質・低工数:業界メディアの取材、行政機関からの紹介
高質・高工数:学術論文からの引用、全国紙の特集
低質・低工数:Webディレクトリ登録、地元ポータルへの掲載
低質・高工数:相互リンク依頼の大量送付
最初に狙うのは「高質・低工数」。たとえば学習塾なら地域ニュースサイトへの寄稿、士業事務所なら専門誌Web版のQ&Aコーナーなどがここに該当します。
質を落とさずリンクを増やす3つの方法
- 既存取引先のサイトから紹介文リンク
- 自治体・商工会議所の会員ページ活用
- 業界団体の無料プレスリリース掲示板
いずれも費用ゼロで獲得でき、リンクの削除リスクも低いのが特徴です。
コンテンツ・サイト構造比較の手順
競合に勝つには「どのページで・何を・どう見せるか」を再設計する必要があります。ここではURL構造とコンテンツタイプを中心に比較します。
手順1:URL構造マッピング
自社と競合のサイトマップをダウンロードし、スプレッドシートで以下の列を作成します。
- URL
- 階層(何階層目か)
- タイトル(30文字以内に要約)
- キーワード種別(サービス/ナレッジ/会社情報など)
各サイトの行数を数えると、たとえば競合Aはサービス詳細ページが80本あるのに対し、自社は25本しかなく“情報量の壁”が推測できます。
手順2:コンテンツタイプを分類する
無料版SimilarWebで競合URLを入力し、「Content Topics」から主要トピックを取得します。学習塾サイトなら
- 学習方法
- 進路指導
- 保護者ガイド
—などが表示されるため、自社に欠けたトピックを洗い出せます。
手順3:ページ深度とPVの相関を見る
Search Consoleから自社の「最も表示されたページ」上位100件をエクスポートし、URLの階層数とクリック数を散布図で確認します。階層が深いほどPVが落ちていれば、構造そのものがネックです。逆に競合が浅い階層で主要キーワードを獲得しているなら、内部リンクの張り直しやカテゴリ統合が即効策になります。
| 階層 | 平均クリック数(自社) | 平均クリック数(競合A) |
|---|---|---|
| 1階層 | 1,200 | 2,300 |
| 2階層 | 730 | 1,450 |
| 3階層 | 210 | 980 |
| 4階層 | 60 | 310 |
上表は学習塾A社が実際に確認したデータを簡略化したものです。階層が深くなるほど競合との差が拡大し、内部リンク改善の必要性が明確になりました。
手順4:不足ページの優先度を決める
- 検索ボリュームが大きい
- 競合順位が高い
- 自社に該当ページがない
この三条件を満たすテーマから記事やLPを追加します。食品メーカーなら「原料名+レシピ」、士業なら「地域名+手続き名」のように、指名検索につながるキーワードを優先すると回遊率が伸びやすくなります。
業界別ミニ活用事例
食品メーカー:レシピ記事で被リンク増
自社ブログに調味料を使ったレシピを追加し、料理系メディアから自然リンクが月10本増加。被リンク経由のアクセスが月1,500PV増え、指名検索も前月比18%成長。
学習塾:FAQのマークアップで順位改善
「内申点 仕組み 大阪市」記事に構造化データを追加し、FAQリッチリザルトが表示。クリック率が1.8倍に伸び、指名検索ではないキーワード経由のお問い合わせが月8件増加。
士業事務所:専門記事のシリーズ化
会社設立手続きシリーズを10本公開し、行政書士ポータルから紹介リンクを獲得。全体の流入が25%増え、リンク元経由で月2件の相談が発生。
無料ツール運用ルーチンの作り方
- 週次10分:順位と被リンクのチェック
- 月次60分:キーワードリストの更新とギャップ再計算
- 四半期ごと:サイト構造とコンテンツの棚卸し
ツール値を定点観測し、小さな改善を積み重ねることで、広告費ゼロでも検索流入は右肩上がりになります。
データの読み解き方と優先順位付け
データは「現状把握→課題抽出→施策立案→検証」の順で使います。数字を見た瞬間に施策を決めると、本質的なボトルネックを見落としがちです。
- 現状把握
- 自社と競合の差分を“数値”でリスト化
- 課題抽出
- 差分のうち、成果(CV)に近い指標から並べ替え
- 施策立案
- 効果と難度を2×2マトリクスで分類
- 検証
- 実施後は同じ指標で再計測し、改善幅を記録
このフローを月次で回すだけでも「やるべきこと」が明確になり、属人的な判断を減らせます。
経営層に報告するコツ
専門用語を並べても意思決定は進みません。経営層には“3枚のスライド”だけで十分です。
| スライド | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| ① 市場動向 | 検索ボリューム推移と主要KW | 機会の大きさを共有 |
| ② 競合差分 | 競合と自社の順位・被リンク差 | 危機感の醸成 |
| ③ 打ち手 | 優先度高い施策と期待効果 | 資源配分の決裁 |
表形式で「数字→示唆→行動」を並べると、非マーケ職でも判断しやすくなります。
よくある落とし穴5選
- ツールの数字を絶対視
- 推定値はあくまで目安。必ず実測で補正する
- 被リンク“数”だけを追う
- 質の低いリンクは順位どころかペナルティ要因
- コンテンツ量産で満足
- 検索意図とマッチしない記事は伸びない
- 一度作ったキーワードリストを放置
- 検索需要は季節・法改正で変動する
- 分析担当者の属人化
- 手順と評価軸をドキュメント化し、業務をブラックボックスにしない
運用を続けるためのチェックリスト
- 週次で順位と被リンクを記録している
- 月次でキーワードリストを更新している
- 四半期ごとにサイト構造を棚卸ししている
- 競合3社の主要指標を同じシートで追っている
- 経営層への報告資料を3枚でまとめている
チェックが1つでも空欄なら、運用ルーチンを見直しましょう。
まとめ:無料ツールでも勝てる理由
無料ツールは機能制限があるものの、「勝ち筋を探す」という目的には十分です。大事なのは
- 指標を絞り込んで差分を可視化し
- 効果と難度で優先順位を付け
- 小さな仮説検証を高速で回す
—この3点を継続すること。広告費を掛けなくても、数字が示す通りに動けば結果はついてきます。






