Blog お役立ちブログ
Facebookページだけでも十分?SNSとホームページの役割を徹底解説
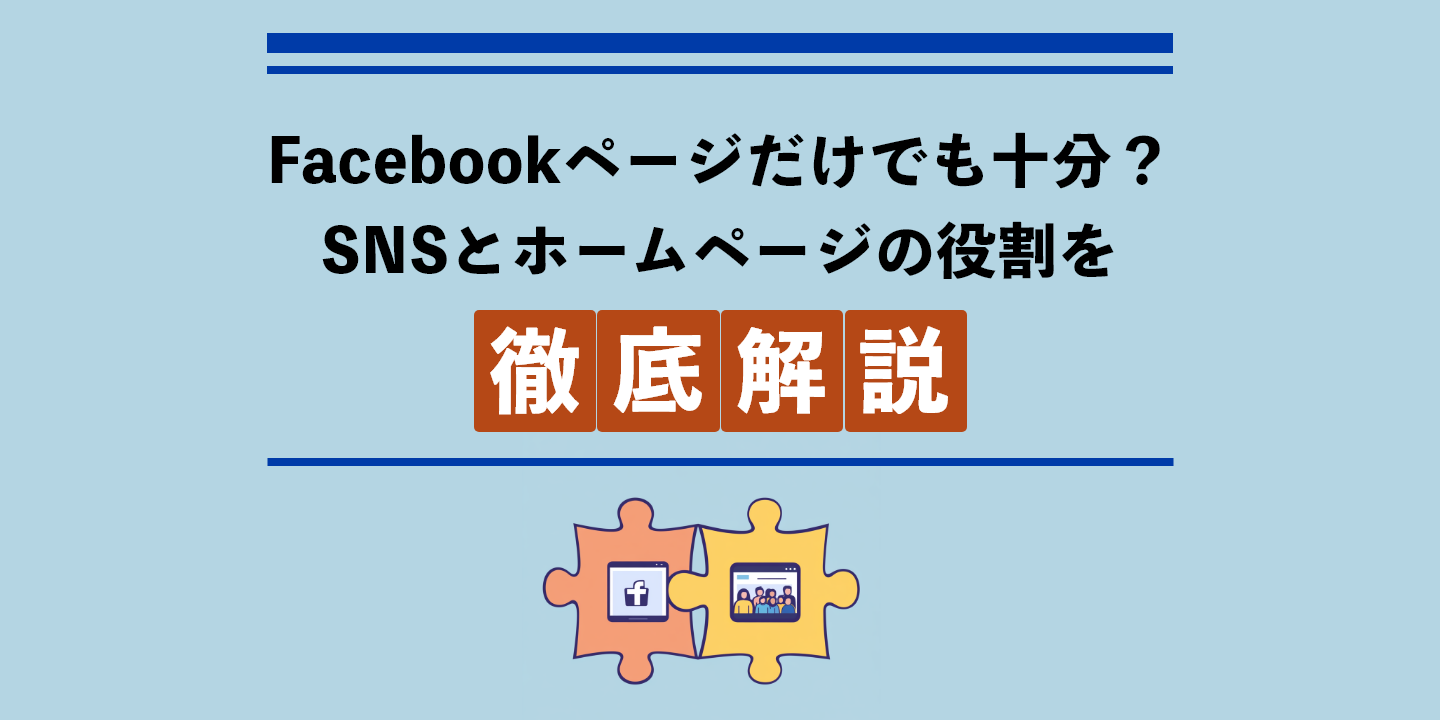
Facebookページだけでも十分?と感じる背景
Facebookページを活用して、店舗やサービス情報を発信している中小企業は多く存在します。友達や常連客とのやりとりを通じて店舗の雰囲気を共有できたり、新商品やセール情報を素早く届けられるなど、SNSならではのメリットは大きいでしょう。SNSを使いこなせば、コストを大きくかけずに情報発信ができるうえ、拡散効果も期待できるため、「これだけで十分なのではないか?」と思う方も少なくありません。
しかし一方で、「新規顧客を増やすにはどうしたらいいのか」「SNSが苦手な人やアクセスしない層に対して情報を届けられているのか」など、疑問や不安もつきまといます。さらに、FacebookなどのSNSはプラットフォームの仕様変更が起きやすく、集客や情報発信の戦略を左右しかねないリスクも存在します。
本記事では、Facebookページだけに依存するメリット・デメリットを整理しつつ、ホームページを持つことで得られる効果、そしてそれぞれの役割の違いについて解説します。SNSだけでも十分なケースと、ホームページを持つべきケースの考え方を分かりやすくまとめますので、ぜひ今後の運用方針を考える際の参考にしてください。
Facebookページの特徴と限界
SNSの拡散力とコミュニケーションのしやすさ
FacebookページをはじめとするSNSには、「拡散」「コメント」「いいね!」など、ユーザー間のコミュニケーションを促進する仕組みが整っています。たとえば新商品の情報を投稿すれば、友達やファンがシェアしてくれる可能性があり、短時間で多くの人へ届くケースもあります。日常的にFacebookをチェックしているユーザーとの接点を持ちやすいため、認知度向上や顧客との距離を縮める効果は確かに大きいといえます。
アルゴリズムの影響を受ける
一方でFacebookの投稿がどれだけ多くのユーザーの目に触れるかは、Facebookのアルゴリズムに左右される面があります。たとえ魅力的な投稿をしても、ユーザーのタイムラインに表示される優先度が低ければ、見てもらえないこともあるのです。これは企業アカウントとしてはコントロールしにくく、運営主体による仕様変更があるたびに悩まされる点でもあります。
SNS利用者以外へのリーチの難しさ
Facebookを活用していない人に対して、情報を届けるのは難しいという課題もあります。特定のSNSを使用していない層へアプローチしたい場合、Facebookページ単独では効率が悪いケースがあります。また、SNS利用者の中でもFacebook自体をあまり使わない世代や層も存在するため、潜在的な顧客へアプローチできないリスクがあるのです。
信頼性やブランドイメージの管理
SNSアカウントだけだと、公式情報や企業姿勢を体系的にまとめる場が不足しがちです。Facebookページだけでは企業全体の信頼感を築くのに限界を感じる人も多いでしょう。SNSの投稿は新着が中心であり、過去の情報が埋もれやすい構造のため、企業として重要なメッセージやポリシーを伝えるには不向きな場合があります。
ホームページを持つメリット
ブランドイメージの確立と信頼感の醸成
公式サイトを構築すると、企業や店舗の理念、商品やサービスの特性、実績、利用客の声などをまとめて発信できます。見やすいデザインやレイアウトで整えておくことで、ブランドイメージをしっかりと訴求し、閲覧者に安心感を与えやすくなります。SNS上でのコミュニケーションが賑わっていても、公式サイトがないと「本当に信用していいのだろうか?」と疑問をもたれることもあるため、オフィシャルな場所としてホームページを用意することは信頼向上に役立ちます。
検索エンジン経由の新規集客
ホームページを持つ最大のメリットの一つが、検索エンジンからの流入です。たとえば「地域名+業種名」「商品ジャンル+おすすめ」など、ユーザーはさまざまなキーワードで検索を行います。ここであなたのホームページが検索結果に表示されれば、SNS利用者以外の幅広い層にリーチするチャンスが生まれます。Facebookページは検索エンジンで上位表示されにくいため、ホームページと比べて新規客を集める力は弱い傾向にあります。
情報整理と長期的な資産化
SNSではタイムラインに沿って投稿が流れていくため、情報が蓄積されても探しにくい問題があります。ホームページであれば、カテゴリ分けや導線設計を行い、ユーザーが知りたい情報へスムーズにアクセスできる構成を作りやすいです。また、ホームページ上に蓄積された記事やコンテンツは長期的に検索エンジン経由で読まれる「資産」となります。SNSのようにアルゴリズムの変更に左右されにくい点も大きな利点です。
企業独自の運営方針が貫ける
SNSはプラットフォームのルール変更やアカウント停止リスクがゼロではありません。それに対してホームページは独自ドメインで運営するため、自社で運営方針をコントロールしやすい特徴があります。レイアウトや機能面も自由度が高く、自分たちのブランドイメージに合った見せ方を追求できます。
Facebookページとホームページの役割比較
下記の表では、Facebookページ(SNS)とホームページがどのように役割や特徴を異にしているかをまとめています。
| 項目 | Facebookページ(SNS) | ホームページ |
|---|---|---|
| 到達経路 | タイムライン・友達のシェアなど | 検索エンジン・直接アクセスなど |
| 発信スタイル | 新着情報中心。短文や写真、動画での投稿 | 企業の理念や商品詳細など、体系的・包括的な情報の提供 |
| 拡散力 | 投稿がバズれば大きな拡散を期待できる | 自然検索で幅広い層が訪問。SNSほどバズりにくいが、安定した集客が見込める |
| 信頼感・ブランディング | アカウントのみでは企業としての本格的な信頼を得にくいケースあり | オフィシャルな場所としての役割が強く、ブランドイメージを確立しやすい |
| 情報の整理・保管 | タイムライン上で過去投稿が埋もれやすい | カテゴリ分けなどで情報を整理し、ユーザーが探しやすい |
| 長期的な資産化 | アルゴリズム次第で閲覧数が変動しやすい | コンテンツが検索エンジン経由で長期的に読まれる可能性大 |
| 運営リスク | プラットフォーム依存。規約変更やアカウント停止などのリスク | 独自ドメイン・サーバーで運営。自社方針で運営しやすい |
| コスト | 無料登録だが広告出稿や運用工数次第で費用がかさむ可能性あり | サイト制作費・更新費用・ドメイン代・サーバー代など初期費用および運用費が必要 |
このように、両者にはそれぞれ一長一短があります。Facebookページだけで十分か、あるいはホームページの運営も必要かは、ビジネスの目指す方向性や顧客層、情報発信のゴールによって異なります。しかし多くの場合、店舗の専門性を示したり、詳細情報を検索で拾ってもらったりするためには、ホームページを持つことが望ましいといえます。
ホームページの制作・運用ステップ
ホームページを作ろうと思っても、「どこから手を付ければいいのかわからない」という声は多く聞かれます。以下の表は、ホームページ制作と運用の大まかなステップを示したものです。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1.目的の明確化 | なぜホームページを作るのか、どのような情報を発信したいのかを整理 | 新規集客、ブランド強化、問い合わせ増など、ゴールによって設計やコンテンツの方向性が異なる |
| 2.構成の設計 | 必要なページ構成・導線・機能を考える | サイトマップやワイヤーフレームを作成して、ユーザーが情報にたどり着きやすい設計を |
| 3.デザイン制作 | 企業イメージに合ったデザインやレイアウトを考案 | トンマナ(色・フォント・写真の使い方など)を統一し、ブランディングを意識 |
| 4.コンテンツ作成 | 企業紹介・サービス説明・事例・お客様の声など、文字や画像を準備 | わかりやすく説得力をもたせるために、ユーザー視点で情報整理する |
| 5.サイト構築 | システム開発・CMS導入・レスポンシブ対応など | 予算や運用体制に応じてツールを選択し、モバイルフレンドリーを重視 |
| 6.公開・検証 | サイトを公開し、アクセス解析でユーザー行動をチェック | 継続的に改善ポイントを洗い出し、運用やコンテンツ更新を行う |
ホームページ制作は、一度作って終わりではありません。公開後も定期的にアクセス状況を確認し、必要に応じて内容を更新・修正することが大切です。特に、中小企業の場合は最新情報の更新が止まると、来訪者が「活動していないのかな」と感じてしまうリスクがあるため、運用体制をしっかりと計画しておくことが重要です。
Facebookページとホームページを組み合わせるメリット
Facebookページとホームページをそれぞれ活用することで、単独運用では得られない相乗効果が期待できます。
- 広範囲のユーザー層にアプローチ
- Facebookページ:常連客やファン層、SNSの拡散力を生かしたリアルタイムの情報発信
- ホームページ:SNSを使わない層や検索エンジンを利用する層にもリーチ可能
これによって、より多様なユーザーに情報を届けられるようになります。
- ブランド力と信頼性の向上
Facebookページの投稿で親近感を演出しつつ、公式サイトできちんとした企業情報やサービス内容を示すことで、ユーザーに安心感を与えやすくなります。問い合わせや来店意欲の向上につながる効果が期待できるでしょう。 - 情報発信の場を使い分けられる
新商品やイベント告知などはFacebookページを中心に拡散し、より専門的な詳細情報やFAQなどはホームページでまとめるといった使い分けが可能です。更新の頻度を役割ごとに振り分ければ運用コストを分散しやすくなります。 - リスクヘッジが可能
SNSのアカウントが何らかの理由で凍結されたり、仕様変更に伴ってユーザーにリーチしづらくなったりしても、ホームページがあれば最低限の集客経路を保てます。逆にホームページが検索エンジンで順位を落としても、Facebookページから補完できるなど、複数のチャネルを活用することでリスクを分散できます。
成功事例・具体例
1. 地域密着型のカフェ
地元の常連客に支えられてきたカフェが、さらなる集客を目指してFacebookページを始めました。SNS運用によりイベント情報や限定メニューの告知を行った結果、周辺地域のファンが徐々に増え、来店客が増加しました。さらに公式ホームページを開設したところ、検索エンジンから観光客や出張中のビジネスパーソンが訪れるようになり、想定以上に新規顧客を獲得できるようになりました。
2. 専門サービスを提供する個人事業主
Facebookページのみを使って活動情報を発信していた個人事業主の事例です。顧客は友人や紹介からの依頼が中心でしたが、ビジネス拡大のためホームページを制作し、サービス内容を具体的に掲載するようにしました。結果、検索キーワードからの流入が増え、SNSを利用しない顧客層からの問い合わせも増加。Facebookページとホームページの相互リンクで両方へのアクセスを促し、ビジネスの幅を広げることに成功しました。
3. 地域イベント主催団体
地域のイベント情報をFacebookページだけで告知していた非営利団体が、ホームページを開設してイベントの詳細や過去の様子をしっかりと紹介するようにしました。すると、イベント参加者が増加しただけでなく、協賛企業の獲得にもプラスに働きました。SNSでの活動は今まで通り継続しつつ、「より公式な形で情報発信できる場」を持つことで信頼感を高めたといえます。
Facebookページとホームページの活用を成功させるポイント
以下の表では、運用を成功させるための具体的ポイントを示します。Facebookページだけでも、ホームページだけでもなく、両者をうまく活用するためのチェックリストとして活用してみてください。
| ポイント | Facebookページ活用 | ホームページ活用 |
|---|---|---|
| 投稿・更新頻度 | 定期的な投稿を行い、ファンとのコミュニケーションを維持 | 最新情報やブログ記事をこまめに更新して、検索エンジンからの評価を向上 |
| コンテンツの方向性 | イベント告知や新商品、裏話など、よりカジュアルな内容を出しやすい | 企業紹介・商品ページ・よくある質問など、深い情報を整然とまとめる |
| リンクや導線設計 | 投稿文でホームページへのリンクを積極的に貼り、興味を持った人を誘導 | トップページや記事内にSNSボタンを設置し、SNSでもフォローしやすくする |
| ターゲットの明確化 | 既存顧客やファンに向けて投稿。イベント時には拡散を狙う | 新規顧客や検索ユーザーに向けて、基本情報やサービス内容を丁寧に説明 |
| コメント・問い合わせへの対応 | 迅速に返信し、ユーザーとの信頼関係を育む | 問い合わせフォームを整備し、問い合わせを受けたら迅速かつ丁寧に回答 |
| 分析・改善 | ページのインサイト(閲覧数やいいね数など)をチェックし改善に活かす | アクセス解析ツールで流入キーワードや閲覧ページを把握し、改善を続ける |
こうしたポイントを押さえるだけでも、運用の質は大きく変わります。SNSとホームページはそれぞれ特性が違うため、一元化するのではなく役割を明確に分けて相互補完させることが大切です。
まとめ
Facebookページは手軽に開設でき、拡散力やファンとのコミュニケーションに優れたツールです。一方で、アルゴリズムや利用者層の偏りといった制約があり、新規顧客へのリーチや企業としての信頼獲得面で物足りなさを感じる場合があります。そうしたときには、ぜひホームページの開設を検討してみてください。検索エンジンからの集客やブランドイメージの確立、情報の体系化など、Facebookページだけでは得られないメリットを享受できる可能性が高まります。
とはいえ、すべての企業や店舗がホームページを必ずしも持つべきとは限りません。運用コストや目的を踏まえて、Facebookページの役割と、ホームページを持つ意義を比較検討することが重要です。多くの場合は、それぞれの強みを活かしつつ組み合わせることで、より効果的な情報発信と新規集客、信頼獲得が実現できるでしょう。






