Blog お役立ちブログ
クラウドファンディング募集ページとホームページを連携して効果を高める方法
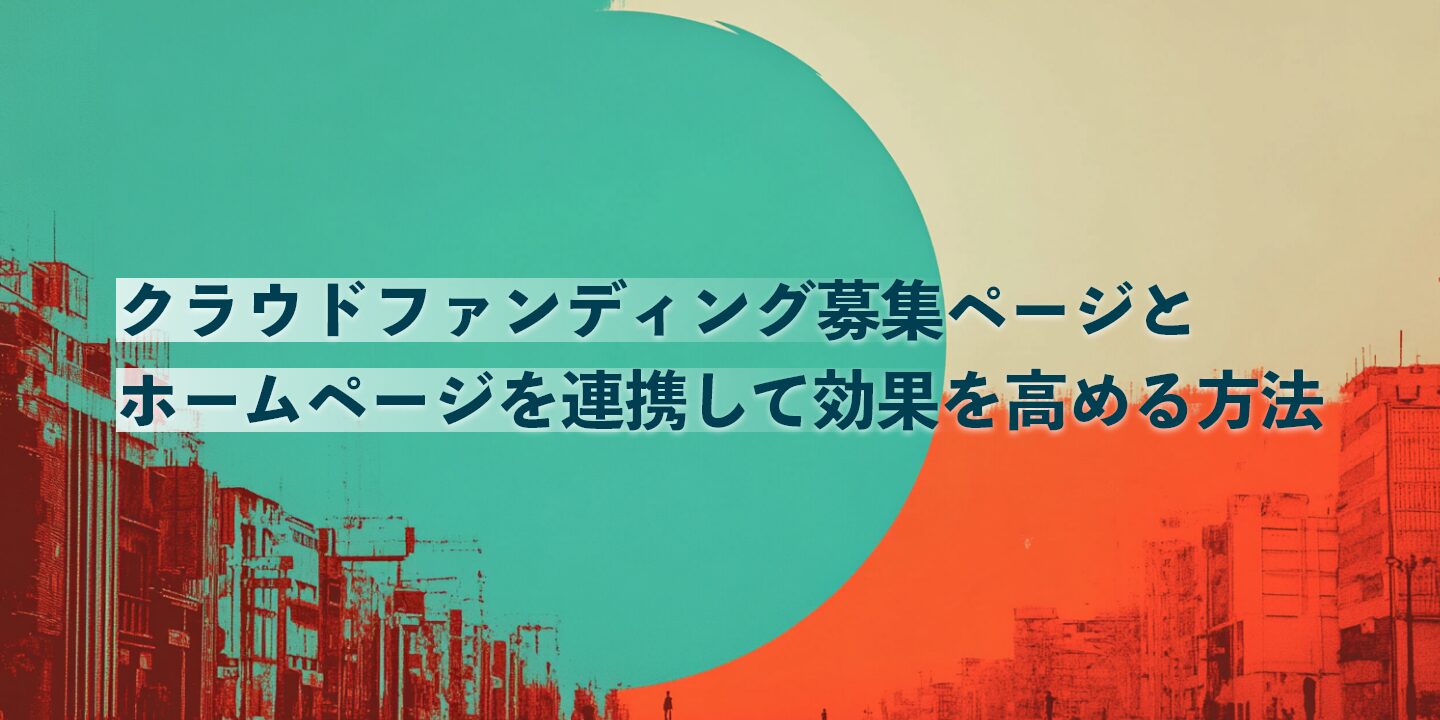
中小企業がクラウドファンディングを活用する際、プロジェクトの募集ページだけでは十分に情報を伝えきれない場合があります。募集ページには基本的な概要やリターン内容を掲載することが多いものの、運営者の想いや実績、今後のビジョンなどが伝わりにくいと感じる方も多いでしょう。そこで活用したいのが自社ホームページとの連携です。
ホームページをうまく活用することで、次のようなメリットが得られます。
- 追加情報の提供
クラウドファンディング募集ページでは触れきれない事業の背景や運営者の想いなどを詳しく掲載できる。 - ブランドイメージの構築
既存のホームページ上で企業や事業のコンセプトを伝えることで、ブランドイメージをより鮮明に印象付けられる。 - 顧客との長期的な関係構築
クラウドファンディングが終了した後でも、ホームページを通じて支援者や新規顧客とつながりを維持できる。 - 検索エンジン対策
ホームページのコンテンツを充実させることで、関連キーワードでの検索流入を狙え、支援者の裾野を広げるチャンスが生まれる。
こうしたメリットを最大限活かすためには、クラウドファンディングのプロジェクト内容とホームページの情報を適切に組み合わせ、タイムリーな更新を行うことが大切です。本記事では、クラウドファンディング募集ページとホームページを連携するときに意識したいポイントや手順、運用方法などを詳しく解説していきます。
連携前に押さえておきたいポイント
実際に連携を行う前に、あらかじめ以下の要点を押さえておくことで、後々の運用がスムーズになります。
1. 目的とゴールを明確にする
クラウドファンディングを通じて得たいものは資金だけではなく、支援者やファンとの関係、認知度、ブランドイメージなど多岐にわたります。そのため「ホームページでは何を最終的に達成したいのか」を明確にすることが重要です。支援者に伝えたいメッセージや得てほしい行動を洗い出し、ホームページ上のコンテンツとの整合性を図りましょう。
2. ホームページの現状を把握する
現状のホームページに訪れるユーザー属性やアクセス数、滞在時間などを把握しておくと、連携後の変化を比較しやすくなります。また、ホームページがスマートフォンなどモバイル端末で見やすいデザインになっているか、問い合わせフォームは使いやすいかなど、基本的な使い勝手にも注意が必要です。
3. 運用負担を見積もる
クラウドファンディングの期間中は、進捗報告やリターン内容の追記など、情報更新が頻繁に必要となります。募集ページとホームページの両方にアップデートが発生する場合は、担当者の作業負担が増える可能性が高いです。どこをどのように連携し、どの部分は募集ページだけに集約するか、あるいはホームページ側でまとめるかといった役割分担を考えましょう。
4. デザイン・ブランディングの整合性
クラウドファンディングの募集ページはプラットフォームのテンプレートデザインに沿って作られることが一般的です。一方、自社ホームページは独自のデザインやコンセプトがあるでしょう。両者を行き来したときに、ユーザーが「同じ事業者である」と一目で分かるように配色やロゴの使い方、メインビジュアルなどを統一感のあるものに整えることが大切です。
以下の表は、連携前に特に確認しておきたい主なチェック項目をまとめたものです。
| チェック項目 | ポイント |
|---|---|
| 目的・ゴール設定 | 資金調達以外に得たい成果(認知度向上、顧客育成など)を明確にする |
| ホームページの現状 | 現在のアクセス数、ユーザー属性、デバイス別閲覧状況などを把握 |
| 運用負担の見積もり | 募集ページとホームページの更新頻度を想定し、役割分担を決める |
| デザイン・ブランディング | ロゴ・配色・メインビジュアルの一貫性を意識し、ユーザーが違和感なく移動できるようにする |
クラウドファンディング募集ページの活用術
クラウドファンディングの募集ページは、支援の申し込みやリターンの提示、プロジェクト概要の説明などが中心になります。ここでは、募集ページをより効果的に活用するためのポイントを解説します。
1. プロジェクトのストーリーを強調する
クラウドファンディングでは、プロジェクトの背景や目的が支援者の興味や共感を得る上で極めて重要です。単に資金調達の金額だけを強調するのではなく「なぜこの事業を行うのか」「実現することで社会や顧客にどんな価値が生まれるのか」といったストーリーをしっかりと伝えましょう。
2. リターン内容を魅力的に設計する
支援者にとってどのようなメリットがあるのかを具体的に示すことは大切です。たとえば、自社の製品やサービスの先行利用権、特別なイベントへの招待、限定グッズなどをリターンとして設定するケースが多いですが、これらがターゲット層に合っているか、魅力的なものになっているかを検証しましょう。
3. 定期的な進捗報告でファンを巻き込む
募集期間中には、プロジェクトの進捗をこまめに報告して支援者とのコミュニケーションを育む必要があります。目標金額の達成率や、開発・生産の進捗、取材・メディア掲載情報などを共有することで、支援者のモチベーションを保ち、さらに拡散を促す効果も期待できます。
4. SNSとの連携
SNSアカウントを活用して募集ページの情報を拡散し、リアルタイムで反応を得る方法も非常に有効です。SNS投稿やライブ配信で舞台裏や試作品などを紹介し、リターンを手にした支援者のコメントをシェアするなど、親近感を高める工夫が求められます。
以下の表では、クラウドファンディング募集ページ運用のポイントをまとめています。
| 運用ポイント | 具体例 |
|---|---|
| ストーリーの訴求 | 事業を始めたきっかけや今後の展望をわかりやすく物語形式で記載する |
| リターンの設計 | 既存顧客向け、潜在顧客向け、VIP向けなど複数の魅力的なコースを用意 |
| 定期的な進捗共有 | 週1回の進捗ブログ更新、SNSでもダイジェストを発信 |
| 支援者とのコミュニケーション | コメント欄やメッセージ機能を活用し、質問や感想に即レスすることで好感度を高める |
ホームページ運用・更新のポイント
クラウドファンディング募集ページと並行して、ホームページの運用にも気を配らなければなりません。支援者の多くは、より詳しい情報や企業の信頼性を確認するためにホームページを訪れるからです。ここでは、ホームページ側で意識したい更新・運用のポイントを紹介します。
1. プロジェクト特設ページやバナーを設置する
ホームページのトップページやメインビジュアル部分に、クラウドファンディングへのリンクやバナーを掲載することで、訪問者の目に留まりやすくします。特に新規訪問者や既存顧客がアクセスした際、すぐにプロジェクトの情報を得られる導線を整えることが大切です。キャンペーン期間中はトップに特設ページへのリンクを常時配置するなど、明確に誘導しましょう。
2. 事業内容や実績を整理して掲載する
クラウドファンディングの募集ページには書ききれない自社の歴史や他の事業実績、受賞歴などがある場合は、ホームページでしっかり情報提供しましょう。支援者や初めて訪れるユーザーに対して「この会社は信頼できる」という印象を与えるには、企業のコンセプトや方針、過去の実績が整理されていることが重要です。
3. 活動報告・ブログの更新
クラウドファンディングの進捗報告をホームページ内のブログやニュースセクションで発信すると、支援者だけでなく一般ユーザーにも事業内容の深い理解を促せます。新しい取り組みやイベント情報、メディア掲載などを継続的に報告することで、検索エンジンにおいても更新頻度の高さが評価され、間接的にサイトの認知度向上に寄与します。
4. モバイル最適化
クラウドファンディングのプラットフォーム自体は多くの場合、モバイル対応されています。ホームページ側もスマートフォンなどで閲覧したときにストレスなく閲覧できるレイアウト・文字サイズ・ボタン配置になっているか再度確認しましょう。支援のハードルを下げるうえで、モバイルユーザーへの最適化は欠かせません。
連携後のコミュニケーション・ブランディング強化
クラウドファンディングが終了したあと、プロジェクトに興味をもってくれた層や支援してくれた層に対して継続的に情報を届けることが、今後のビジネスを拡大するうえで非常に重要です。ここでは、連携後に注力すべきコミュニケーション施策やブランディングのポイントを紹介します。
1. メルマガやSNSで定期的にフォローアップ
支援者は「自分が支援したプロジェクトがどう成長していくか」を見届けたいと思っています。定期的にメールマガジンやSNSで成果報告や新サービスの情報を発信しましょう。ホームページの更新情報を載せることで、常にサイトへ誘導できる仕組みも作れます。
2. ホームページ上でのリターン報告
クラウドファンディングのリターンが実際に届けられた様子や、支援者と共につくりあげたイベントの写真などをホームページで公開するのも効果的です。具体的な成果物や感謝メッセージがあると、新たに興味を持ったユーザーや今後リピーターになる可能性のある人々に対しても好印象を与えられます。
3. コミュニティ化を促す仕組み
支援者が情報共有やコミュニケーションを行えるプラットフォームを用意するのもよい手段です。SNSグループ、オンラインサロン、フォーラムなどが考えられます。これらをホームページで案内し、ファン同士の交流を促すことで、プロジェクトや企業を応援してくれる人々の輪が広がります。
4. ブランドメッセージの徹底
クラウドファンディングを成功させたあとも、自社のブランドや理念を発信し続けることで、ユーザーの愛着を高められます。ホームページやSNSなど、どのチャネルでも一貫したメッセージを届けることで、企業やプロジェクトの世界観が明確になります。
具体的な連携手順と活用事例
ここでは、クラウドファンディング募集ページとホームページを実際にどう連携させるか、その手順を例示します。あくまで一例ですが、作業イメージをつかむ参考にしてください。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 企画段階 | – クラウドファンディングの目的とゴールを社内で明確化 – 募集ページに掲載する内容とホームページで補完する内容をリストアップ |
| デザイン準備 | – 募集ページに合わせたロゴやキービジュアルを確認 – ホームページ側で特設ページを設ける場合はデザイン案を作成 |
| 募集ページ作成 | – プラットフォームの仕様に沿って基本情報(ストーリー、リターン、目標金額)を入力 – 企業ロゴやカラーを使ってブランドイメージが伝わるように調整 |
| ホームページ連携 | – トップページまたはバナーで募集ページへリンクを設置 – 事業内容や企業情報のページを見直し、支援者が知りたい情報を整理 – ブログ等で進捗や最新情報を継続発信 |
| 募集期間中の運用 | – SNSやメルマガなどでクラウドファンディングを拡散 – 質問への回答や感謝メッセージを即時対応 – ホームページ側でも進捗の要点を定期的にアップデート |
| 募集終了後 | – 結果報告を募集ページとホームページ両方で実施 – ホームページでリターンや今後のプロジェクト計画を公開 – 支援者コミュニティの運用を開始 |
活用事例のイメージ
- 新商品開発を目的としたクラウドファンディング
募集ページでは商品コンセプトや開発の背景を中心に訴求し、ホームページでは既存商品との関連性や企業のサステナビリティ方針など、より深い情報を掲載。支援者が「どんな会社が作っているのか」を理解しやすい構成を実現。 - 地域活性化プロジェクト
募集ページに地元の魅力やイベント内容をストーリー仕立てでアピール。ホームページには観光案内や地域の歴史、連携先の団体情報などを掲載し、支援者がより詳細を知りたいときにスムーズに移動できる導線を確保。
これらの事例を参考に、自社の目的やターゲットに合わせて適切に連携をカスタマイズしていくと、より多くの支援者や顧客の共感を得られるはずです。
まとめ
クラウドファンディングの募集ページとホームページを連携させることで、単なる資金調達以上の大きな効果が期待できます。情報を分散させるのではなく、それぞれの役割を明確にしたうえで統合的に発信することが大切です。募集期間中の進捗報告や支援者とのコミュニケーションはもちろん、キャンペーン終了後のブランド形成やファン化施策にもホームページが大いに活用できます。
- まずは連携の目的・ゴールを明確にすること。
- 運用負担やデザイン面の一貫性を考慮し、役割分担をしっかりと決めること。
- 募集ページではストーリーやリターンを、ホームページでは詳細情報や実績を補完しあう形を意識すること。
- 終了後も定期的に情報を更新して、支援者との関係を深めていくこと。
これらを実践することで、クラウドファンディングの効果を最大化し、事業の認知度やブランド価値を高めることができるでしょう。ぜひ取り組んでみてください。






