Blog お役立ちブログ
サイトデザインの色数を絞ってブランドイメージを強化するポイント
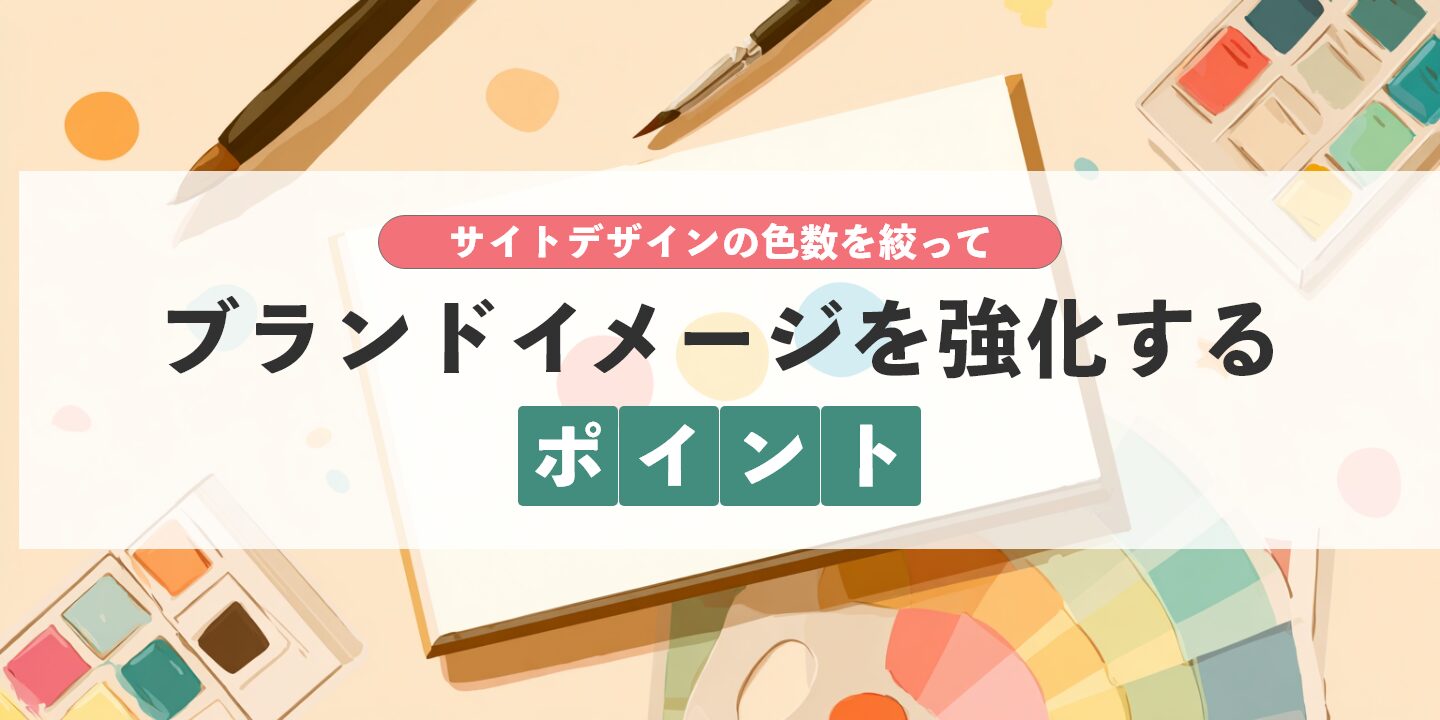
はじめに:色数を絞ることの意義とメリット
企業やサービスのWebサイトを運用するうえで、「色数を絞る」というのは非常に大きな意味を持ちます。カラフルなデザインは一見華やかに見えますが、使う色を増やしすぎると画面全体に統一感を欠き、訪問者に「散らかった印象」を与えがちです。一方、使用する色を厳選して絞りこむことで、「シンプル」「上品」「洗練」というポジティブなイメージが生まれ、ブランドとしての軸を一貫して伝える効果が得られます。
特にブランドイメージを大切に考える企業の場合、サイトデザインの色数が多すぎるとブランドの軸がぼやけてしまい、印象に残りにくくなる懸念があります。反対に、「コーポレートカラー」や「ブランドカラー」を明確に打ち出し、それを支える補助色の数を最小限にすることで、サイト訪問者に対して「一貫したメッセージ性」を届けることができるでしょう。
本記事では、色数を絞ることのメリットや、色彩心理を活かしたブランドイメージの強化方法、具体的な配色の選定手順などを詳しくご紹介します。中には「色数を減らしすぎると地味になるのでは?」という不安をお持ちの方もいるかもしれません。しかし、ポイントを押さえれば「シンプルでありながら強く印象づける」デザインをつくることができます。ぜひ参考にしてみてください。
色彩心理がブランディングに与える影響
色はユーザーの印象形成に大きな影響を与えます。Webサイトにおける第一印象は、レイアウトやフォントといった要素と同様に、色の使い方でも大きく左右されます。たとえば、赤は「情熱的・活発」、青は「安心・信頼」、緑は「自然・リラックス」、黄は「元気・好奇心」など、人間は無意識のうちに色からさまざまなイメージを受け取ります。これを「色彩心理」と呼び、ブランディングにおいて非常に重要なテーマです。
色彩心理がブランドにもたらす効果
- 差別化
他社と異なる色を使うことで競合との差別化につながります。特に、コーポレートカラーが他社のサイトやロゴカラーと大きく違う場合、ユーザーの記憶に残りやすくなります。 - 親近感
企業や製品のテーマに合った色を使うことで、「このブランドは自分に合っている」と感じてもらう効果が期待できます。たとえば、自然志向を大切にする企業が緑をメインとした配色を採用すると、一貫性が高まり説得力が生まれます。 - ブランドの一貫性
広告や名刺、パンフレットなどあらゆるデザイン資産において、同じブランドカラーを使うことは統一感を演出します。ユーザーは無意識に「この色=あの企業の色」と覚えてくれるようになり、結果的に認知度向上につながります。
このように色が人間に与える印象は大きく、企業の個性やブランドメッセージを伝える上で欠かせない要素です。したがって、Webサイトにおいても色数を戦略的に絞りこむことは、強いブランドイメージづくりにつながるといえます。
ブランドカラーの選定手順
では具体的に、どのように自社のブランドカラーを選んでいけばよいのでしょうか。重要なポイントは、まず「企業コンセプト」や「ブランドの方向性」を明確にすることです。以下のステップで考えるとスムーズです。
- ブランドの価値観を洗い出す
「信頼感」「革新性」「自然との調和」「温かみ」「挑戦的」など、企業やサービスの根幹をなす価値観を整理します。 - 連想できる色をピックアップする
価値観に合う色を複数ピックアップしてみます。たとえば「信頼感」を大切にしたいなら青系統、「温かみ」を強調するならオレンジ系統といった具合です。 - 競合他社の色使いを確認する
まったく同じ業界の競合と被るカラーを採用すると、区別がつきにくくなる場合があります。ただし、あえて同じ業界にない色を採用することで「差別化」につなげる戦略もあります。 - メインカラーとサブカラーを3色程度に絞りこむ
サイトのメインカラー、サブカラー、アクセントカラーと呼ばれる3種類が定番です。アクセントカラーは一部ボタンや強調したい要素に使う色で、最も目立ちやすい色が選ばれます。 - デザインサンプルを作成・検証
実際にサイトのワイヤーフレームや簡易デザインを作り、ピックアップした色を当てはめてみます。画面全体のバランスや文字可読性、印象をチェックし、必要に応じて調整します。
下記は「サイトデザインでメインカラーと補助色をどのように配置するか」の例です。色数を最低限に抑えてもしっかり訴求できるよう、役割を明確にすることが重要です。
| 役割 | 使用する色の例 | 説明 |
|---|---|---|
| メインカラー | コーポレートカラー系 | 企業の印象を最も強く表現する色 |
| サブカラー | メインカラーの補色 | メインカラーを引き立てる。必要に応じて2色まで |
| アクセント色 | 補色・鮮やかな色 | ボタンや見出しに使用し、ユーザーの視線を誘導する |
上記のように役割を分ければ、色数が少なくても十分にメリハリのあるデザインを実現できます。
複数色を使う場合の注意点
ブランドカラーは基本的に1~3色程度に絞るケースが多いですが、場合によってはもう少し色を増やすこともあります。ただし、その際には以下の点に注意するとよいでしょう。
- 色の比率をあらかじめ決める
例として「メインカラー70%」「サブカラー20%」「アクセントカラー10%」のように比率を定めると、デザイン全体で色数を増やしても統一感を保ちやすくなります。 - 類似トーンや彩度を揃える
たとえ色相(赤・青・緑など)が違っても、トーン(明度・彩度)を似た系統にするだけで、まとまり感が高まります。 - 要素がぶつかり合わないようにする
同じ画面内に赤と緑を同量配置すると、クリスマスのような印象を与えるなど、余計な連想が生まれることがあります。違う色を使う際には全体の調和を意識し、目的のメッセージを損なわないように注意しましょう。 - 可読性・視認性を確保する
ボタンやテキストに派手な色を使っても、背景色とのコントラストが弱いと視認性が低下します。ユーザーが見づらいと感じる配色は離脱率を高める恐れがあるため、色を増やすほど「読めるか」「見やすいか」を厳しくチェックしましょう。
色数を絞るメリットとデメリットの比較表
色数を減らすことで得られるメリットは大きい反面、「想定とは異なる地味な印象になってしまうのでは?」という懸念もあります。以下の比較表を参考に、自社サイトの課題や目的と照らし合わせて検討してみましょう。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ブランドイメージ | 一貫性が生まれ、印象に残りやすい | 色選択を誤ると単調・地味なイメージを与える可能性がある |
| ユーザー体験 | 重要な箇所を強調しやすく、理解しやすい | 間違った要素に色を使ってしまうと、誤解を招く・クリック率低下のリスクがある |
| デザイン工数 | カラーパターンが少ないため、修正や更新がスムーズ | 同じ色ばかりでレイアウトを変えても代わり映えがしない場合、より丁寧にデザインを考える必要がある |
| 差別化 | 統一感のあるデザインにブランドカラーが際立ち、企業独自の個性を発揮しやすい | 同業他社と似た配色になると、むしろ埋没してしまう恐れがある |
メインとなる企業カラーがしっかりと定まっている場合は、メリットの方が大きいと考えられます。一方で「どうしても暗い印象になってしまう」「ライバル企業が同じ色を使っていて目立たない」などの課題が見えた場合には、アクセントカラーを見直すといった対策が必要です。
色数を絞ったデザインを実践するための具体例
実際に色数を少なくしてブランディングを高めるために、どのような工夫をすればよいでしょうか。以下に具体的な例を挙げます。
- 背景を無彩色(白・黒・グレー)でまとめる
サイト背景やメインのコンテンツエリアに無彩色を使うと、文字情報や画像が映えるうえ、ブランドカラーがより際立ちます。背景色を無彩色に統一すれば、ボタンやリンクの色を強調しやすい点もメリットです。 - 企業ロゴと同じ色をキービジュアルに大きく使う
ファーストビューに配置されるメインビジュアルで企業ロゴと同系統の色をベースにすると、一目で「この企業は○○を重視している」というイメージを与えられます。人間の目は画面中央や大きなビジュアルにまず注意を向けるため、インパクトのあるブランディングを実現できます。 - ボタンは統一した色だけを使う
ボタンの色をいくつも変えると、ユーザーがどこをクリックしてよいのか分かりづらくなります。主なアクションボタンは1色、サブのアクションボタンは別の1色と決めておくとよいでしょう。 - 文字色・リンク色は基本的に固定する
「テキストは黒系」「リンクは企業カラー」といった形でルールを決めると、ユーザーがマウスオーバー時やページ遷移時に迷いにくくなります。あちこち異なる色のリンクがあると混乱を招くため、色数を最小限に絞っておくのが得策です。 - ビジュアル要素に使う色は企業カラーの系統でまとめる
写真やイラストなどを差し込む際も、可能であればフィルターや補正で企業カラーのトーンに寄せる方法があります。全体的なサイトの世界観がブレにくくなり、ブランディング効果を高められます。
色数の少ないデザインを際立たせるテクニック
色数を最低限にするからこそ、各要素の「配置」や「余白」がより重要になります。単調な印象にさせないためのテクニックを紹介します。
1. 余白を活かす
色数を少なくすると、どうしても平坦なデザインになりがちです。そこで、行間やブロック間に十分な余白をつくることで、メリハリをつけましょう。余白は「読みやすさ」や「高級感」の演出にも効果的です。
2. フォントバリエーションを工夫する
色に頼らず、フォントの太さや大きさを変えることで情報の重要度を整理できます。たとえば、見出しは太字・大きめに、本文は読みやすい標準サイズ、サブ情報は小さめにするなど、色以外の方法でアクセントを加えるのです。
3. シンプルなアイコンやイラストを用いる
派手な画像や背景を使わずとも、統一感のあるアイコンやイラストを組み合わせるだけでアクセントをつけられます。企業カラーと親和性の高いアイコンを採用することで、全体の雰囲気を崩さず情報をわかりやすく伝えられます。
4. モノトーン×ブランドカラーで引き立てる
モノトーン(白・黒・グレー)をベースにして、要所要所でブランドカラーを差し込む手法は、多くの企業サイトで採用されています。たとえば、背景を白やグレーにして文字色は黒をメインにし、ボタンだけはブランドカラーにする、といったレイアウトです。これにより、ブランドカラーの存在感が際立ちます。
5. 配色ガイドラインを作成する
色数を制限するだけではなく、複数人でサイト運用を行う場合は「配色ガイドライン」を用意しておくことがおすすめです。どの部分にどの色を使うのか、使ってはいけない色の組み合わせは何かをまとめておくことで、一貫性あるデザインを保ちやすくなります。下記はガイドラインを作る際の項目例です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メインカラー | コーポレートカラーの具体的なカラーコード |
| サブカラー | メインカラーに合う補助色のカラーコード |
| アクセントカラー | CTAボタンや強調したい要素に使う色 |
| テキストカラー | 標準本文、見出し、リンクの色 |
| 背景カラー | ヘッダー、フッター、コンテンツエリアの色 |
| 禁止配色パターン | 視認性が低下する組み合わせや、企業イメージにそぐわない色合い |
ガイドラインを運用チーム全体で共有すれば、更新や新規ページ追加の際にも配色の統一性を維持しやすくなります。
まとめ
色数を絞ってブランドイメージを強化する方法は、一見シンプルそうに思えますが、実際は「どの色を採用するか」「どれくらいの比率で使うか」「どのような要素に当てはめるか」といった検討を丁寧に行う必要があります。ポイントは以下の通りです。
- 企業コンセプトやブランドの方向性を明確にし、その価値観と合う色を選定する。
- メインカラー・サブカラー・アクセントカラーに役割分担し、色の比率を意識する。
- 色彩心理を活用してユーザーの印象形成をコントロールし、ブランド力を高める。
- あらかじめルールづくり(配色ガイドライン)を行い、サイト全体で一貫性を保つ。
こうした取り組みを重ねることで、企業のメッセージと色がしっかりリンクし、ユーザーの印象に残りやすくなります。「色を減らす=地味になる」と決めつけるのではなく、「少ない色で最大限のインパクトを出す」ための工夫を取り入れてみてください。きっとサイトが持つ魅力やブランドイメージが、より一層引き立つはずです。






