Blog お役立ちブログ
試作・サンプル品をアピールする特設ページが生むBtoB受注の秘訣
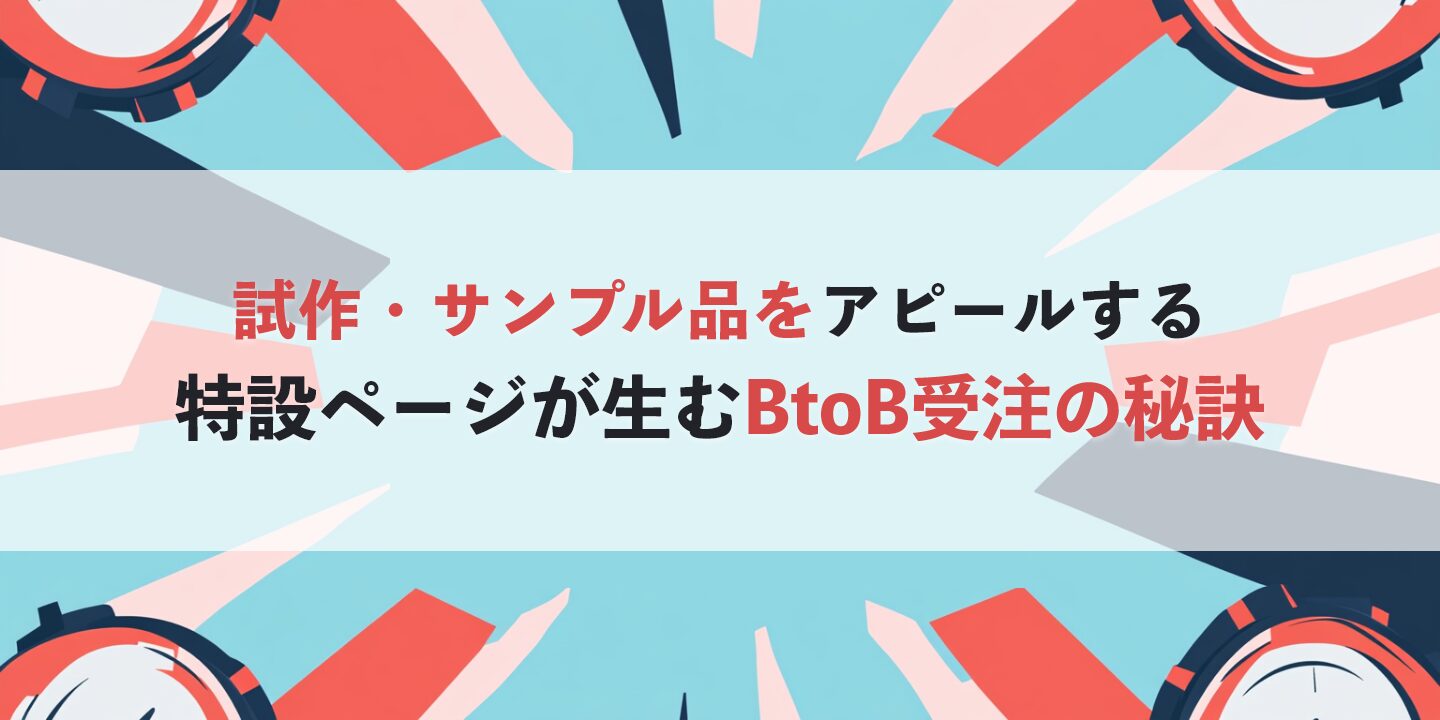
特設ページの役割と特徴
中小企業の製造業が新たな取引や大手企業からの問い合わせを獲得するには、自社の技術力や対応力を分かりやすく示す必要があります。従来はカタログやパンフレットを用意して直接営業する形が一般的でしたが、近年ではWebでの情報発信がさらに重視され、特設ページというかたちで専門的な情報をまとめる手法が注目されています。
特設ページの特徴は、単に製品カタログを並べるだけでなく、“見込み客の興味関心を強く引き付ける要素”を盛り込んだ構成にあるといえます。特に、試作やサンプル品を紹介する場合には、実際の事例写真、開発ストーリー、こだわりの技術ポイントなどをわかりやすくまとめることで、「こんなものが作れますよ」という具体的なイメージを持ってもらうことが大切です。
また、特設ページは単独で完結せず、会社案内や他の実績紹介ページとリンクさせることで自社全体の強みを伝える役割も担います。シンプルに「こんな試作ができます」と説明するだけでなく、その背景や独自の価値を訴求する工夫が重要になるのです。
試作・サンプル品を効果的に見せるポイント
BtoB受注を狙う場合、取引先は「自社の要望に応えてくれる技術や対応力があるか」という視点でサイトを閲覧します。試作やサンプル品を紹介する特設ページで効果的にアピールするには、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
- 具体的な仕様や素材への言及
「こういう素材も扱える」「こういう加工技術に対応できる」という記述があると、潜在的な依頼主が「うちの案件も対応可能かも」と想像しやすくなります。 - 開発ストーリーや課題解決の流れを示す
ただ「作りました」だけでなく、「どんな課題があって、どのようなアイデアで解決したか」を伝えると説得力が増します。 - 大まかな納期や対応フローを記載
BtoBの商談はスピードが重要になる場面も多いものです。特設ページで目安の納期や対応フローを示すと、打ち合わせ前のハードルが下がります。 - 他社にはない独自の技術力を強調
「自社だけの特許技術」「長年積み上げたノウハウ」など差別化ポイントを見せると、興味を引きやすくなります。
下記の表では、特設ページに盛り込むと効果的な要素をまとめています。特設ページ作りの参考として活用してみてください。
| 要素 | 内容の例 |
|---|---|
| 実際のサンプル写真 | 仕上がりの様子や製品の用途がイメージしやすい角度・背景で撮影した写真 |
| 開発ストーリー | なぜ製作に至ったか、技術的に苦労した点や克服策、最終的に得られた成果 |
| 技術的なポイント | 使用した素材の特徴、加工技術、独自のノウハウなど専門性を含めた解説 |
| 期待できる効果 | 「軽量化に成功」「コスト削減につながった」など、製作物がもたらすメリット |
| 対応できる範囲 | 大きさ・素材・数量・納期など、受注可能なスペックと条件 |
大手企業から注目されやすい要素とは
大手企業が下請けや協力会社を選ぶ際、最も重視するのは「確実に納品してくれそうか」「高品質・安定供給ができるか」「コスト管理はどうか」という点です。特設ページでも、このような視点でアピールする内容があると問い合わせにつながりやすくなります。
信頼感の醸成
大手企業は取引相手に対して厳格なチェックを行いがちです。社内体制や品質管理の手順がどうなっているか、ISOなどの認証取得状況があるかなど、比較的細やかな情報を必要とすることが少なくありません。そこで、特設ページの中で「品質管理体制」や「生産管理のフロー」を簡潔に整理し、一般公開できる範囲で伝えておくことが有効です。
過去の協力実績や受賞歴
「実績紹介」として取り上げる際、可能な範囲で大手企業との共同プロジェクトや納入実績などを示すと信頼度が高まります。守秘義務の関係上、具体的な社名を出せないケースもあるでしょう。その場合は、業種や製作物の概要をぼかして記載する形でも問題ありません。さらに、業界で表彰された経験や展示会に出品した事例などがあれば、積極的にアピールしましょう。
製造工程の可視化
「どのように作っているのか」を写真や簡単な動画で伝える方法は、大手企業が感じる“相手の製造過程への不安”を払拭する一助となります。特設ページ内に図解やフローチャートを置くのも、視覚的に理解しやすくおすすめです。
成功事例から学ぶ実績紹介の仕方
実績紹介は、特設ページの中でも重要な役割を担います。自社の過去事例や開発ストーリーがどのように書かれているかで、サイト訪問者の印象や信頼度が大きく左右されるからです。
以下の表では、実績紹介の見せ方と、その効果を簡単にまとめています。
| 実績の見せ方 | 効果 |
|---|---|
| 写真や動画でビフォーアフターを比較する | 視覚的な変化が明確となり、成果物の価値を訴求しやすい |
| インタビュー形式で背景を語る | 実際の担当者の声から具体的な制作意図や工夫点を把握できる |
| 事例ごとに成果を短文でまとめる | 「改善前→改善後」が一目で分かり、サイト訪問者の理解が進む |
| 失敗談やトラブルシュートを記載する | 問題解決能力や柔軟な対応力をアピールできる |
実績紹介ページと特設ページは、しばしば混同される場合があります。しかし、試作・サンプル品にフォーカスしてBtoB受注を強く狙うのであれば、「実績紹介ページをまとめて一箇所に置く」よりも、「個別の特設ページ」でより深く掘り下げて紹介する方が効果を発揮することが多いです。理由としては、以下のような点が挙げられます。
- 訪問者の興味度合いに応じた情報量の調整がしやすい
一般的な実績一覧ではスペースの都合で情報を詰め込みづらいですが、特設ページなら技術の背景や製造工程などをじっくり解説できます。 - SEO面でのアプローチがしやすい
実績紹介ページが一枚のページにまとまっている場合、キーワードの最適化が難しくなりがちです。特設ページとして個別化すれば、検索エンジンに対してもより専門性の高いコンテンツとして評価されやすくなります。
特設ページ制作の流れと運用の注意点
特設ページの制作は、計画を立てずに急いで作ってしまうと「更新が大変」「構成が分かりにくくなる」といった問題につながりやすいです。以下のステップに沿って進めると、比較的スムーズに運用まで行き着くことができます。
- ターゲット選定と目的の明確化
- 「どの業種のどんな企業に向けてアピールしたいのか?」
- 「どの技術や製作物を強く打ち出したいのか?」
これをはっきり言語化しておくと、後のページ構成やデザインにも反映しやすくなります。
- 構成案とコンテンツ準備
- 写真素材、動画素材、開発ストーリーなどを整理
- 見出しごとのテーマを決めて情報を配置
特設ページは写真や図版が多くなる傾向にあります。できるだけオリジナルの素材を用意すると説得力が増します。
- 制作・実装
- デザインとコーディング
- レスポンシブ対応や読み込み速度のチェック
大手企業の担当者もスマートフォンやタブレットで閲覧するケースが増えています。レスポンシブデザインは必須です。
- 公開前チェック・校正
- 誤字脱字、重複表現、レイアウト崩れなどを入念にチェック
- 自社の強みがしっかり伝わる導線になっているか再確認
特設ページの印象は、細部のクオリティでも左右されるので丁寧な確認が欠かせません。
- 公開・周知
- 既存顧客への案内、SNSなどでの告知
- 社内外での周知徹底
特設ページを作っただけでは十分な効果を得にくい場合もあります。周知・告知を合わせて行い、アクセス増加を促しましょう。
更新・メンテナンス体制の重要性
特設ページは作って終わりではありません。実際の受注状況や顧客からのフィードバックを反映しながら、更新・改善を重ねることで効果を持続させることが大切です。社内にウェブ担当がいない場合は、制作会社や外部パートナーと連携して定期的にメンテナンスを行う仕組みを作ると良いでしょう。
下記の表に、メンテナンス時に確認すべきポイントと具体的な対策例を示します。
| 項目 | 対策例 |
|---|---|
| 掲載情報の古さ | 古い写真や情報は定期的に見直し、必要に応じて新しい実績や写真に差し替える |
| 受注や問い合わせ内容の分析 | お問い合わせフォームの内容やアクセス状況を振り返り、興味が集まる技術を強化 |
| サーバーやセキュリティの確認 | CMSやプラグインのバージョンアップ、アクセス負荷のチェックを怠らない |
| 文章表現の改良 | 業界用語の多用は避け、わかりやすい言葉に書き換えるなど、ユーザー目線を優先する |
継続的に情報を更新することで、検索エンジンからの評価が保たれるだけでなく、「最新の情報を提供している製造業」として取引先からの印象も良くなります。逆に古い情報のまま放置されていると、「この企業は今も同じ技術でしか対応できないのだろうか」と不安を招く可能性もあるので注意が必要です。
まとめ
試作やサンプル品をアピールする特設ページは、単なるカタログの延長ではなく、自社が持つ技術力や信頼性をストーリー仕立てで伝える場として捉えると、BtoB受注を狙ううえで大きな効果を発揮します。ポイントは「見る人の視点に立ち、なぜ自社の試作に価値があるのかを具体的に示すこと」と、「制作後の更新・運用体制を整えて常に最新の情報を届けること」です。これらを意識してページを作成・運用すれば、大手企業を含む新規顧客との接点が広がり、ビジネスチャンスを引き寄せる可能性が高まるでしょう。






