Blog お役立ちブログ
自社ブログの更新を外注するときの進め方と注意点
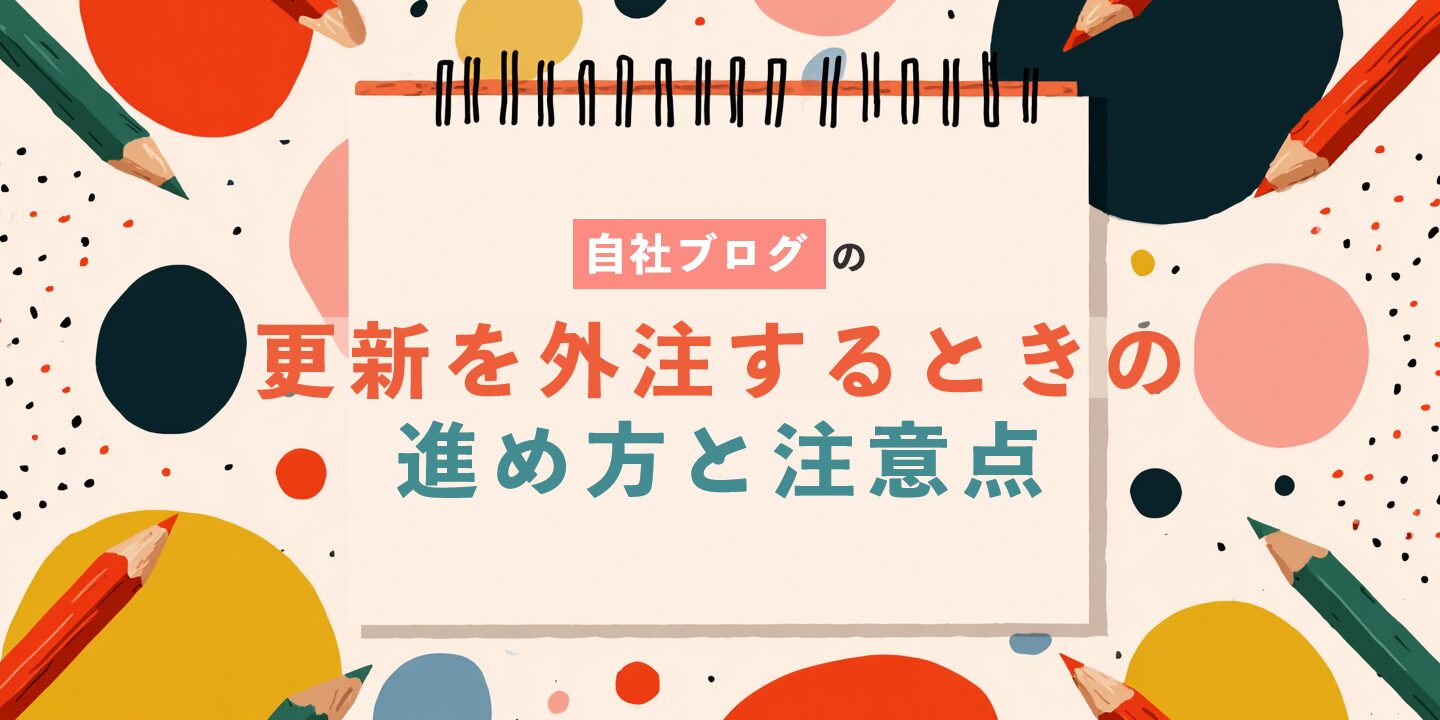
自社ブログは顧客との接点を増やし、検索流入を伸ばす最強の資産です。しかし経営者が直接キーボードに向かう時間は限られ、専門用語を平易に書き換えるスキルも社内にはなかなかありません。そこで有力な選択肢になるのが「外注」という手段です。本章ではまず「なぜ外注するのか」を整理し、その前提となる社内準備とパートナー選定の視点まで解説します。
なぜ自社ブログを外注するのか
時間不足の解消
日々の見積り、現場立会い、品質チェック――経営者の仕事は多岐にわたります。ブログ更新を外注すれば、1本2〜3時間を要する記事作成作業を手放し、本来注力すべき経営判断に集中できます。
自社ブログ運用を社内で完結しようとすると、ライター採用から育成、企画立案、画像手配、CMS入稿、公開後の分析まで多段階のプロセスが待ち構えています。外注はこの一連の作業を“パッケージ”として依頼できるため、業界平均で1本あたり3〜5時間短縮できるというデータもあります。浮いた時間を顧客面談や新規事業検討に充てることで、ブログ投資をはるかに上回るリターンを得る企業も少なくありません。
専門性の担保
ライターには業界知見が必須です。建築なら一級建築士監修、機械なら技術士監修の体制を敷くことで、一次情報を損なわない記事を量産できます。
専門性の担保については「監修者付き」「技術ライター2名体制」など外注先の体制を確認しましょう。例えば機械メーカーの場合、設計図面を外部に渡せないケースがあります。その場合はNDAを結んだ上で図面をマスキングし、要素技術だけを共有する方法が一般的です。外注側がリバースエンジニアリングに強いと、図面を渡さずともヒアリングだけで精度の高い記事を起こすことも可能です。
コスト効率
人件費と比較して外注費が高いと感じるかもしれませんが、採用・教育・離職リスクまで含めれば、成果物ベースで支払える外注は総コストを抑えやすい手段です。
コスト効率を測る際は“単価×本数”だけでなく、企画会議・社内確認・修正対応に割く時間単価も加味します。時給5,000円相当の経営者が月5時間レビューに費やせば、それだけで25,000円の機会損失です。外注費10万円が高いか安いかは、こうした隠れコストを可視化してはじめて判断できます。
| 視点 | 外注 | 内製 |
|---|---|---|
| 時間投資 | 要件定義と確認のみ | 企画〜執筆〜校正をすべて担当 |
| 費用構造 | 成果物単価×本数 | 固定人件費+間接コスト |
| ノウハウ蓄積 | 専門ライターの知見を享受 | 社内にスキルを蓄積可能 |
| スピード | 外部リソースで即増強可 | 人員補充に時間がかかる |
外注前に整理しておくべき自社情報
ペルソナと目的
自社ブログが狙う読者像とゴール(問い合わせ、資料DL、採用応募など)を明文化しておくと、ライターはブレずに文章を組み立てられます。社内会議で散発的に語られる“なんとなく”のターゲット像を文書化するだけで、記事の訴求点は劇的に鋭くなります。
トーン&マナー
「職人らしい温かみ」「メーカーらしい厳格さ」など、ブランドイメージを示すガイドラインを作りましょう。文体例を3〜5パターン示すと共有が円滑です。誤字脱字よりもブランド毀損となり得る語調のズレを防ぐ効果があります。
社内リソースと責任範囲
誰が原稿確認を行い、校閲は何営業日以内に返すかを決めておくと、スケジュール遅延を防げます。特に複数部署が関与する場合は、承認フローを図式化して外注先に渡すと誤解が起こりません。
| 整理すべき自社情報チェックシート | 例 | メモ |
|---|---|---|
| ペルソナ | 建材を比較検討中の30〜50代 | 詳細プロフィールを添付 |
| KGI/KPI | 月間問い合わせ20件 | 3か月単位で見直し |
| トーン&マナー | 信頼感重視、技術詳細も記載 | 禁止表現も記載 |
| 承認フロー | 営業→技術→社長 | 48時間以内に返信 |
外注パートナー選定のチェックポイント
実績と専門領域
建築記事の実績があるか、機械安全規格ISO13849に触れた記事を書いた経験があるかなど、ポートフォリオを必ず確認します。検索順位やCV数など成果指標を公開できる外注先は信頼度が高い傾向にあります。
品質管理体制
複数ライターを束ねる編集者がいるか、校閲フローが明確かが品質を左右します。SOP(標準作業手順書)の有無や、校正ツール導入状況も評価軸になります。品質保証書を提示できる外注先なら、納品後の手直し負担が大幅に減ります。
契約形態と料金モデル
文字単価、記事単価、月額運用の3タイプがあります。初期は記事単価でスタートし、安定したら月額運用へ移行する企業が多いです。それぞれの長所短所を把握し、自社の更新頻度と内部工数に合わせて選択しましょう。
外注先を比較する際には、見積書の単価だけでなく「運用提案力」にも目を向けてください。たとえば隔週更新を提案する会社と週次更新を提案する会社があった場合、単価がやや高くても企画会議と効果測定までワンストップで担う週次更新プランのほうが、中長期的な費用対効果は高くなるケースが多くあります。
また、料金モデルを選ぶ際はリスクヘッジの観点から“段階的契約”を推奨します。最初の1か月はお試しで2本だけ発注し、記事の品質とコミュニケーションを確認。その後、4本→8本とスケールさせる流れにすると、失敗コストを抑えつつ安定運用へ移行できます。
ここまでを整理すると「外注が向いている企業」は次の三つに集約されます。
- 社長または少数精鋭のスタッフが多能工化しており、執筆時間を捻出できない
- 高度な専門知識をユーザー目線に翻訳してくれる第三者を必要としている
- 社内人件費より成果物単価で支払うほうが総コストが下がる
逆に「内製が適している企業」は以下のようなケースです。
- 執筆が得意な社員が在籍し、記事制作を教育と育成の機会にしたい
- ノウハウを社内に蓄積し、将来的にメディア運営を事業化したい
- 機密情報の関係で外部に開示できない資料が多い
どちらを選ぶにせよ、重要なのは「自社の経営目標に沿った形でブログを運用する」ことです。そのための第一歩が、外注前のゴール設定と社内フローの整備であると覚えておきましょう。
最後に、外注プロジェクトを軌道に乗せるために欠かせないのが「編集カレンダー」です。月初に1か月分のテーマと公開日を決定し、原稿締切とレビュー期限をカレンダーに落とし込みます。これにより、ライター・編集者・社内確認者のタスクと責任が可視化され、遅延の予兆を即座に発見できます。
編集カレンダーはスプレッドシートで十分機能しますが、タスク管理ツールと連携すればリマインド通知も自動化でき、確認漏れを防ぎます。こうした運用設計まで提案できる外注パートナーこそ、長期戦となるブログ運営の真の味方になるでしょう。
発注から公開までの具体的フロー
外注を成功させる鍵は「工程を細分化し、合意のうえで進める」ことです。曖昧な状態で書き始めると、修正回数が極端に増え、スケジュールも膨張します。ここでは実務で最も採用される五段階フローを紹介します。自社の承認プロセスに合わせて調整してください。
1. キックオフミーティング
発注側と外注側が同席し、目的・KPI・担当者・連絡チャネルを確認します。初回は1時間程度で十分ですが、録画や議事録を残し、後日の認識ズレを防ぎます。
2. 要件定義
記事フォーマット、文字数、画像枚数、引用ルールを文書化します。難解な専門語は「用語集」にまとめ、ライターと共有しましょう。
3. プロトタイプ記事
本番前に1本だけ試作し、トーン&マナー・見出し構造・SEO設計を評価します。合格点をクリアしたら量産フェーズへ進みます。
4. 量産フェーズ
月4〜8本程度を目安に、編集カレンダーに沿って執筆→レビュー→修正を繰り返します。レビュー期限を48時間以内に設定すると、公開サイクルが安定します。
5. 公開・効果測定
CMSに入稿し、公開後は検索順位・流入・滞在時間を計測。記事単位でKPI達成率を可視化し、次月のテーマ決定に反映します。
| 工程 | 主担当 | 期間の目安 | 成功のポイント |
|---|---|---|---|
| キックオフ | 発注・外注 | 1日 | 目的とKPIを文書化 |
| 要件定義 | 発注側 | 3日 | 用語集を共有 |
| プロトタイプ | 外注側 | 5日 | 合意形成を最優先 |
| 量産フェーズ | 外注側 | 継続 | レビュー48hルール |
| 公開・測定 | 発注側 | 毎記事 | 指標を月次で報告 |
品質を確保するためのチェックリスト
品質は納品時ではなく「工程ごと」に管理することで、手戻りを最小化できます。以下は実務で使われるチェックリストの一例です。自社の業界特性に合わせてカスタマイズしてください。
執筆前チェック
- 目的とペルソナが明文化されているか
- 参照資料は最新版か
- 禁止表現・避けるトーンが共有済みか
執筆中チェック
- 見出しタグの階層が正しいか
- 専門用語に一次説明が添えられているか
- 引用元URLが原典かつ信頼できるか
納品時チェック
- 誤字脱字ゼロか(校正ツール+人の目でダブルチェック)
- 画像にaltテキストが入っているか
- メタディスクリプションが120文字前後で設定済みか
| 工程別チェック項目 | 例示基準 | 合格ライン |
|---|---|---|
| 執筆前 | 目的記載率 | 100% |
| 執筆中 | 用語解説率 | 90%以上 |
| 納品時 | 誤字脱字 | 0件 |
チェック項目をスプレッドシート化し、担当者列に「ライター」「編集」「技術監修」「最終承認」を設定すると、誰がどこで止めているか一目で分かります。これだけで修正依頼メールの往復が半減したというケースも珍しくありません。
外注で起こりがちなトラブルと対策
スケジュール遅延
原因: レビュー担当者が多忙で確認が滞る
対策: あらかじめ「代理承認者」を指名しておく
品質バラつき
原因: ライターによる執筆品質の差
対策: スタイルガイドとサンプル記事で基準を数値化
コスト増大
原因: 追加修正が発生し文字数が膨らむ
対策: 初回要件定義に「想定修正回数」を明記し、超過分は別途見積り
| トラブル | 典型症状 | 初期サイン | 予防策 |
|---|---|---|---|
| 遅延 | 公開日未定のままズレ込む | レビュー未完了が24h超 | 代理承認 |
| 品質不足 | 読者離脱率↑ | 校正指摘が多い | スタイルガイド |
| 費用膨張 | 追加見積り連発 | 修正指示が曖昧 | 回数上限明記 |
こうしたトラブルは「起こり得る前提」で契約書と運用ルールに落とし込むことで、大半を未然に防げます。特に中小企業では“言った言わない”が致命的になりやすいので、Slackやメールのログを残し、定例MTGで合意事項を読み上げる運用を推奨します。
進行管理を強化するツール活用術
外注プロジェクトは距離と時間帯が異なるメンバーで進むため、ツール選定が成果を左右します。以下はよく使われるSaaSと活用ポイントです。
コミュニケーション
- Slack: スレッド機能でテーマ別に議論を整理。原稿URLを貼るだけでプレビューできるため確認がスムーズ。
- Teams: Office連携が強く、Word原稿をそのまま添削したい企業向き。
タスク管理
- Trello: 工程を「To Do/Doing/Done」で可視化。納期をカードに設定して期限切れアラートを自動化。
- Asana: ガントチャート表示が可能。複数記事を横断した進行を俯瞰できる。
ドキュメント
- Google Docs: 同時編集と変更履歴が強力。承認前の修正過程も保存されるため、責任所在を追跡しやすい。
- Notion: 用語集とスタイルガイド、公開記事のURLを一元管理。検索性が高く、後から参画したメンバーもキャッチアップしやすい。
ツールは多機能であるほど良いわけではありません。重要なのは「誰が」「いつ」「何を」行うかを一目で把握できること。最低限、コミュニケーションツールとタスク管理ツールの二つが連携し、通知が迷子にならない構成にしましょう。
社内リソースを活かしたハイブリッド運用
完全外注ではなく「企画は社内、執筆は外注」というハイブリッド型も有効です。たとえば機械メーカーでは技術部がテーマだけをリスト化し、ライターが記事化、最終校閲を品質保証部が行う三段階体制がよく採用されます。
ハイブリッド型のメリットは、専門性を担保しつつ執筆負荷を下げられる点です。一方、工程が増えるため納期管理がシビアになります。ガントチャートを共有し、各担当の遅延がどこに波及するかを全員が把握できる状態をつくりましょう。
外注比率が高いほどスピードは上がりますが、自社にノウハウが残りにくくなります。逆に社内比率が高いほど教育効果は期待できますが、担当者変更時に運用が止まるリスクが増加します。経営資源の状況に応じて、四半期ごとに最適比率を見直すことが、長期的なブログ成長のカギとなります。
KPI設定のコツ
外注後の成果を測る指標は「検索流入数」だけでは不十分です。指名検索増加率や記事経由の商談化率も追うことで、投資対効果を多角的に把握できます。特に工務店では「来店予約」、機械メーカーでは「カタログ請求」が直接的な成果指標になります。KPIを三層(集客・興味・行動)に分け、四半期ごとに進捗レビューすると、施策の成否を正確に評価できます。
外注費用とROIの考え方
外注費用は「記事単価×本数」で単純計算しがちですが、それだけでは損益を正確に把握できません。重要なのは「投下コストがどの時点で回収できるか」を時系列で示すことです。
- 直接費
- 記事制作費(例:1本4万円×月4本=16万円)
- 画像購入費(1記事2点×3,000円=6,000円)
- 間接費
- 社内レビュー工数(2h×5,000円/h×月4本=4万円)
- KPIレポート作成(1h×5,000円)
- 成果指標
- 検索流入:月間+2,000セッション
- コンバージョン:月10件(成約率30%、客単価50万円)
| 項目 | 月額コスト | 年間コスト | 年間売上寄与 | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 直接費 | 166,000円 | 1,992,000円 | ||
| 間接費 | 45,000円 | 540,000円 | ||
| 合計 | 211,000円 | 2,532,000円 | 1,800万円 | 約7.1倍 |
上記の例では、投資額を回収するまで約2か月、1年後には7倍超のリターンが見込めます。外注費は“コスト”ではなく“投資”として捉えることで、社内稟議も通しやすくなります。
成果を最大化する運用ポイント
継続的なキーワードリサーチ
検索ニーズは季節やトレンドで変化します。四半期ごとにキーワードを見直し、既存記事のリライト計画を立てましょう。新規作成よりリライトのほうが制作コストを3割抑えつつ、上位表示を狙いやすいのが特徴です。
クロスチャネル連携
ブログ単体で完結させず、メルマガやSNSと連動させることで読者との接触回数を増やせます。特に商工会など地域密着型組織では、ローカルニュースレターにブログ記事を転載し、オフライン流入をオンラインに誘導するといった施策が効果的です。
データドリブンな改善ループ
月次レポートで「記事別CV」「平均滞在時間」「離脱ページ」を可視化し、改善案を翌月の編集会議に反映します。このPDCAを12サイクル回すだけで、トップページの流入源が検索からブログに置き換わった事例もあります。
人材育成との両立
外注に任せきりにせず、社内メンバーが下書きを書き、プロライターがリライトする“レビュー支援型”を導入すると、社員の文章力が自然と向上します。将来的に内製へシフトしたい企業は、早期からこうしたノウハウ移転型スキームを組み込むと移行コストを抑えられます。
まとめ
自社ブログの外注は、時間・専門性・コストという三つの壁を一挙に乗り越える有効な手段です。しかし成果を最大化するには、
- 目標とペルソナを明文化し、
- チェックリストと編集カレンダーで品質と進行を管理し、
- KPIを多層で設計してROIを定量化する――
という三段階の設計が欠かせません。この記事を指針に、外注パートナーとの協業体制を整え、長期にわたって資産価値の高いブログを育ててください。






