Blog お役立ちブログ
社名変更したのに古いドメインはどうすればいい?最適な運用法を解説
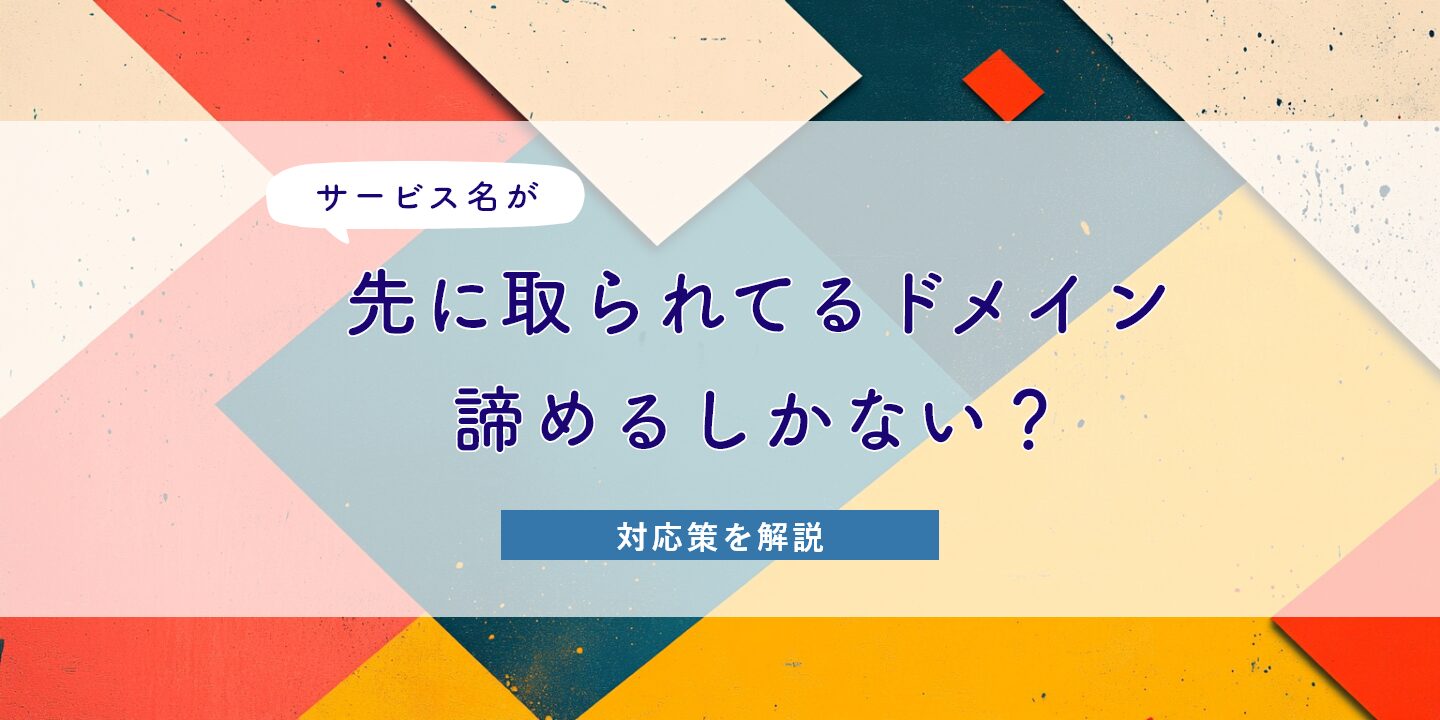
社名変更とドメインの関係性
中小企業が社名変更を検討する背景には、事業拡大やリブランディング、新サービスの開始などさまざまな理由があります。実際に社名を変更することで、新たなブランドイメージや企業ビジョンを広く発信しやすくなるというメリットがあります。
一方で、ウェブサイトのドメインは一度取得すると継続して使うケースが多く、「社名変更をしてもそのまま古いドメインを使い続けて良いのだろうか?」と疑問を持つ方も少なくありません。新しい社名に合わせてドメインも変えるべきか、あるいは古いドメインのまま運用しても問題ないのか。結論はケースバイケースですが、両者にはメリットとデメリットが存在します。
本記事では、古いドメインを使い続ける場合と、新しいドメインへ切り替える場合のメリット・デメリットを整理し、移行手順やリダイレクトのポイントを解説します。特にSEOやブランド認知にかかわる重要なテーマなので、それぞれの企業環境やリソースを踏まえた最適な選択をする手がかりにしていただければと思います。
古いドメインを使い続けるメリットとデメリット
まずは、社名変更後にも古いドメインを継続使用するケースです。何も作業をしないまま使い続けるのは手間も少ないように見えますが、実際はデメリット面も考慮する必要があります。
メリット
- 被リンクや検索エンジン評価の継承
長年運営してきたドメインには、多くの被リンクが集積している可能性があります。検索エンジン上でも一定の評価が得られている場合、新ドメインに切り替えるよりも「評価を失いにくい」という利点があります。 - SEO順位の安定
ドメイン変更に伴うサイトの大幅なリダイレクト作業が不要になるため、検索順位への影響が少ないと考えられます。とくにドメイン移行時に起こる可能性がある一時的な順位下落を回避できます。 - 手間やコストが抑えられる
新ドメイン取得費用や、ウェブサイト内のリンク修正、リダイレクト設定など、大がかりなリニューアル作業が不要になります。人的リソースやコストの削減につながるでしょう。
デメリット
- ブランドとドメイン名の不一致
新しい社名にまったく合わないドメインを使い続けると、企業イメージやブランディング面で違和感が生じます。名刺や広告物などで「新社名」と「旧ドメイン」が混在すると、顧客や取引先が混乱する恐れがあります。 - 今後のブランド価値の蓄積に不利
ブランディングを強化する上で、社名やサービス名と一致するドメインを使用したほうが長期的には覚えやすく認知されやすいです。古いドメインを使い続けると、新ブランド名で検索された際に一貫性を欠く懸念があり、長期的なリスクをはらみます。 - 社名変更を周知する機会損失
新ドメインへの移行に合わせてプレスリリースなどを発信することが、社名変更の周知やマーケティングの一環になる場合もあります。古いドメインを使い続けると、こうした発信のタイミングを逃す可能性があります。
新しいドメインへ切り替えるメリットとデメリット
続いて、新ドメインを取得し、サイト全体を移行する場合のメリットとデメリットです。ブランディング観点では魅力がありますが、SEOや実務的な面でのリスク管理が欠かせません。
メリット
- 新ブランドイメージの確立
新しい社名やブランド名とドメインを一致させることで、覚えやすく、顧客や取引先にも違和感なく伝わりやすいです。名刺やパンフレット、広告などでの統一感を出し、ブランド認知を一気に高めるチャンスとなります。 - 将来的な資産価値向上
新社名の知名度や評価が高まるにつれ、そのドメイン自体の価値も相乗的に上がります。長期的にはブランド浸透とSEO評価の両立が期待できます。 - リニューアル効果による訴求力アップ
新ドメイン移行を機に、ウェブサイトのデザインやコンテンツを総合的に刷新する場合があります。これにより、ユーザーから見てもサイトが「より新しい・魅力的」だと感じられ、アクセス数や反響が大きくなる可能性があります。
デメリット
- SEO評価の引き継ぎリスク
ドメインを変更すると、古いドメインにあった被リンクや検索エンジン評価を新ドメインへしっかりと継承するために、リダイレクトやサイトマップの再提出などの対応が必要です。作業が不十分な場合、一時的にアクセス数や検索順位が落ちるリスクがあります。 - 移行期間のリソース消費
ドメイン取得手続き、DNS設定、サイト内リンクの変更、リダイレクト設定など、多くの手間と時間、場合によっては費用がかかります。中小企業にとっては負担が大きいと感じることもあるでしょう。 - 周知・告知の手間
名刺やチラシ、既存顧客へのメール連絡など、周知すべき範囲が広いと告知に多くのリソースを割く必要があります。誤った情報が出回ると混乱を招く可能性もあるので、慎重なスケジュール管理とコミュニケーション計画が重要です。
ドメイン移行の基本手順
実際に「古いドメインから新しいドメインへ」切り替える場合の基本的な流れを簡単にまとめます。
以下の表は、大まかな工程とそれに伴う主な作業です。
| 工程 | 主な作業内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 計画策定 | ・新ドメインの取得 ・予算とスケジュールの設定 | ブランディング戦略・運用リソースも合わせて検討 |
| 2. 準備作業 | ・テスト環境で新ドメインを設定 ・URL構造の確認 | リンク切れ防止のため全ページのURLを把握 |
| 3. 移行前告知 | ・既存顧客や取引先への事前アナウンス ・SNSなどで周知 | 移行後のURL変更を分かりやすく伝えること |
| 4. リダイレクト設定 | ・301リダイレクト(恒久的転送)の実施 ・DNS変更 | 正しく設定しないとSEO評価の継承が難しくなる |
| 5. 移行後テスト | ・リンク切れ、表示崩れなど不具合チェック ・検索エンジンへのサイトマップ再送信 | 移行完了後も数週間は経過観察を行う |
| 6. レビュー・最適化 | ・アクセスログや検索順位の変動を確認 ・必要に応じて改善施策を実行 | 移行による順位変動は一定期間発生する可能性あり |
上記の工程をしっかり踏むことで、ドメイン移行時のトラブルを最小限に抑えながら、長期的なSEO評価の引き継ぎを成功させやすくなります。特に301リダイレクトの設定は、旧ドメインで受けていた被リンクの評価を新ドメインへ正しく引き継ぐ上で不可欠です。
具体例:中小企業がドメイン移行を成功させるポイント
ここでは、ある中小企業が社名変更と同時に新ドメインへ移行した例をイメージしてみましょう。
A社の事例(架空のイメージ)
- 旧社名:ABC商事
- 新社名:XYZ株式会社
- 旧ドメイン:abc-company.jp
- 新ドメイン:xyz.jp
A社は社名変更に合わせてウェブサイトをリニューアルすることを決定しました。そこで以下のポイントを意識して作業を行いました。
- サイトのURL構造を整備
新しいドメイン名に合わせて、URLの階層やページ構成をより見やすく再設計。古い不要ページを整理し、サイト全体がスリムで分かりやすいレイアウトに。 - 事前の周知活動
取引先や主要顧客にはメールやニュースレターで新ドメインの開始日を告知。またSNS公式アカウントでも「〇月〇日から新しいドメインへ移行します」と告知し、周知徹底を図った。 - リダイレクト設定の徹底
旧ドメインの各ページから、新ドメインの対応するページへ301リダイレクトを設定。特にリンク人気の高い「商品ページ」や「お問い合わせページ」は漏れがないようダブルチェックした。 - 移行後のモニタリング
新ドメインに移行してから数週間、アクセス解析や検索エンジンの順位変動を綿密にチェック。大きな順位下落はなかったものの、一部ページでアクセス数が減少していたため、すぐに内部リンク強化を実施し、リカバリーを図った。
結果的に、A社は新ドメインに移行した当初はわずかなトラフィック減少を見たものの、1~2か月程度でほぼ回復。その後は新社名とドメインが一致したことでブランディング効果が出やすくなり、SNSや広告での発信力が高まったという成果が得られたと想定されています。
古いドメインを残す場合のリダイレクト設定とブランド浸透策
新社名に完全移行するのではなく、古いドメインをあえて残して、メインは新ドメインを使いつつ古いドメインも活用する選択肢もあります。たとえば、以下のようなケースです。
- 旧ドメインにアクセスしたユーザーを新ドメインのトップページ(または該当ページ)へ301リダイレクトする
- 古いドメインをキャンペーン専用サイトやサービス別サイトなど独立した形で残し、新ブランドへ誘導する仕組みを作る
この場合でも、ポイントとしては「古いドメインから新ドメインへ誘導し、ユーザーや検索エンジンに迷惑をかけない設定」をきちんと行うことが大切です。また、社名変更をしっかり周知するために、以下のようなブランド浸透策が有効です。
- リニューアル告知バナーの設置
旧ドメインにアクセスしたユーザー向けに、「社名が変わりました!新サイトはこちら」といったバナーを掲示し、新ドメインへのリンクをわかりやすくする。 - 期限を決めた運用
古いドメインを永続的に残すのではなく、ある程度の移行期間を定めておき、最終的には新ドメインへ一本化する方針を検討する。 - 名刺や案内状の整理
古いドメインを混在させ続けると、お問い合わせが分散しやすくなる。移行期間を過ぎたら新ドメインへ統一した表記を行い、顧客に徐々に慣れてもらう。
企業によっては、古いドメインも認知度が高かったり、特定サービスでのブランディングが根付いている場合があります。そうしたケースでは、アクセス解析の結果を見ながら、古いドメインを段階的にクローズしていくアプローチも検討できます。
企業規模別の進め方とリソースの考え方
中小企業とはいえ、会社ごとに組織体制や人員、予算規模が異なります。下記の表は、あくまで一例ですが、企業規模感と必要なリソース、対策をまとめたイメージです。
| 規模感 | 想定リソース | 主な課題・対策 |
|---|---|---|
| 社員数が少ない中小企業 | ・担当者1~2名 ・限られた予算 | ・なるべくドメイン変更の工数を減らす ・外部制作会社に部分的に依頼するのも検討 |
| ある程度の人員体制がある中小企業 | ・広報担当やWeb担当複数 ・多少の広告費用 | ・新ブランド周知に合わせたPR活動も同時に行う ・リダイレクト設定と並行してSNS発信強化 |
| 事業拡大期の中小企業 | ・専門のWeb部署 ・一定のマーケティング予算 | ・ドメイン移行を機に大規模リニューアル ・ブランド統一で広告効果を最大化 |
小規模な企業ほど「ドメイン移行の大きな負担を避けたい」という声が多い一方で、将来の成長やブランド力強化を考えるなら、ある程度の投資をかけてでも早めに統一ドメインを運用したほうがメリットを享受しやすいです。判断に迷う場合は、移行時期を段階的に設定し、実務負荷が集中しないようにスケジュール調整を行うとよいでしょう。
表:リダイレクト種類・目的一覧
ドメイン移行時にはリダイレクト設定が重要ですが、リダイレクトにも複数の種類があります。以下の表は主なリダイレクト方法と、それぞれの目的・特徴を示したものです。
| リダイレクト方式 | 用途 | SEO評価への影響 |
|---|---|---|
| 301リダイレクト | 恒久的な転送 最推奨 | 被リンクや検索評価をほぼ継承できる |
| 302リダイレクト | 一時的な転送 テスト用など | 一時的な転送として扱われる場合が多く、評価移転は不十分なことが多い |
| 307リダイレクト | 一時的転送 HTTP/1.1の仕様 | 302と似た用途。恒久転送としては推奨されない |
| メタリフレッシュ | ページ内でのリダイレクト | ユーザー体験は悪化しがち。SEO面でも301ほどの効果は期待薄 |
ドメインを変更するときは、基本的に「301リダイレクト」を利用し、検索エンジンが「このページは新ドメインに恒久的に移行しました」と正しく認識できるようにすることが鉄則です。
ドメイン移行チェックリスト
実際にドメイン移行作業を行う際は、チェックリストを用意するとミスが減ります。以下に一例を示します。
| チェック項目 | 実施済み | コメント・備考 |
|---|---|---|
| 新ドメインの取得・設定が完了しているか | DNS設定が反映されるまで時間がかかる場合あり | |
| サイト内リンクの全修正 | 相対パス/絶対パスを含めて総点検 | |
| 301リダイレクトの設定 | 旧URL→新URLに問題なくリダイレクトされるか確認 | |
| サイトマップの更新・再送信 | 検索エンジンにインデックスを促す | |
| アナリティクス設定の更新 | トラッキングIDが正しく導入されているかチェック | |
| 社外向け告知(メール、SNS等) | 変更時期と新URLを明確に案内 | |
| 古いドメインのSSL証明書更新状況 | リダイレクト用に古いドメインのSSLが必要な場合あり | |
| 不具合チェック(スマホ・タブレット) | デバイスごとにデザイン崩れやエラーがないか確認 |
こういったリストを事前に用意しておくと、移行後の不具合や問い合わせ対応に追われるリスクが軽減され、スムーズにブランド浸透へ移行できます。
まとめ
社名変更とドメインの問題は、実際に手を動かす担当者にとって大きな悩みになりがちです。古いドメインを使い続ける場合は、既存のSEO評価を維持できるメリットがある反面、ブランド名との不一致が長期的に企業イメージへ影響を与える懸念があります。一方で、新しいドメインへ切り替える場合は、ブランディングを強化しやすい利点があるものの、リダイレクト設定や周知活動に手間と時間がかかります。
どちらを選ぶかは、企業の事業戦略やリソース状況、今後の成長計画などを総合的に考慮して決めるのが最善です。大切なのは、どちらの選択肢をとっても「ユーザーや検索エンジンに対して正しい情報を提供すること」です。リダイレクトの適切な設定や周知方法を誤ると、アクセス数の減少や混乱を招きかねません。
中小企業の場合、限られた人員や予算のなかで効率よくドメイン移行を進めたいと考えるのは自然なことです。まずは現状のドメインがどれほど被リンクやSEO評価を蓄積しているのかを把握しつつ、ブランド強化による長期的なベネフィットと天秤にかけ、綿密なスケジュールとチェックリストを用意して進めましょう。最初の移行計画段階でしっかりと方向性を固め、必要に応じて外部の専門家や制作会社と連携しながら進めると、社名変更とドメイン移行をスムーズに両立できるはずです。






