Blog お役立ちブログ
会社案内動画って需要あるの?作るメリットは?
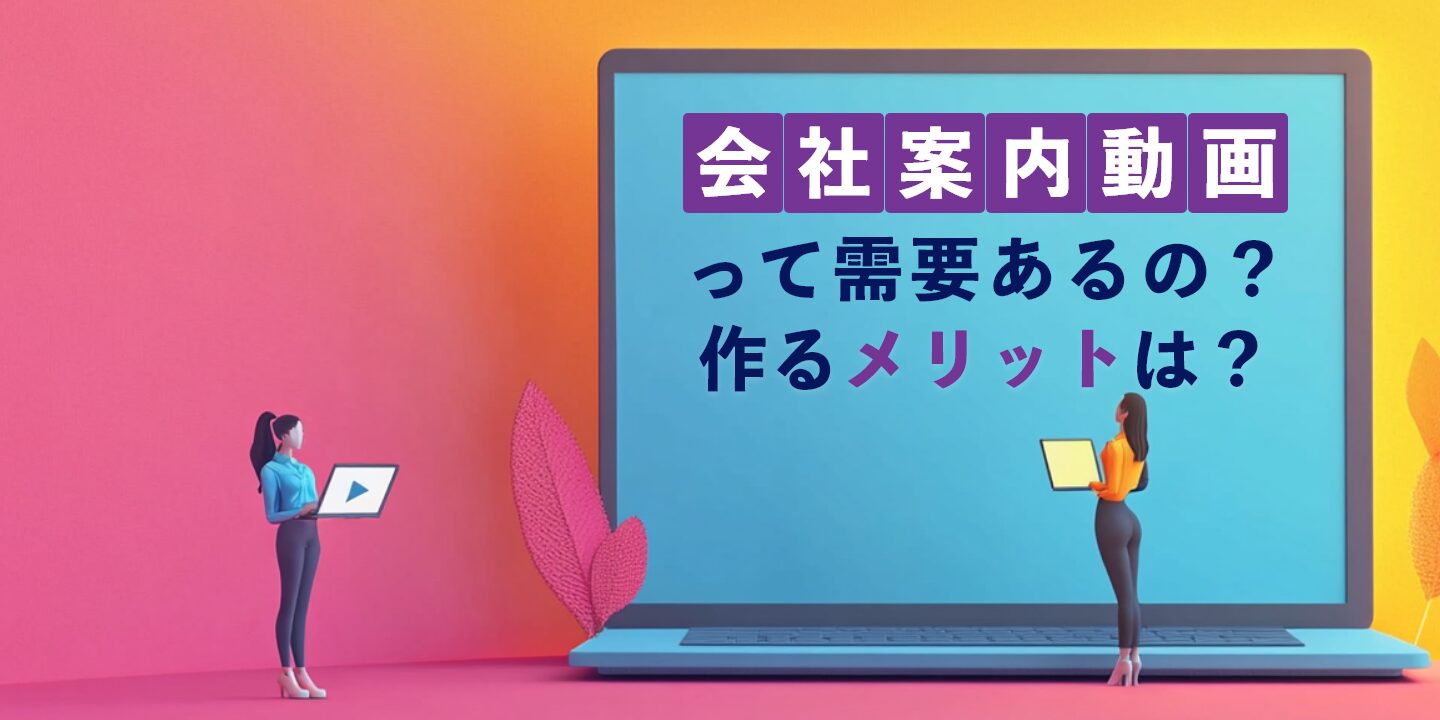
会社案内動画とは何か
会社案内動画とは、中小企業を含むさまざまな企業が、自社の事業内容や理念、サービス概要を映像でわかりやすく伝えるために作成する動画コンテンツのことです。テキストや写真と比べ、視覚と聴覚に直接訴求できる特性があります。そのため、動画を活用することで、企業の魅力や特徴を短時間で効果的に伝えられる可能性が高まります。
例えば、これまでは会社案内パンフレットやホームページの「企業情報」のページを読んでもらうだけだったところを、動画を通じてよりスピーディに社内の雰囲気やサービスの流れを伝えられます。見てもらう人にとっては、文章を長々と読むよりも、実際の映像を目で追うほうが理解しやすい場合が多いのです。
さらに、近年ではウェブサイト上だけでなく、SNSやオンライン展示会などの場面で動画が活用されるケースが増えました。そのため、会社案内動画を「どのような場面で見せたいか」を明確にすることが、効果的な動画制作の出発点となるでしょう。
なぜ需要があるのか
会社案内動画の需要が高まっている背景には、以下のような要因があります。
- 視聴環境の変化
スマートフォンやタブレットなど、外出先でも気軽に動画を視聴できる環境が整いました。通信速度の高速化やSNSの普及により、動画コンテンツへのアクセスが容易になっています。 - 情報量の増大
インターネット上には膨大な情報があふれています。文章だけでは伝えきれない内容や企業の雰囲気を、映像なら短時間で集約して見せることが可能です。 - オンライン商談・説明の普及
オンライン会議ツールやウェビナーなどが浸透し、画面越しでも相手の企業を理解してもらわなければならないケースが増えました。このとき、動画を併用することで企業の全体像をスムーズに伝えられます。 - 差別化・信頼感の醸成
動画によって社内の様子や実際のサービス風景をリアルに見せることは、「この会社はどんな人がどんなふうに動いているのか」を具体的に伝えます。結果として、テキストや画像のみの情報発信とはひと味違うアピールができるのです。
このように、企業規模の大小にかかわらず、「動画でわかりやすく魅力を伝えたい」「より多くの人に興味を持ってもらいたい」というニーズが高まっていることが、会社案内動画への需要を支えています。
会社案内動画を作るメリット
次に、「会社案内動画にはどんなメリットがあるのか」を具体的に整理してみましょう。代表的なメリットは以下のとおりです。
- 理解度・印象度が高い
文章や画像と比べ、動画は動きと音声を伴うため、視聴者に強い印象を残しやすいといわれています。視覚と聴覚の両方から訴求できるので、企業のイメージやサービスの内容が相手に届きやすくなります。 - 差別化につながる
テキストや静止画では似たり寄ったりになりがちな情報も、動画であればオリジナリティを出しやすくなります。企業の雰囲気や代表者の思いを直接伝えるなど、差別化ポイントを魅力的に演出できます。 - 信頼感・安心感の向上
代表者のメッセージや社内風景、事業の実績などを動画で見せることで、視聴者は企業の実体をより身近に感じやすくなります。結果として「信頼できそうだ」「安心して取引できる」というポジティブなイメージにつながります。 - SNSやオンライン展示会での拡散・活用
自社サイトに載せるだけでなく、SNSやオンラインイベント、メールマガジンなどでも活用が可能です。文字だけの投稿よりも目を引きやすく、SNSで拡散されるチャンスも高くなります。 - 長期的な情報資産に
一度制作した会社案内動画は、撮り直しや編集さえ行えば長期間活用できます。営業ツールとしてもイベント用資料としても利用できるため、事業拡大や新規顧客開拓の際に役立つ資産となります。
以上のように、会社案内動画には多面的なメリットがあります。もちろん、制作費用や手間が発生しますが、それを上回る価値を生み出すケースが十分にあるのです。
テキスト・写真だけの場合との比較表
「動画にするか、テキストと写真だけで済ませるか」という悩みを抱える中小企業は少なくありません。そこで、テキスト・写真と動画を比較した表を用意してみました。あくまで一般的な傾向ですが、判断の材料として活用してください。
| 比較項目 | テキスト・写真中心の場合 | 会社案内動画の場合 |
|---|---|---|
| 情報量・伝わりやすさ | 読む人の読解力に左右されやすい | 視覚と聴覚に同時に訴求でき、直感的に理解しやすい |
| 制作コスト | 比較的低コスト | 撮影・編集費用などがかかる |
| 印象度・記憶定着 | 文字や静止画だけでは印象が薄くなりがち | 動きや音声があるため記憶に残りやすい |
| 更新・修正のしやすさ | テキスト修正のみで対応可能 | 映像の撮り直しや再編集が必要 |
| 活用範囲 | 紙面やウェブ上の読み物としての活用 | ウェブ・SNS・展示会・オンライン商談など幅広い場面で活用可能 |
この表からわかるように、会社案内動画にはメリットと同時にコスト面や編集の手間があるというデメリットも存在します。しかし、映像による訴求力や印象の強さを考慮すると、特に競合他社と差別化したい場合や、企業規模に関係なくオリジナリティを出したいときには強い武器になり得ます。
会社案内動画の制作手順と注意点
「実際に会社案内動画を作るにはどうすればいいのか」という疑問を持つ方も多いでしょう。ここでは、一般的な制作手順を大まかに示します。
- 目的とターゲットの明確化
- 何のために、どんな人向けに作る動画なのかを明確にする
- 動画の利用シーン(自社サイト・SNS・オンライン展示会など)をイメージする
- 企画立案
- コンセプトや内容構成を決める(事業紹介、社内紹介、代表メッセージなど)
- 台本やシナリオを作成し、必要な撮影リストを洗い出す
- 撮影と編集
- 社内の雰囲気やサービスの風景を撮影する
- 撮影素材を基に編集し、テロップやBGMなどを加えてわかりやすく仕上げる
- 公開・運用
- ウェブサイトやSNSなど、活用したいプラットフォームにアップロードする
- 必要に応じてバージョン違い(短尺版など)を作り、運用を継続する
- 効果測定と改善
- 視聴回数や離脱率などをチェックして改善策を探る
- 定期的に動画をアップデートして、最新情報を伝える
この一連の流れで見落としがちなのが、「動画を活用して何を得たいのか」という目的設定です。単に「周りが作っているから」という理由で動画を制作しても、満足のいく結果につながらないことがあります。事前に自社の強みや魅力を十分に洗い出し、どのように映像化すればより効果を発揮できるかを考えることが肝要です。
また、動画を制作する際には以下のような注意点もあります。
- 過剰な長さにならないようにする
視聴者が集中して見られる時間には限りがあります。5分以上にわたる動画の場合、内容を分割するなどの工夫も検討しましょう。 - シナリオ・台本の作り込み
あらかじめしっかりと構成を考えないと、撮影や編集で余計なコストがかかるうえに、完成した動画のメッセージが散漫になる可能性があります。 - 撮影・編集の専門スキルが必要
自社で制作する場合は、撮影機材や編集ソフトの操作に慣れた人材が求められます。外部委託する場合でも、ディレクションに一定のリソースが必要です。
以下の表では、会社案内動画を制作する際の「自社内制作」と「外部委託」のポイントを比較します。
| 項目 | 自社内制作 | 外部委託 |
|---|---|---|
| 必要な設備・スキル | 撮影機材・編集ソフト・映像制作の知識が必要 | 制作会社やフリーランスの専門家が対応する |
| コスト | 内製化できれば大幅に抑えられる可能性もある | 専門家のスキルを買う形になるためコストは高め |
| クオリティ・演出 | 担当者のスキル・経験に左右される | プロの技術やノウハウを活かせる |
| コミュニケーション面 | 社内調整のみでスピード感はあるが、経験不足だと試行錯誤が必要 | 発注内容のすり合わせが重要だが、仕上がりの期待値は高い |
| 制作期間 | 担当者の他業務との兼ね合いで変動 | 制作会社のスケジュール次第だが目安を立てやすい |
どちらを選ぶにしても一長一短があるため、会社の状況や目的を踏まえて最適な方法を選びましょう。
活用アイデアと具体例
作った会社案内動画はどこで、どのように活用できるのでしょうか。以下のようなアイデアがあります。
- 自社ウェブサイトのトップページに埋め込む
訪問者に向けて一目で企業イメージを伝えられます。文字だけでは伝わりにくい雰囲気や強みを凝縮して見せることができます。 - オンライン展示会やイベントでの配信
物理的なブースがないオンラインイベントでも、動画を流すことで企業やサービスをアピールしやすくなります。 - SNSでのシェア
代表者の思いが込められたショートメッセージや、社内風景のダイジェストを短尺動画にまとめて投稿すれば、多くの人の目に留まる可能性が高まります。 - メールマガジンや営業メールの添付資料として
テキストだけのメールでは訴求力が弱い場合がありますが、動画を加えることで営業トーク以上の臨場感を相手に提供できます。 - リクルートや教育用途
社員教育や新卒・中途採用活動で会社の雰囲気や実際の仕事内容を伝えるのに活用できます。
また、活用範囲ごとに動画の尺(長さ)や構成を変えてみるのも一つの手です。たとえばウェブサイトのトップページに載せる動画は1分前後、SNS用には15~30秒程度に短くまとめるなど、用途に合わせて調整するとより効果的です。
下の表では、活用先と動画の推奨尺や特徴を簡単にまとめています。
| 活用先 | 推奨尺(目安) | 特徴 |
|---|---|---|
| 自社ウェブサイト | 1~3分 | 企業の概要やサービス内容を網羅的に伝えやすい |
| SNS(短尺動画向け) | 15~60秒 | テロップやキャッチーな演出で目を引きやすい |
| オンライン展示会 | 3~5分 | 商品やサービスのデモ映像など詳細に説明する |
| メール添付・営業用 | 30秒~1分程度 | 興味喚起を狙う短いメッセージが効果的 |
| リクルート・教育用途 | 3~5分 | 社員のインタビューや現場風景をしっかり見せる |
よくある疑問と回答
ここでは、会社案内動画を制作する際によく寄せられる疑問と、その解決策をいくつか挙げてみます。
疑問1:動画の制作費が高いと聞くが、本当にコストを回収できるのか?
- 回答:コスト回収がどの程度見込めるかは、活用方法と事業の性質によります。ただし、動画を営業ツールや広告素材として継続的に使い回すことで、長期的なリターンが期待できます。特にサービス内容の理解促進や信頼度アップにつながる場合、受注率が高まったり問い合わせ数が増えたりするため、結果的にコストを回収できるケースは少なくありません。
疑問2:テキストや写真だけでも十分なのでは?
- 回答:テキストや写真でも情報を伝えられますが、動画には「企業の雰囲気」や「人の表情」「実際の動き」など、静止画や文章だけでは伝えきれない要素を演出できる強みがあります。差別化やインパクトを求めるのであれば、動画が効果的でしょう。
疑問3:うちのような中小企業でも作る意味はあるのか?
- 回答:もちろんあります。動画制作は以前よりもハードルが下がっていますし、SNSやオンラインでの集客が普及する中では、規模に関係なく映像を活用したプロモーションが可能です。むしろ、競合他社と差別化を図るチャンスともいえます。
疑問4:外部に任せるとき、何を準備すればいい?
- 回答:動画の目的やコンセプト、紹介したいポイントの整理が必要です。また、撮影に協力してくれる社員や現場の調整、必要な素材(過去の写真・ロゴデータなど)を揃えておくとスムーズに進みます。
疑問5:動画の完成後、どのように運用すれば効果的か?
- 回答:まずは自社サイトやSNSに掲載し、視聴データや反応を見ながら改善を行います。オンライン展示会や顧客との商談時にも活用して、対面で説明する手間を省ける場面があるかもしれません。必要に応じて短いバージョンを作成するなど、複数の用途を想定して運用しましょう。
まとめ
ここまで、会社案内動画の需要やメリット、制作手順、具体的な活用方法などを解説してきました。中小企業が動画制作を導入する際に感じる疑問や不安は多くありますが、その多くは準備と運用のポイントを押さえることで解消できます。動画はテキストや写真にはない「動き」や「臨場感」を伝えられるため、企業の魅力をよりリアルに発信できる強力なツールです。コスト面や労力をかける価値は十分にあるといえるでしょう。
自社のブランディングやサービス理解の促進、営業・採用活動など、目的を明確にすることで動画制作がもたらす効果を最大限に活かすことができます。初めての取り組みの場合は、動画の尺や撮影内容を絞り込み、まずは短い動画から始めてテストしながら運用するのも一つの方法です。最終的には「どのように作るか」だけでなく、「作った動画をどのように活用していくか」こそが成功の鍵となります。






