Blog お役立ちブログ
メールフォーム返信が迷惑メールフォルダ行っちゃう?原因と対処法
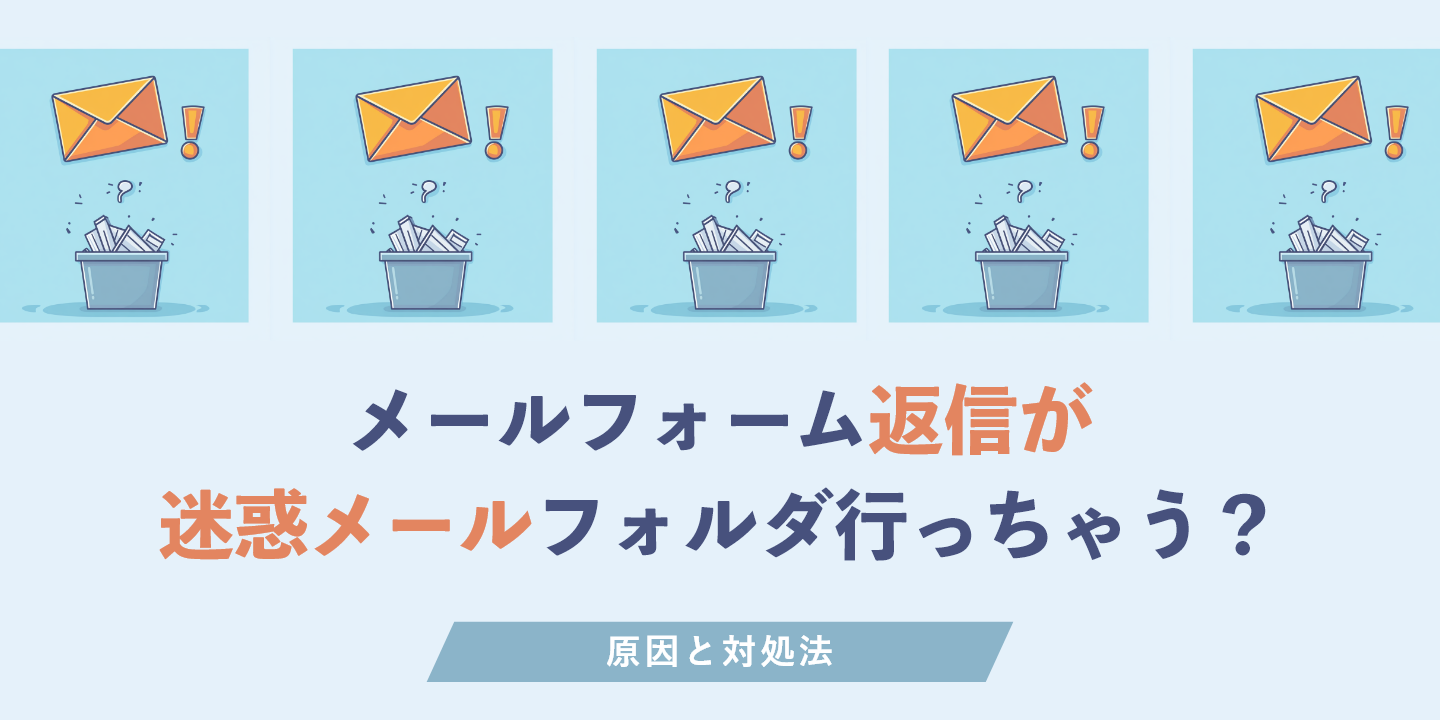
メールフォーム返信が迷惑メールフォルダに入る主な原因
問い合わせフォームを設置している中小企業にとって、フォームから送信されるメールがきちんと届かないというトラブルは深刻です。特に、顧客側の迷惑メールフォルダに振り分けられたまま気づかれないと、お客様からのクレームや信頼低下につながりかねません。ここでは、なぜ迷惑メールフォルダに行ってしまうのか、その主な原因を解説します。
サーバー設定や認証の不備
迷惑メール対策にはSPFやDKIMなどのメール認証技術があり、それらの設定が不完全だと「送信元が信頼できない」とみなされる場合があります。特に独自ドメインを使っているケースでは、サーバー管理画面やDNSレコードをきちんと設定していないことが原因になりやすいです。
メール本文や件名がスパムと判断されやすい
過度な宣伝文句や、一見すると怪しげに見えるキーワードが含まれていると、迷惑メール判定を受けやすくなります。また、件名があまりにも汎用的すぎたり、英語ばかりだったり、過剰な記号が多いといった場合にもフィルタの対象となりがちです。
送信元IPアドレスやドメインの評価
迷惑メールを大量に送信している、あるいは過去にスパム被害歴のあるIPアドレスやドメインからメールを送信すると、メール全体が疑わしいとみなされます。共用サーバーを利用している場合、同じサーバー内の他社や他ユーザーがスパム行為を行っていると、そのIP全体の評価が下がることもあります。
受信側のメールソフトやフィルタの設定
受信者側が利用しているメールソフトやプロバイダのスパムフィルタの設定次第で、送信元アドレスに関係なく迷惑メールフォルダに振り分けられることもあります。お客様が知らないうちにフィルタを強化しているケースも考えられます。
以下の表は、迷惑メールフォルダに入ってしまう要因をまとめたものです。
| 主な要因 | 詳細 |
|---|---|
| SPFやDKIMなどの設定ミス | メール認証が通らず、送信元の正当性を証明できない |
| 過度な宣伝文句や怪しい表現 | フィルタによってスパム判定される |
| 送信元IPやドメインの評価の低さ | 過去にスパム送信の履歴がある、または同一サーバー内に問題ユーザーがいる |
| 受信側のフィルタ設定 | お客様が高精度のスパムフィルタを設定している |
迷惑メール判定の仕組みと対策の基本
メールが迷惑メールに分類される仕組みは複合的です。ここでは、迷惑メール対策でよく知られる技術や対策の基本について解説します。
スコアリング方式
多くのメールフィルタは、受信したメールの本文や件名、ヘッダー情報などからスパムの可能性を数値化し、一定の基準値を超えると迷惑メールと判断します。たとえば、
- 件名に「無料」「特別価格」などの言葉が頻出
- 本文に大量のURLが含まれる
- 送信元ドメインの認証(SPFやDKIM)が通っていない
などの条件が重なるとスコアが上がり、結果的に迷惑メールフォルダに振り分けられる確率が高まります。
メール認証技術(SPF・DKIM・DMARC)
迷惑メールやなりすましを防ぐために、SPF(Sender Policy Framework)やDKIM(DomainKeys Identified Mail)、DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)といった認証技術が使われます。
- SPF
送信元サーバーのIPアドレスをDNSに登録し、送信ドメインからメールを送る権限があるかを検証する仕組みです。 - DKIM
電子署名を使って、メールの本文やヘッダーが改ざんされていないかを検証します。 - DMARC
SPFとDKIMの結果をもとに、受信側に対してメールをどのように扱うか(受け入れ、隔離、拒否)をポリシーとして提示する仕組みです。
以下の表では、これらの認証技術の概要と効果を比較しています。
| 技術 | 概要 | 効果 |
|---|---|---|
| SPF | 送信ドメインで許可されたサーバーからのみメール送信を行う | 送信元を偽装しにくくし、なりすましを防止 |
| DKIM | 電子署名によりメールの改ざんがないことを証明 | メールヘッダーや本文の正当性を保証 |
| DMARC | SPFとDKIMの検証結果に基づいて受信側へポリシーを提示し、報告を受ける | より高度なレベルでなりすましやフィッシングを防止 |
適切な文面作成
スパムと誤認されないためには、次の点に配慮した文面作成が重要です。
- 題名(件名)と本文に一貫性を持たせる
- 過剰なHTML装飾や不自然な表現を避ける
- 大量のURLを羅列せず、必要最低限にする
- 過度なセールストークを控え、問い合わせに関連した必要情報のみに絞る
フォームからの自動返信メールは、受信者にとって内容が明確で、問い合わせをしたことを思い出せるようなテキストであることが望ましいでしょう。
設定面で押さえておくべきポイント(SPF・DKIMなど)
ここからは、具体的にサーバー設定やDNSレコードで注意すべき点を解説します。特に独自ドメインを利用している場合は、自社のDNS設定を確認し、SPFやDKIMが正しく設定されているかどうかを調べることが重要です。
SPFレコードの設定
SPFレコードは、独自ドメインのDNS設定に「このドメインの正当な送信元サーバーはどれか」を記述する仕組みです。以下の点に注意しましょう。
- 利用しているメールサーバーや外部サービスの送信元IPをすべて記載する
- 「include」の使い方に注意する(複数の外部メールサービスを併用している場合など)
- ひとつのドメインに複数のSPFレコードを設定しない(1行にまとめる)
DKIM署名の設定
DKIMを有効にするには、メールサーバー側とDNS側の両方の設定が必要です。サーバー設定画面でDKIM署名をオンにしたうえで、DNSのTXTレコードとして公開鍵を登録します。設定が完了すると、送信されるメールのヘッダーに電子署名が付与されます。
DMARCポリシーの設定
DMARCまで設定しておくと、より高いレベルでなりすましメールを防止できます。DMARCレコードをDNSに追加し、
- none(検証のみ)
- quarantine(隔離)
- reject(拒否)
などのポリシーを指定可能です。ただし、いきなりrejectに設定すると誤判定で正しいメールが弾かれてしまうこともあるため、まずはnoneまたはquarantineから試す方が安全といえます。
送信ドメインと実際の差出人アドレスの整合性
たとえば、フォームから送信するときの「差出人(From)アドレス」が外部のメールアドレス(フリーメールなど)を使っていると、なりすましと判断されてSPFやDKIM認証が通りにくくなります。フォームから送信する場合は、できるだけ独自ドメインのメールアドレスを使うことがおすすめです。
迷惑メール対策に役立つ具体的な工夫とチェックリスト
設定面を整えたら、次は実運用で迷惑メール判定を回避するための工夫を紹介します。以下の表は、問い合わせフォームの運用でチェックすべき項目と、その確認の目安をまとめたものです。
| 項目 | 内容 | 確認の目安 |
|---|---|---|
| 差出人アドレスの設定 | 独自ドメインを使用しているか | サーバー管理画面でFromアドレスを変更 |
| メール本文・件名 | 過度な広告文句・怪しげな表現がないか | テンプレートに記載の言葉やリンク数を定期的に確認 |
| SPF/DKIMの有効化 | DNSレコードに正しく設定されているか | 各種検証ツールやサーバー管理画面からステータスを確認 |
| DMARCポリシーの設定 | noneからquarantineに段階的に設定を移行してみる | 受信拒否率が増えないかチェックしつつ徐々にレベルを上げる |
| テスト送信 | 異なるメールサービス(複数のフリーメールなど)で受信テストを行う | 月に1回程度、複数アドレス宛にフォーム経由でテスト送信する |
| お問い合わせ後の案内文面 | 自動返信が届かない場合の対処や、迷惑メールフォルダの確認を促す一文を入れておく | お客様に混乱を与えない程度に、軽く注意喚起 |
| 受信サーバーの監視 | エラーメールやバウンス率を監視し、問題があれば早期に原因を調べる | 確率が高まるとサーバーログを確認し、サポートに問い合わせ |
文面の工夫
自動返信メールには、以下の要素を入れておくと良いでしょう。
- 件名に「お問い合わせありがとうございます」など、問い合わせであることを明確に示す
- 冒頭で「お問い合わせいただきありがとうございます」と挨拶し、いつ・どのフォームから送信した内容であるかを簡潔に提示
- お客様が送った内容を引用または転記(入力内容がわかるようにする)
- 迷惑メールフォルダに振り分けられていないか、念のため確認を促す
コミュニケーションの二重化
自動返信メール以外にも、お客様へ重要な情報を伝える際には、別のチャネル(電話やSNSなど)を活用するなど、連絡手段を一つに限定しない工夫があると安心です。特に大事な手続きや決済案内などでは、メールのみだと万一の行き違いが生じる可能性があります。
外部問い合わせフォームサービスの利用確認
外部の問い合わせフォームサービスや決済システムを利用しているときは、そのサービス内でのメール送信設定(SPFのinclude設定など)を確認する必要があります。サービスによっては独自のメール認証機能を備えている場合もありますので、マニュアルを参考に設定を整えてください。
運用上の注意点とトラブルシュートの考え方
設定が完了しても、状況によっては迷惑メールフォルダに入る可能性はゼロになりません。運用しながら気を付けたいポイントや、実際にトラブルが発生したときの対処法をまとめます。
定期的な受信テスト
一度設定して安心するのではなく、月に1回程度、実際に自社フォームから異なるメールアドレスへテスト送信を行うのがおすすめです。迷惑メールフォルダに入っていないかを確認し、問題があれば早めに対策を講じましょう。
ログの確認とエラー通知
サーバーの管理画面やメールサービスによっては、送信失敗やバウンス(メールが戻ってくる)情報を確認できます。それらのログを定期的にチェックし、迷惑メール判定や配信エラーが多発していないか監視することが大切です。
受信側へのお願いは慎重に
お客様に「弊社からのメールを受信許可リストに加えてください」と頼むことも一つの方法ですが、あまりに丁寧すぎたり強調しすぎたりすると逆に不信感を与えかねません。自動返信メールやサンクスページ(フォーム送信完了画面)などで、さりげなく「メールが届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認ください」と伝える程度に留めるのが良いでしょう。
どうしても解決しない場合
どうしても解決しない場合は、利用中のサーバー会社のサポートに問い合わせてみるのも手です。SPFレコードやDKIM署名がサーバー側で自動化されていたり、SSL証明書の設定と連動していたりと、サービスによって仕組みが異なることがあります。専門的な部分はプロのサポートを活用すると安心です。
まとめ
問い合わせフォームの返信メールが迷惑メールフォルダに入ってしまうトラブルは、SPF・DKIMなどの設定不備、件名や本文の表現、サーバーやドメインの評価など、多岐にわたる原因が考えられます。まずはDNSレコード(SPF・DKIM・DMARC)の正確な設定を行い、信頼される送信元であることを明確に示しましょう。そのうえで、迷惑メールに分類されやすい文面を避ける工夫や、定期的な受信テストとログの確認が重要です。
中小企業がメールフォームの返信不達で失う信用は、小さくありません。自社の問い合わせ対応が円滑に行えるよう、今回紹介した対策を段階的に取り入れ、安心してメールを送受信できる体制づくりに取り組んでみてください。






