Blog お役立ちブログ
中小企業におけるスマホ対応ホームページの重要性
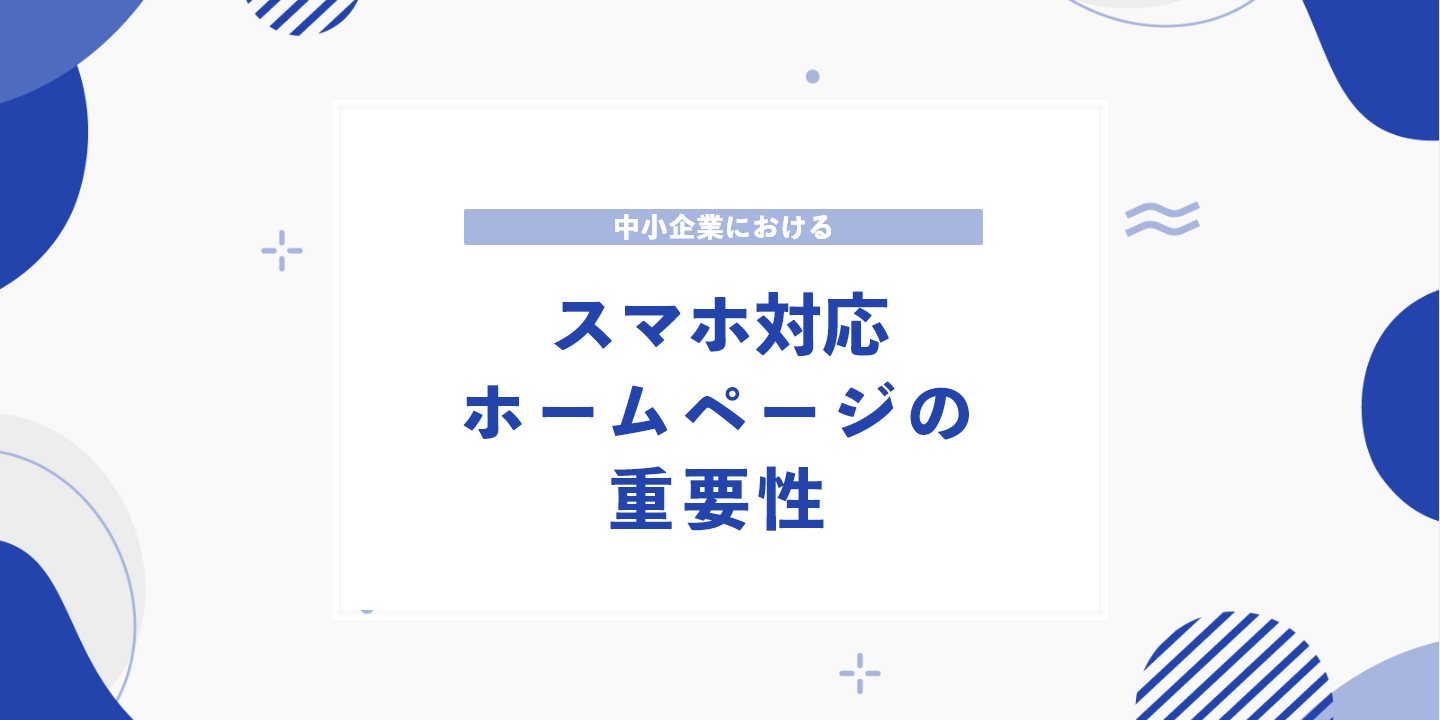
中小企業が新規ホームページやネットショップ、コーポレートサイトなどを制作しようとする際、まず直面するのが「どの制作会社に依頼するか」という問題です。実績が豊富そうだから、料金が安そうだから、といった単純な理由で選んでしまい、後から「思っていたのと違う」「コミュニケーションがうまくいかず、納期が遅れた」などのトラブルになるケースも少なくありません。
本記事では「制作会社選定基準を踏まえた失敗しないためのポイント」をテーマに、失敗を防ぐためのチェック項目や比較の仕方を詳しく解説します。特に、コミュニケーションの取り方や、アフターフォローの重要性など、実際に発生しがちなトラブル要因をふまえて、リスク回避するための具体的なポイントをまとめています。今まさに制作会社を検討中の方だけでなく、過去に失敗した経験があり、次こそは失敗を避けたいという方にも参考になる内容です。
制作会社選定における基本的な流れ
まずは、一般的に制作会社を選ぶ際の流れを整理します。実際にはもっと手順が複雑になる場合もありますが、大枠を把握しておくことで、どのタイミングで何を確認すべきかがクリアになるはずです。
- 目的・ゴールの整理
新たに制作を依頼するサイトやページの目的を明確にします。例えば「商品の販売促進」「サービス紹介」「採用強化」など、ゴールをはっきりさせることが大切です。 - 制作予算の把握
おおよその予算感を設定します。ここでは「具体的にいくらまでOK」という数字でなくても、上限や下限のイメージを明確にするのがポイントです。 - 候補となる制作会社のリストアップ
インターネットで検索したり、知り合いに紹介してもらったり、展示会やセミナーで出会った会社など、複数候補をリストアップします。 - 実績やサービス内容の確認
候補の制作会社の実績サイトやサービスメニューを確認し、自社の目的に合っているかをチェックします。 - 問い合わせ・ヒアリング・見積依頼
実際にコンタクトを取り、制作の流れや担当者とのコミュニケーションを確かめながら、見積りや納期の目安をもらいます。 - 比較・検討
複数社の見積りや提案内容を比較しながら、どの制作会社が最も自社に合っているかを吟味します。 - 契約・制作開始
契約書や仕様書を取り交わしたうえで、制作プロジェクトをスタートさせます。
この流れの中で特に重要となるのが「自社の目的・ゴールを明確にすること」と「複数社をしっかり比較すること」です。それを行うか否かで、最終的な成果に大きく差がつきます。
失敗しないための基準と比較ポイント
次に、具体的にどのような基準で制作会社を比較すればよいかを整理していきます。ここでは、大きく分けて以下の観点を押さえるとよいでしょう。
- 目的に合った専門性
- 料金体系・コストパフォーマンス
- コミュニケーション体制
- 制作実績の質と幅
- スケジュール管理能力
- アフターフォローの充実度
下記に「比較ポイント」と「確認する主な質問例」をまとめた表を作成しました。検討時のチェックリストとして活用してみてください。
| 比較ポイント | 確認する主な質問例 |
|---|---|
| 目的に合った専門性 | – 自社の業界実績や同業他社の制作事例はあるか – 運用やマーケティング面もサポート可能か |
| 料金体系・コストパフォーマンス | – 見積りは明瞭か – 追加費用が発生するタイミングや理由は明確か |
| コミュニケーション体制 | – 専属担当者との連絡手段・頻度はどうなっているか – 打ち合わせや修正依頼の進め方はスムーズか |
| 制作実績の質と幅 | – デザインのテイストは自社に合いそうか – 運用実績や成果事例はあるか |
| スケジュール管理能力 | – 制作フローは具体的に提示されるか – 納期遅延のリスクや対処方法はどう説明されるか |
| アフターフォローの充実度 | – 更新や改善のサポート範囲はどこまでか – 保守費用や運用代行の有無はどうなっているか |
これらの観点をまんべんなくチェックすることで、失敗を防ぎやすくなります。特にコミュニケーション体制は、実際に制作が始まった後で認識違いや方針のブレが発生しないようにするための重要項目です。
コミュニケーションの重要性と具体例
制作会社とのやり取りがスムーズかどうかは、最終的な成果物のクオリティにも大きな影響を与えます。なぜなら、ホームページやランディングページは最初のヒアリングから始まり、何度も情報共有やデザイン確認などを経て完成に至るからです。双方の連絡方法や担当者の対応スピードに難があると、小さな修正作業が積み重なり、大きな遅延やトラブルを招きがちです。
具体的なコミュニケーション・トラブル例
- メールでのやり取りが中心で、レスポンスが遅く、緊急時に対応が間に合わなかった
- 初回ヒアリング内容が不十分だったため、デザインが大幅に作り直しになった
- 仕様変更のお願いをしたが、途中で誰も把握しておらず、納期がズレ込んだ
これらのトラブルを回避するには、「案件ごとに専属の担当者をつけてもらえるか」「コミュニケーション方法(チャットツール、オンライン会議、電話など)の選択肢があるか」「対応可能な時間帯」を事前に確認しておくことがポイントです。
制作実績の正しい見方とチェック方法
制作実績を確認する際に、ただ「オシャレだから良さそう」といった感覚的な判断をするだけでは失敗のリスクが高まります。重要なのは、「自社と似たような業界・ターゲットに対する制作実績があるかどうか」です。
例えば、BtoB向けの堅めのイメージを重視したホームページが得意な会社もあれば、ネットショップの売上向上を得意とする会社もあります。自社が求めるサイトやサービスにマッチしたスキルを持っているかを見極めることで、より実践的な提案や運用ノウハウを期待できます。
また、実績サイトの公開後に成果を出している例があれば、そこを詳しく確認することで信頼度が上がります。しかし、制作会社によっては実績を公開しづらいケース(契約上の理由など)もあるので、すぐに見つからない場合はヒアリング時に直接質問するのが確実です。
以下の表は、制作実績をチェックするときの視点を整理したものです。
| チェック視点 | ポイント |
|---|---|
| デザイン・UI/UXの品質 | – ユーザーにとって見やすい構成か – コンセプトやブランドイメージが一貫しているか |
| 業種・業態の類似度 | – 自社に近い業種・事例があるか – ターゲットとするユーザー層が似ているか |
| 実装技術・機能面の対応可否 | – ECサイトなら決済機能、予約サイトなら予約管理機能などを含めて実現できるか |
| 運用後の成果・改善事例 | – 公表されている範囲でアクセス数や問い合わせ数が増えた事例があるか |
| 制作会社の担当領域 | – デザインのみなのか、コーディングやSEO対策、運用サポートなど幅広く対応できるか |
アフターフォロー・運用体制の確認事項
ホームページやサイトは、制作して終わりではありません。むしろ公開後の運用や改善こそが成果を左右するといっても過言ではないでしょう。サイトの更新やメンテナンス、セキュリティ対策、さらには解析ツールを用いたユーザー行動の分析など、運用フェーズで必要になる作業は多岐にわたります。
- 更新作業の対応範囲
文章の入れ替えや、画像の差し替え程度なら自社で行える場合もありますが、デザインやレイアウトを伴う修正は制作会社に依頼するケースが多いです。その際の料金や納期がどうなっているか、契約段階で確認しておくと安心です。 - アクセス解析や改善提案
アクセス解析レポートの提供や、コンバージョン率を上げるための改善提案などのサービスがあると、さらに効果的にサイトを活用できます。これらのオプションを提供している会社とそうでない会社では、長期的な成果に差がつくことが多いです。 - 保守・セキュリティ対策
CMS(コンテンツ管理システム)のバージョンアップやプラグインの更新、セキュリティホールへの対処など、定期的なメンテナンス作業は必須です。これらを自社内で行うのか、制作会社に任せられるのか、費用やサポート体制を事前に確認しておきましょう。
失敗事例とリスク回避のポイント
ここでは、実際にありがちな失敗事例と、それを回避するための対策を紹介します。自社が同じ轍を踏まないよう、事前にチェックしておくとよいでしょう。
| 失敗事例 | リスク回避のポイント |
|---|---|
| 明確な要件定義がないまま契約し、後から仕様変更が頻発した | – 事前に要件定義書を作成し、制作会社との認識をすり合わせる – 追加料金や納期の変更条件を契約書に明記しておく |
| 担当者の交代が頻繁で、情報共有が不十分なままプロジェクトが進行 | – プロジェクト開始時に専属担当者を決める – コミュニケーションツールや共有ドキュメントを整備する |
| 実際の見積りと請求額に大きな乖離があり、予算オーバーになった | – 見積り内容の内訳を細かくチェックする – 追加作業が発生した場合の費用計算ルールを明確にする |
| 運用開始後、更新作業や修正対応に時間がかかりすぎた | – 運用フェーズの対応体制を事前に確認する – 緊急対応やスケジュール調整のフローを取り決めておく |
特に「明確な要件定義」の大切さは、多くの専門家が口をそろえて指摘するところです。要件定義が曖昧なまま制作を進めると、デザインや機能面での手戻りが発生しやすく、予算や納期が大きく膨れ上がる原因となります。
制作会社とのスムーズな連携手順
最後に、契約から納品までの具体的な連携手順をあらためてまとめます。ここをきちんと把握しておくことで、見落としが起きにくくなり、よりスムーズにプロジェクトを進められます。
- 要件定義・コンセプト策定
何のためにサイトを作るのか、どんな機能が必要なのか、ターゲットは誰か。これらを社内で整理し、制作会社と共有します。可能であれば、箇条書きやワイヤーフレームなどビジュアル化できる資料を用意すると、認識のズレが生じにくくなります。 - 見積り・スケジュール確定
制作会社から提示される見積書とスケジュール案を確認します。不明点や懸念点があれば遠慮せず質問し、納得したうえで契約書を交わします。 - デザイン案・プロトタイプ作成
要件定義をもとに制作会社がデザイン案やプロトタイプを作成します。数パターン提案されることもあり、自社のイメージやブランドと合っているか、利用者目線で分かりやすいかをチェックします。 - デザイン確定・コーディング
デザイン案を確定したら、コーディングや実装フェーズに移行します。この段階で突然の大幅な修正が入ると、スケジュールが崩れる原因になるため、細部の確認を入念に行いましょう。 - テスト・修正
テスト環境で動作確認を行い、不具合やレイアウト崩れなどをチェックします。不明点や微調整が必要な箇所は、スケジュールに余裕をもって伝えます。 - 納品・公開
テストが完了し、問題がなければ本番公開します。公開直後はアクセス数や問い合わせフォームなどをしっかり確認し、早期に問題があれば対処します。 - 運用サポート・改善
公開後の運用に関して、どこまで制作会社に依頼するのか、あるいは自社で行うのかを明確にしておきます。定期的にミーティングを実施し、アクセス解析の結果を踏まえた改善を回していくことで、より高い成果が期待できます。
この一連の流れをしっかり踏まえておくと、プロジェクト全体の見通しが良くなり、依頼側・制作側の双方がスムーズに作業を進めることができます。
まとめ
制作会社の選び方を間違えると、想定以上の費用や時間をかけてしまったり、完成品の品質に納得がいかなかったりと、さまざまなリスクが生じます。その一方で、適切な基準をもって比較し、プロジェクトの進め方を慎重に計画することで、トラブルを大幅に減らすことは十分可能です。
特に以下の点は、制作会社の選定や連携時に必ず押さえておきましょう。
- 事前に目的とゴールを明確化
サイトの用途やターゲットがはっきりしていないと、制作会社もベストな提案ができません。 - 複数社から見積りを取り、コミュニケーションの質を比較
価格だけでなく、担当者の対応や専門性、アフターフォローの充実度を総合的に検討します。 - 要件定義と仕様書をしっかり整備する
後から仕様変更が頻発すると、予算や納期が膨らむ原因となります。 - 納品後の運用フェーズを視野に入れた契約内容
長期的に運用する場合、保守や更新作業、改善提案などが受けられるかどうかを確認しておきましょう。
これらを踏まえ、制作会社と目的を共有しながら二人三脚でプロジェクトを進めていくことが、最終的な成功への近道です。この記事が、これから制作会社を選ぶ方の参考になれば幸いです。






