Blog お役立ちブログ
Webサイトの成功を導くサイト戦略
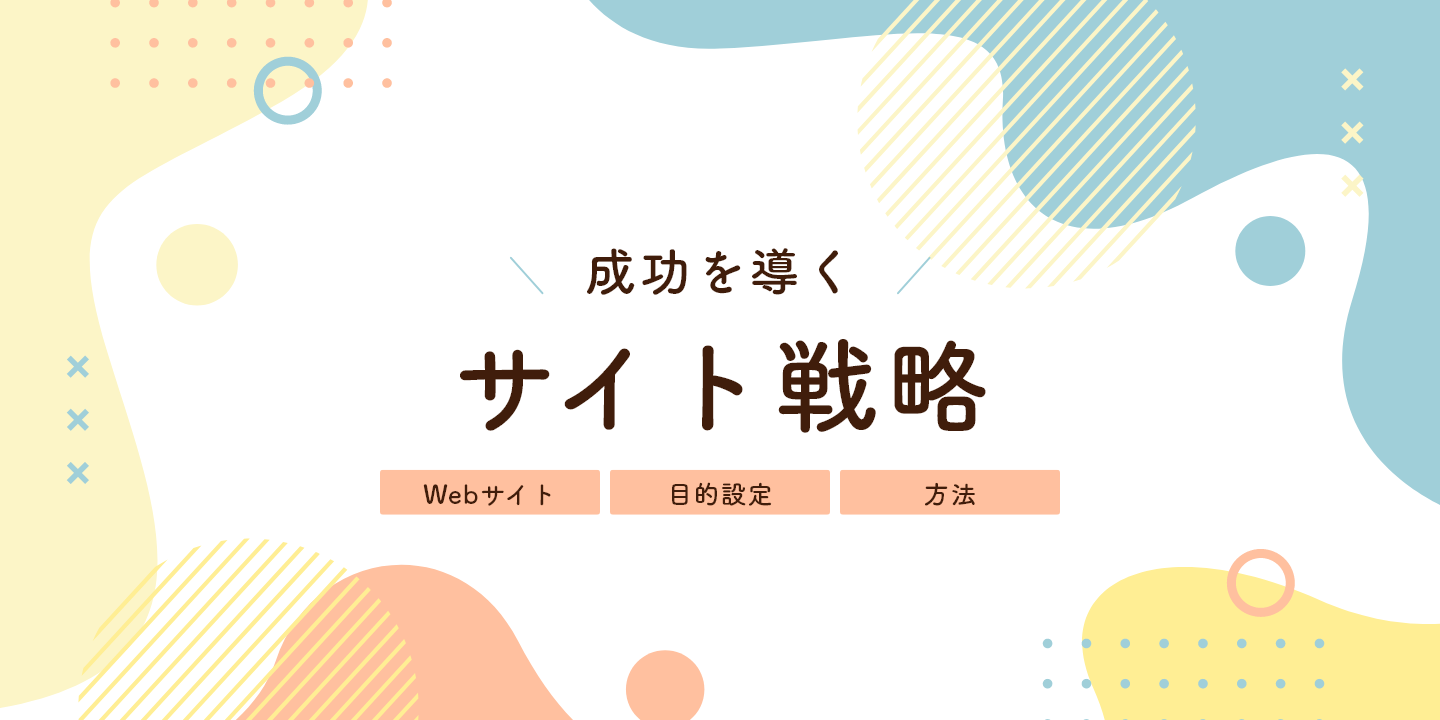
中小企業が自社のWebサイトを運用する際、「とりあえずホームページを作った」というケースで終わってしまうことがあります。しかし、明確な目的を設定せずにサイトを運用していては、成果が出ているのかどうかも判断できず、費用対効果を高めることが難しくなります。
本記事では、Webサイトの目的設定がなぜ重要なのか、具体的にどのような項目を設定し、どのように運用・改善を進めていけばよいのかを整理して解説します。新規顧客の獲得・採用力強化・ブランド認知など、さまざまな目的に合わせてWebサイトを最大限に活用するための考え方や手順について、できるだけわかりやすくまとめました。
Webサイトに目的設定が必要な理由
Webサイトに目的設定を行うことは、サイト運用の「方向性」を明確にするために欠かせません。作業コストや広告費をかけても、何を実現したいのかが曖昧だと、施策の良し悪しを判断できないばかりか、結果的に時間や費用を無駄にしてしまう可能性があります。
目的がないと評価指標が定まらない
例えば、新規顧客獲得という目的がないまま広告費を投入しても、結果を測定するための指標(コンバージョン数や問い合わせ数)が明確でなければ、サイト運営が成功しているかどうか判断できません。目的に応じた指標を設定し、それをもとに成果をチェックすることで、運用方針の軌道修正や改善をスムーズに行えます。
社内の合意形成がしやすくなる
「サイトをどのように育てたいか」を明確にしておくと、社内の担当者間で運用方針のすり合わせがスムーズに行えます。たとえば採用目的であれば、採用担当者と連携しながら応募数や説明会の参加者数を測定し、サイトの改善を継続的に行うことができます。ブランド認知を目的とするのであれば、会社のイメージアップにつながるコンテンツやSNSの活用などに注力する合意を得やすくなります。
リソースの最適な配分
中小企業であれば、リソースや予算が限られているケースが多いでしょう。目的がはっきりすれば、「何にどれだけリソースを割くべきか」明確になり、闇雲に広告を打つ、闇雲にコンテンツを増やす、といった効率の悪い運用を回避できます。
目的の種類とゴールの具体化
Webサイトの目的には大きく分けて、以下のような種類があります。それぞれに合わせてゴールをより具体的に設定すると、運用の指針が立てやすくなります。
- 新規顧客獲得
- 見込み客の問い合わせ数を増やす
- 購入や契約に至るアクションを増やす
- 採用活動
- 応募者数や応募の質を高める
- 企業イメージを伝え、応募意欲を高める
- ブランド認知・イメージ向上
- 社名・サービス名の認知度を高める
- 顧客や取引先からの評価向上
- 情報発信・リード獲得
- ホワイトペーパーのダウンロード数を増やす
- メルマガ購読やセミナー参加などのリスト獲得
- ECサイトでの売上拡大
- 購買率や客単価の向上
- リピート率の向上
具体的なゴール設定例
目的を定めただけでは抽象的なので、それをさらに数値や行動に落とし込んでゴールを設定すると実行プランを立てやすくなります。例として新規顧客獲得を目的とした場合、以下のようなゴールを細分化できます。
- 月間問い合わせ数を○件以上獲得する
- サイト経由の成約率を○%にする
- 各問い合わせにかかる獲得コストを○円以内に抑える
具体的な数値を入れることで達成度合いが測りやすくなり、定期的なモニタリングと改善がスムーズになります。
KGI・KPIの考え方と設定方法
Webサイトの目的を設定したら、それを達成するための道筋としてKGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)を設定します。
KGIとKPIの違い
| 用語 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| KGI(Key Goal Indicator) | 最終的な重要目標を示す指標 | 月間問い合わせ数○件、採用応募数○件など |
| KPI(Key Performance Indicator) | KGIを達成するために必要な中間指標 | サイト訪問数、CVR(コンバージョン率)など |
- KGI は「最終的にどうなっていれば成功か」を示す数値目標
- KPI は「KGIを達成するために、どれだけの行動や成果が必要か」を示すプロセス指標
設定のポイント
- 実現可能性のある数値を設定する
大きすぎる目標だとモチベーションが維持できません。実際のデータをもとに試算し、現実的な数値を設定しましょう。 - 複数のKPIを設定しすぎない
重要な指標に絞ることで管理・改善がしやすくなります。 - 定期的に見直す
市場環境や自社の状況が変化すると、KPIやKGIを修正しなければならない場合もあります。四半期ごとや半期ごとの見直しを検討するとよいでしょう。
目的に応じた運用と改善のポイント
目的設定やKGI・KPIを定めても、実際に運用してみると想定外の課題が発生することもあります。ここでは、代表的な目的別に運用・改善のポイントを解説します。
新規顧客獲得
- サイトへのアクセス増加施策
検索エンジン最適化、広告の活用、SNSでの情報発信などを行い、まずはアクセスを増やします。 - コンバージョン最適化
問い合わせフォームの入力項目を最適化し、離脱を防ぐ。訪問者が行動を起こしたくなる導線づくりが重要です。 - アクセス解析を定期的に確認
「どのページから問い合わせが多いのか」「どのキーワードで流入しているのか」などのデータを基に改善を繰り返します。
採用活動
- 求職者のニーズを把握
サイト上で社風・働く魅力をわかりやすく提示し、応募のハードルを下げる。 - 応募導線をわかりやすく
問い合わせ先やエントリーフォームなど、興味を持った人がすぐアクションできる流れを作りましょう。 - SNSや採用サイトとの連携
サイト単体では十分な認知度を得にくい場合は、SNSや他の採用プラットフォームも活用し、多面的に応募者と接触します。
ブランド認知・イメージ向上
- 一貫性のあるデザイン・メッセージ
ロゴやカラーリング、キャッチコピーなどを統一し、企業イメージを根付かせます。 - 情報発信の質を高める
新商品の情報や業界トピックに関する知見を積極的に発信することで、専門性をアピールし、ブランド価値を高めます。 - 広報担当者との連携
サイト以外のメディア露出やPR活動とも連携し、一貫したブランドストーリーを作り上げると効果的です。
成功を導くサイト戦略の手順例(表を交えた解説)
ここでは、サイトの目的設定から運用・改善までの一連の流れを整理した例を示します。
| フェーズ | 主な内容 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 目的・目標設定 | – サイトの目的を決める – KGI・KPIを設定する | 目的が複数ある場合は優先度を明確化 |
| 設計・制作 | – サイト構成やデザインを決定 – コンテンツプランを立案 | 目的達成に必要なページや機能が揃っているか |
| 集客施策 | – SEO対策や広告出稿 – SNS運用やメール施策 | ターゲットユーザーに合った施策を選定 |
| 運用・計測 | – アクセス解析の実施 – コンバージョン測定 | Googleアナリティクスなどの分析ツールで定期チェック |
| 改善・施策の最適化 | – 施策の効果を検証 – デザインや導線の見直し | KGI・KPIの達成状況を踏まえて改善策を検討 |
- 目的・目標設定
各部門と話し合いながら、「何のためにサイトを使うか」を明確にします。そのうえでKGIやKPIを定め、数値的な到達目標を決めておくことで運用時の判断基準ができます。 - 設計・制作
目的に応じたページ構成やデザインを考えます。新規顧客獲得を重視するなら問い合わせ導線や商品・サービス紹介ページを強化し、採用重視ならば企業情報や社内の雰囲気を伝えるページに注力するといった形です。 - 集客施策
設計・制作段階で想定したターゲットに対して、検索エンジン最適化や広告、SNSなどを組み合わせて流入を増やします。狙いたいキーワードやユーザー属性に応じて、どのチャネルに注力するかを決めましょう。 - 運用・計測
定期的にサイトのアクセス数や問い合わせ数、応募数などをチェックします。月次や週次でレポートをまとめ、改善ポイントを洗い出します。 - 改善・施策の最適化
分析データを踏まえ、フォームの入力項目を減らす、デザインを変更する、記事の更新頻度や内容を見直すなど、目的達成につながる調整を繰り返し行います。
目的別・実施施策の比較表
下記に代表的な目的に対して実施しやすい施策例をまとめました。自社の最優先目的に合わせて、どの施策に注力すべきか考える際の参考にしてください。
| 目的 | 主な施策 | 特徴 | 運用コスト |
|---|---|---|---|
| 新規顧客獲得 | – SEO対策 – リスティング広告 – ランディングページの最適化 | 直接成果(問い合わせ・契約)に繋がりやすい | 広告予算や制作コストがかかる場合あり |
| 採用活動 | – 採用コンテンツ(社員インタビューなど)の拡充 – SNS活用 – 説明会案内ページの整備 | 企業の魅力や社風の訴求が重要 | 応募者対応の負担も考慮 |
| ブランド認知・イメージ向上 | – ブログやコラムの継続発信 – SNSのファンコミュニティ – オウンドメディア企画 | 長期的なブランディング効果を狙う | 継続的な情報発信が必要 |
| 情報発信・リード獲得 | – メルマガ登録フォーム – ホワイトペーパーのダウンロード – セミナー告知 | 見込み客と継続的な関係を築く | コンテンツ制作や運営業務が発生 |
| ECサイトでの売上拡大 | – 商品ページの最適化 – カート離脱対策 – リピート施策(ポイント制度など) | 直接売上アップが見込める | 在庫管理や決済システムとの連携が必要 |
比較表の活用方法
- まず自社で最も重視したい目的を決める
- 目的に沿った施策の導入難易度やコストを把握する
- リソースや予算、社内体制をふまえて実施可能な範囲から優先的に取り組む
目的が複数ある場合は、同時並行で取り組むのではなく、優先度の高い施策から順に着手するほうが効率的です。
トラブルを防ぐための事前チェックリスト
Webサイトを運用していると、思わぬ課題が発生することもあります。以下のような項目を事前にチェックすることで、大きなトラブルを防ぎやすくなります。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 権限と管理体制 | サイト管理者や更新担当者は誰か、ログイン情報の管理は適切か |
| 更新頻度の目安 | 定期的に更新すべきコンテンツはどれか、どれくらいの頻度で行うか |
| コンタクト先の明確化 | 問い合わせフォームや採用エントリー先はわかりやすく設置されているか |
| セキュリティ対策 | CMSのバージョン管理、プラグインの更新や不正アクセス対策はできているか |
| バックアップ | 定期的にバックアップを取得しているか、復元体制は整っているか |
これらの項目をあらかじめ整理しておけば、万が一トラブルが起きても素早く対応が可能です。特に、担当者が交代した際に運用が継続できるよう、情報共有の体制を整えておきましょう。
まとめ
Webサイトの目的設定と戦略立案は、中小企業が限られたリソースの中で最大の成果を出すために極めて重要です。明確な目的がなければ、サイトの制作や運用、広告出稿などの判断軸が曖昧になり、成果を正しく把握できなくなる恐れがあります。
したがって、まずは「新規顧客獲得」「採用活動」「ブランド認知」「情報発信・リード獲得」「ECサイトでの売上拡大」など、自社の現状や目標に合致する目的を整理します。そのうえでKGI・KPIを設定し、コンテンツの方向性や導線設計、集客施策などを一貫性のある戦略として組み立ててください。
さらに、運用や改善においてはアクセス解析や問い合わせ数などの数値を定期的に確認し、施策の効果を検証しながら軌道修正を繰り返していくことが成功への近道となります。表で示したように、目的に応じて取り組むべき具体的な施策は異なるため、目標を達成するために最適なプランを選択するようにしましょう。
自社のWebサイトを明確な目的と戦略に基づいて運営すれば、競合との差別化や顧客とのつながりが深まり、最終的に事業の成長を後押しする力になります。Webサイトの運用は継続的な取り組みですが、試行錯誤を重ねながら改善を続けることで、必ず成果につながっていくはずです。






