Blog お役立ちブログ
複数ドメインを持ってるけど分散しすぎ?その解決策と注意点
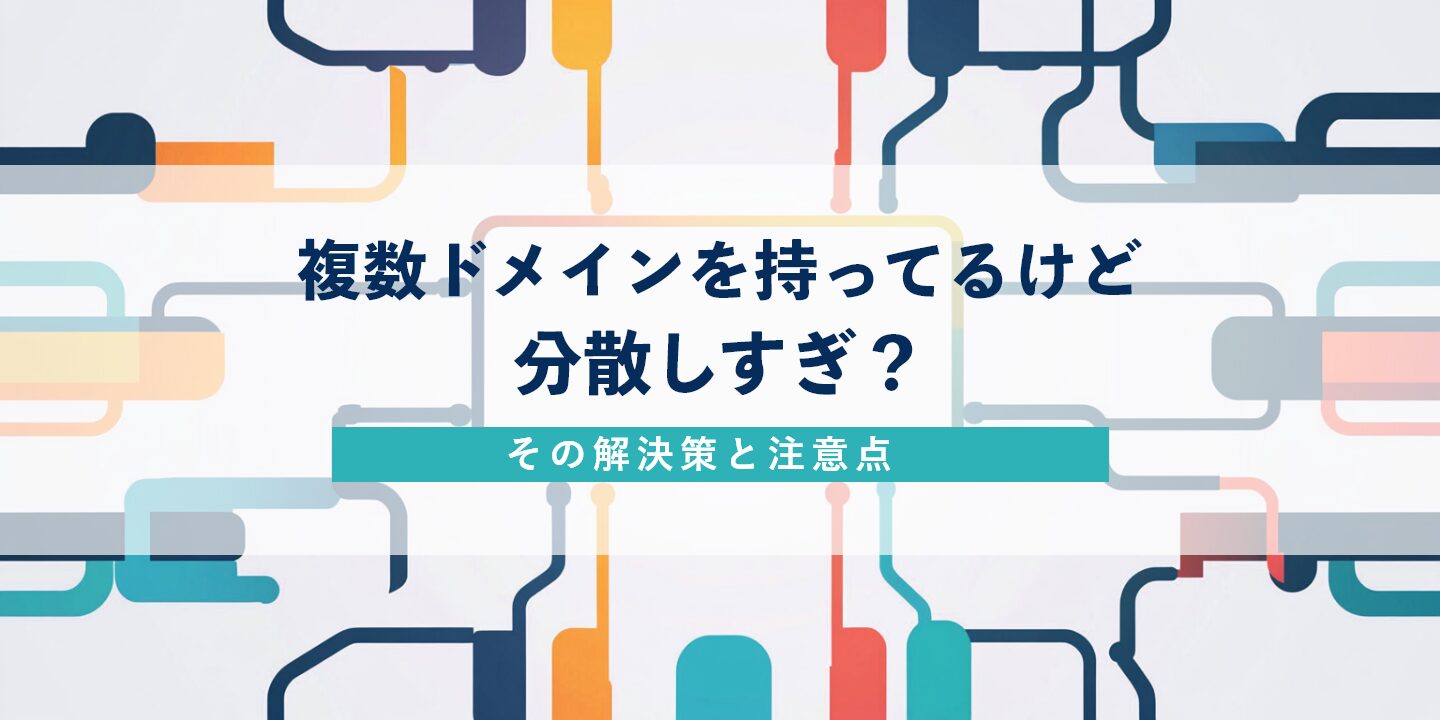
複数ドメインを持つ背景とよくある課題
中小企業が複数のドメインを持つ理由はさまざまです。新規事業を立ち上げる際、部門ごとにウェブサイトを独立して制作したり、期間限定のキャンペーン用サイトを立ち上げたまま放置してしまったりするケースもあるでしょう。以下のような背景から、気づけばドメインが増え過ぎてしまうことがあります。
- 事業部ごとに異なる商品やサービスを展開しており、サイトのターゲットが違うと感じた
- 新サービスの立ち上げ時に臨時でサイトを作り、そのまま残してしまった
- 既存のコーポレートサイトとは別で、採用情報だけ切り出す形で別ドメインにした
しかし、ドメインを増やした当初は狙いがあったとしても、しばらく経つと下記のような課題に直面することが多いのです。
- 複数サイトを管理するため、更新頻度がばらばらになり、どのサイトも鮮度を保てない
- 各サイトのドメインパワー(SEO上の評価)が分散し、検索結果での順位が上がりにくい
- サイトごとの運用コストが積み重なり、全体では大きな負担になる
こうした「分散しすぎ」の状態を放置していると、集客面だけでなくブランド力や費用対効果の面でも大きな機会損失を招く可能性があります。
分散によるデメリットとリスク
複数のドメインがあることで、表面的には「それぞれ独立した事業サイトを持つ」メリットがあるように思えます。しかし実際には以下のようなデメリットやリスクを伴うことが多いです。
- 【SEO効果の分散】
サイトの評価は基本的にドメインごとに行われます。複数のドメインにサイトを分割すると、いずれのサイトもコンテンツ量や被リンク数が不足しがちになり、検索順位の向上が難しくなります。また、同じ会社のサービスであるにもかかわらず、ドメインが違うために検索エンジンやユーザーから見た評価や信頼が分散してしまう恐れがあります。 - 【運用コストの増大】
ドメイン取得や更新の費用、サーバーの維持費、セキュリティ対策の手間などがドメイン数分かかります。もちろん、それぞれ別々にしっかりと運用できればよいのですが、人手や時間が限られた中小企業では、サイトを複数運用するほど管理が回らなくなるケースも多いです。 - 【ブランドイメージの統一感欠如】
サイトやドメインが分散していると、「○○会社のサービス」という統一したブランディングが行いにくくなります。ユーザーが複数のサイトを行き来しても、同じ企業が運営していると分かりづらいといった問題も起こりがちです。 - 【アクセス解析やデータの集約が困難】
サイトがばらばらに存在するため、それぞれのアクセス解析結果やコンバージョンデータが分散します。全体を俯瞰して戦略を立てるのが難しくなり、マーケティング施策の効果を正確に把握できないことも大きなリスクです。
ドメインを統合するメリット・デメリット
複数のドメインを運用するか、それとも統合して一つのドメイン(または最小限の数)にまとめるかの判断には、一長一短があります。以下の表を参考に、メリット・デメリットを整理してみましょう。
| ドメイン統合のメリット | ドメイン統合のデメリット |
|---|---|
| ・SEO評価を集中させやすい | ・サイト移転やリダイレクトの手間が発生 |
| ・運用コストや管理作業を削減できる | ・URLが変更になることでユーザーが戸惑う可能性 |
| ・ブランドイメージを統一しやすい | ・短期的には検索順位に変動が生じることがある |
| ・アクセス解析データを一元管理できる | ・場合によっては再設定すべき箇所が多くなる |
多くの場合、中小企業であれば「一つのドメインに集約する」ほうが効果的です。特にオンラインでの集客を重視する場合は、検索エンジンでの評価を高めるためにも、メインとなるコーポレートサイトを軸に情報を集約し、そこから各サービスページへつなげる導線を作ると、ユーザーにもわかりやすくなります。
ただし、サイトごとのターゲットが大きく異なり、全く別のブランド戦略を取っている場合などは、あえて複数ドメインを維持するケースもあります。どちらの選択肢が自社にとって最適かを検討する際には、下記のようなポイントを意識しましょう。
- 統合することでより強固なブランドメッセージを訴求できるか
- サイト移転に伴うリダイレクトやURL変更のリスクをきちんと管理できるか
- ターゲットやサービスの内容が明らかに異なるのであれば、別ドメインのほうがユーザーに混乱を与えないか
ドメイン統合やリダイレクトの具体的な手順
複数のドメインを統合する際、ただ「古いドメインを放置して新しいドメインにサイトを作る」だけでは不十分です。主に以下の手順やポイントを押さえておく必要があります。
- 【メインドメイン(統合先)を決める】
まずはどのドメインを主軸とするのかを明確にしましょう。社名に近いものや、既に利用者が多いドメイン、検索順位が高いページが多いドメインなどが候補となります。 - 【サイト構造の再設計】
統合先のドメインのサイト構造を見直し、どのようにページを配置するかを計画します。事業部やサービスごとにディレクトリを分けるなど、整理しやすい構造にしましょう。 - 【コンテンツの整理・統合】
分散していた各ドメインのページ内容を確認し、重複や類似ページを整理します。重複が多い場合はまとめたり、不要なページは削除するなど、コンテンツをクリーンにしましょう。 - 【リダイレクト(301リダイレクト)の設定】
SEO上、ページ評価を引き継ぐためには301リダイレクトを使うのが一般的です。古いドメインの各URLを新しいURLにきちんと振り替えてあげることで、検索エンジンに「このページは移転した」と正しく認識してもらえます。 - 【サーチコンソール等の設定変更】
統合先のドメインを検索エンジンに認識させるために、サーチコンソールやサイトマップ、アナリティクスの設定を更新します。アクセス解析も新しいドメインの方へ一元化することで、データ分析がやりやすくなります。 - 【テストとモニタリング】
リダイレクト設定後、意図した通りのページ遷移になっているか、リンク切れがないかなどをテストしましょう。移行直後は検索順位が多少変動することもありますが、きちんと対策を行えば徐々に安定してくるはずです。
下表は、ドメイン統合の大まかな流れと、各ステップでチェックすべきポイントをまとめたものです。
| ステップ | 主な内容 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 1. 統合先ドメイン選定 | メインドメインを決める | 企業名やサービス名との整合性、既存の流入状況 |
| 2. サイト構造の再設計 | 新サイトの構造を策定し、情報を整理 | ページ階層の分かりやすさ、ユーザー導線 |
| 3. コンテンツ整理 | 重複・類似ページの統合や不要ページの削除 | SEO評価や閲覧数の高いページを優先 |
| 4. リダイレクト設定 | 旧ドメインから新ドメインへ301リダイレクトを実装 | リンク切れの有無、リダイレクト先の整合性 |
| 5. 設定変更・告知 | サーチコンソールやアナリティクスの更新、URL告知など | 設定の反映状況、旧URL利用者への案内 |
| 6. テストと監視 | 遷移テスト、アクセス解析の確認 | 検索順位の変動監視、クローラーエラーの有無 |
このように、ドメイン統合は複数の工程を経て丁寧に進めることが重要です。
統合後の運用と注意点
ドメインを統合して終わりではなく、その後の運用が非常に大切です。下記のポイントを押さえておきましょう。
1. コンテンツの定期的な更新と拡充
統合した後のメインドメインは、新たに集約されたコンテンツの力を最大限に引き出すチャンスでもあります。更新が止まってしまうと、せっかくの統合効果が薄れてしまいます。定期的な記事更新やサービス情報の追加などを計画的に行いましょう。
2. リンクチェックと被リンク管理
旧ドメインに貼られていた被リンクが新ドメインに正しく引き継がれているか、リダイレクトの整合性を継続的にチェックします。外部サイトからのリンクが多い重要ページほど、リンク切れや誤った設定がないかを重点的に確認しましょう。
3. ブランドイメージの強化
ドメインがひとつにまとまったことで、企業としてのブランドイメージをより強く発信できるようになります。ロゴやカラー、フォントなどのデザイン要素を統一するとともに、「すべてのサービスがこのサイトに集約されている」というメッセージをわかりやすく打ち出すと効果的です。
4. アクセス解析の活用
新たにまとまったサイトのアクセス解析データをしっかりと活用し、サイト改善や集客施策に活かしていきましょう。以前は分散していたデータがひとつに集約されるため、ユーザーの行動パターンやコンバージョンへの流れが理解しやすくなります。
複数ドメインか統合かの判断基準
実際には、すべてのケースで「ドメインを完全に統合すべき」とは限りません。サービスの性質やブランド戦略によっては、複数ドメインで展開したほうがユーザーにとってわかりやすい場合もあります。判断に悩む場合、下記のような項目で検討してみるとよいでしょう。
| 判断基準 | 統合を優先する例 | 複数ドメインを残す例 |
|---|---|---|
| ターゲット層とサービス内容が近いか | 事業部ごとにターゲットが似通っている。 コーポレートサイトから各サービスを自然に誘導できる | 完全に異なるブランド・商品領域を扱っている。 ユーザーが違うため、混在すると混乱を与える |
| 社名やメインブランドとの整合性を重視するか | コーポレートのイメージを押し出したい。 社名やメインブランド名をサイト名に含めたい | 企業名を出さずに個別のブランドとして認知されたい。 別事業として立ち上げているため、分離したい |
| 運用リソースやコストを最小化したいか | 一括で更新作業やSEO対策を行いたい。 人手不足のため多サイト管理は難しい | それぞれに専任担当がいて、複数サイトの運用が可能。 サイトごとのコストを吸収できるほどの利益がある |
| ブランディング戦略と競合状況をどう考えるか | 統一感のあるブランド戦略で差別化を狙いたい。 同業他社との競合が激しく、サイト評価を高めたい | サービスごとに異なるブランドで差別化しており、 競合もそれに近い形で運用している |
上記のような観点を踏まえながら、総合的に判断することが重要です。とはいえ、前述のとおり中小企業の多くは統合したほうがメリットを得やすいケースが大半です。特に管理や更新にリソースを割けない場合は、ドメインをまとめてサイトの力を集中させるのが得策でしょう。
まとめ
複数ドメインを所有していると、「部門ごとにサイトを作りたい」「別々のブランドとして運営したい」というメリットを期待できる反面、SEO評価や運用リソースが分散してしまうデメリットが大きくなりがちです。
特に中小企業の場合は、人材や予算が潤沢にあるわけではなく、多くのドメインを抱え込むほど管理負担が増してしまいます。そのため、以下の点を意識して、統合するかどうかの方針を決定するとよいでしょう。
- ターゲットが近い事業やサービスであれば、可能な限り一つのドメインにまとめて強みを活かす
- ドメインを統合する際は、301リダイレクト設定やサイト構造の再設計、コンテンツの整理を慎重に行う
- 統合後も定期的にコンテンツを更新し、リンクのチェックや被リンクの管理を怠らない
- もしあえて複数ドメインを続けるのであれば、ブランドやターゲットの明確な住み分けがあるかを再確認する
ドメインを集約することで、サイトの評価や運用効率は大幅に向上する可能性があります。会社のブランドやサービス内容をわかりやすく届けるためにも、ドメイン統合はしっかりと検討すべきテーマと言えるでしょう。






